2012年05月02日
医者の不養生、坊主の不信心、では弁護士は?
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 出張 智己
 出張 智己(でばり・ともき)
出張 智己(でばり・ともき)医者の不養生
「医者の不養生」というのは、ひとには養生をすすめる医者も、自分は案外いい加減なことをしていることのたとえだ。理屈のよく分かっている立場の人が、自分では実行をしないことのたとえでもある。儒者の不身持、坊主の不信心、紺屋の白袴など、似たような状況を指し示す言葉は他にもある。弁護士にも何かあるだろうかと思ってインターネットを調べたが、確立した表現はないようだ。欧米では、"Few lawyers die well, few physicians live well"(弁護士が良い死に方をすることは稀だし、医者が健康に生きることも稀だ)というようだが、これは、弁護士は恨みを買いやすいという話で、少し語感が違う。ひとには法令遵守をすすめる弁護士も、自分はいい加減なことをしていることを喩えるとすれば、「弁護士の法令違反」ということになろうか。
今回は、自戒の趣旨も込めて、「弁護士の●●●●」の、「●●●●」に入る言葉を考えてみたい。
「自由と正義」
「自由と正義」という雑誌がある。日本弁護士連合会が発行する、一般にも購読可能な弁護士の機関紙だ。そこでは、巻末に、懲戒を受けた弁護士の氏名が実名で公告されるほか、処分の理由の要旨が公表される。弁護士としての品位を失うべき非行の実例を知る手がかりになる。パラパラとめくってみると、弁護士報酬についての説明不足や、預かり金の横領など、弁護士業務と密接に関係するトラブルもあれば、私生活上の行状における不品行など、およそ弁護士業務に関係しないものもある。「明らかにこれは駄目だろう」と思うようなものもあれば、普段から気をつけていないと足下をすくわれかねないようなものまで多岐にわたる。様々な類型のものがあるが、その中で、弁護士という職業の本質にかかわる非行は何だろうかと思う。
弁護士像
弁護士に相談するときには、ほかでは決して言えないような秘密を打ち明ける。弁護士は、秘密を守り、依頼者の正当な利益を最大化するために尽力し、決して裏切ることはない。そういう信頼があってはじめて成り立つ関係だ。自分の手の内をすべてさらけ出して相談したにもかかわらず、その後、弁護士が敵陣営に与したとすれば、依頼者にとって、とんでもない背信行為ということになる。弁護士は、依頼者を裏切らない。そういう弁護士像を維持できなければ、業界として、この仕事は成り立たなくなってしまう。「利益相反」が弁護士法上も厳しく規制されている所以だ。
利益相反
利益相反とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる場合をいうことが多い。弁護士業務の文脈では、「パイを分けるような関係」や、「擬似信認関係」のケースでは、特に注意を要する。
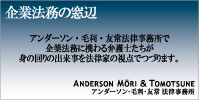
「パイを分けるような関係」は、遺産分割協議などが典型である。相続人の何人かが一緒に相談にきて、誰が何を相続するかを決めるような場合、一人の取り分が大きくなれば、他方は小さくなる関係にある。相続人間では、いつ仲違いが生じるかも分からない。一旦仲違いが生じれば、その後、相続人の一人だけに的を絞って、その人のために全力を尽くしたいと思っても、それはかなわず、その案件から手を引くほかなくなる。そうしないと、敵に見立てられた側からは、「自分の味方だと思って秘密を打ち明け、相談をしてきたのに、裏切るのか」と非難されることになり、「決して裏切ることはない」という弁護士像の根幹が揺るぐことになる。刑事事件で、複数の共犯者の弁護にあたる場面も、「パイを分けるような関係」のバリエーションといえる。主犯格の者の刑は、自ずと重くなることから、犯行に至る経緯や役割分担など、様々な局面で「あいつが悪い」「自分はあいつの指示に従っただけだ」などと罪のなすり付け合いが生じる。一方の弁護に注力すると、他方の立場が悪くなる、という意味において、遺産分割協議の事例と共通するところがある。
「擬似信認関係」のケースは、もう少し分かり難い。例えば、弁護士甲が、大学の同級生のAが取締役を務める会社Xの法律相談に応じているような場面である。Aは、同級生のよしみで弁護士甲に会社Xの仕事を紹介し、日常的な法律相談の窓口になっていたとしよう。Aは、「会社Xの仕事は、自分が紹介したのだし、もともと、同級生で気心も知れているわけなので、当然、甲は、自分の利益のために助言をしてくれるはずだ」という信頼をおきやすい。しかし、この場面における依頼者は、あくまでも会社Xであって、Aが固有の資格において依頼者になるわけではない。したがって、Aがよせる信頼は、弁護士とその依頼者の間の信認関係に基づくものではない(両者の間には、擬似的な信認関係が生じているにすぎない)。普段は、この点が意識されなくても、大きな支障はないかもしれない。しかし、株主Yが会社Xに対し、取締役Aを含む現経営陣の責任を追及する訴えの提起を請求したとすればどうだろうか。Aは、弁護士甲に対し、株主Yの請求について、会社としてどのように対応すればよいかを相談するだろう。これに対し、「株主Yの請求には理由がないので、請求に応じる必要はない」とアドバイスする程度であれば、依然、会社Xに対する助言として問題のない範疇かもしれない。しかし、その後、株主Yが、取締役Aに対して代表訴訟を提起した場面で、Aが弁護士甲に対し、Aの代理人になってほしいと依頼してきたとすれば、話は変わってくる。株主代表訴訟においては、取締役Aと会社Xとの間には、利益相反の関係がある。株主Yが勝訴すれば、取締役Aは、会社Xに対して賠償金を支払うことになるため、会社Xの目から見れば、Aの出捐(賠償義務の履行)で、その資産が増加する関係にあるからである。「擬似信認関係」は、「誰が依頼者か」という問題に帰着する。前述のとおり、弁護士が会社の顧問として助言する場合、会社が依頼者本人であって、取締役Aを含む同社の担当者が、固有の資格で依頼者になるわけではない。しかし、担当者との接点が大きければ大きいほど、担当者の目から見て、弁護士に対する信頼が生じやすいことも事実である。このような、信頼関係にかかわる誤解を防止することが、担当者との日々のやり取りの中で重要な課題となることもある。
誰の目から見て、どう映るか?
弁護士に対する信頼を維持する上で、「誰の目から見て、どう映るか?」という問いかけは重要である。たとえ、真実は、依頼者の利益のために奔走し、最善を尽くしていたとしても、「自分の利益に走っていたのではないか」という疑念が生じれば、それ自体、弁護士の信頼を維持する上で、有害である。
英米法の判例の中に、ひとつ有名な事例がある。
Xは、未成年者Yのために、その資産を管理するものとされていた。その資産の中に、店舗の賃借権が含まれていたが、Yが成人する前に、賃貸借期間が満了した。家主は、未成年者が賃借人として営業することを嫌い、賃貸借の更新を拒絶した。その後、Xは、自らが賃借人となり、当該店舗を借り受け、営業した。
この事例において、Xは、真実、Yのために賃貸借契約の更新に奔走し、最善を尽くしていたのかもしれない。その甲斐なく、賃貸借契約が終了し、どうあがいてもYのために賃借権を取得させる方途が否定されたのだとすれば、その後、Xが全く独自に家主と交渉し、店舗を借りてもよさそうなものである。しかし、このような考え方は否定された。もし、これが認められれば、類似の事例において、「依頼者のために全力を尽くさない」誘惑が生じる。また、Yの目から見れば、「Xが自分で借りた」という事実自体、Xへの信頼をゆるがせにする事実であるところ、「Xが真実、Yのためにどれほど全力で交渉したのか」という証明に付き合わされること自体、願い下げであろう。
弁護士にも同じことが言える。依頼者にとっての最善を尽くしたことが、事後的・客観的に立証できるとしても、「決して裏切ることはない」という弁護士像に疑念を生じさせる行為自体、全力で回避しなければならない。依頼者との信認関係に疑いを生じさせる要素は、すべて事前に排除する必要がある。
プロフェッション
プロフェッションという言葉は、西欧ではもともと医師、聖職者、弁護士の三職種を指して用いられた言葉であった。これらは、それぞれ、ひとの体、ひとの心、ひととひとの関係性を取り扱う職種であり、職業倫理に裏打ちされた信頼を背景に、ひとの知られたくない秘密にアクセスする職業であった。信頼は、構築するためには長年の歳月を要するが、崩れるのは一瞬だ。ひととひとの関係性を取り扱うその職責に照らし、「弁護士の信認違背」のそしりを受けることは致命的だ。取り扱う事件のひとつひとつについて、「誰の目から見て、どう映るか」を振り返る必要がある。
出張 智己(でばり・ともき)
1998年3月、東京大学法学部卒業。2000年3月、東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2001年10月、司法修習(54期)を経て、弁護士登録(第二東京弁護士会)、現事務所入所。2006年7月、英国オックスフォード大学においてMagister Juris(法学修士課程)を修了(学位授与は2006年10月)。現事務所復帰。2010年1月、現事務所パートナー就任。
著書に「新会社法の読み方 ― 条文からみる新しい会社制度の要点−」(社団法人金融財政事情研究会、2005年、共著)、「Securities World 2005」(European Lawyer、2005年5月、共著)、「International Succession Third Edition, Chapter 26 "Japan" 」(Oxford University Press、2010年1月、共著)など。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください