2012年05月21日
転ばぬ先の杖:予防法務とは?
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 伊藤 麻里
 伊藤 麻里(いとう・まり)
伊藤 麻里(いとう・まり)突然の高熱?
次の週末には大型連休に突入するという4月下旬のある日、家族の一人が高熱を出した。今年の4月は例年にも増して寒暖の差が激しかったので、そんなこともあるかなという気もしたが、よくよく話を聞いてみると手足が痛いと言う。高熱に加え、関節の痛みといえば、素人ながらも、インフルエンザを疑うところ。
そうはいっても、桜の盛りも過ぎた春真っ盛りにインフルエンザに罹患することなんてあるのかと思い、検索サイトで調べてみると、意外や意外、ゴールデンウィーク前後というのは、約5ヶ月間続くというインフルエンザ予防接種の効果がそろそろ切れて、再度インフルエンザが流行する時期とのこと。思い起こせば、家族は11月中にはインフルエンザの予防接種を終えていたので(私自身はインフルエンザの予防接種を受けた時期が12月中旬と遅かったが)、予防接種の恩恵が得られない時期に突入していたことが判明した。
土曜の夜ではあったが、インフルエンザであれば一刻も早いタミフル服用をと、救急外来に駆け込んだ。その結果、やはりインフルエンザと判明したので早速タミフルを服用し、翌日には熱が下がり始めた。ただ、インフルエンザというのは、熱が下がった後もその後数日は強い感染力があるので、自分を含む他の家族に感染しないか、戦々恐々として、加湿器を動かしつつ家中を消毒するなど種々の対策を講じた。
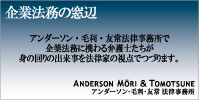
そんな嵐のような週末が過ぎて月曜を迎えると、私自身は一社会人としての振る舞いが問われることとなる。言うまでもなくインフルエンザは強い感染力を有する感染症であり、濃厚接触者としては、依頼者とのFace to Faceの会議を行うことはもちろんのこと、オフィスに顔を出すこと自体憚られる。ただ、他方で、日本では大型連休を前に仕事は大詰めの時期を迎えている上、そもそも海外は日本のホリデーなんのその、通常運行でビジネスが進んでいるため、「じゃあそういうことで」といって投げ出すわけにもいかない。
ただ、こんなこともあろうかと、日頃より、案件毎にチームを組んで業務に取り組んでいることから、仮に私が外出禁止という状況に至ってもなんとかなるように、他のチームメンバーに次々と電話やメールで連絡。また、私どもの事務所では、世界中どこにいても24時間対応できるよう、メールサーバ・ドキュメントサーバにリモートでアクセスできるようにしていることから、感染力がまだまだ高いと思われる解熱後2日間に限り、自宅で業務を行った。そして、遅めに接種したインフルエンザワクチンのおかげもあってか、私自身は発症せず、また、クロージング間近といった案件がなかったことも幸いして、特段の問題が生ずることなく、その後は通常業務に復帰することができた。
予防法務の意義
ところで、企業法務には、予防法務・戦略法務・臨床法務の3側面があるといわれている。将来の法律問題・紛争を避けるために事前に法的な策を講ずることを予防法務と呼び、その予防法務をさらに発展させて法令等に関する知識を経営戦略等に積極的に生かすことを戦略法務、また、裁判その他法律上の係争が現実に生じた場合に対処することなどを臨床法務と呼ぶことが多い。例えば、新たな業務提携を始める際に、法令・判例等を十分考慮して、相手方と交渉し業務提携契約を締結することは予防/戦略法務と、また、現実に業務提携を開始した後に相手方と紛争状態になった際にその解決を図ることは臨床法務と呼ばれることになる。
業務提携契約を締結する段階において、多くの依頼者の関心事は、業務提携の具体的な内容や進捗スケジュールなど前向きな事項であり、また、業務提携の当事者としては、関係が悪化することを前提とした話を直接相手方とすることはビジネス上難しいケースもある。したがって、我々弁護士が、提携計画の前提が崩れる、あるいは、重要な経営戦略につき相手方との意見対立が解消しないなどの理由により、業務提携が不調に終わる場合の処理条件等につき必要な交渉を行い、契約書の条項を作りこんで、将来依頼者に法律問題が生じ、また法的紛争に巻き込まれることを可及的に防ぐのである。こうした交渉・契約書の作りこみは、前向きに案件を進めていきたい依頼者の営業部隊の方々を悩ませることにもなるのだが、弁護士の視点からは、必要不可欠なものであると考えている。
ただ、どんなに予防法務を尽くしても、依頼者が法的紛争に巻き込まれることを完全に避けることはできない。相手方とどんなに良好な関係を築いていたとしても、提携事業自体が頓挫することはあるし、また、相手方の経済状況が急激に悪化することもある。そして、かかる局面に直面すれば、依頼者とその弁護士は、一体となってその解決に向けて必要な法的手段を講じていくこととなる。
インフルエンザであれば、タミフル・リレンザといった万人向けの特効薬があるが、法的紛争においては、法律・判例は必ずしもそのような特効薬にはならない。ビジネス上の法的紛争についていうならば、予防法務の局面で作成した契約条項に、その特効薬としての効き目が期待されるのであって、予防法務を尽くしていない場合、特に、紛争になるまで何らの相談のなかった案件の場合、契約書上の手当ても全くないか、あっても不十分で、場合によっては、想定外の不利益を受けることや長期にわたる訴訟に巻き込まれることを覚悟しなければならなくなる。逆に、業務提携の開始時点での予防法務を尽くしていれば、紛争に巻き込まれること自体は避けられなくとも、早期に解決を図ることができる。
つまり、予防法務によっても全ての法的紛争を避けることはできるわけではないが、予防法務を尽くすことによって、法的紛争となった場合における適切な対処方法が確保されるわけである。インフルエンザになぞらえるならば、予防法務とは、インフルエンザの予防接種(=法的紛争に巻き込まれること自体を避けるための方策)とタミフル・リレンザの開発・製造(=法的紛争に巻き込まれた際の被害を極力小さく抑えるための方策)の両側面を有する業務ということである。
今回、予防接種をしていたにもかかわらずインフルエンザに罹患したことで予防接種の限界は感じたが、その一方で、タミフルというその特効薬の恩恵を痛感した。予防法務における適切な対処は、事後的に法的紛争に巻き込まれた依頼者にとって、高熱と関節の痛みに苦しむインフルエンザ患者にとってのタミフルなのであるから、今後も、前向きに案件を進めていきたい依頼者と協働しつつ、依頼者を守る特効薬作りに励んでいきたいと思う。
伊藤 麻里(いとう・まり)
1999年3月、東京大学法学部卒業。司法修習(54期)を経て、2001年10月、弁護士登録(第二東京弁護士会)、現事務所入所。
2007年5月、University of Southern California(LL.M.)。2008年1~4月、 米カリフォルニア州Palo Alto市のFinnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner法律事務所Palo Alto Office勤務。2008年3月、ニューヨーク州弁護士登録。
2008年9月、当事務所復帰。2011年1月、当事務所パートナー就任。
共著に「新会社法の読み方 ― 条文からみる新しい会社制度の要点」(社団法人金融財政事情研究会、2005年)、「新会社法と金融実務」(銀行法務21 2005年/9月増刊号 No.651)。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください