2回裏 球団事務所
2013年12月17日
2

男は「すまん、すまん」と言って、中島の前のソファにどかっと腰をおろした。先ほどの写真に写っていた男は、白髪まじりの頭髪を短めに刈り込み、口元にうす笑いを浮かべていたが、上目づかいで鋭い視線だと中島は思った。
「久松です」
関西弁とも東京とも違う、抑揚のないアクセントだった。「株式会社神戸ベイライツ球団代表取締役社長 久松優」と大書された名刺を差し出すと、下からのぞき込むように中島の顔を見てから、にっと前歯をむき出しにして、ことさらに作り笑いを浮かべた。
「東京から急遽まいりました中島です」
「わざわざ、東京から、ご苦労様なこってす」
久松の物言いは、迷惑だ、余計な口を出すなと聞こえなくもない。
「何しろ、東京本社では事情がわからないものですから。植田オーナーが心配されてのことです」
好きなやり方ではないが、中島は植田の名前を出すことで、自分の権威強化を試みた。よくも悪くも、スポライ社内で植田の威光に逆らえる者はいない。自分の邪な意見をごり押しするために、権力者の名前を借用するのは論外であるが、会社の内にも外にも、そういう輩は多い。しかし、今回は、事実そのとおりだったし、初対面の相手とどちらが優位に立つかという重要な局面でもある。不愉快なことを言われて、久松の本心が見えるかも知れない。
「まあまあ、そうしゃかりきにならんでもよろしやろ。わっしの方でも、マスコミに無責任な後追い記事を書かんよう、釘を刺しておきましたさかい、オーナーにご心労をおかけすることはありまへん」
久松は急にあやしげな関西弁を使って、中島の狙いをいなした。なかなか一筋縄ではいかない印象を受け、中島は一層気を引き締めた。
「大変不躾なことを率直にうかがいますが、やはり報道された飛ぶボール疑惑は、事実無根であると」
「当たり前やないか」
「それを聞いて、安心しました。ただ、マスコミの方は、夕方の関西スポーツに後追い記事が出たとか出ないとか」
久松は一瞬、嫌な顔をした。
「ようご存知で。関スポの社長に、取材禁止にするぞと、どやしたった」
「他の社も含め、それで収まるでしょうか」
「収まるも何も、関スポにとって、うちは重要な取材源、収入源や。記事が書けなければ、新聞も売れんのだから。共存共栄ちゅうことですわ」
スポーツ新聞や一般紙の運動部、あるいは、経営陣と営業サイドは、そのとおりかも知れない。しかし、手練れの社会部の記者がこのまま黙っているとは思えない。企業不祥事が起きた場合、初動段階の判断ミスが後々まで尾を引いたり、致命傷となることもありうる。中島は過去の自社トラブル処理の経験からそう思ったが、ここで必要以上に久松と敵対しても意味がないので、まずは基本情報の収集を優先し話題を転じた。

「顧問弁護士に、書き込みをした者の調査を依頼したところやけど、法的手続にちょっと時間がかかるそうなんや」
中島も、匿名掲示板に会社の悪評を書き散らした者の契約者情報を開示するよう、インターネット・サーバー管理業者に要求したことがある。しかし、管理業者は、通信の秘密や個人情報保護という理由を口にして、裁判所の正式な決定書を出してもらわないと開示できないという対応だった。
そのときは、複数のサーバーを経由した書き込みであったため、その都度、書き込みをしたログの保存請求、その発信者情報の開示請求、さらに、その次のサーバー内のログ情報の保存請求、発信者情報の開示請求を繰り返していかねばならなかった。しかも、そのサーバーがもし海外の企業であれば、ほとんどお手上げとなる。
裁判所の審理期日は、1回の期日と次の期日までの日にちの間隔が大きいため、結局、違法な書き込みをした発信者の情報にたどりつく前に、書き込みをしたデータ・ログの保存期間が過ぎてしまったこともあった。また、たどりついた発信者情報が、不特定多数が使用するパソコンであったとして、書き込みをした者を取り逃がしてしまった苦い経験もした。
もし自分が普通の一個人であったら、そんな手間も費用もかけられないなと、中島はそのとき思った。
目的は同じなのだから、一度の裁判手続で悪質な書き込みをした発信者情報まで明らかになるような制度設計も本来必要なはずである。しかし、現実のインターネット技術の進歩や複雑化に法制度が追いついていないという感想を持ったのだった。
もっとも、今回は匿名の書き込みではなく、ブログ主の情報ということだから何とかなるかも知れない。しかし、すでにブログ全体を削除し、存在を消してしまっているとネット上の記事にはあった。サーバー運営会社の方に契約者情報は残っていると考えられるが、それが明らかになるのは果たしていつになることか。
「肝心のブログ主に、思い当たる関係者やアルバイトはいないのですか」
「それが、おかしなことに、それらしい怪しいのがおらんのや」
会社でまじめに仕事をしている人間が、裏に別の顔を持っていても不思議ではない。個人的な違反行為が発覚した場合、やはりあいつかと言われるよりも、まさかあの人がと言われる場合の方が多い気がする。
「球団職員やアルバイトは、どのくらいの人数がいるのですか」
「そこなんや。球団職員は30名程度だけれども、アルバイトは、外注業者や警備会社まで含めると、球場に出入りしている人間は、軽く2、300人はいるのとちがうか」
「関係者用のIDタグは球団で管理・把握していますよね」
「まあな」
ベイライツ球場でも名前入りのIDパス・システムはあるようだ。スポライ本社でも、1年近く前に、他の大型オフィスビルと同様、部外者の立入禁止やテロ対策を目的として、IDパスによる入館システムを取り入れた。導入当初、中島はIDパスを入れたひもつきのタグを首からぶらさげる姿が、首輪をつけられた飼い犬のようだと嫌だったが、いつの間にか気にしなくなってしまった。
言いよどんだ久松社長が、話をつづける。
「名前入りのIDパス・システムはあるにはあるんやけど、何しろ業者の人数が多いのと、すべての出入口やドアにセキュリティ・ゲートを設置するわけにもいかないんで、人の出入りはコンピュータに記録していないんや」
「確かに、そうでしょうね。そうかと言って、自分から名乗り出ろと言ってみても、出てくるかどうか」
「そうやろな」
「試合中に飛ぶボールにすりかえたという話ですから、試合中に、そういう場所に出入りできる人は、かなり限定できるんじゃないですか」
「ボールを準備する用具担当やアルバイトのボールボーイに怪しいのはおらんと言うたやろ。納得のいく調査をするのはええが、最初から、うちの社員を疑ってかかるのは、どうかと思うで」
久松がむっとした表情で横を向いた。別に疑ってかかっているわけではない。調査というのは、可能性をひとつひとつ潰していくことでもある。遠慮していては調査はできない。それでも、初対面から対立しすぎるのは、今後の協力という点で、中島もどうかと思い、話を変えた。
「選手の方にも影響は出ていますか」
「まだ、わからんけど、多少はあるやろ」
「やはり動揺はするでしょうね」
「マスコミに余計なことは話すなと言っておいた。かん口令や。少しでも話したら、都合のいいコメントを載せられるだけやからな」
「いずれにせよ、球団としての対応は必要になりますね」
今回の飛ぶボール疑惑を一切否定する久松社長の話を、素直に信じてよいものなのか、中島にはまだ確信が持てない。久松の態度は、よからぬ事実を隠したがっているか、見たくない事実を見ないようにしているとも考えられる。とりあえずは、中島なりに事実関係の調査を行うほかない。
「そうは言っても、こっちも営業、営業で大変なんや。ボール取り替えて、なんの得があるんや。あんたさんも聞いとるやろ、『商店街さん、いらっしゃい』とか」
「はい」
選手たちが商店街に出かけていって臨時店長を務める人気企画だ。
「あれは、好評なんやで。あれをきっかけに、商店街が活性化したっちゅう御礼の手紙をもらうのが、うれしいんや。社会経験の少ない選手にとっても、普通のファンと直に触れることで、こういう人々に支えられて、野球ができるという喜びを認識させる教育効果もあることやし一石二鳥やな」
営業の話となると、久松は一方的に話しつづけた。
「今度の夏休みには、全試合、県内の少年野球チームの子どもたちに始球式をやってもらって、家族やチーム向けに、チケットの割引販売をしたのも大好評やった。プロのマウンドで投げたってのは、何よりの励みになるし。これからも、秋の終盤戦に向けて、どんどんアイデアが湧き出てるところや。今年はクライマックス・シリーズ進出は間違いないし、ひょっとしたら球団史上初の日本シリーズもあるで。大忙しや」
そう言うと、久松は、にっと白い歯をむき出しにした。若干自慢話ではあるが、久松の営業の考えは筋が通っているし、近くに在阪人気球団のタイガースがいるベイライツにとって、地元人気が増えてきたのは、久松社長の営業成果である。
「営業は結果、数字がすべてや。なあ、そやろ」
売上げはすべてを解決する。
植田オーナーの経営信条でもある。スポライはそれで企業規模を拡大し、コンビニ以外の事業へも積極的に進出した。プロ球団買収もその1つで、近年の成績低迷はともかく、グループ全体にプラスのシナジー効果を生み出してきたと言える。何しろNHKから民放まで、ほぼ毎日、スポーツニュースで企業名を連呼してもらえるのだ。知名度アップと宣伝効果だけでも莫大である。
しかし、今は久松の営業自慢や感慨に感心しているときではないと、中島は思い直す。
「久松社長は、この後、どう収束をはかるお考えですか」
「そうやな。社内で調査したけど、そういう事実はありませんでしたとでも発表したらええやろ」
「それで、マスコミやファンが納得するでしょうか」
「じゃあ、どうしたらええんや」
「例えば、外部の有識者による第三者委員会を立ち上げて、徹底的に調査してもらい、違反する事実がなかったことをはっきりさせる方がよいのではないでしょうか」
中島は自分の考えを述べた。これという確信があったわけではないが、近年、会社の不祥事が発生した場合に、社外の第三者委員会が調査し結果を公表することで、真相究明と再発防止をはかるケースを見聞きしている。調査機関が外部の第三者であることによって、調査方法や調査結果について社会に信用してもらうことを制度的に担保していると言える。
「そこまで、大ごとなんやろうか。そんなことをしたら、かえって話題になって、しばらく報道がつづいてしまうやないか」
「それはそうですが、逆に簡単な内部調査で、事実はなかったと言っただけでは、憶測であれこれ疑惑を書き立てられる危険性もあります」
久松が少し口を歪めて嫌な顔をした。話の行きがかり上、中島も食い下がる。
「ベイライツと選手のためにも、きちんとした調査で、潔白を証明することは大事です」
「わかった、わかった。それなら、顧問弁護士に相談するから」
「顧問弁護士はあくまで身内です。調査委員は中立的な立場の社外の人でないと」
中島の話をさえぎるように、久松は身を乗り出して、鋭い目つきになった。
「よう、評論家。本社でそう呼ばれてるらしいな。偉そうな建前論ばかり並べて、数字を出さない人間は会社では信用されんぞ」
そう言って、またしても、にっと歯を見せた。
評論家か。さまざまなリスク分析をした上で、損失が上回りそうな場合には、どうしても慎重論を述べてしまう中島に対し、快く思わない者が、社内でそう呼んでいることは知っていた。
企業である以上、リスクを取らねば、事業が成功しないことは中島も理解している。しかし、大きなリスクを一切無視したり、そういう検討自体を後ろ向きだと排除するブレーキのない、いけいけの営業論が企業の長期的な存続にプラスをもたらすとは思えない。実際、リスク管理や慎重な反対意見を排除してきた金融機関や大企業が不祥事により崩壊し、あるいは、深刻な被害をもたらす大事故を引き起こした事例は枚挙に暇がない。いかに顧客や社会の目線に立って考えられるか。トップまでマイナス情報が上がらなくなった組織は劣化、腐敗が始まっていると思ってよい。中島はあえて、損な役回りと承知で引き受けてきた。
もっとも、組織という列車が全速力で走ろうとしているときに、一人の小さな声が聞き入れられないのも事実だった。その結果が現在の閑職であると言ってよい。以前、特製うなぎ弁当の一件でPOSシステムの見直しを提言したときも、店舗への販売強要行為が発覚した営業サイドから筋違いの恨みを買ったことだろう。
あいつが営業の足を引っ張ったと社内で噂になるそんなこんながいくつか重なった。会社規模が巨大になり、大手商社から今中新社長を迎えたスポライでは、植田がかばい切れるものでもないし、トップのあり方として、前向きな営業意見の方を尊重するのは正しいことだと中島は理解し、現在の部署を受け入れたのだった。むろん、心の傷は負ったままだ。
それにしても、中島が来訪するまでの短時間に、久松がそこまで社内情報を入手していたとは、さすがに営業の猛者はあなどれない。ここは敵地、アウェーに来たのだと実感する。
「まあ、そう恐い顔をするなって。わかった、わかった。今後のことは、君の意見も一部採用するから」
先刻までのお客様待遇から、君呼ばわりで、上下関係を明確にしようとする久松の巧妙さがわかる分、中島は久松をはげしく嫌悪した。それはまた、飛ぶボール疑惑に踏み込まれたくないのではないか、疑惑は疑惑ではなく事実ではないのかという裏付けのようにも感じられる。
「お、もうこんな時間か、いかん、いかん」
中島の心持ちを無視するように、久松は席を立つと、ドアを開け、木村君と名を呼んだ。
「失礼いたします」
ややあって入室した木村は軽く一礼すると、応接セットの端まで近づき立ち止まった。はっきりした声としなやかな動きが重苦しい場の空気を一瞬で変え、中島はささくれ立った気持ちが和むのを覚えた。
「おう、社長室長の木村亜矢子君や。わっしは神戸経済界の会合で営業してくるので、ここで失礼するが、今後のことやら第三者委員会のことやら、木村君と打ち合わせて進めてくれ」
中島も自然と立ち上がった。
「こちらは中島君。本社の植田オーナー直々のお目付役で、恐い人だ。言うことは、何でも聞いたってな」
「かしこまりました」
事務的だが相手を安心させる落ち着きのある声だ。木村の返事に満足そうにうなずいた久松は、立ち上がると、ベルトのあたりを左右にゆすって、まくれ上がったズボンのすそを下げた。立ったままの中島から、久松は見下ろす背丈である。
「中島君。この木村室長は、かわいく見えて、アメリカのビジネス・スクールで専門的に球団経営を勉強した優秀な女だ。君の指示は、なーんでも聞くように言ってあるから、遠慮なく使ってくれたまえ」
最後も、久松はにっと白い歯を強調してみせた。「なんでも」を強調した嫌らしい響き、何より人間を道具のように扱う言い方が、中島には不快だった。本社から離れた球団トップに君臨する以上、何らかの不正や公私混同はあるかも知れない。今回の調査次第では、久松の思わぬ悪事が発覚する可能性もある。そうなったら、それで対処するまでだと中島は心に決めた。
3
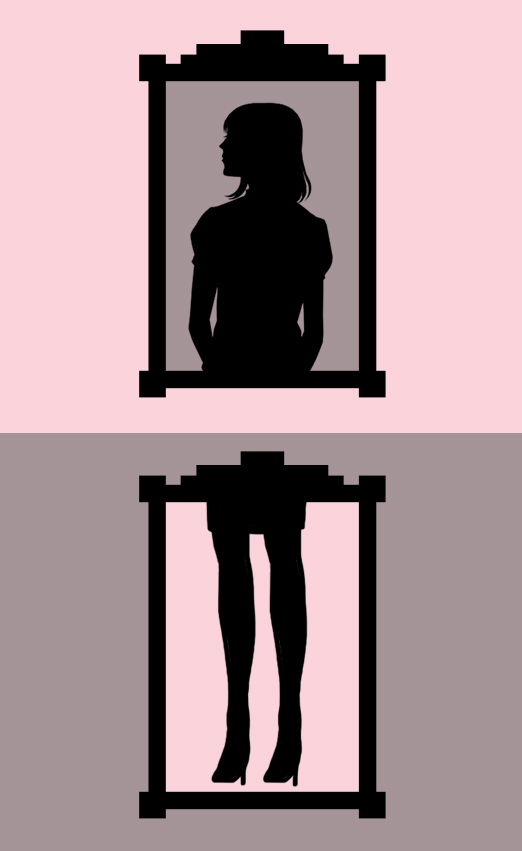
「いや、私の方こそ、そのような立場の方とは知らず、失礼しました」
名刺交換をした後、応接机の一角をはさんで木村の右隣のソファに座った中島は、気持ちの高ぶりを感じずにはいられなかった。思いもかけず、早くも話をする機会ができたばかりでなく、今後、調査を一緒に行う時間も多いはずだ。
言うまでもないが、中島に邪心はない。42歳になっておかしな期待をするほど思い上がってはいないし、仕事の遂行上、気持ちよくできるなら、その方がよいに決まっている。久松社長に嫌な思いをさせられた後だけに、なおさらだ。
「さっそくですが、何から始めたら、よろしいでしょうか」
「そうですね。先ほど久松社長と話題に出た社外の第三者委員会の人選は早めに考えて打診する必要がありますね。それから、実際に試合で使用するボールは、どのように準備しているのか、途中でボールをすり替えることなどできるのかどうか、球場で教えてください。あと、やはり玉原監督や名指しされた選手たちにも、念のため事情というか話をお聞きしたいと思います」
「かしこまりました。それでは、早速、明日、段取りをつけておきます。委員会の人選の方は、どうお考えですか」
「委員の先生は、人格識見すぐれたと言うか、社会的に納得できる人が必要ですね」
「人数は、何人くらいをお考えですか」
「あまり大きな組織では動きも悪いし、日程調整も難しいので、いろいろな分野から3、4人プラス事務方がいいと思っています」
中島は基本的に年下の部下相手でも、ですます調で話をする。年齢や地位の上下ではなく相手に接したいという気持ちからだったが、反面、部下と距離があるとか、他人に心を許さないと評価されがちなことは本人もわかっている。評論家という印象を与えやすいのだと思うが、こればかりはなかなか直らなかった。
「木村室長、こういう場合、アメリカなんかでは、どうしていますか」
中島は自分の考えを述べた上で、木村の能力とセンスを確かめる意味も含め、質問してみた。
「ケース・バイ・ケースだと思いますし、アメリカの事例を詳しく知っているわけではありません。私見ですが、調査と事実判断が必要となると、一人は弁護士などの法律家が必要でしょう。日本では、検事さん出身の弁護士が起用されることが多いようです」
「なるほど。中立性を考えると、会社の顧問ではない弁護士ということになりますか」
社長の久松より、木村室長の方が、社会的客観性があって判断が頼りになると中島は思った。
「それから、メディアからの信頼という意味では、記者出身のジャーナリストで、穏健な方がいいですね」
「そうですね」
「飛ぶボールかどうかという意味では、科学的特性というか数値的なことがわかる人がいればよいかも知れません。それから、プロ野球OBもいる方が、当事者の感覚はわかりますし、何かと現場の反発は、避けられると思います」
元検察官の法律家、マスコミ関係者あたりまでは、中島も考えていたが、技術者やプロ野球OBまでは思い至っていなかった。
「もっともな意見です。さて、具体的な人選はどうしましょうか。相手の都合や謝礼金の点もありますしね」
「問題はそこなんです」
木村は一呼吸置いて、中島の顔を見て話しつづけた。
「球団経営は、収入は多そうに見えますが、選手の人件費や球場使用料など結構高額になり、いつも赤字で、調査を行う予算がまったくないんです」
「ある程度は、スポライ本社に掛け合うことも可能だと思いますよ」
「第1に、社外の第三者委員会を設置して調査するとなると、完全に独立した調査権限と内容の自主的な公表権、そして、何よりも調査時間に応じた多額の調査報酬が必要となると思います。現在はペナントレースの真っ最中で、チームも球団も、あまり時間と費用をかけたくないのが本音でございます。
第2に、これは聞きかじりですが、社外に第三者委員会を設置すべきなのは、会社の経営陣自身が不祥事に加担していて、公正な調査の実施が期待できない例外的な場合にすべきで、企業体である以上は、本来は、会社自身でまず内部調査を行うべきだというのが一般的な意見だそうです。実際、その方が関係者からの事情聴取にしてもスムーズですし、何しろ外部の先生方よりも、球団内部のことをよく知っています」
中島にとって思わぬ抵抗意見であったが、議論としては間違っていない面がある。
「つまり、木村室長は、社外の第三者委員会ではなく、内部調査の方法によるべきだと言いたいのですか」
「失礼しました。そうは申し上げていません。しかし、経費的な理由や実際の調査のしやすさから考えると、まったく部外者だけの第三者委員会にこだわる必要はないと申し上げたのです」
「どういうことですか」
「どうでしょうか。時間的に急ぐ必要がありますから、委員会の人選を進めるのと並行して、中島様を含めた私たち球団内部を中心に実際の一次調査を行い、その結果を委員の先生に報告して、疑問点や追加調査が必要であれば、それに従うということでは」
「うーん」
中島は、思案した。
「人柄をまったく存じ上げない先生がいきなり乗り込んできて、調査やら記者会見やら、球団や本社のコントロールが及ばないところで派手に動かれますと、必死にペナントを戦っているチームや監督、選手たちの負担となります。わたくしとしましては、それだけは避けてほしいと中島様にもお願いしたいです」
木村は真剣な表情で、中島のことを見ている。チームや選手たちを思う気持ちは中島も一緒だ。もちろん、玉原監督を守れという植田の特命のこともある。
「わかりました。植田オーナーの意向も、真相究明が目的ですし、日程的な問題もありますから、木村室長が言うとおり、ひとまず私たちで下調査を始めてみて、その上で、委員の方の意見を聞くことにしましょう」
中島にとっても未経験のマターだ。第三者委員会に一任するとなると、どうなるか不安はある。球団とは利害関係がない自分が調査するのだから、事実を隠ぺいすることはありえないと考えた。何より自分の手で真実を知りたいと思う。
「ありがとうございます。それでは、私の方で、調査委員の先生をリストアップしてみます」
明るく微笑んだ木村室長は、背筋を伸ばした姿勢のまま、ていねいにおじぎをした。ストレートヘアーがわずかに揺れて胸元にかかる。
「まあ、責任重大ですから、一緒に頑張りましょう。よろしく」
「こちらこそ、ご指導のほどよろしくお願いいたします。それから、中島様の宿泊先ですが、ベイライツ・ホテルにお部屋をお取りしましたので、何なりとフロントにお申し付けください。
明日ですが、午前10時にこの球団事務所におこしいただけますか。監督・選手との面談等の段取りをつけておきます。その後、球場に行って、試合の使用球の準備状況をご説明するようにいたします。本日は移動のお疲れもあるでしょうから、夕食をお召し上がりになって、ゆっくりお休みくださいませ」
木村は明日の予定を説明した。職務が迅速で的確、実に頼もしいと中島は思った。幸先よし。これからの調査で何が出るか。もちろん、違反の事実なしとなれば一番よいが、何らかの真実が明らかになるのであれば、この目で最後まで見届けてやろう。中島は不安よりも、楽しみの方を感じていた。(次回につづく)
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください