6回表 若きIT経営者
2014年02月04日
1
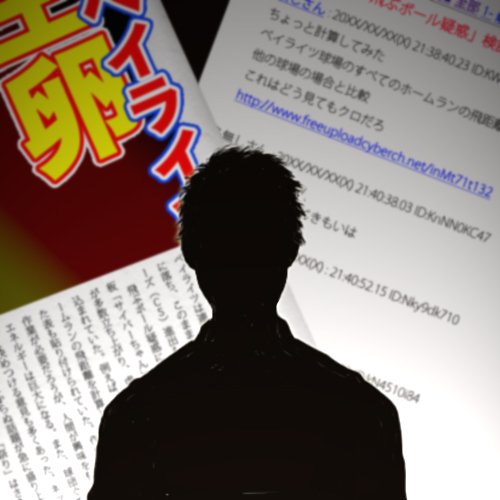
「申し訳ございません」
「まあ、笑ってばかりもおられんな」
にこやかに笑っていた植田力が真顔になった。いつもの眼光鋭い表情に戻る。植田はコンビニ・チェーン、スポライの総帥として「コンビニ王」と畏怖され、また、プロ野球セ・リーグ、神戸ベイライツ球団のオーナーでもある。
新規企画部次長である中島光男は、東京・天王洲にあるスポライ本社の会長応接室で植田と向き合っていた。中島は植田の特命を受け、ベイライツが6回の攻撃イニングだけ「飛ぶボール」を使っているのではないかという疑惑を調査するために、単身球団へと乗り込んでいた。昨夜は暴徒と化したファンから生卵を投げつけられ、その写真がスポーツ新聞に載ったのだった。
ネットの記事で「飛ぶボール疑惑」が報じられて以来、ベイライツは連敗をつづけ、首位陥落どころか、3位に落ち、このままでは初めてのクライマックス・シリーズ(CS)進出もおぼつかない状況である。
CSは、シーズン終了後、日本シリーズ進出チームを決めるために、リーグの上位3チームで行う短期決戦である。セ・リーグでは2007年(平成19年)から採用されている。導入により、シーズン終盤の消化試合が減少し、3位を争うチームのファンが盛り上がることから、観客動員が増えるというメリットがある。
飛ぶボール疑惑については、ネットの巨大匿名掲示板「サイバーちゃん」で疑惑を検証するなどのサイトが多数立ち上がり、虚実ないまぜに様々な推測が書き込まれていた。例えば、ベイライツ球場のすべてのホームランの飛距離を計算し、他の球場の場合と比較した表も貼り付けられていた。作成するのに根気のいる作業が必要だろうが、人間が興味をもったものに注ぐエネルギーは巨大になる。
また、球団ぐるみの不正行為と決めつける意見も多くあった。ネット社会の住人の間では、よからぬ話題が急に盛り上がった状態を「祭り」と呼んでいる。「祭り」はさらに何かのきっかけが「燃料」として投下されると、無秩序に広まって「炎上」し、「生け贄」を血祭りに上げる。
その場限りの生半可な弁明は事態を悪化させる場合が多い。スポライ球団は今のところ表立った反論をしないことで、疑惑の拡大を防ぐしかない消極策をとっている。
しかし、現実の世界では、中島自身、球場で背中に硬球をぶつけられ、匿名の脅迫状を受け取っている。生卵の次は、いったい何が飛んでくるというのか。
「犯人さがしというか、真相は少し見えてきたんか」
「それが、どうにも。飛ぶボールを使用していたという確たる証拠はまったく出てきていません。それなら、疑惑を否定できるかと言うと、そこまでの根拠となる事実も見つかっていません」
「どんな調査をしているんだ」
「外部の第三者を中心にした調査委員会のメンバーで、現場の選手や関係者からの聴き取り、新しいボールを審判に渡す方法の確認などを調査中です」
「君を適任と見込んだわしの目は節穴か。何とかせい」
そう言うと、植田は不満げに口をへの字に曲げた。ライバル企業や監督官庁に対しては、獅子のたてがみを振り乱して徹底的な闘争を挑む。部下に対しては親分肌にして過酷なまでの絶対的忠誠を要求してきた。あまりの激務と心労のため、心身の調子を崩した同僚を中島は多く見てきた。死屍累々。メンタルヘルスなどという言葉はまだなく、「24時間働けますか」とテレビコマーシャルがあおっていた時代のことである。
創業者オーナーは、太陽のようなものだと中島は思う。青い地球の存在がそうであるように、ある程度の距離で接する分には、太陽は暖かさと豊かさを与えてくれる。オーナーは魅力的に見えるし、成果をあげた社員は昇進昇給していく。木星や土星のように離れていると太陽の恩恵は届かない。しかし、太陽にあまり近づきすぎると、その圧倒的な熱量で水分は蒸発し、やがて身体まで焼き尽くされてしまう。
それでも、植田は、世間からも社員からも好意をもたれている。それを創業者のカリスマという一言で説明する者もいた。植田が話をすると、途方もない大計画でも面白そうな夢に映り、実現可能な近未来のように感じられる。部下からすると、要求水準が厳しい植田には憎んでも憎みきれない愛嬌を感じてしまうのかも知れない。
新規企画部と言えば聞こえはよいが、中島が配属されている部署は左遷と言ってよい。収益を生まない担当分野から「カーナビ屋」「カレンダー屋」という侮言も聞こえてくる。しかし、新興のコンビニエンス業界だけに、中島はスポライ入社以来、会社の中枢で植田の後ろ姿を追いかけ、人々の生活や社会を便利にしてきた自負がある。
今の日本社会で、コンビニのない生活など考えられない。24時間欲しい商品を手軽に買えるのはもちろん、携帯電話や電気料金の支払代行、コンサート・チケットの優先購入、さらには、他社のインターネット・サイトで購入した商品の受け取りまで可能である。
スーパーで売っているような生鮮食品や一人暮らしの「個食」向け少量パックの総菜類だけではない。今年からは、省エネと環境に配慮した自然派生活をコンセプトに「ピュアスポライフ」という新規ブランド店舗を立ち上げた。コンビニは時代に合わせ変わりつづける。経営の第一線を大手商社である光陵通商出身の今中豪社長に譲ったとはいえ、コンビニ王、植田は健在だ。
閑職で中島の気持ちがやさぐれることがないわけではない。しかし、出世争いと距離をおき、目の前の仕事に没入できれば、それはそれで悪くない。最近はそんな余裕も感じ始めたところへ、今回の植田直々の特命である。高揚する自分を抑えきれない。自分に正直に生きていれば、今の処遇だって「評論家」と非難された性格だって変われるのではないかと中島は信じたくなる。
「おい、中島。何をぼけっと黙ってる。これから、ちょっと面白いものを見せたるから、一緒に来いや」
言い終わる前に、植田は立ち上がり、室外へと出て行こうとする。中島が同乗した植田の専用車は天王洲から品川、新橋と抜けると、日比谷公園で右にUターンし、東帝ホテルの車寄せに付けて止まった。
制帽制服姿のホテルマンが馴れた様子で後部ドアを開け、乗客の頭部がぶつからないよう車体に手を添えて出迎える。そんなことをしなくても、自分の頭を車体にぶつける人はいないと思うが、恭しげな態度に、中島も自然とお礼の言葉を口にした。
9月の東京はまだまだ暑い。しかし、ホテルのロビーに一歩足を踏み入れると、別世界のようにひんやりとする。入口正面には大きく華美な花瓶に色とりどりの生花が飾られ、伝統あるこのホテルが現在も最高のステータスと最高の利用客にふさわしいことを精一杯にアピールしている。
同系のグレーの背広に同じ表情をした会社員の集団、原色で着飾りすぎた年配女性たち、快活に商談するはったりだらけの外国人、数は減ったが不動産か金融かの見るからに怪しげなブローカー風の男。どうして彼らはそれとわかる雰囲気をかもし出すのだろうか。それぞれの人物に何らかの曰くと取り繕った社会的仮面がありそうに思える。通り過ぎるだけで想像力をかき立てられるこのホテルの1階ロビーは飽きない。
一瞬、髪の長い女性の横顔が見えた。ベイライツ球団、社長室長の木村亜矢子だと中島は思った。
もちろん、東京にいるはずもない。背格好の似た女性を見ると彼女に見えるというのは、好意をもっていることの証なのだろうか。ほんの数日でも、ずいぶん会っていない気がする。微笑む顔を見ながら、またゆっくり話をしたいと思う。
女性の後ろ姿を追ったが、利用客の間に消えて見失った。その間にも、植田はぐいぐい歩を進めてしまう。中島はエレベータ・ホールで植田に追いつき、目的の階へと上がった。
2

「植田会長、お待ちしておりました。わざわざのおこし、恐れ入ります」
室内に置かれた会議テーブルの中心に座っていた人物が立ち上がって、植田に向かいの席を進める。その両脇とともに、全員若い男だった。30代半ばくらいか。中島より年下であることは間違いなさそうだ。
室内は明らかにスイート・ルーム仕様の広さだが、ベッドは片づけられて、中央に会議用の大きな円卓が置かれている。まさに秘密の会合用だ。高級ホテルの部屋にはこういう使い方もあるのだろう。入口で出迎えた男がグラスに冷水を注いで、植田と中島の前に置いた。年寄りの冷や水などと言うとどつかれてしまうが、高齢の植田には冷たすぎるはずだ。彼らは相応の礼儀をわきまえている感じだが、細やかな配慮の仕方を知らないのだろう。中島なら、ぬるい水かお茶を用意する。
「これは中島と言って、私の特命で、いろいろ動いてもらっている者だ」
植田が口を開いた。対面相手への箔付けと言えばそれまでだが、そう言われれば嬉しくなる。
「社長の寺川です」
最近、経済誌でよく見かける人物かなと思ったが、当たりだった。中島は、植田が止めないことを確認すると、立ち上がって机の向こう側に回り込んで名刺交換を行った。両脇の側近たちとも名刺を交換する。
寺川旺太朗。ドゥンガ・ディメンション・デパーチャー株式会社、代表取締役社長。略称3Ds(スリーディーズ)。
有名人や一般人の個人ブログ、会員制のSNS、携帯電話ゲームで急成長しているIT企業だ。昨年には東証二部上場も果たしている。
寺川はIT系の若手経営者にしては珍しく、あるいは、短期間で巨額のキャピタル・ゲインを得て何不自由のない暮らしをしている金持ち経営者らしく、皮下脂肪を蓄えた中太りの体型である。白と黒の斜め縞模様の太縁という存在感のある眼鏡をかけて、童顔と言ってよい色白の丸顔をカムフラージュしている。表情はにこやかな笑顔を絶やすことがない。140文字の短い書き込みを行う「つぶやいたー」のフォロワーの間では「寺さま」というニックネームで呼ばれているらしいことも中島は聞き知っている。
寺川の経歴も、いかにも今どきのIT長者にふさわしいものだ。慶明義塾大学法学部を卒業後、三ツ谷住吉銀行に入行すると、米国留学中にMBA(経営学修士)を取得して早々に転職、経営コンサルタントのMTマッケンジー上級副社長まで昇りつめ、30歳の若さで3Dsを起業。わずか4年で上場を果たした。
寺川自身はソフト開発者ではないし、特別にコンピュータ技術に精通しているわけでもない。元はと言えば、帳簿上の数字を管理・分析する銀行・経営コンサル業だ。そういう文系の連中が、インターネットの世界を支配しているのかと中島は思う。
その寺川旺太朗が、人目を避ける場所で、コンビニの植田と直に密談して何の用件があるというのだろうか。
「それでは、早速ですが、植田会長。球団譲渡のお話について、前向きにお考えいただけましたでしょうか」
中島は耳を疑った。聞き間違いでなければ、寺川は、ベイライツを自分の会社に売れと言っているのだ。そんな話を聞こうとする植田も植田だ。
植田の方は「そうやねえ」と応じたきり、言葉を発さずにいる。
「植田会長、私たちのプレゼンテーションをお聞きください。スポライ様が、わが社に球団を売却いただくことは、歴史の必然なのです」
寺川はいきなり大きく出た。
「戦後日本社会にとって、プロ野球チームというのは、公共財、つまり、社会の財産なのです。社会の財産である以上、そのときどきに繁栄している業種が球団を経営することが健全で望ましいわけです。戦後はまず、社会の木鐸、民主主義の礎たる新聞社が球団を保有しました。東京ジーニアス、ドラゴンズだけでなく、毎朝新聞も経産新聞もです。
その次は高度経済成長を象徴する電鉄会社です。タイガース、ホークス、バッファローズ、ライオンズ、みんなそうです。国鉄、今のJRも球団を保有していました。
その当時の娯楽は映画全盛期、オリオンズ、フライヤーズがありました。しかし、人々の生活が豊かになると、食品産業が参入して、スワローズ、ファイターズ、オリオンズを買収します。大手スーパーのホークスや、コンビニのベイライツも同じでしょう」
それは、そのとおりだと中島は思う。だからと言って、今のスポライが球団を手放す理由はない。
「しかし、人々は衣食に満足し尽くし、今やコンピュータ、インターネットの世界に、生きがいを求めています。携帯電話会社がホークスを買収し、ネット市場がイーグルスを創設したのは時代の要請なのです。はっきり申し上げて、スーパーマーケットやコンビニエンス・ストアは社会的使命を果たし終えたのではないでしょうか」
「寺川さん、しかし、スポライは経営が苦しいわけではないから、球団を売却する理由があるとは思えませんが」
顧客向けのプレゼンの場ではない。寺川が一人で話しつづけるのを中島は制した。
「そうでしょうか。スポライ本体は増収増益をつづけています。しかし、ベイライツ球団は、どうですか。毎年30億円以上の赤字をつづけ、スポライに広告費などの名目で補てんしてもらっているじゃないですか」
中島は正確な補てん金額は知らないが、おおよそそんな金額だろう。球団会社単体で、黒字を計上できているのは、選手人件費を抑制しているファイターズ、創設直後のイーグルスなど例外的な球団だけだと聞いたことがある。スポライの全国的知名度アップの広告費と考えれば、30億円は大した金額ではない。何しろ毎晩のニュースで会社名を連呼してもらえ、新聞で試合結果を大きく取り上げてもらえるのだ。その経済効果は計り知れない。球団を保有するメリットは大きい。しかし、それでもプロ野球チームの収入と支出のバランスが企業単体のビジネスとして成り立っていないことは事実だ。
「これからは、FA資格を取得する主力選手の引き止めに人件費負担も増えるでしょう。エースの江口史隆は今年FA資格を取得したと思いますが、彼のために、いくら資金の用意しているのですか」
当然、江口のFA資格取得は調査済みかと中島は思う。FA、フリーエージェント制度は、選手に移籍の自由を認める米国大リーグの制度で、日本でも1993年(平成5年)に導入され、現在、高卒選手は一軍に8年間在籍すると、国内チームへの移籍が認められることになる。
プロ野球選手は、球団による指名や複数球団によるくじ引きというドラフト制度によって、入団交渉権を持つ球団を決められてしまう。それが選手の職業選択の自由を侵害していると主張して、高額の年俸や契約金を支払う資金力を有する人気球団、東京ジーニアスの強い後押しでFA制度が導入されたことは知られている。
ドラフト制度の理念である12球団の戦力均衡による野球界全体の活性化は、FA制度や以前存在していた大学・社会人出身選手による逆指名制度によって、その分後退してしまったことは間違いない。カープや昨年までのベイライツのように中心選手がFAで流出するだけで、Bクラスが定位置というリーグの二層化問題もおきている。
また、選手にFA移籍が認められたことで、中心選手たちの年俸は軒並み高騰し、そのことも各球団の経営を圧迫する要因の1つとなっているのは事実だった。親会社の利益を食い潰しているという批判も的外れではない。
「さらに問題は、ベイライツ・ホテルとドーム球場の建設費です。これらはグループの別会社が所有していますが、私どもの調査によれば、土地取得費と建設費の借入残高は約640億円。スポライ本社とベイライツは借入金を連帯保証していると聞いていますが、この保証債務は、球団の収支決算書には記載されていません。保証債務は記載する必要がないからです」
中島は建設費用についてはタッチしたことがないが、財務分析の専門家である寺川の理詰めの発言がまったくのでたらめという訳ではあるまい。
「長年の成績低迷がつづいて、観客動員数や収入も右肩下がりです。あっ失礼。これは私どもが指摘するまでもない公知の事実でした。しかし、建設費の債務と利子の支払い年々が負担になって、返済期間の延長を銀行に申し入れていることも知っています。私どもにベイライツをお売りいただければ、一挙に解決することができます」
何も問題ないと思っていたことを次々と指摘され、中島は言い返す材料がない。さすがに、寺川もここでひと呼吸置いて、水をひと口飲んだ。植田は表情を変えず、腕組みをして聞いているままだ。レースのカーテン越しに日差しが入る室内に沈黙が流れる。
寺川が一段とにこやかな笑顔を浮かべて、身を乗り出した。
「ところで、飛ぶボール騒動は、一向に収まりそうにないですね」
「現時点の調査では、そのような事実は一切ないということですので、ご心配には及びません」
中島は少しむきになって言い返した。実社会の厳しさも知らないマネーゲームの若造になめられてたまるか、増長するなとも思う。
「中田さん、いや失礼、中島さん、それはどうでしょうか」
こいつ、わざと名前を間違えて、こちらをかっかさせようとしているなと思う。中島を怒らせて得があるとも思えないが、そういう交渉スタイルなのだろう。気が短いことで知られる、いらっちの植田は、なぜか、二人のやりとりを楽しむように目を細めて見ているだけだ。
「インターネットの世界を専門として生きている私にもわからないのですが、ネットの世界には、全体の意志のようなものが確実に存在します。ネット社会の一般意志と言ってもよいものです。意志の担い手である一人一人の顔や名前は見えなくても、ネット社会の住人たちは、残忍な犯罪だと思えば、知能の劣る少年を死刑判決で吊すこともできます。あるいは、テレビタレントを政治的独裁者に仕立て上げることもできるのです」
一転、感情を押し殺して語る寺川に、ネットは万能の神なのか、ふざけるなと思うと同時に、中島は恐ろしさも感じた。
「われわれ3Dsの意識調査によると、飛ぶボール問題への社会からの非難は広がりを見せて増えつづける一方です。また、今後、他球団のオーナーや日本プロ野球機構からも、何とか早く解決しろという批判が出てくると予想しています。私どももネット社会の一般意志は尊重せざるをえません」
確かに、3Dsがその気になれば、持ち駒であるオピニオンリーダーのブログや、会員制のSNSを動員して、ある程度の世論誘導も不可能とは言い切れない。
「この際、球団を手放してしまう方が、スポライ本体に傷がつかないという経営判断もあると思いますよ。このままでは本丸が深手を負って落城という危険もあります。ネットで一度火がつくと消火することは難しい。私どもはそれが怖い」
話し方はにこやかだが、プレゼンの最後は恫喝ということか、ご立派なMBA様だ、そう簡単に思いどおりに行くものかと中島は思う。欲しいものを獲得するためなら、どんなものでも最大限に利用しようという割り切った発想自体、中島にはなじめない。
「わかりました。次回会うときは、具体的な金額を提示してください。こちらの売却条件を考えておきます。現段階の希望は、新球団でもチャンプ玉原さんを監督に留任してもらうことです」
中島は驚きのあまり、隣で発言した植田力の顔を凝視せざるを得なかった。オーナーはこんな若造どもの絵空話に乗ろうとしているのか。本当に、スポライはベイライツを売却するのか。信じられない。今中社長は、この話を知っているのか。彼の出身企業で大株主になっている光陵通商は、承諾するだろうか。中島の頭の中には、当惑と疑問しか浮かんで来なかった。(次回につづく)
▽この物語はフィクションであり、登場する人物や会社、組織などはすべて架空のもので、実在のものとは異なります。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください