2014年03月10日
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 寺﨑 玄
 寺﨑 玄(てらざき・まこと)
寺﨑 玄(てらざき・まこと)私は2011年12月から2013年6月まで、約1年半の期間にわたり、任期付公務員という形で、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課に弁護士として在籍した。航空局では、主に前期と後期に分けて、①関西国際空港と大阪国際(伊丹)空港の経営統合、および、その後のコンセッションに向けた準備業務、ならびに、②民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)の制定、および、同法に基づく国管理空港等のコンセッションに向けた準備業務に携わった(「コンセッション」とは何か、についてはこの文章の後半で触れる。)。
金融庁、法務省、経産省といった官庁に弁護士が出向することは、現在ではそれほど珍しくはなく、私の事務所からもこれらの官庁に多くの弁護士が出向している。しかし、いわゆる現業官庁の1つである国交省が出向として弁護士を採用するのは、私が初めての試みということであった。
出向に行く前に、とある友人(複数)に「きっと航空局に行ったらCAさんと合コン三昧だろうから、その際は絶対に呼ぶように。」と言い含められてきた。当然、私にはそんなやましい(?)気持ちは微塵もなかったことは言うまでもないが、それにしてもいざ着任してみて、右を見ても左を見てもなんだか男性だらけである。それもそのはず、国交省は全官庁の中で最も女性比率が低い官庁(総務省調べ。http://www.soumu.go.jp/main_content/000175450.pdf参照)なのである(なお、当然ながらCAさんが中央合同庁舎の我々の部屋を訪問することなどなく、前述の友人との約束は果たされることなく終わった。)。
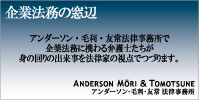
また、「現業官庁」という言葉を使ったが、これは公共事業や現業などの事業役務を行う官庁のことをいう。当然、関係事業者の出入りも多く、地元との交渉といった現場業務や、人によっては地方勤務を経験することも多い。そんなこともあってか、国交省はバイタリティー溢れる、(表現として適切か分からないが)「男子校的な」職場であった。法律事務所はどちらかというと契約を作ったり、相談に応じて法的アドバイスを行ったりといった「インドア」的な傾向のある業務が多いので、ある意味では真逆の世界といっても過言ではなかった。
私も最初は文化の違いに面食らっていたが、じきに自分でも驚くべきスピードで溶け込んでしまった。そのことが、相手のニーズを汲んで最適なアドバイスを示す弁護士という性質からくるものなのか、あるいは自分が男子校出身で元々そういうノリがあっただけなのか、それは今でもよく分からない。
また、地方出張も多く経験し、様々な現場を見る機会を頂いた。ペーパーベースの作業がどうしても多くなってしまう弁護士にとって、この機会は現場を見ることの重要さを再認識させてくれるとともに、個人的な話としては空港や飛行機がより好きになる貴重な機会となった。おかげさまで、今ではプライベートで旅行に行っても、まず空港でしばらくの時間を費やし、滑走路への進入経路を分析しながら、B737-800やA320(プロペラ機が飛んでいるとよりよい。)の着陸を見守るという、いまひとつ他人には理解してもらえることの少ない愉悦に身を委ねることになるのである。
出向中、「弁護士と官僚は何が違う?」ということをよく聞かれた。違いは挙げるとキリがないのだが、個人的に一番思ったことは、官僚はともかく説明力が問われるということである。1つのドキュメントを仕上げるために、法律事務所であれば自分とその上の弁護士だけで議論・判断して終了、ということはよくあることだが、官僚は、まず課長、部長、局長をそれぞれ説得し、同時に(必要に応じ)財務省を説得し、業界や地域関係者の皆様のご納得を得て、さらに国会議員の先生にもご了解を得て、ようやく外に出す、ということになる。重要なものであればあるほど、「背景を知らない、忙しい人に1枚紙で5分でポイントを説明する」という能力が求められる世界なのである。
実は、このような能力は、弁護士も持っていてしかるべきであるし、単に正確な結論を導くことだけが優秀な弁護士の要件ではないことは言うまでもない。しかし、特に我々企業法務を担当している弁護士の場合は、企業側のご担当者も大変よく勉強されており、事実の飲み込みも速いことが多いため、ややもするとそれに甘えてしまっていることがあるのではないか、と改めて考えさせられた。特に、これから弁護士業界全体として業務拡大を目指していく中で、「1枚紙で5分でポイントを説明する」という能力は、おそらく非常に重要になってくるであろう。
冒頭で「コンセッション」という言葉を使ったが、これは正確には「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(いわゆるPFI法)の改正によって2011年に導入された、「公共施設等運営権制度」(http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/shiryo_sb3023.pdf参照)のことである。従来の日本におけるPFIは、いわゆる「ハコ物整備」のパターン(サービス購入型)がほとんどであった。すなわち、公共インフラの運営を民間に委託する、ということが世界では頻繁に行われているが、日本ではほとんど行われてこなかったのである。本制度は、このような民間委託を活性化させるために導入された制度であり、アベノミクスの「第三の矢」としても期待を受けている取り組みである。
実は日本には100近い数の空港が存在するのだが、国等の公的主体が運営することによる経営感覚の不足等のさまざまな理由により、そのポテンシャルを活かしきれていないという議論があった。LCCのような新しいプレイヤーの存在もあり、航空産業は今、過渡期にあるといえる。この機会に、空港を上記のコンセッションという仕組みを利用して民間委託していくことで、より地域経済の活性化を促進しよう、ひいては日本の空を変えよう、ということが、今回の取り組みの狙いである(http://www.mlit.go.jp/common/000994705.pdf参照)。
この件については出向中に企業の方々とお話しする機会を得たが、多くの方々の感想は、「面白そう。でも、色々と不透明な所があってそこがリスクだよね。」というものだった。確かにインフラともなると長期の投資が想定されるが、先の大震災における仙台空港の被害も記憶に新しいように、さまざまなリスクが想定される。しかし、そういった「先の見えないことの手当て」「リスクの分配」こそ、「○○が起きたらどうしよう」ということをいくつもいくつも考えて契約書の中に入れ込むことを生業としている弁護士の腕の見せ所である。国交省が弁護士という今まで全く興味を持たなかったフィールドの人間に声を掛けてくれたのも、そのためなのだと考えている。
出向から戻り、私は弁護士業に復帰したが、今ではインフラ全般、特に空港のみでなく、船舶、鉄道、道路といった「乗り物」に関係する分野の仕事に多く携わらせて頂いている。いわば「乗り物弁護士」(造語)である。弁護士である以上、色んな分野から自分で選んでいくことができる中で、なぜ私が今現在この分野に特に力を入れているかといわれれば、単純に「仕事の中でモノが見えるって楽しい」という思いが強いからである。それはあるいは、7歳の時に初めて飛行機に乗った時の感動から始まっているのかもしれない。
空港に関係する業務に関与できたのは全くの偶然ではあるが、多くの空港を訪れ、そこで働く人々や地元の期待を聞くにつれ、日本の空港、さらには日本のインフラはもっとそのポテンシャルを発揮できるのではないか、もっと多くの子供たちや、お年寄り、外国の方々にも活用してもらえるようなものにできるのではないか、という思いを強くし、弁護士という立場から、少しでもそのお手伝いをできたらこれ以上の幸せはない、と思っている。さて、今度の旅行は、どこの「空港」に行こうかな。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください