2014年04月07日
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 宮 健太郎
 宮 健太郎(みや・けんたろう)
宮 健太郎(みや・けんたろう)トルコに駐在する初の日本の弁護士ということで、パクソイのメンバーのみならず、現地駐在の日本人からも歓迎してもらった。私の派遣は一定の成果を収めることができたようで、現在は当事務所から2人目が赴任している。
私のトルコとの最初の出会いは、2011年秋にトルコを半周するパックツアーに参加したことであった。その時にはもちろん、1年半後にトルコに赴任することになるとは夢にも思わなかった。その旅行中に抱いたイメージは、赴任後も大きく変わることはなかったが、実際に現地で勤務して初めて分かったこともある。本稿では、旅をするだけでは分からない現地の実情について、分かりやすくお伝えできればと思う。
まずは、イスタンブールでの典型的な一日について、朝から順を追って見ていこう。
イスラム教国での一日の始まりと言えば、エザーンと呼ばれる礼拝への呼びかけだろう。1日に5回モスクからスピーカーを通じて流れるが、その第1回目が日の出前から大音量で街中に鳴り響く。最初は時差ボケもあり目が覚めてしまっていたが、1週間で慣れ、以後は全く気にならなくなった。
 毎朝パンを買っていた屋台のおじさん
毎朝パンを買っていた屋台のおじさん通勤には地下鉄を利用した。通勤路線は、開通(延伸)してからまだ5年ほどしか経っていないため、新しくてきれいであった。しかも、まだまだ自動車通勤が主流のため、ビジネス地区行きであるにもかかわらず、空いていて座れることも多かった。本数は東京の地下鉄と同じくらいあるし、終電の時間も日本と同様で、利便性も遜色ない。
 パクソイが入居しているビル。入口のゲートは虹彩認証で開く仕組みになっている。
パクソイが入居しているビル。入口のゲートは虹彩認証で開く仕組みになっている。ちなみに、PCのキーボードは、日本から持っていったものを使っていた。トルコ語は、アラビア文字ではなくアルファベット表記なのだが、ドイツ語のようにウムラウト付きの文字や、フランス語のようにCの下にニョロ(セディーユ)が付いた文字も使われる。それらの文字に対応したトルコ語キーボードは、英語キーボードと微妙に配置が異なり、ブラインドでタイプできないからである。
夜は自宅近くの食堂で食べることが多かった。深夜12時以降も開いている食堂が多く、日本にいた時より便利だった。イスタンブールの街中ではほとんど英語が通じないため、最初の頃は特に、カフェテリア形式の食堂に行くことが多かった。食べたい料理を指差せば、とりあえず分かってもらえるからである。
トルコ料理は基本的にうまい。新鮮な野菜もふんだんに使われているので、栄養が偏ることもない。和食と比べると油っこいので、よく胃がもたれたが、トルコめしに飽きたことはなかった。
トルコ料理といえば、シシ・ケバブやドネル・ケバブなどを思い浮かべる人が多いだろう。その通り、トルコの伝統料理には羊肉が使われることが多い。もっとも、羊肉は匂いが強いため、家庭料理で使われることは減ってきているらしい。羊肉は、ちゃんと下処理をしているレストランであれば問題ないのだが、安い食堂だと癖があることも多いため、私は鶏肉を選ぶことが多かった。シシ・ケバブやドネル・ケバブには鶏肉ヴァージョンもあり、それを野菜とともに小麦粉の生地で包んだデュリュムという食べ物が好物であった。
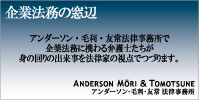
トルコ人の99%がイスラム教徒と言われているが、イスタンブールなどの都市部では飲酒は普通に行われている。ただ、全国的に見ると、全く飲まない人の方が多数派らしい。現地でよく飲まれているお酒としては、ビール、ワイン、そしてラク(ぶどうから作られる蒸留酒)がある。いずれもトルコ国内で生産されているが、酒税の税率が高いため、やや割高である。
変わった飲み物として、アイランというヨーグルト飲料がある。これは日本の「飲むヨーグルト」に近いが、甘味が加えられておらず、代わりに塩味が付けられている点が異なる。最初は受け付けなかったが、徐々に違和感なく飲めるようになった。なお、日本で日常的に使われている外来語でトルコ語由来のものはほとんどないが、「ヨーグルト」は実はその一つである。
トルコ人はのんびりお茶をするのが大好きである。これは全国共通のようで、どの地方に行っても外でお茶(現地ではチャイという。)を飲みながらおしゃべりをしているおじさん達を見かける。(女性たちは家の中でスイーツを食べながらお茶をしているようである。)パクソイでも、事務所の中で同僚の弁護士の部屋に行くと、まず座らされ、間もなく熱いチャイが出てきたものだった。
ただ、トルコ人がいつものんびりしているのかと言うとそうではない。移動時の彼らは、人が変わったようにせっかちになる。元々の骨格が良いせいか、彼らの歩くスピードはとてつもなく早い。私は大阪人で、その中でも速い方だと自負しているのだが、トルコではどれだけ頑張っても追いつけない人が多くいた。日本とトルコの差がよく表れていたのが、駅などにある下りエスカレーターだった。日本では、片側が立つ人用、もう片側が歩く人用という運用がなされていることが多い。これに対してトルコでは、片方が歩く人用、もう片側が駆け下りる人用になっていることが多かった。
イスタンブールは、近年人口が急増しており、現在の人口は1400万人を超えているが、交通インフラの整備が全く追いついていない。渋滞のひどい都市として世界的に有名であり、ワースト1の座をモスクワと争っている状況である。せっかちな彼らが渋滞にイライラしながら運転しているので、当然、運転マナーも悪い。朝夕のラッシュ時にタクシーに乗ろうものなら、急加速・急減速や車線を無視したすり抜けなどは当たり前、隣車線のわずかなすき間も見逃さない芸術的な運転テクニック(日本語では割り込みとも言う。)を目にすることができるだろう。
ビジネスに関しては、「先のことを深く考えない、その反面、決断が早い」というのがトルコのビジネスマンの特徴だと思う。日系企業の場合、ボトムアップでの決裁となり、意思決定に時間がかかってしまうのが通常だと思われるが、そのような行動様式はトルコでは理解されない。トルコでビジネスを展開したいと考えているのであれば、このスピード感の違いについてまず理解しておく必要があるだろう。特に、民営化やM&Aのビッド(入札)案件では、厳しい入札期限が設けられているため、日本の感覚でやっていては入札すらできないという事態さえ起こり得る。
 ゲジ公園で座り込みを続ける人々(2013年6月8日撮影)
ゲジ公園で座り込みを続ける人々(2013年6月8日撮影)
 ゲジ公園に設けられた青空図書館(2013年6月8日撮影)
ゲジ公園に設けられた青空図書館(2013年6月8日撮影)
 ゲジ公園に続く道路に築かれたバリケード(2013年6月8日撮影)
ゲジ公園に続く道路に築かれたバリケード(2013年6月8日撮影)
 時折行われたデモ行進の様子(2013年6月8日撮影)
時折行われたデモ行進の様子(2013年6月8日撮影)トルコが早く政治的安定を取り戻すことを願っているが、この時に感じた若いエネルギーを二度と体感できなくなるのはちょっぴり寂しい気もする。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください