2014年10月20日
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
安達 理
 安達 理(あだち・おさむ)
安達 理(あだち・おさむ)そもそも株式会社の起源をご存知だろうか。大航海時代、東南アジアでの香辛料貿易のため、1602年に設立されたオランダ東インド会社が世界初の株式会社と言われているらしい。日本の鎖国時代、長崎出島で交易をしていたオランダ商人の会社である。1600年設立のイギリス東インド会社が恒常的な会社ではなく、一航海ごとに出資者を募り、全売上げを分配する方式だったのに対して、オランダ東インド会社は、継続的な資本を持った会社であった。出資者は有限責任で、株式の譲渡も自由、17人会と呼ばれる経営陣により経営される等、すでに現在の株式会社と同様な性格を有していた。17世紀から400年以上も続いていると思うと、株式会社というのは、さぞかし優れた仕組みであり、近・現代社会の発展にも大きく寄与する装置なのだろうと察せられる。
現在の日本の会社の実態に目を向けてみる。国税庁の税務統計(平成24年度分)によれば、法人数253万5,272社のうち、株式会社(旧有限会社を含む。)242万2,469社、合名会社4,219社、合資会社2万1,467社、合同会社2万804社、その他(企業組合、相互会社、医療法人等)6万6,313社。株式会社のうち、資本金1,000万円以下のものは、207万4,990社。これに対して、上場会社数は、3,546社(会社四季報(東洋経済・2014年秋号))。株式会社の形態が多く、いわゆる大企業よりも中小企業の方が圧倒的に数が多いことが分かる。ちなみに、中小企業の多くは、個人企業が法人形態に転換、いわゆる法人成りしたものと言われている。個人企業が法人成りして株式会社の形態をとる目的は、表向きは、会計の明確化による経営合理化、その実、「株式会社」という名称による社会的信用を得るためと税法上節税の目的を達するためと言われている。
さて、会社法の基本書(教科書)を手に取ってみる。それによると、会社とは、営利を目的とする社団法人であると書いてある。会社の基本概念である「営利性」「社団性」「法人性」。そうそう、私が学生のとき(当時、会社法は、商法の一部であったが)も、そう習った。法人である会社は、自然人とは異なり、自ら意思を有し、行為することができないので、自然人や会議体を会社の機関とし、その意思や行為を会社の意思や行為とすることにする。すなわち、株主総会、取締役会、監査役会等の機関が設置される。学生の時分は、漠然とこれら商法(会社法)の条文や教科書に書いてあることを所与のものと思い、単純に株主総会や取締役会といった会社機関の集合体が会社なのだと思った。
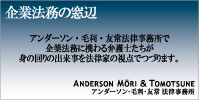
その後、国際的な企業法務を扱う弁護士になってみると、学生時代に勉強した商法(会社法)が定める日本の会社の機関は、外国会社のそれとは大きく異なり、全然所与・必然のものではないことを痛感する。たとえば、外国企業の依頼者が日本に子会社を設立する際、誰を「監査役」に選任するのかを聞こうと思って、「auditorは、誰にしますか?」と聞くと、「我が社の監査法人は、○×監査法人です」と返事が来たりする。そういうときは、日本の会社の機関について少し説明したうえ、監査役と監査法人が区別できるように少し言葉を足して「statutory auditor」や「corporate auditor」等の訳語を当ててみたりする。逆に、外国の会社には、board of directorsの中にnominations committee、compensation committee、audit committeeといったcommitteeがあったりすることを知る。平成14年改正商法により導入された委員会制度に相当する仕組みである。同改正以前、「committee」を「委員会」と直訳すると、学級委員会や図書委員会みたいに見えて違和感を覚えたものである。そうこうしているうちに、商法は、毎年改正を重ね、ついには、平成18年に会社法が施行された。今や、私が学生時代に勉強した会社機関とは、全く異なる機関設計が可能となっている。
ところで、「会社は誰のものか」という議論がある。法律を勉強する以前の私は、会社員の序列は、下から順に平社員、係長、課長、部長、取締役、代表取締役社長、会長へと昇進し、会社は、そのトップである社長か会長のものくらいに思っていた。ところが、会社法を勉強すると、株式会社は、株主と取締役に所有と経営が分離されていると教わる。そうすると、会社は、株主のものということになる。ただし、「会社は、株主のもの」ということは、株主が会社を好き勝手にできる、たとえば、航空会社の株主が飛行機に乗り放題になったり、携帯電話会社の株主が携帯電話を使い放題になったりすることを意味しない。あくまで、株主は、その保有する株式を通じて、会社に対して、細分化された持分を有する、すなわち、株主総会で議決権を行使し、取締役や監査役を選任し、利益配当等を受けることができるというに過ぎない。この点では、ドイツに、従業員の代表を監査役会に選出する制度があることが興味深い。「監査役会」と言っても、ドイツの監査役会は日本の監査役会とは異なる機関のようであり、単純に日本の制度との比較はできないが、従業員を会社の経営に参加させるということであり、会社は株主のものであるという原理を修正するものと言えよう。
弁護士になって数年仕事をした後、私は、アメリカのロースクールに留学したが、Corporations(会社法)の講義は、目からウロコであった。会社法の目的は、agency problem(代理人問題)をいかに解決するか、agency cost(代理人コスト)をいかに削減するかであるというのである。たとえば、あなたがパン屋さんを始め、大繁盛したとする。あなたは、店をもう1店舗増やすことにするが、1人で2店舗を同時に切り盛りすることはできない。そこで、新店舗の店長として従業員を雇うことにする。さて、オーナーであるあなたと従業員店長の間には、情報の格差(オーナーは、従業員店長の店で何が起きているかを直接知り得ない。)があり、利害の対立(オーナーは、従業員店長の賃金を安く抑えたいが、従業員店長は、高い賃金が欲しい。)もある。これがagency problem。この問題をどう解決するか。新店舗にビデオカメラを設置して、モニタリングする。出勤時間や制服について従業員店長と契約書を交わす。いずれもお金がかかる。これがagency cost。会社においても、株主対経営者、支配株主対少数株主、債権者対株主の間にそれぞれ情報格差と利害対立があり、すなわち、agency problemが存在する。解決策は、(1)仕組み・会社組織を設置する(株主と経営者の間に取締役会というモニタリング・システムを置く等)、(2)法的義務や責任を課す(経営者の忠実義務・善管注意義務等)、(3)マーケットに委ねる(企業買収や経営者解任等)等が考えられる。これら解決策にかかるagency costをトータルでいかにミニマイズするか。それが会社法の目的だというのだ。経済学的なアプローチであるが、経済学のケの字も知らない私には、とても斬新に感じられた。そして、そういった観点からすると、会社は、もはや誰かのものとかではなく、経営者、支配株主、少数株主、債権者といった関係者間の利害を調整するための器に過ぎない。
折しも、今年、改正会社法が成立し、来年春に施行される予定である。平成17年の会社法制定以来の大改正である。企業統治や親子会社等に関する改正が行われるが、とりわけ、社外取締役に関する改正が話題であろうか。社外取締役の義務付けは見送られたものの、社外取締役を置いていない一定の大会社・上場会社は、来年から「社外取締役を置くことが相当でない理由」を定時株主総会で説明しなければならなくなる。社外取締役をめぐっては、コーポレート・ガバナンスの強化や経営の透明性の観点から必要性が叫ばれる一方で、上場規則で義務付けられているアメリカでも企業不祥事が起きているとか、企業業績への貢献は期待できないとか、適切な人材の不足を指摘する声もある。さて、agency costは、削減されるであろうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください