町田教授インタビュー、「次のオリンパス」「次の東芝」を防ぐために
2015年10月15日
東芝の不正決算が日本企業のコーポレート・ガバナンスや会計監査に対する不信感を強めている。東芝のガバナンス体制や海外の受け止め方、監査法人の責任などについて青山学院大学大学院の町田祥弘教授に聞いた。
――東芝という会社をどのように見ていますか。
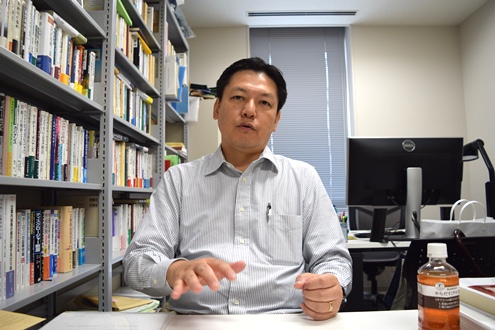 町田 祥弘(まちだ・よしひろ)
町田 祥弘(まちだ・よしひろ)――経営者の何が悪かったのか。
町田教授:日本の多くの会社が、東芝はひとごとではないと思っているはずだ。経営者が「利益を出せ」と号令を掛けるのはいいが、日本の経営者は往々にして具体策を示さない。事業の選択とか、不採算部門の廃止などは経営者の仕事だ。それをしないで現場に号令だけ掛けている経営者は能力がないということだ。旗だけ振って利益が上がるのであればそんな楽なことはない。利益を出せと言っても、現場には事業を大きく変える権限はない。かといって、硬直的な組織では、従業員は経営トップに逆らうという選択肢はない。結果として、現場の“工夫”として、不正に手を染めたのだろう。すべての責任は、無能な経営者にある。
――世界的な受け止め方はどうでしょうか。
町田教授:これは、オリンパスのときに似ているが、国内の受け止め方よりも、グローバルの方が厳しい。海外から見た場合、東芝は日本を代表する企業であり、ガバナンスも日本の制度で求められる最も厳格な指名委員会等設置会社を「選択」しているという理解だった。会社法で新しく入ってきた監査等委員会設置会社は、これよりも導入しやすい、いわば脆弱なガバナンスだ。当然、安倍政権のガバナンス改革は機能しているのかとの懸念がわく。ギリシャなどの問題を抱えた欧州や、金利上昇リスクを抱えた米国に対して、郵政の上場もあり、日本株に対する期待が高まっていたところに東芝問題が起き、本当に、日本に期待して大丈夫なのかといった評価もある。
――何がいけないのでしょうか。
町田教授:日本は、ガバナンスで3つ、会計基準で4つの「選択肢」が認められている。選択肢が多いというのは、何が日本企業にとって合うのか、何が機能するのかの結論を出さずに、先送りしてきた結果だ。典型的な「決められない日本」の姿だった。欧米では、少なくとも上場企業については、ガバナンスも会計も一つだ。上場会社のガバナンスは一つに収斂すべきだ。会社にとって受け入れられやすいかどうかではない。制度対応がすぐにできないというならば、強制適用までの期限を例えば10年といった具合に設ければいい。経営者を規律づけるのが会社法であって、それが経済界の言うがままでは機能しない。4年前にオリンパス事件が発覚したときも、社外取締役1人の設置さえ義務づけられなかった。制度間競争という言い方をするが、制度どうしが競争するわけではないし、個々の会社は一つしか選べない。ガバナンスの場合、経営者に任せて競争させれば何が優位になるのか。経営者にとって楽な方だ。グローバルに見ると、監査委員会を独立取締役のみから構成するのはほぼ常識。取締役会の議長を独立取締役が務めるという傾向もある。さらに、独立取締役の任期制限を置いている国もある。日本の指名委員会等設置会社でさえ、グローバルの水準まで行っていないのに、監査等委員会設置会社という、さらにその下のステップをつくったに過ぎない。
――監査法人の責任についてはどのように考えますか。
町田教授:監査調書を読むことができない外部者としては確定的なことは言えないが、ひとつ気になるのは、不正リスク対応基準に上がっているような項目をどの程度、意識して監査したのかということだ。この基準で強化された不正リスクに対応する手続きをとったのか。果たして、懐疑心を高めることが求められる例示された項目に十分留意したのかどうか。2012年夏に社外取締役が「なぜ、こんな楽観的な見通しを示せるのか」と取締役会で質問したことがあったという報道があった。監査法人は取締役会の議事録を読んでいるはずで、それを受けてどこまで懐疑心を発揮して売上サイクルをチェックしたのだろうか。パソコン事業の押し込み販売では、その過程で利益が売上高を上回ることもあった。そうした分析をしなかったのだろうか。もちろん、東芝が本気でごまかそうとして嘘をついていたという第三者委員会の報告もある。監査人として然るべき手続をとったにもかかわらず、巧妙に欺かれていたという可能性も捨てきれない。事後的なことで評価するのは厳しい作業で、冷静な対応が必要だ。
東芝のケースは、不正リスク対応基準の最初の適用対象になるかもしれない。そこでは、懐疑心の考え方が、どのように使われるのかも気になる。アメリカの処分事例では、明確に監査基準に反していたのではないが、もっとしっかり見ていれば不正を発見することができたという場合に、懐疑心の欠如という処分事由を使うことがある。不正リスク対応基準が新設された後の事案ということもあって、東芝の監査に関しても、明確な監査基準違反がない場合には、「懐疑心を発揮していなかった」という処分理由が示されるおそれがある。これは今後の日本における処分事例のモデルケースになるかもしれない。
――東芝の場合、マスキングという手法がとられました。異様な取引に見えます。
町田教授:ITや半導体などの業界ではこれまで、業界の取引慣行とか、固有の取引という言い方で不正の追及を逃れてきた側面がある。いつまでそれを許していいのか。不正リスク対応基準を議論した企業会計審議会監査部会では、今回のような、いわゆる「循環取引」については継続審議とし、後日、日本公認会計士協会が検討して対応策を提示するということになったはずである。その答えが出る前に東芝の問題が起きた。
――内部統制報告制度は機能しなかったのか。
町田教授:内部統制制度は難しい所に来ている。問題起きたら訂正報告書を出せばいいと思っている節がある。不祥事が発覚した後に訂正内部報告書という形で「開示すべき重要な不備」を公表する企業が年に40社以上あり、通常の評価の結果として「開示すべき重要な不備」を報告する企業の倍の数になっている。企業側は、不祥事や訂正案件があったら訂正報告書を出せばいいとして、適切な内部統制評価をしていないのかもしれない。モラルハザードが起きているということだ。例えば、「重要な不備」を出した企業には、リスクを勘案した絞り込みではなく、フルに整備・評価を求めるなどの対策が必要だ。これでは、まじめにやっている会社は馬鹿を見る。
――監査報酬の問題も指摘していますね。
町田教授:例えば、東芝と同じ監査法人が監査を担当している日立製作所は売上高に対する監査報酬の割合が0.024%となっている。ところが東芝は0.015%とかなり低い割合だ。監査報酬は基本的に人件費の積み上げからなるものなので、これは監査にかけている時間が相当少ないことを意味する。東芝が、監査報酬を相当強く値切っていたのかもしれない。金融庁で会計監査の在り方に関する懇談会が始まった。監査で不正を見つけたいというならば、そのことを社会で明確に認識して、対応策を考えなければいけない。現行の監査法人の体制や仕組みではそれができないというのであれば、不正検査の知見を持つ人を雇うことも検討すべきだ。私は、個別事案である東芝の案件を週刊誌的に批評することよりも、ネクスト・オリンパス、ネクスト・東芝をなくすことを真剣に考えることに取り組みたい。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください