愛知県がんセンター「治験プロトコールに違反した抗がん剤投与」(5)
2018年02月02日
より有効な病気の治療法を開発するために人の体を使って行う臨床研究は被験者の保護とデータの信頼性確保が欠かせないが、日本では近年明らかになったディオバン事件にみられるように、臨床研究をめぐる不祥事が絶えない。この連載の第1部では、生命倫理研究者の橳島次郎氏と朝日新聞の出河雅彦記者の対談を通して、「医療と研究をきちんと区別する」という、現代の医学倫理の根本が日本に根づいていないことを、不祥事続発の背景事情として指摘した。第2部では、患者の人権軽視が問題になった具体的な事例を検証する。第1弾として取り上げるのは、安全性と有効性が確認されていない新規抗がん剤の臨床試験(治験)で、説明を受けないまま被験者にされ、副作用に苦しんだ末に45歳で亡くなった女性の遺族が損害賠償を求めた「愛知県がんセンター抗がん剤治験訴訟」。その最終回となる第5回では、原告側の主張をほぼ認めて損害賠償の支払いを命じた名古屋地裁判決の内容を紹介し、その意義を考える。
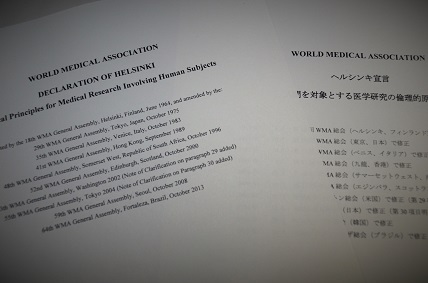 世界医師会のヘルシンキ宣言(右は日本医師会による日本語訳)
世界医師会のヘルシンキ宣言(右は日本医師会による日本語訳)主な争点に対する裁判所の判断は次の通りだった(被告である主治医はO医師、治験薬を投与されて死亡した患者はY子さんと表記する)。
1. 死因と治験薬投与の関係
本件治験薬(254S)の過剰投与を含む3剤併用の化学療法により骨髄機能に重篤な障害を来し、血小板数が著しく減少して急性の血小板減少症による出血傾向が発現したほか、白血球減少症による消化管内などの感染症を併発し、その結果死亡するに至ったことの医学的機序は明らかというべきである。
2.O医師の過失
治療に当たり、当時標準的治療法とされ、薬理上も高度の合理性を備えたPVB療法を採用せず、未だ十分に安全性、有効性が確認されておらず、第Ⅰ相の臨床試験結果からは骨髄毒性による重篤な造血機能障害の危険性が指摘され、シスプラチンよりは治療効果が弱いと報告されていた本件治験薬の使用を決めた。使用方法も、本件プロトコールが被験者保護の見地から定めた投与量、投与間隔を守らず、禁止事項とされた他の抗がん剤との併用を行った。血小板減少がグレード4(血小板数が1立法ミリメートル中1万個以下)の段階に達しても、投薬中止、骨髄機能回復確認などの一般的処置を採らず、重篤な血小板減少症の発現が高度の蓋然性をもって予見できたにもかかわらず、同じく骨髄毒性を用量制限因子とする治験薬とビンブラスチンを併用し、しかも治験薬を過剰投与して、あえて骨髄毒性を増幅させる3剤の化学療法などを継続した結果、骨髄抑制に伴う出血と感染のためY子を死亡するに至らしめたものと認められる。
被告Oは、医師として、当時の医療水準に適合する診療行為を行い、かつ、患者の危険防止のため当時の医学的知見に基づく最善の措置を採るべき注意義務に違反したほか、Y子の人権を尊重しつつ、専門医として要求される高度の知識・技術を駆使して的確な診断を行い、必要な処置を遅滞なく実施し、疾病の回復を図るため最善の診療を行うという診療契約上の債務の履行が不完全であった。
3. プロトコール違反
Y子の疾病が標準的治療法によって効果が得られないとか、適切な治療法がないといった事情はなく、Y子の血色素と肝機能が治験プロトコールの症例選択条件として定めた水準に達していなかったにもかかわらず、Y子に治験薬を投与したほか、他の抗がん剤との併用禁止や、投与量及び投与間隔について定めたプロトコールの規定にも違反していたことは明らかである。
患者を被験者とする第Ⅱ相の臨床試験は、人体実験の側面を有するものであって、医療行為の限界に位置するから、専門的科学的検討を経て策定された治験計画(プロトコール)に基づき、被験者の保護に配慮し慎重に実施される必要があり、とりわけ、被験者保護の見地から定められたプロトコールの規定に違反する行為は、特別の事情がない限り、社会的にも許容することができず、社会的相当性を逸脱するものとして違法と評価されるべきである。被告Oのプロトコール違反行為は、治験薬の骨髄毒性から被験者を保護するための重要な規定に違反したものであり、違反の程度も重大で、高度の危険性があった。プロトコールに違反した診療行為には何ら学理上の合理的根拠、医学的相当性を認めることはできない。治療目的で薬事法の承認前の治験薬を使用する場合であっても、特別の事情がない限り、被験者保護の見地から設けられたプロトコールを遵守しないことが、医師の裁量の範囲内にあるものとはいえない。
被告Oは、本件プロトコール作成に関与した医師として、各規定の趣旨を熟知し、病院の倫理審査委員会に対しても、本件治験薬の臨床試験を本件プロトコールに基づいて行う旨や、本件治験薬の第Ⅰ相臨床試験で検討された安全域で行う旨の倫理審査申請書を提出していたのであるから、プロトコールの規定に反する治験薬投与という違法行為を敢えて行うことについて故意または過失があったことが明らかである。
4. データの改ざん、捏造
Y子の骨髄機能や肝機能などについて治験の連絡票や臨床調査表に虚偽の記入をしていた。被告Oは、真実を記載すると治験薬が入手できなくなると考えたためであると供述するが、虚偽の記入をしなければ治験薬を入手できないといった事情はなかったことが認められ、被告Oの動機は必ずしも明らかではないが、Y子に対する臨床試験が、症例選択条件や投与方法などの点でできるだけプロトコールの定める要件を充足したものであるように外形を整えようとした可能性が最も強い。臨床試験の基礎データとして虚偽の数値を記載することは、ヘルシンキ宣言の精神にも反し、倫理的に非難されるべき行為であることは明らかである。
5. 臨床試験におけるインフォームド・コンセント原則違反
1990年10月から実施されている「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」(GCP)においては、被験者に対する説明事項として、①治験の目的及び方法、②予期される効果及び危険性、③患者を被験者とする場合には、他の療法の有無と内容、④被験者が参加を拒否しても、不利益を受けないこと、⑤被験者が治験参加に同意した場合でも、随時同意を撤回できること、⑥その他被験者の人権の保護に関し必要な事項の6項目が定められ、これらはFDA(※筆者注=米国食品医薬品局)規則のインフォームド・コンセントの基本的事項と基本的に変わらない。これらの事情と、1964年に採択されたヘルシンキ宣言に謳われた基本原則を考えれば、被告OのY子に対する本件診療当時においても、臨床試験を行い、あるいは治験薬を使用する治療法を採用する場合には、インフォームド・コンセント原則に基づく説明義務として、一般的な治療行為の際の説明事項に加えて、当該医療行為が医療水準として定着していない治療法であること、▽他に標準的な治療法があること、▽標準的な治療法によらず当該治療法を採用する必要性と相当性があること、並びにその学理的根拠、▽使用される治験薬の副作用と当該治療法の危険性、▽当該治験計画の概要、▽当該治験計画における被験者保護の規定の内容及びこれに従った医療行為実施の手順――などを被験者本人(やむをえない事由がある場合はその家族)に十分に理解させ、その上で当該治療法を実施するについて自発的な同意を取得する義務があったというべきである。福島雅典証人や被告Oが供述する被告病院における同意取得の実態や、その他の医療機関における同意取得の実態は、インフォームド・コンセント原則の重要性の認識が、未だ臨床現場に浸透していないことを示すものでしかない。
被告Oの陳述書によれば、OはY子に対し、「Y子の悪性腫瘍に対する治療は抗腫瘍剤による治療が中心になる」「この腫瘍についてはブレオマイシン、ビンブラスチン、シスプラチンの3剤併用療法(PVB療法)が効果的とされてきたが、そのうちシスプラチンは、腎機能障害を起こす可能性が強いのでY子のような乏尿障害のある場合には使いにくい状況にある」「シスプラチンと同じ系統の白金製剤であって、まだ厚生省から認可のおりていない254Sという名の治験段階の薬があって、この薬は第Ⅱ相の効果試験に入っていて臨床的な成績はまだ多くないが、シスプラチンに比べて腎機能障害が少ないと報告されている」などと説明し、Y子からは、疑問や質問も発せられることもなく、「お任せする」と返答したとされる。Oの陳述による事実関係を前提にしても、本件治験薬を使用した治療法が医療水準として定着していない治療法であること、Y子の身体状態がプロトコールの症例選択条件を満たしていなかったこと、プロトコールの規定に違反する投与量、投与方法をあえて採用することなどの説明がない上、本件治験薬を使用する治療法が、PVB療法より治療効果があると認めるべき根拠や知見もなかったのだから、OはY子に対し、正しい情報提供を怠ったものというほかない。Y子が、本件化学療法の危険性を十分理解した上で、自律的判断に基づき主体的な意思決定としてこれを承諾したものでないことは明らかであり、被告Oのインフォームド・コンセント原則違反の事実は明らかである。
被告Oの陳述書や尋問に対する供述は、すべてOの記憶によるもので、客観的資料を根拠とするものでなく、説明や同意取得についてはいずれもY子の診療録や看護記録に記載がないことから、Y子に対する治療法などの説明や同意取得に関するOの陳述書記載部分、供述部分は極めて不自然、不合理な内容であって、採用することができない。一方、Y子の夫がOから受けた説明内容を書き留めた手帳の記載内容は作為が加えられた跡もなく、診療録や看護記録の記載内容とも符合するもので、信用性が認められるから、Oは、Y子やその家族に対し、薬事法に基づく承認前の治験薬を使用することや、臨床試験として本件治験薬をY子に投与することすら説明しなかったものと認められる。
原告側は、データを改ざんしたO医師の行為を、「信頼性のないデータ、科学的評価に耐えない有害なデータを作り出す臨床試験に参加させられることのない被験者・患者としての基本的人権を違法に侵害する不法行為」と位置づけて、損害賠償を求める理由の一つとして提訴後に追加した。この主張の根拠の一つとして挙げたのが、「何人も、その自由な同意なしに医学的または科学的実験の対象とされない」という国際人権B規約の規定だった。原告側は法廷で、この規定に関して、「『自由な同意』があろうとなかろうと、何人も『医学』、『科学』の水準を下回る実験の対象とされないことを規定しているものと解される」としたうえで、実施時の医学・科学の水準を規定するプロトコールに則って行うべき臨床試験において、「データの捏造・改ざんがもし行われればその実施は医学科学の名に値しないものであること多言を要しない」と主張した。
この主張に対し被告側は法廷で、次のように反論した。
「原告らが実体法上の根拠として挙げる国際人権規約の条項も、原告ら主張に係る権利を締約国の国民の基本的人権として保障しているものとはいえない。条約および国際法規の遵守義務を定めた憲法98条2項の規定は、国及び公共団体には、条約等の趣旨に沿った立法行政上の措置をとるべき行政的責務があることを定めたものであって、条約等が国内法を介しないで私人相互間の関係にも直接適用または類推適用されることを定めたものではないと解すべきだからである」
「被告らは、患者の自己決定権や生命・身体に対する権利が被侵害法益として存在することは否定しないが、それ以外に、原告ら主張のごとき権利が独自の法益として不法行為法上存在するとか、診療契約上認められるとする見解は到底納得することができない。原告ら主張に係る権利は、詰まるところ、自己決定権や生命・身体に対する権利に包摂ないし吸収される問題にすぎない。この権利は原告らのいうように『日本の法体系上、未だ充分に成熟していない』どころか、それ以前の問題ということである」
「プロトコール違反ならびにケースカードおよび連絡票への不実記載の問題は、理論上、Y子の権利侵害とはなり得ないのである」
判決は、原告側が主張の根拠とした国際人権B規約には触れず、「信頼性のないデータ、科学的評価に耐えない有害なデータを作り出す臨床試験に参加させられることのない被験者・患者としての基本的人権」にも言及しなかった。前述したように、「臨床試験の基礎データとして虚偽の数値を記載することは、ヘルシンキ宣言の精神にも反し、倫理的に非難されるべき行為であることは明らかである」と指摘したうえで、「被告Oがもっぱら個人的関心や科学的に疑わしい研究の実験材料にするため、Y子に対して治験薬を投与したことの証左であると断定するには足りず、これによってY子の具体的利益が侵害されたというにも足りないから、本件不法行為の態様に関する事情として、慰謝料算定の際に斟酌されるにとどまるものというべきである」と述べている。
そして、Y子さんの精神的苦痛に対する慰謝料の認定理由については次のように記している。
Y子は、被告Oの、医師として当時の医療水準に適合する診療行為を行い、患者の危険防止のため当時の医学的知見に基づく最善の措置を採るべき注意義務に違反し、かつ、臨床試験の際に厳しく遵守されるべき被験者の安全に対する配慮にも著しく欠けた非人道的な行為により、さらには、被験者の自己決定権を無視し、Y子に対し情報開示することも、同意を求めることもないまま、勝手に臨床試験の対象とし、本件治験薬を投与するという倫理的にも厳しく非難されるべき違法行為により、継続的に骨髄毒性の強い化学療法に曝され、その結果、点状出血斑等皮膚から出血症状のほか、消化管内等に感染症を併発し、多量の粘血便の排出や多量の鮮紅色下血を来するとともに高熱を発し、脳出血による中枢神経系の異常も出現し、痛ましい姿で死亡するに至ったものであって、その精神的苦痛は甚大であり、そのほか、被告OのY子に対する診療過程には、被告Oが、Y子の臨床試験の基礎データ等について虚偽の記入をするという倫理的に非難されるべき行為もあったから、(略)Y子の余命が1年ないし1年半と推定されることを斟酌しても、Y子の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、3000万円と認めるのが相当である。
判決後、Y子さんの夫は記者会見し、「妻には、『お前の死は無駄ではなかった。社会に貢献したんだよ』と報告します」「二度とこういうことを繰り返してほしくない。判決が今後の医療に少しでも役立てばいい」と語った。
この訴訟は原告、被告双方がともに控訴せず、一審判決が確定した。判決確定を伝えた2000年4月8日の朝日新聞朝刊の記事(名古屋本社発行版)には、「臨床試験にあたって、インフォームド・コンセントの徹底を図り、患者の人権を守る」などとする合意書を県と遺族側が交わしたことと、「もっともな判決内容で、県としても誤りを認めざるを得ない。判決を厳粛に受け止め今後の教訓としたい」という、県健康福祉部理事の言葉が記されている。
Y子さんの夫が、愛知県とO医師に損害賠償を求める訴訟を起こしてから名古屋地裁が判決を出すまでの約7年の間に、製薬企業が新薬の製造販売承認を得るために行う臨床試験である治験の規則は格段に厳しくなった。薬事法が改正され、それまで局長通知だったGCP(旧GCP)が、法律に基づく省令(新GCP)に格上げされ、1997年以降、被験者への説明と同意取得は文書で行うことが法的に義務づけられたからである。日本の治験のあり方を大きく変えたこの法改正は、Y子さんの夫による提訴後間もなく起こったソリブジン薬害と、医薬品の承認ルールについて欧米と協調する必要に迫られたことが直接的なきっかけだった。
治験に関する規則が大幅に変更された後に出された愛知県がんセンター治験訴訟の判決はどのような意味を持つのだろうか。原告弁護団の一員だった増田聖子弁護士はこう語る。
「名古屋地裁判決は、治験のプロトコール違反、インフォームド・コンセント原則違反の違法性を初めて認めた判決だ。この裁判では、治験に関する法律が未整備だった時代のインフォームド・コンセントの取得や治験薬投与のあり方が問われたが、裁判所はヘルシンキ宣言の原則を立脚点に、被験者の権利は擁護されるべきであると判断して、損害賠償を命じた。その意義は極めて高い。治験を含め、人を対象とする臨床研究は科学的かつ倫理的な方法で行い、被験者の権利を守らなければならないということを、研究にかかわるすべての人々が認識し、実践する必要があるが、名古屋地裁判決から17年以上たった今も、こうした原則を遵守しないで行われる臨床研究が後を絶たない。法律の整備を進めるだけでなく、医学の基礎教育の中でヘルシンキ宣言についてしっかりと教育する必要がある」
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください