2018年03月14日
西村あさひ法律事務所
弁護士 菅野 百合
1 はじめに
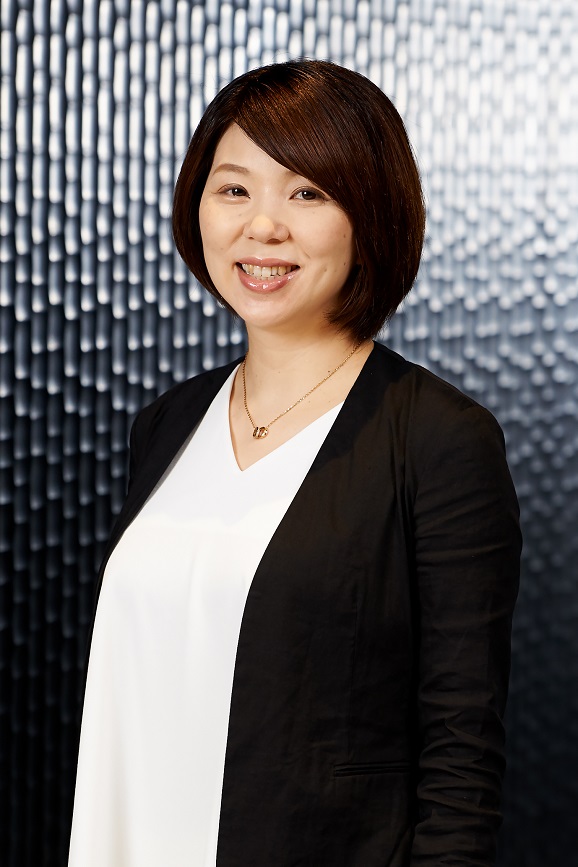 菅野 百合(すがの・ゆり)
菅野 百合(すがの・ゆり)そこで、本稿では、AIが雇用や働き方に与える影響と、そこから生じると思われる労働法上の問題点を紹介する。
2 AIが雇用や働き方に与える影響
AIの活用が雇用に与える影響としてまず挙げられるのは、人間の仕事がAIに代替され、人間の雇用が奪われるのではないか、という「AI代替」とも呼ばれる議論である。この分野の先行研究として最も有名なオックスフォード大学のカール・ベネディクト・フレイ博士とマイケル・オズボーン准教授による2013年の分析結果では、米国の職業の約47%が今後10~20年間に70%超の可能性で機械に代替されると推計し、話題を集めた。日本についても、2015年に、野村総合研究所、フレイ博士及びオズボーン准教授が、AIなどの自動化技術が日本の雇用に与える影響に関する共同研究を行い[1]、今後10~20年後に、日本の労働人口の約49%が就いている職業がAIに代替されるとの推計結果を出している。もっとも、フレイ博士らが行った上記の研究結果には様々な評価があり、こうした“自動化技術か人間か”といった二者択一的な観点からだけでなく、AIなどの自動化技術が雇用に与える影響をより多面的に捉える方向で、国内外で様々な調査・研究が進んでいる。
AIによる雇用への影響は、AIが雇用(仕事)を代替する場合もあれば、業務の一部を代替するにとどまる場合もあり、逆に新規の雇用や業務を生み出す場合もある他、業界、職種・業務内容、労働需給環境、自動化技術の導入コスト等、様々な要因によってその影響の程度や範囲が異なり得るため、一概に評価することは難しい。もっとも、将来的にどの範囲の職種でどの程度の影響があるかは不明でも、AIなどの自動化技術の進展により、少なくとも一部の職種について、何らかの雇用代替がなされるであろうとの予測は、もはや社会的な共通認識となってきているように思われる。
他方で、AIには、人の仕事や業務の一部を補完・代替する効果に加え、業務の生産性を向上し、人々の「働き方」を変化させる効果も期待されている。安倍内閣が「働き方改革」を最重要政策の一つと位置づけ、その流れを受けて多数の企業が「働き方改革」に経営課題として取り組むなか、多様な人々の労働参加と多様な働き方を可能とするためには、労働生産性の向上が必須であり、今後はますますAIやICTなどのテクノロジーを活用していくことが期待される。AI等の技術革新が今後進むと、企業においては、ヒトと機械との適切な役割分担を行い、ヒトにしかこなせない仕事にヒトを最大限有効活用することが非常に重要となる。そのため、人事労務の様々な場面(採用、組織・人材配置、人事評価、社内訓練・教育等)で改革が求められ、人々の「働き方」が大きく変化するのではないかと考えられる。
この他、AI等の自動化技術が様々な企業活動に活用されていく流れのなかで、人事労務の分野にAI等のテクノロジーを活用していく「HR Tech」(Human Resource×Technology)と呼ばれる動きが、欧米を中心に注目されている。HR Techと言われるサービスの多くは、大量のデータを蓄積し、それを短時間で分析する高性能化したコンピューター技術と画像認識技術を活用したAIのシステムによって、採用(求人、面接)、社員教育・人材開発、人事評価、メンタルヘルス、社員の健康管理等の様々な側面でサービスを提供する。こうした人事労務領域でのAIの活用によっても、人々の「働き方」に変化がもたらされると考えられる。
3 AIと労働法に関する法的問題点
(1) 採用とAI
HR Techの一つとして、採用の場面でAIが活用されるようになってきており、この動きは今後急速に進展するのではないかと考えられる。かかる活用の具体例としては、AIが、様々なデータ(質問への回答やSNS等のインターネット上で公開されている情報等)から採用候補者の行動特性や能力を判定し、企業とのマッチングを行うというものがある。これまで採用担当者が行ってきたエントリーシートや面接等における選別・評価は、その基準や手法が属人的であり、ブラックボックス化しやすいものであったといえる。これに対し、AIが採用時の評価を行うメリットは、AIによる評価は、設定された採用基準の適用を公正・客観的に行うことができ、採用過程の透明性が増す点にある。また、膨大な採用データの処理について、AIの活用で採用業務を省力化できるメリットもある。
現状では、採用場面におけるAI活用は、人事担当者等による採用の判断をサポートしたり、参考として用いられたりといった程度にとどまっており、採用の意思決定自体をAIが行うところにまでは至っていない。しかし、将来的には、採用の意思決定あるいは実質的な決定に近い候補者の絞り込みのレベルまでAIが行う事態も想定される。それでは、このように、人事採用に関しAIが利用され、あるいはAIが採用の意思決定まで行うことについては、法的にどのような問題があるであろうか。
そもそも、労働契約は、雇用主たる企業と労働者との合意によって成立し、企業には、契約自由の原則から導かれる採用の自由がある(労働契約法1条、3条1項)。この採用の自由には、どのような者をどのような基準で採用するかを決める選択の自由、採用の判断材料を得るための調査をする調査の自由が含まれる[2]。
従って、企業には雇用する者を選択する局面で広汎な裁量が認められるから、①AIによる分析が間違っていた場合や、②企業がAIによる分析結果を過度に重視してしまったような場合、あるいは、③AIによる分析に信頼性があるのかにつき企業が十分に検証していなかったり、④AIによる分析手法を企業が理解せずに利用したりしていたとしても、企業に直ちに不法行為責任が認められるわけではない。また、採用時にAIを用いてどのような選考をしているかを採用候補者に対して説明しなくても(あるいは、理解していないのでそもそも説明できなくても)、それが直ちに違法となるわけではない。
これに対して、企業が人事採用の場面で応募者を調査する側面は、応募者の人格的尊厳やプライバシーなどとの関係で一定の制約を受ける。具体的には、まず、調査方法については、社会通念上妥当な方法で行われることが必要であって、応募者の人格やプライバシーなどの侵害になるような方法による調査は、場合によっては不法行為を構成することになる。また、調査事項についても、一般に、企業が質問や調査をなし得るのは応募者の職業上の能力・技能や従業員の適格性に関連した事項に限られると解すべきであるとされている[3]。この点、厚生労働省も、採用選考は公正に行われる必要があると示している[4]ところであり、個人情報保護の観点からも、職業安定法第5条の4及び平成11年告示第141号により、採用を行う企業が社会的差別の原因となるおそれのある個人情報や思想・信条を収集することは原則として認められないものとされている。
以上からすると、人事採用に際して、AIが応募者の採用関係情報を分析・評価するに当たって、応募者の人格やプライバシーに特に配慮しなければならない情報(例えば病歴や社会的身分、思想・信条)を収集し使用した場合には、そのことが不法行為を構成しないかが問われることになる。また、違法性を帯びるまでには至らなかったとしても、企業側にとって、上記の点について配慮を欠いた場合、レピュテーションリスクや社会的・倫理的な問題が生じるおそれがあるため、人事採用に際してAIを活用する場合は、応募者の人格やプライバシーへの配慮に注意する必要がある。
(2) 従業員のモニタリングとAI
HR Techの中には、ウェアラブルデバイスやウェアラブルセンサー等を活用して、従業員の位置情報、移動・行動情報、脈拍・血圧等の生体信号、まばたきや眼球運動、身体の動き・ぶれ・姿勢、脳波などの様々なデータを計測してデータ化し、あるいは、ウェアラブルデバイスにカメラを搭載して従業員の視点から見る様々な画像・動画を入手してそれらをデータ化して、これらのデータをAIに解析させることで、各従業員の行動状況や仕事への集中度・関心度・満足度・ストレスの有無等を把握したり、各従業員・部署・組織単位でパフォーマンス分析を行い、人事評価や配属・人材活用、更には組織の活性化等に役立てるといったものも含まれる。また、従業員の健康管理の目的で、企業がウェアラブルデバイス等で従業員の健康情報をモニタリングすることも、今後は想定されよう。
しかしながら、個人の位置情報や、他者とのコミュニケーションの様子・頻度、自らの生体反応等の情報は、個人の行動や内心と密接に結びつくため、プライバシーに関する情報となり得るものであり、こういった情報を企業がモニタリングすることが、果たしてプライバシーの侵害とならないかが問題となる。
この点、判例では、従業員のプライバシー権は無制約に保障されるものではなく、雇用主が従業員の情報を把握する合理的な必要があり、また、手段が相当であれば、従業員の情報を把握することは許容され、雇用主による監視が、従業員のプライバシー権の侵害とされるのは、監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益と比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合であると解されている[5]。
かかる判例の基準を、AIを活用した上記の従業員のモニタリング・システムに当てはめると、企業が、人事評価や人材活用、組織の活性化等の目的でウェアラブルデバイス等によって従業員の様々な情報を取得することは、相応に合理的であり、特定の従業員への狙い撃ちではなく、合理的・公正な基準で対象者を定め、勤務時間内に限ってモニタリングを実施するのであれば、結論として、従業員のプライバシー権の侵害に当たらないと評価される場合もあるものと解される。
もっとも、これまでの判例の事例では、企業が個別の従業員の情報について把握する場合、業務上の必要性との関連性がある程度明確であったように思われるが、AIの活用によって想定されている企業による従業員のモニタリングは、多様な情報を大量に常時取得し蓄積する点で、情報把握の範囲や程度が従来とは比較にならないように思われる。従って、かかる場合でも、従来の判例の枠組みで、業務上の必要性を認め、使用者による労務指揮権の行使としてのモニタリングを直ちに認めてよいのかは、十分問題となる余地がある。さらに、従業員に対してこのようなモニタリングを実施すること自体については使用者側に労務指揮権が認められる場合でも、実際にかかるモニタリングを実施する場合には、運用が適正になされるように必要な社内規程も整備した上で、事前に従業員に対してその必要性等を十分に説明し、理解を求めることが必要であると解される。
因みに、さらに、ウェアラブルデバイスから取得した様々な情報は、従業員の氏名等と紐付けて管理されるのが通常であり、これらの情報と照合することにより特定の個人を識別することが可能であるため、個人情報保護法2条が定める「個人情報」に当たり得る[6]。特に、健康情報については「要配慮個人情報」に該当する可能性があり、その場合は取得にあたって従業員の同意が必要となり、オプトアウトによる第三者提供も認められないことに十分な注意が必要である。
(3) 「AI代替」と配置転換
AIにより仕事全体が代替され、企業の特定の部門全てが不要になる場合、あるいは、業務の一部がAIに代替されることによって、従来より少ない人員しか必要でなくなった場合でも、その仕事に就いていた労働者が直ちに職を失うとは限らない。特に、わが国企業は、これまでの幾多の技術革新の波を経験する中でも、機械により代替される職種に就いていた労働者を解雇することなく、別の仕事に就くための教育訓練を施して配置転換する等して、結果的に雇用を維持してきた。これは、わが国では、従来、期間の定めのない労働者(いわゆる正社員)について、長期雇用システムを前提に職種や勤務地の限定なく雇用することが通常であり、企業側は配置転換により労働者の適性配置や人材活用を柔軟に行うことができる一方で、このような正社員を解雇する法的ハードルが高かったため、配置転換が、解雇回避措置として機能してきたためである。
実際、判例は、職種や勤務地を限定しない労働契約を締結している従業員との関係では、企業が労働者の賃金を維持する限り、企業側に広い範囲で配転命令権を認めている。ただし、配転命令権も無制約ではなく、①当該配転命令に業務上の必要性がない場合や、②業務上の必要性が存する場合であっても、他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、または、③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときといった「特段の事情」が存する場合には、権利濫用として無効とされてきた[7]。もっとも、判例は、一般に、使用者側に何らかの合理性があれば業務上の必要性を広く認め、不当労働行為に該当する場合や差別的意図・嫌がらせ等の「不当な動機・目的」をもってなされた場合等、限定的な場合にしか権利濫用を認めない傾向にあると指摘されている。
以上のとおり、日本の企業には、当該労働者の賃金を維持する限り、配置転換を命ずる広汎な裁量権が認められている。従って、AIなどの自動化技術の導入により、ある職種の仕事がなくなった、あるいは人員削減を余儀なくされた場合には、労働力の適正配置といった業務上の必要性があるとして、当該職種に従事する労働者をこれまでの業務と全く関係のない他の職種に配置転換することも、基本的には認められる。裏を返すと、わが国企業は、配置転換に関する広汎な裁量権を認められている一方、労働者の解雇には厳しい制限が課されている(下記(4)で詳述)ため、企業側としては、AIなどの自動化技術で代替される労働者についても、実務上、まずは配置転換で対応するのが通常ではないかと考えられる。
(4) 「AI代替」と解雇
上記のとおり、AIなどの自動化技術により仕事が代替される場合でも、企業が配置転換で人員を吸収できる限度では、解雇の問題は生じない。しかし、将来的に、AIなどにより仕事が代替される規模が大きく、配置転換だけでは余剰人員を吸収しきれないレベルに至った場合には、企業が解雇を選択せざるを得ない事態も十分に想定し得る。また、AIなどの自動化技術が企業に浸透し、ほとんどの業務で何らか自動化技術への対応が必要になるにもかかわらず、これに能力的に対応できない労働者を企業が解雇するケースも考えられる。
この点、期間の定めのない労働契約における解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用として無効となるものとされている(労働契約法16条)。ここで、解雇が認められるための「客観的に合理的な理由」には、例えば、労働者の勤務成績の不良や、経営上の必要性(合理化による職種の消滅と他職種への配転不能、経営不振による人員整理)が含まれる。また、「客観的に合理的な理由」が認められる場合でも、当該解雇が「社会通念上相当」と認められない場合には解雇は無効となるが、この相当性の要件について、従来の判例は、(長期雇用システムを前提とする)正社員との関係では、解雇の事由が重大な程度に達しており、他に手段がなく、かつ労働者の側に宥恕すべき事情がほとんどない限定的な場合にのみ、解雇に相当性を認めている。
従って、企業としては、たとえAIなどの自動化技術に能力的に対応できない労働者がいたとしても、当該労働者の能力不足や成績不良を理由に直ちに解雇できるわけではなく、まずは、当該労働者がAIリテラシーを獲得できるようにするための社員教育を施し、あるいは、対応能力がない、または低くても従事できる職種に配置転換する等の解雇回避措置を講じた上で、それでも改善の余地がない場合に、初めて解雇を検討することができるものと解される。また、経営上の必要に基づく解雇の場合も、黒字経営である限りは早期退職優遇制度や希望退職で人員削減を図るのが先決であると解されており、現状では、解雇の法的ハードルは、依然として高いものと解される。
4 まとめ
AIが雇用や働き方に与える影響に関連する労働法上の問題点は、AIの活用が未だ黎明期であるため議論が十分なされていないが、AIの活用が今後進展するにつれ、この問題は非常に先鋭的な形で
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください