子育てに自信が持てない親たちへ、小児科医界のレジェンドが贈る珠玉のメッセージ
2018年09月09日

うちの子、8か月になったのにハイハイしない。もう年長さんなのにひらがなが書けない。すると、おかあさんたちはもやもやと悩み出すのです。WEBで検索すれば、ものの数秒で医学専門用語も標準的発達も知ることができる時代です。その結果、子どものちょっとした発達の遅れも見逃さない、見逃させない、という育児が正しいことのように感じられてしまいます。しかし、それはとても窮屈な育児です。
育児情報の氾濫は、早期発見を促し早期介入を可能にするという利点もあります。その一方で、医学的根拠のない情報に心を奪われ、個人差といえる遅れや個性を病気と決めつけて怯え、悩み、後悔する“強迫観念に満ちた育児”に陥るリスクを大きくさせます。
最近、診察室にやってくるおかあさんが、医師が質問をしたり、説明をしたりする前に「これ、溶連菌ですね。迅速診断はできますよね?」などと先回りすることが多くなってきたと感じます。視線が合いづらい、言葉が遅い子どもについて、「この子、発達障がいですね。自閉症と言うよりは学習障害でしょうか」などと結論を急ぎたがるのです。
情報過多は育児に限らず多くの場面でものごとをかえって難しくするものです。育児では、楽しむこと、心のゆとりを持つこと、自信を持つことが何より大切なはずなのに。情報化社会は育児にとってはかえって逆風なのかもしれません。
働くおかあさんたちは、育休明けに保育園に入れるように事前調査したり、職場と調整したりと、妊娠中からせわしない気持ちに追われています。ようやく保育園が決まり、職場に復帰したとしても、ここでも頭を抱えます。保育園に入ったばかりの子どもは、”流行りもの”をもらってきては、熱を出したり、下痢したり吐いたりします。
こんなとき、「ああ、わたしはなんのために働いているのか」「わたしがおかあさんで、この子はかわいそう」と、自分を責め、後悔するのです。そんなおかあさんたちに伝えたいことは、本書でもくり返したように、「ごめんね」「申し訳ない」と悩み苦しむことこそが愛情の証なのだということです。
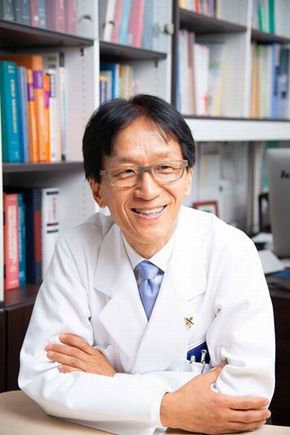 高橋孝雄氏
高橋孝雄氏たとえば、胎児の脳に大人と同じような“しわ”(脳回と呼びます)ができるのは、おおよそ妊娠27週以降のこと。それ以前に生まれれば、脳の表面はツルツルです。しかし、NICUに運びこまれ、あらゆる治療を受けながら保育器のなかで育っても、予定通り脳には脳回が刻まれていく。遺伝子の頼もしさを感じるのはこんなときです。
ひとの体の中でも、脳は遺伝子によって特に強く守られています。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください