生活保護基準引き下げと1万人不服審査請求運動
2018年09月27日
「今、ただでさえ生活苦で、財布の中もいくらも入っていない状態です。一言で言うと、『室内ホームレス状態』とでも言った方がいいくらいです。」と男性は切り出した。
9月14日(金)午後、厚生労働省の記者クラブで、生活保護問題対策全国会議など3団体の合同で、今年10月からの生活保護基準引き下げに抗議する記者会見が開かれた。記者会見では、私を含む支援団体関係者、弁護士らの発言に加え、生活保護を利用する当事者からの発言もあった。
自らを「室内ホームレス状態」と語った男性は、都内在住の49歳。精神障害で働けないため、生活保護を利用している。
「室内ホームレス状態」とはどういう状態なのか。彼の言葉に耳を傾けてみよう。
「部屋の中にはエアコンがありますが、冷暖房は電気代がかかるので、使うにも使えない状態です。風呂に入るにもガス代がかかるので、洗面器に水を入れて、水をかぶって、それで体を洗っているんですが、そもそも汗かきの体質なので、周りの人から臭いと指摘されたりして、それも悩んでいます」
「今でも一日一食か、良くても二食が当たり前になっていて、三食食べるのも月に何日かになっています。『生きられるだけ、まだマシな方だ』と言いたいんでしょうが、差別扱いも甚だしいと思ってしまいます。これでは友達付き合いも婚活もできるはずがなく、趣味のカラオケも行く回数を減らしました。知り合いを5人失いました。食べて寝るか、近所を散歩するくらいしかできないような状態です」
生活保護は本来、先日、最終回を迎えたテレビドラマのタイトルにもなった「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)を国民に保障するための制度である。男性は、生存をしていくのに精いっぱいで、「健康」で「文化的」なレベルからはほど遠い今の自分の生活を「室内ホームレス状態」という言葉で表現したのだろう。
この男性はこれまでも引き下げに反対する申し入れに参加し、厚生労働省の担当者にも直接訴えてきたが、厚生労働省の担当者は「わかりました、わかりました」と言うだけで、結局、何も聞いていないと感じたという。
彼は「ただでさえ、物価は上がっているのに、生活保護基準を下げようと言うのは明らかにおかしい」と指摘した上で、「これまで引き下げられた保護基準、今後、引き下げられるであろう保護基準を元に戻してほしいと願っています。」と発言を締めくくった。
記者会見では同じく東京都内在住の70歳の男性も生活保護利用当事者として発言を行った。彼も、今年の夏の暑さへの対応の問題と、引き下げが人間関係にもたらすマイナスの影響について語っていた。
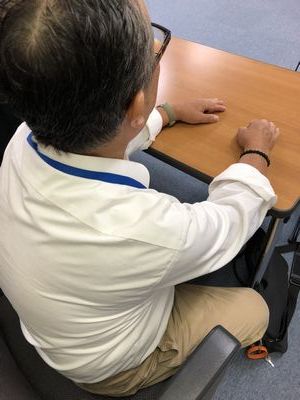 右手首に数珠をつけて自らの生活状況を語る70歳男性
右手首に数珠をつけて自らの生活状況を語る70歳男性「一番困っているのは人の付き合いです。友達と食事に行くことができなくなりました。年に一回や二回は友人と付き合いたいと思っていましたが、それもできない。友達がいなくなりました」
「次に困るのが冠婚葬祭です。父親はすでに亡くなっていますが、法事などがあっても交通費がかかるので、行くことができません。私は長男だが、できないので自分の弟に任せており、親戚とはほとんど付き合っていません。まわりでは、『生活保護を受けている奴は悪だ。脱落した人だ』という雰囲気になってしまっています」
こちらの男性は「衣食」については、やりくりをして何とかなっていると語っていたが、友人や親戚との付き合いを断ち切らないといけないような生活が「健康」で「文化的」な生活と言えるのか、という点は問われなければならないだろう。
では、生活保護の基準はどの程度、引き下げられるのだろうか。
今回、見直しが実施されるのは、生活保護のうち生活費部分にあたる生活扶助の基準である。今年10月以降、2020年まで3年間にわたって段階的に基準が改定され、平均で1.8%(国費ベースで年160億円)の減額となる。ほぼ全ての世帯が引き下げとなった前回(2013年)の見直しと異なり、今回は約3分の1の世帯では基準が引き上げられるが、都市部の夫婦と子2人の世帯、高齢単身世帯等では約5%引き下げられることになる。
「たかが5%」という印象を持つ方もいるかもしれないが、月に数十万円、生活費に使える人と月に数万円しか使えない人とでは「5%」の意味は全く違ってくる。また、生活扶助基準は前回(2013年)の見直しにおいて平均6.5%、最大10%という過去最大の引き下げが実施されており、利用者にとって今回の引き下げは「家計を切り詰めた上に、さらに切り詰めなければならない」ことを意味する。
以下は東京23区など大都市部の生活扶助基準の推移を示した表である。
 生活扶助基準の推移(日本弁護士連合会の資料より)
生活扶助基準の推移(日本弁護士連合会の資料より)前回の引き下げは2013年から3年間にかけて段階的に実施されたが、2014年の消費税率引き上げ(5%から8%へ)では過去の例にならって生活扶助基準も一律2.9%増額されている(引き下げた上で、消費税分を引き上げた)。2012年と2015年の数字を比較して、引き下げ幅が小幅に見えるのはそのためだが、物価上昇分を踏まえると、実際の家計に与えている影響は大きい。
2012年までの基準はほぼ横ばいであったが、70歳以上の高齢者にはかつて月1万数千円の老齢加算が上乗せ支給されていた。老齢加算は、高齢者の特別なニーズに対応するもので、
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください