「『やらない』なんてずるい」「子どものためでしょう?」。
PTAには保護者を追い詰めるそんな言葉が渦巻いています。「平等に負担しているかどうか」の相互監視や、前例踏襲を乱すことを許さない同調圧力は、精神的にも肉体的にも保護者の大きな負担となってきました。
ほとんどの保護者が関わる大きな問題にもかかわらず、「学校から独立した任意の団体」であるPTAの問題は、いつも「保護者間の問題」にとどまってきました。そんな中、選挙のマニフェストに「保護者の負担軽減」を掲げ、PTA問題を政治マターにしたのが、兵庫県川西市の越田謙治郎市長(41)です。
この夏ごろに市に「PTAのあり方検討会」を設置する予定で、役員経験者や校長、有識者らにPTAの運営について議論してもらい、モデル的なPTA活動を市民に示すといいます。果たして、現場のPTAが変わるきっかけになるのでしょうか。越田市長に聞きました。(聞き手・田中聡子 朝日新聞記者)
 川西市長の越田謙治郎さん
川西市長の越田謙治郎さん
越田 謙治郎(こしだ・けんじろう) 兵庫県川西市長
1977年生まれ。同志社大卒。教育関連の出版社勤務後、2002年、25歳で川西市議に初当選。2011年、兵庫県議に転身。18年10月の市長選で川西市長に初当選。
選挙でPTAを問うたわけ
――なぜマニフェストに「PTA」を入れたのですか?
マニフェストを固めるために子育て世代の人と話していた時、「PTAをなんとかしてほしい」「PTAが大変や」って話があったんです。子育て世代だけでなく、各地のPTA経験者からも「なんとかするべきじゃないの?」という声がありました。地域や単P(学校単位のPTA)にもよるけれど、「役員が決まらないと帰れない」とか、「役員をできない理由を、みんなの前で発表しないといけない」とか、多くの人が不満を抱えて「しんどい」と感じていました。
かつては地域に自営業者がいっぱいいて、保護者もいっぱいいて、共働きではなくても生活できました。そんな「元気な自営業の男性と専業主婦がたくさんいる」社会でPTAは続いてきたのでしょう。
ところがいまは、自営業者は減り、男性も女性も働きに出ています。少子化で保護者の数そのものも減っています。それなのにPTAは基本的に同じことを続けている。
「本当にこれ、必要?」と思っている活動でも、「変えたい」と言うと「自分でやれ」って言われかねない。「それなら1年間我慢しよう」となって、いつまでも変わらないんです。だったら長期的に取り組める行政がなんとかしよう、と。
――「PTA会長」という肩書で選挙に出た人はたくさん知っていますが、PTAの活動内容に疑問を呈するようなことを掲げて選挙に出た人は、これまで聞いたことがありません。
子育てで直面する課題は、子どもの育ちに応じて変化し続けます。妊娠中の産科医不足から始まり、医療費助成や待機児童問題。保育園に入れたら「待機児童解消」とは言わず、教育やいじめの問題へと移る。そして中学生になると学校給食。子育て世代には、実は共通するキーワードがないんです。それが子育てに予算がつきにくい要因でもあると感じます。
ところがそんな中、どの段階でも課題になるのが、実はこのPTAです。幼稚園・保育園の保護者会から中学、高校まで、ずっとかかわり続けることもある大きな問題。それなのに、政治はこれまで「学校と別の組織だから」という理由で放置してきたのです。
任意組織でも市長にできることはある
――直接変えるのではなく、「検討会」という方法を選んだのは?
最初はマニフェストに「PTAの見直し」と書こうとしていたんです。でも、「PTAって、任意の組織でしょ?」っていう当たり前の突っ込みが入りました。確かに任意の組織を市長が変えるのはおかしい。でも、組織のあり方を見直すきっかけをつくることはできます。
それに任意の組織だから、市長がまったく関与できないということはありません。自治会やコミュニティー組織のあり方を、市が検討することは当然あります。任意の組織とは言っても、補助金を出したり、市や学校が絡んでいたりすれば、無関係ではありませんよ。
――まだ少ないですが、これまで積極的な参加を推進する一方だった市P連(市を単位とした単Pの上部団体)なんかの中からも、組織や活動のあり方を見直す動きがあります。
 maroke/shutterstock.com
maroke/shutterstock.com
議会で、「PTAの連合組織ががんばってもだめで、SOSがあってから市が動くべきじゃないか」という意見がありました。当然、連合組織のみなさんの協力は不可欠で、ちゃんと別段話し合いたいと思います。彼らもがんばっていて、改革するよう単Pの背中を押してくれています。
でも、いろんなステークホルダーや、先輩であるPTA役員のOB、目上の地域組織の人たちなんかがたくさんいて、PTAの組織だけでは改革しにくい面もあるでしょう。単Pに改革を呼びかけても、言われる側の単Pの会長が「くじで負けたからやってるだけです」って立場であれば、一緒に長期的に取り組むことは難しい。
何より、既存の組織の人たちだけで話し合うと、自分たちは「一生懸命できる」ので、「できる人目線」が中心になりかねません。現場のPTAには、いやでいやで仕方ない人もいますから。
――PTAについての記事を書くと、「よく書いてくれた」というエールと同じくらいの熱量で、「子どものためだろう」「『やりたくない』なんてわがままだ」といった意見も寄せられます。今回の市の検討会にも批判があるのでは?
批判というか、不安でしょうね。「越田がPTAをつぶそうとしてる」といううわさもあるそうです。好意的な人もいれば、PTAが「よき思い出」の人は「いままで自分たちがやってきたことを市長が否定している」と受け取るのでしょう。もちろん、過去の全否定ではありません。PTAを通じて社会に貢献した人や、やりがいを見いだすことができた人もきっといるでしょう。すばらしいことです。
僕が問題にしているのは、同じことができない時代も、できない人にも、同じような活動が求められているということです。
――「やりたい人がやりたい時にやりたいことを」という人から、「全員義務にすべきだ」という人まで、「理想のPTA」は人によってばらばらです。検討会で話し合うにしても、ある程度議論の方向性を示さないと結論がまとまらないのでは?
価値観を押しつけるわけにはいきませんが、本当に子どもたちのためになっているのか、これからも続けていけるのかについてよく議論してほしいですね。そのうえでモデル的な活動を示し、1年間試してくれる学校があればお願いし、また課題を洗い出す。そういうサイクルで進めたいと考えています。
社会の問題として認知されるきっかけに
 川西市長の越田謙治郎さん
川西市長の越田謙治郎さん
――直接に役所が任意団体に手をつっこむのはおかしい。でも一方で、直接「だめじゃないか」とはできない。そこでたどりついたのが「検討会によるモデル的な活動の提示」ですね。少しじれったさもありますし、示されたモデルを活用するかどうかも単P次第……。
「めっちゃ頑張ろう」であっても、みんなが話し合った結果であればいいでしょう。ただ、「うちができたんだから、あそこでもできる」とか「あっちでできたんだから、うちもできる」とかはなしにしましょう。もう一つ重要なのが、一回決めたことであっても、変えていいというルールを設けてほしい。本来は、毎年「今年は何しよう」と考えるのがあるべき姿。でもそれは大変ですよね。いずれにせよ、最後は自分たちが考えて決めるしかありません。
――PTAって「話し合って決める」ことが、めちゃくちゃ大変なんですよね……。
こうやって市が「検討会やります」とぶち上げて、オープンの場で議論する。「PTA改革ってなんやねん」「壊されちゃうのか」「廃止してくれるのか」と、いま、多くの人がいろんなことを考えているはずです。その意見を出し合うきっかけになるでしょう。そういうきっかけがこれまでなかったから、いつまでもPTAの問題が「保護者の問題」とされ、「社会の問題」と認知されなかったのではないですか?
――検討会の人選が、議論の流れに大きく影響しそうですね。人選によっては、結論が正反対にもなりかねません。どのように選ぶのでしょうか。
検討会を設けることになった問題意識を共有してくれる人にお願いしたい。「今のままでなんの問題もない」という人は困ります。逆に「PTAなんかこわしちゃえ」という極論も受け入れられないでしょう。両極端ではなく、PTAの現状に対して「なんかせなあかん」と考えている人でなければいけない。
会長や役員経験者には絶対に参加してもらいたいし、有識者や校長、地域のコミュニティー団体の代表者にもお願いしたいですね。
――地域団体といえば、PTAが仕事を減らそうとした時に「自治会に反対された」という話が少なくありません。
実情を分かってもらわないといけない。地域のみなさんが学校や子どもたちにめちゃくちゃ協力してくれているのは間違いない事実です。かといって、行事のたびに「PTAから人を出して」と強制されても、なかなか難しい。地域の方だって、「おれらがこれだけやってるんだから、PTAも手伝えよ」と言ってるわけではないでしょう。いつからかお願いするようになったことを繰り返しているだけ。今までと同じことをするのが、一番楽ですからね。
地域活動をされている方の方が学校の保護者よりも年齢層が上です。変えようとしている時に、「若いもんは知らないだろうが、こういう経緯があって」なんて言われると、反論しにくいかもしれません。だからこそ、市が間に入っている検討会で議論してもらう意義があるでしょう。
法律上、人権上おかしなことは放置できない
――いまこの瞬間にも、「役員やらないなら理由を言え」と病歴を開示させられたり、会員にならなかったために村八分にされたりといった「オトナのいじめ」がどこかで起きています。そういう個人に対して、何かできることはないでしょうか。
それは課題ですね。最低限守ってほしいことや、やめてほしいことのガイドラインは必要でしょう。法律上、人権上おかしなことは、放置してはいけない。
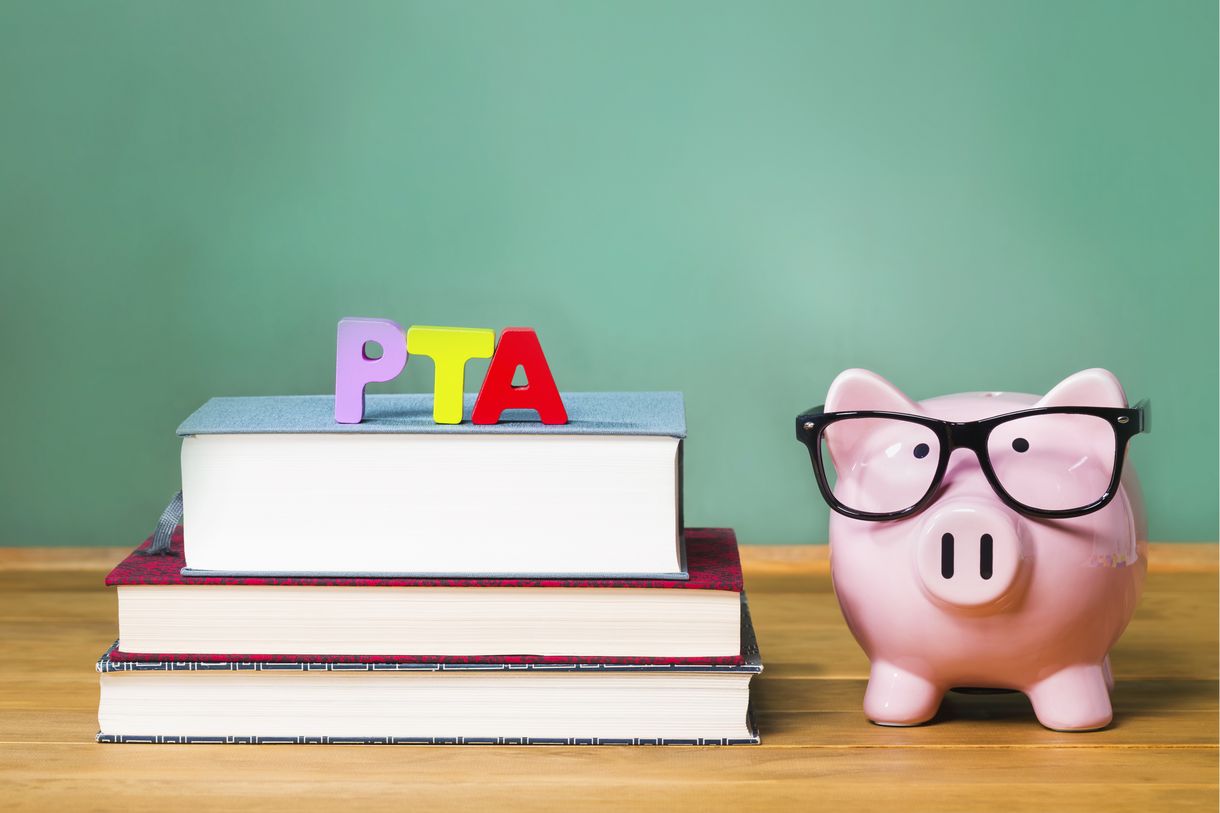 TierneyMJ/shutterstock.com
TierneyMJ/shutterstock.com
まず、任意の組織だということだけは守ってほしいので、早い段階で市から学校に示します。会費を徴収する組織なのに、「気づいたら勝手に会員になっていた」というのは許されません。学校の名簿が自動的にPTAに渡っているのも問題です。
「役員やりたくないんだったらなんでやりたくないか理由を言え。じゃなかったら役員だ」というのも、民主主義の社会としてはあり得ないんですよね。「理由」も昔は「仕事」ぐらいでよかったのが、いまは働く人が多いから、介護だとか、病気だとか、自分のパートナーがこんな事情で大変だとか、そういうすごくプライベートなことまで公の場で言わないといけない。
しかも、さんざん自分のプライバシーをさらした揚げ句、「免除していいと思う人は手を挙げて」という段になったら、「この人が免除されたら自分に回ってくるかも」と思ってみんなだんまりだったという話も聞きました。役員決めのためのじゃんけんやくじ引きも、おかしいですよね。
よく話に聞く、非会員の子どもに「会員じゃないからおまんじゅう配らないぞ」とか「卒業生へのプレゼントはやらないぞ」とか、あるでしょう。「本当に子どものための組織なんですか?」と思いますね。だったらそれぞれ自分の子どもにやってくれって話。「親が会費を払ってないからあげない」という理屈でいうと、受益が全くない学校の先生がお金を払うことが、全く理にかなわなくなります。
◇
【お知らせ】
越田さんをパネリストに招いた「PTAフォーラム ~取り戻そう、自分たちの手に~」が5月18日に開かれます。校長や保護者らによる講演やグループディスカッションのほか、憲法の視点からPTA問題を発信する木村草太さんへの質問コーナーがあります。終了後、懇親会(会費制)も予定しています。詳細は以下の通り。
◇日時 5月18日(土) 午後2時半~6時
◇会場 東京・築地の朝日新聞東京本社2階読者ホール
◇申し込みは「こちら」から。参加費2千円。
◇主催:PTAフォーラム実行委員会 後援:論座、東京すくすく(東京新聞)、朝日新聞#ニュース4U
◇問い合わせ ForumPTA2019@gmail.com
 川西市長の越田謙治郎さん
川西市長の越田謙治郎さん maroke/shutterstock.com
maroke/shutterstock.com 川西市長の越田謙治郎さん
川西市長の越田謙治郎さん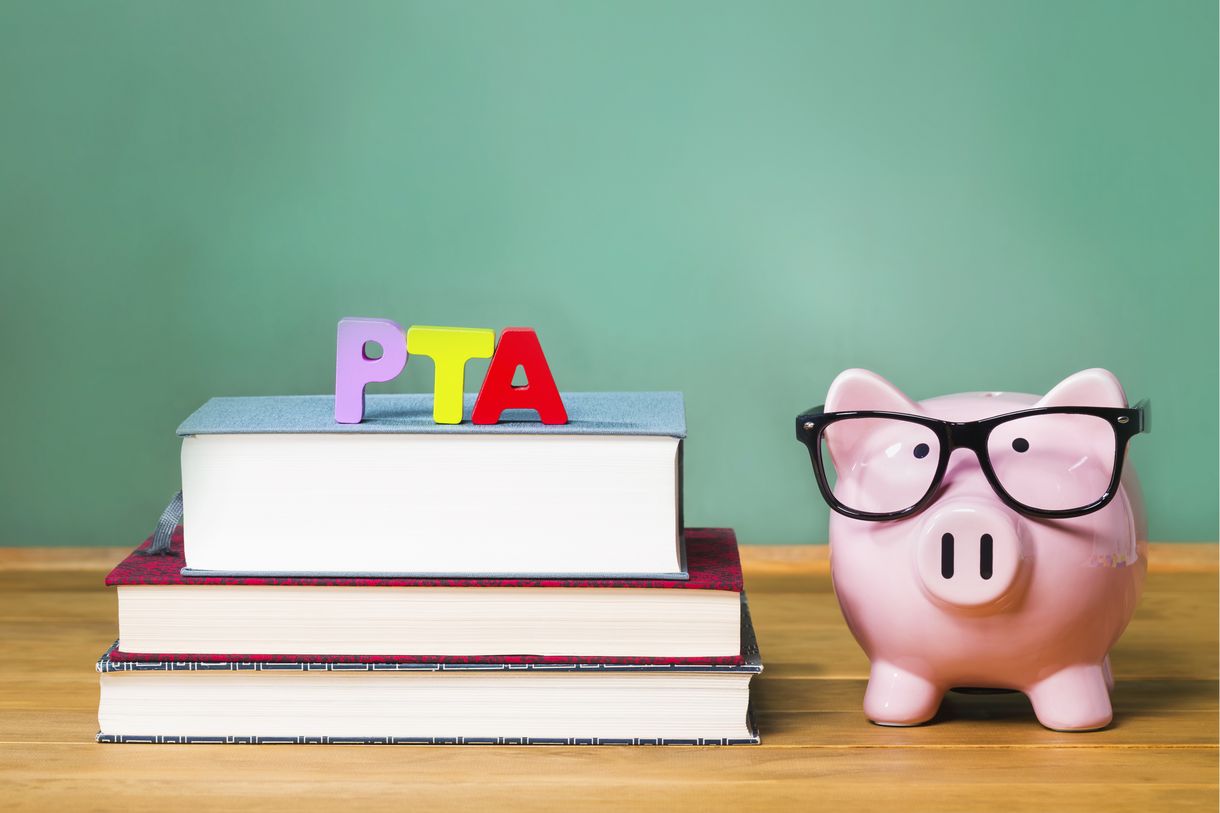 TierneyMJ/shutterstock.com
TierneyMJ/shutterstock.com