2019年10月07日
9月5日(木)15時に南鳥島近海で台風15号が発生した。中心気圧は1002hPa、最大風速は18m/sだった。翌6日(金)になっても6時に1000hPaと20m/s、15時に996hPaと25m/sと、勢力はあまり変わらなかった。しかし、海水温の高い日本近海で勢力が一気に発達した。7日(土)10時に970hPa、35m/s、8日(日)6時に960hPa、40m/s、21時には神津島周辺で955hPa、45m/sと「非常に強い」勢力まで発達した。
そして、9月9日(月)3時頃に三浦半島付近を通過、5時前に千葉市付近に上陸し、水戸付近を通って太平洋に抜けた。千葉市では35.9mの最大風速を記録し、観測史上最大の最大風速や瞬間風速を記録した地域も多い。上陸時は、中心気圧960hPa、最大風速40m/sの「強い」勢力だった。
この台風から得た10個の課題と教訓を以下にまとめてみる。
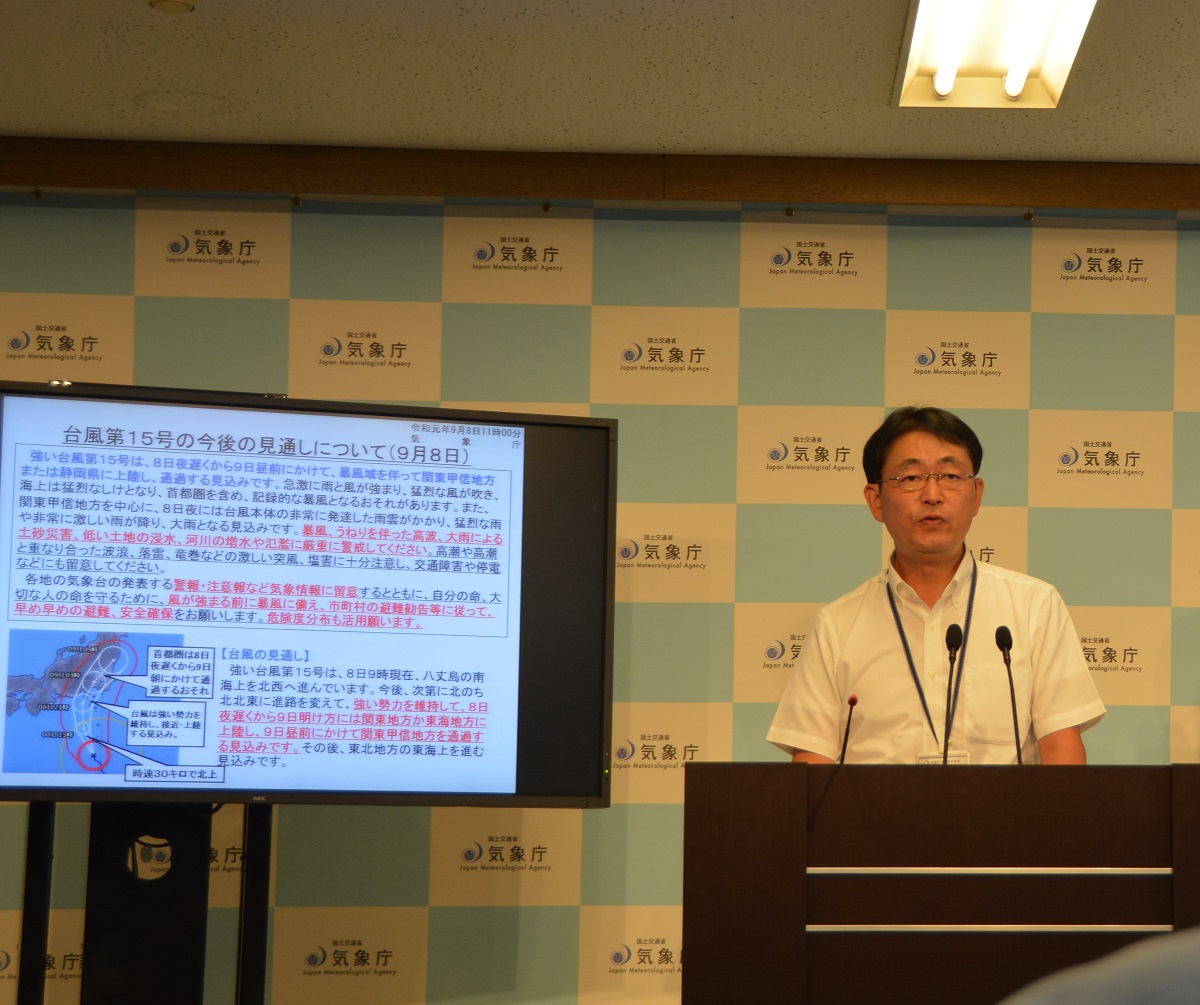 記者会見で警戒を呼びかける気象庁の中村直治予報官=2019年9月8日午前11時5分
記者会見で警戒を呼びかける気象庁の中村直治予報官=2019年9月8日午前11時5分 台風15号はコンパクトで強風域が小さいので、台風が接近するまでは強い風が吹かない。金曜の帰宅時点では、予報円も大きく、首都圏直撃という危機感は、多くの人になかったと想像される。それが、週末になって急に発達した。
気象庁が臨時の記者会見を開いたのは、上陸前日の9月8日(日)の午前11時だった。首都圏を直撃することが確実になり、「首都圏を含めて記録的な暴風になる恐れがある」と、最大限の警戒を呼びかけた。日中での備えを考えれば、ギリギリのタイミングだったと考えられる。日曜の午後に十分な備えができたかどうかがポイントである。そして、日曜の夜から月曜の朝にかけ、いきなりの強風に襲われた。
 JR山手線品川ー大崎間の線路をふさいだ倒木=2019年9月9日
JR山手線品川ー大崎間の線路をふさいだ倒木=2019年9月9日 多数の倒木による鉄道の運転再開が遅れたため、東京都心に本社をおく大会社は、自宅待機の判断をしたところも多く、テレワークの環境整備もあり、月曜の午前中は、都心のオフィスビルはガラガラだったと想像される。
成田空港では、空港の足となる鉄道やバスが運休し、高速道路も通行止めになったため、空港が孤立状態となった。昨年の台風21号で問題となった海上空港の孤立が、高速遠距離交通に頼る陸上空港でも起きてしまった。台風通過後に、国際便の飛行機が続々と着陸したため、当日の夜には1万3千人を超える人が足止めになった。交通機関が途絶えると、乗務員なども空港に来ることができないため、欠航になった出発便もあった。
 孤立した成田空港では、水やクラッカー、寝袋などが配布された=2019年9月9日
孤立した成田空港では、水やクラッカー、寝袋などが配布された=2019年9月9日 千葉県は災害が少なく、東京都心に近い一部地域を除けば、豊かな農村地帯である。このため、県民の生きる力が高く、市町村や県の防災担当は大らかな雰囲気があるようだ。
千葉県庁は、県域の西北端の千葉市にあり、災害慣れしていなかったこともあってか、市町村の被害報告を待つ形になった。千葉県の市町村数は54と多く、県のプッシュ型支援には限界もある。情報・通信が途絶した市町村からは連絡が入らず、9日に東京電力が示した停電復旧見込みが11日だったこともあり、事態の深刻さに気付くのが遅れた。
県の状況把握が遅れた結果、メディアも含め、9日の段階では大きな被害が出たとの認識は
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください