「宮崎・早野論文」は何が問題だったのか
2019年10月18日
2018年12月、福島県伊達市の住民に対して行われた外部被曝線量に関する市町村の業務の一環としての公衆衛生活動の結果公表に不正があったと、いくつかの大手メディアが一斉に報じました。
これは2016年および2017年に、英文医学雑誌『Journal of Radiological Protection』から発表された福島県伊達市の地域住民の外部被曝線量に関する2編の査読論文が研究参加の同意のない住民のデータを含んだ上、不正による誤りがあったという情報に基づいて行われた報道でした。論文の筆者は東京大学の早野龍五名誉教授と福島県立医科大学の宮崎真講師で、メディアでは「宮崎・早野論文」とも呼ばれています。
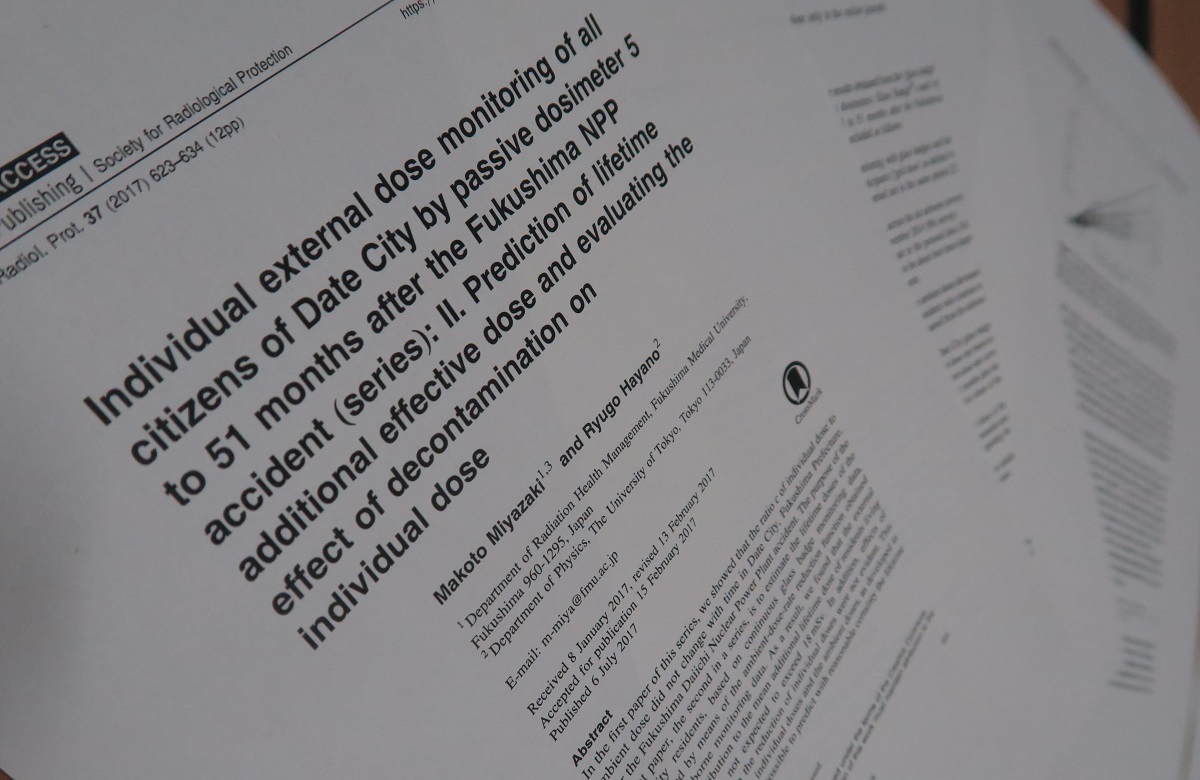 「宮崎・早野第2論文」
「宮崎・早野第2論文」なお、最初に断りを入れておきますが、論文の著者らの計算の誤りが被曝線量の過小評価であると問題視する声があります。しかし、調査委員会が指摘しているように、個人的には論文の主たる結論に変化を生じさせるような大きな誤りではないと考えているため、今回これを議論するつもりはありません。
後から見れば、本件に関してメディアは報道内容の検証が不十分なまま報道したことになります。その報道が地域住民や福島第一原発事故後の放射線被曝を心配する国民に与えた影響は小さくありません。このように日本では、科学に対するジャーナリズムの質が低いと言わざるを得ない出来事がしばしば起きてしまっています。ではなぜこのようなことが起こってしまうのでしょうか。
私は福島第一原発事故後に福島県浜通り地区で除染作業員の健康問題や風評について研究しながら、外科診療に従事する医師です。この問題について、先日、我々の意見をまとめた短報を英オックスフォード大学出版局が発行する医学誌『QJM』で発表しました。ここで私たちは、災害時の公益性の高い公衆衛生活動と研究活動の間に明確な境界を設けることが、住民の健康を守るという優先すべき課題にとって障壁となりうることに言及しました。
今回は、少しとっつきづらい問題ではありますが、この問題の背景にある、地方自治体が行う公益性の高い公衆衛生活動と研究倫理に関して論説したいと思います。この問題の根底ある、倫理の問題は医学の世界でも大変難しいとされているものです。私自身もそうですが、医学生時代に医療倫理について学び、その底の深さと難しさに辟易とした医師も少なくないと思います。
特に今回の件を難しくしているのが、災害時の地域住民の健康データの取り扱いという非常に公益性が高いものが題材となっている点です。
ご存知の通り、災害時には情報が錯綜し、非常に混乱します。東日本大震災の時に多くの誤った情報がメディアやSNSで流布したことはみなさんの記憶に新しいと思います。そういった状況の中で、災害を被った地方自治体はリアルタイムで情報を集め、その情報を取捨選択の上、最終的には情報を統合し、地域住民を守るために災害対策を継続的に行っていく必要があります。
 避難地域の住民を対象に行われた健康診断=2012年1月14日、福島県伊達市
避難地域の住民を対象に行われた健康診断=2012年1月14日、福島県伊達市 また、災害時の地域住民の健康データは地方自治体が適切な対策を立てるために必要であると同時に、研究データとしての性格も有します。とはいえ、こうしたデータの取りまとめ自体は地方自治体が住民の健康を守るために行わなければならない、いわば公衆衛生上の〝業務〟であり、一般的な研究とは一線を画すものです。
一方で、災害時に地域住民の健康データを公表する場合、それは地域住民の健康を守るための行為であるにもかかわらず、「データの目的外使用だから、地域住民への研究参加の個別同意が必要だ」という研究の視点からの考えもあり
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください