測定できないリスクには、“ベストシナリオ”より最大限の警戒であたる
2020年03月05日
新型コロナウイルスの市中感染リスクが高まり、2月下旬以降、雪崩を打ったようにイベント中止やテレワークの動きが広がっている。突然の学校休校も追い打ちをかけ、日本全土に不安が広がっているが、一方で、1月の段階で対策を取った企業もある。
 Casa nayafana/shutterstock.com
Casa nayafana/shutterstock.comソフトウエア開発とデザインを手掛けるフェンリル(大阪市)は1月29日、2月に予定していた7つのイベントを全て中止・延期すると発表した。大阪、名古屋、東京など全国にまたがり、小さいものは30人規模で、最大で100人規模。既にホテルの会場を予約していたものもあった。
イベント中止による金銭的損失は、会場キャンセル料の約7万4000円。数週間前だったため、会場費の30%ほどで済んだ。登壇を依頼していたゲストには、「こんな時期ですしね」と理解してもらえたという。
アプリケーション・ウェブ共同開発部の田林徹也部長は、「イベントの開催でウイルスを広めてしまったら、取返しがつかないと思いました」と振り返る。イベントを担当する事業部に自身の考えを伝え、話し合った末に、新型肺炎の感染リスクがなくなるまで延期することでまとまったという。
当時は、武漢からチャーター機で帰国した人から感染者が出ていたが、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の問題はまだ顕在化しておらず、市中感染も報じられていなかった。ほとんどのイベントは通常通り、マスク着用やアルコール消毒剤の設置もなく行われていた。
広報の藤本陽子さんは、平常モードの1月に中止を決めた理由について、「当社は中国の大連と成都に開発拠点があり、国外の情報も参考に判断しました」と話す。
日本は通常運行でも、中国は市民の外出や企業の操業も制限された。同社は大連と成都の業務再開やテレワークの体制構築を進める中で、新型肺炎の脅威を身近に感じたという。
「今の状況を見ると、早々と方向性を決定してよかったと思います」と田林部長は語った。
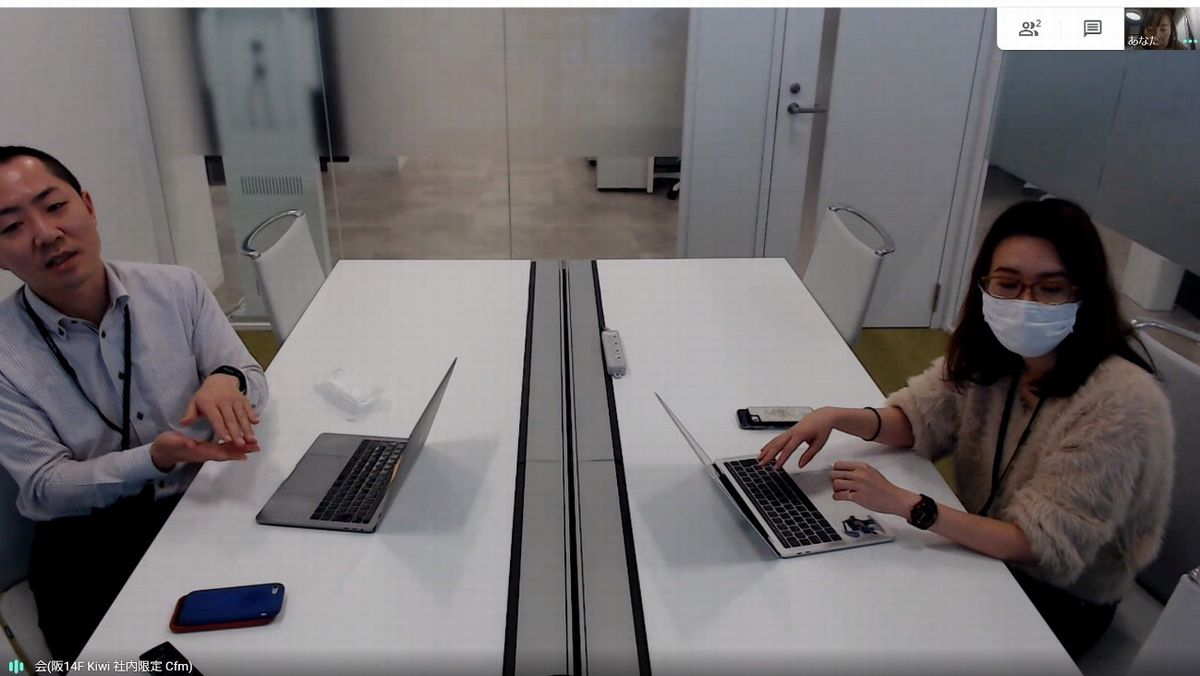 ウェブ会議システムで取材に応じるフェンリルの田林部長(左)と藤本陽子さん=2020年2月27日、筆者撮影
ウェブ会議システムで取材に応じるフェンリルの田林部長(左)と藤本陽子さん=2020年2月27日、筆者撮影「測定できないリスクに対しては、ベストシナリオを考える必要はなく、最大限の警戒であたるべきです」
そう話すのは、オーディオブックを配信するオトバンクの久保田裕也社長だ。同社は従来から「出社自由」だったが、1月27日に原則として「全社テレワーク」に切り替えた。
久保田社長は1月下旬、出張でオーストラリアを訪れた際に、周囲にいた中国人の会話から、新型肺炎の深刻さを感じ取った。
中国は当時、武漢市が封鎖された直後で、感染が他都市に飛び火しつつあった。中国人の切迫した雰囲気に自分でも情報を集め、「どうなるか読み切れない。最大限の警戒をする必要がある」と感じ、26日に全社員に「午前7時から午前10時まで全従業員が電車通勤回避」「不要な出社を控え、基本的に在宅勤務を実施」と通知、非常時モードに入るよう求めた。
同社はオーディオブックを制作しており、社員は収録のために社内のスタジオを使うこともある。もし午前中に作業をしたいなら、朝のラッシュを避けて7時前に出社し、その日は午後3時までに退社するルールだ。受付には1月時点でアルコール消毒液とサージカルマスクを設置した。
非常時モードに切り替えて1カ月が過ぎた。久保田社長も今はオンラインで大半の業務をこなしている。
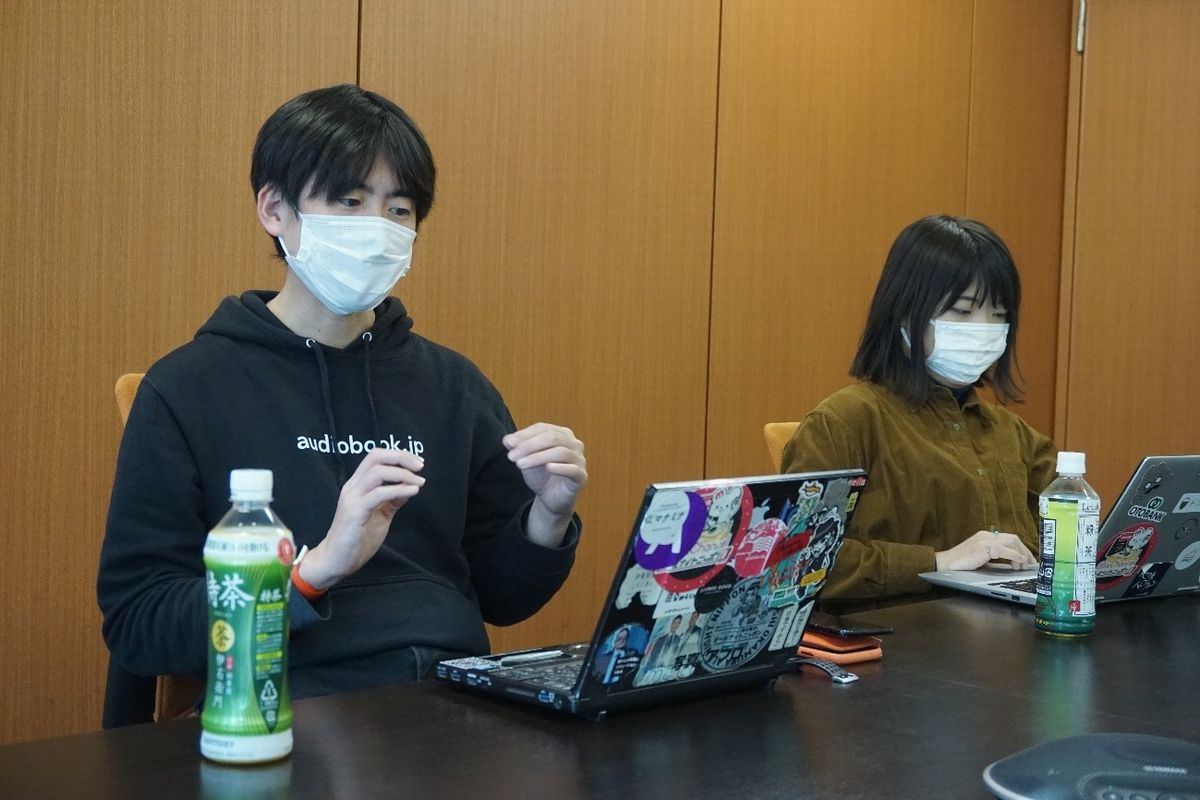 インタビューに応えるオトバンクの久保田社長(左)=2020年2月19日、筆者撮影
インタビューに応えるオトバンクの久保田社長(左)=2020年2月19日、筆者撮影
中国を視察した世界保健機関(WHO)の報告によると、集団感染の75~85%が家族感染で、家族の誰かがウイルスを家庭に持ち込み、一家に広がる傾向が鮮明となっている。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください