「自由」の中で不自由な子どもたち
2020年05月12日
時間がまったく動かない、と僕はいら立ちながら考えた。家畜がそうであるように、時間もまた、人間の厳しい監督なしでは動こうとしないのだ。時間は馬や羊のように、大人の号令なしでは一歩も動かない。
この少年の言葉を読んで、あなたは何を思っただろうか。
実はこれ、大江健三郎の短編小説『芽むしり仔撃ち』からの一節だ。戦時中、感化院に保護された「不良少年」たちが集団疎開する物語だ。
子どもたちが到着してまもなく、山奥の疎開先の村は疫病に襲われ、村人たちは突然、ひっそりと村を捨てて出ていく。自分たちをまるで動物のように扱う村人の監視から急に解放され、戸惑う子どもたち。経験したことのない「自由」の中で不自由な彼らの姿は、どこかコロナ支配下の日本の子どもたちと重なって見える。
あなたの周りにも、そんな子どもがいないだろうか。
私の暮らす高知県土佐町でも3月にコロナで学校が閉鎖された。家で暇をもてあそぶ中1と小5の娘たちを見て、私は我が家の教育を大いに反省した。コロナ休校が始まった当初、まるで一日一日を「消化」するように過ごす娘たちに、私はやるせない想いがした。「せっかく」学校がないのだから、家の裏にある川に遊びに行っても良いし、本を読んでも良いし、好きなことをやれば良いのに。
同時に、日本の教育に対してもこれまで以上の危機感を抱くようになった。友人の話やネットには、家でだらだらしたりゲームばかりしている子どもの姿があふれていた。
 高知県土佐町の夕暮れ(筆者撮影)
高知県土佐町の夕暮れ(筆者撮影)日本における貧困問題に長年取り組んできた稲葉剛は、新型コロナウィルスの感染拡大が、新自由主義追求の果てにできた今日の「危機に弱い社会」を露呈したと指摘する(『「危機に弱い社会」を作ってきた。新型コロナと新自由主義の帰結。稲葉剛さんインタビュー』)。
コロナによる経営悪化で、「使い捨て労働者」化した派遣社員はいとも簡単に職を失い、働き口を失った多くの大学生は高騰する学費を払えないと退学を覚悟し、住むところを失った「ネットカフェ難民」たちは露頭にさまようことになった(こちら参照)。
しかし、コロナ危機で試されたのは医療や経済、福祉体制だけではない。教育も同じだ。
社会の様々な機能が麻痺し、突然学校が閉鎖された時、子どもたちがこれまで受けてきた教育はどのような力を発揮したのだろうか。
もし、「大人の号令」なしでは学ぶことができず、やりたいことも見つけられない子どもがあなたの周りにいたとしたら、それこそがこれまでの教育の「成果」と言わざるを得ない。
しかし、そのような教育はなにも今に始まったことではない。
2018年にちょうど100歳で亡くなった教育哲学者の大田堯によれば、「教育」という言葉はもともと日本語にはなく、開国時に西洋から入ってきた「エデュケーション」の誤訳であり、その悪影響は今日の教育にも及んでいる。
ラテン語の語源には、そもそも「教える」という要素はなく、代わりにあるのは、「養う」や「引き出す」という意味だ。それが、教えるという「上にある者が下の者に施す」との字源をもつ要素とすり替わったことが、従来の講義中心型の授業スタイルと日本の学生の学びに対する受け身な姿勢に繋がっていると大田は指摘する。
しかし、そのような教育を受けてきた人間では世界市場で役に立たないことがわかっているからこそ、国は「アクティブラーニング」(今は「主体的・対話的で深い学び」と言っているが…)への転換を打ち出してきたのだろう。
今、コロナ休校に対して教育現場はどのように対応したら良いか、活発な議論が交わされているが、正直どれも私にはピンとこない。「学びを止めない!」という反論のしようのない空っぽなスローガンの下、オンライン授業や宿題によって学びを提供すべきと主張する者もいるが、問うべきはこれまでの「学び」そのものだろう。
人に魚を与えればその人は一日生き延びることができるが、人に魚の釣り方を教えればその人は一生生きていくことができる、という中国のことわざを思い出す。魚を与えるか、釣り方を教えるか…。もちろん、オンライン授業では学び方を教えられないというわけではない。ただ、学びの本質を変えずに媒体だけ変えて上から施しても意味がないということだ。
また、夏休みや冬休みを潰して授業時間を確保しようと主張する者もいるが、せっかく多くの子どもたちが学校再開を楽しみにしているのに、そんなことをしたら逆に勉強嫌い、学校嫌いの子どもたちを大量生産してしまう。
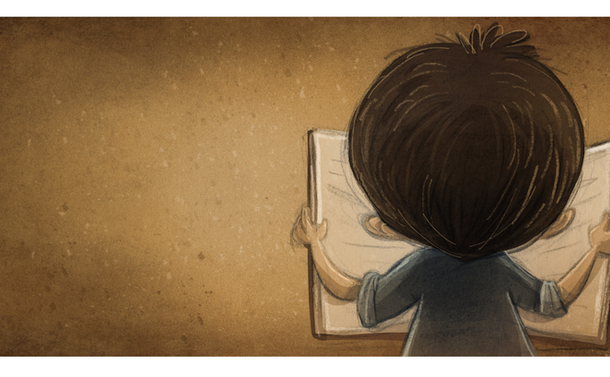 oriol san julian/Shutterstock.com
oriol san julian/Shutterstock.com9月入学制度という意見も出てきている。
「どうしたら子どもたちが自ら学ぶ力を育めるか?」「どうしたら彼らと学ぶ喜びを分かち合えるのか?」
コロナで多くの学校が閉鎖されたこの機会に教育関係者らがこれらの問いと向き合い、9月に仕切り直すということなら良いが、単に時期をずらして従来の教育をやったところで意味はない。
いずれにしても、制度や方法を語る前にそれを支える価値観を論じないから教育の本質が見えてこない。
そうは言っても、休校していない地域としている地域とでは学力格差が開いてしまう、との懸念もある。しかし、そもそも、休校中だからといって子どもたちは本当に学んでいないのだろうか?
千葉県で中学校の校長をしている私の恩師は、子どもは放って置けおけと言う。言われる通りにした私は、コロナ休校が長引くに連れ、娘たちの変化を目の当たりにした。
あまりにも暇な娘たちは、人に本を借りるようになり、休み中にたくさんの本を読んだ。絵もたくさん描いた。遠方の友達に手紙を書き、返事を楽しみに待つようになった。料理やお菓子作りにも挑戦した。山菜に興味を持ち、散歩の途中で見つけたフキなどを持ち帰るようになった。
 ネギを植える娘たち(筆者撮影)
ネギを植える娘たち(筆者撮影)
 川で遊ぶ娘たち(筆者撮影)
川で遊ぶ娘たち(筆者撮影)また、最初は無気力に暇を持て余していた地元の中高生たちが、農家の田植えを手伝うようになり、メキメキと力をつけていく姿も私は見ている。
都会のあらゆる機能がコロナで麻痺している間も、山村ではいつも通り山菜が育ち、農家も自然のサイクルに身を委ねて生きている。そんな中で、最初は時間を「消化」するだけだった子どもたちも、少しずつ時間を「飼いならす」ことを学んでいるように私には見える。
 農作業に挑戦する地元の中高生(筆者撮影)
農作業に挑戦する地元の中高生(筆者撮影) 農作業に挑戦する地元の中高生(筆者撮影)
農作業に挑戦する地元の中高生(筆者撮影)「そのようなことは受験で役に立たない」と切り捨てる人もいるかと思う。しかし、机上の「学力」しか評価できない受験制度にこそ問題があるのではないだろうか。(「学力」論については『AI・非常勤講師任せの「負け組」教育』でも書いているので参考にして欲しい)
AIの時代に企業が求めているのは自ら考え、豊かな想像力とあきらめない精神力を持つ人間ではないのか。そして、そのような人間を、今日の受験制度は評価できているのだろうか。急に受験制度を変えられないというのなら、とりあえず今年は「学力」格差が出ないように受験範囲を狭めれば良いだけのことだ。
「田舎では子どもたちが外でも安全に遊べるかもしれないけど都会ではムリ」と思う人もいるだろう。しかし、子どもの権利という視点から考えれば、子どもが外でのびのびと遊べる環境を整備することは自治体の当然の責任であるし、コロナ支配下で在宅リモートワークが一気に進んだ今、都会一極集中型の社会そのものを見直す良い時期でもあるのではないだろうか。
日本の教育の呪縛から解き放たれなければならないのは、親も同じだ。子どもが暇をしていると、「何かさせなくちゃ」と思い、いろんな勉強や習い事を与えるのが「教育熱心な良い親」で、子どもを放って置くような親は「子どもに関心のない悪い親」だと思いこまされてはいないだろうか。
放っておかれる子どもは、生きるために必然的に学ぶ。何も与えなければ、子どもは何かやることを見つける。子どもがゲームばかりするのが気に食わなかったら、親がゲームを与えなければ良いだけのこと。必要に迫られれば、料理だって洗濯だって自分でするようになる。
不自由の中で、子どもは生きることを学ぶのだ。
もちろん、私の恩師が言う「子どもを放って置く」こととネグレクトとは違う。愛情をもって子どもを放って置くのだ。それが許され、放って置かれた子どもたちは、その安全と成長を地域に見守られる、そんな寛容な社会であって欲しいと心から願う。
親は子どもを信じて、自分が命を燃やす背中を見せればいい。家の中で子どものことばかり気にするからお互いにストレスが溜まるのだ。そして、子どもの幸せを願うよりも先に「勝ち組」に入れることを意識するから不安になるのだ。親は、好きなことや、やるべきことに全力を尽くし、生きるとはこういうことだと見せればいい。
そして、寝る前に子どもと語り合いたいものだ。
「ああ、今日も頑張って生きた。おまえにとって、今日はどんな一日だった?」
 土佐町の棚田に沈む夕日(筆者撮影)
土佐町の棚田に沈む夕日(筆者撮影)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください