信頼回復の切り札「取材プロセスの可視化」の功罪を考える
2020年07月15日
報道に対する読者・視聴者の信頼を取り戻すには、どんな方法が有効か。それについては多くの人がそれぞれに考えをめぐらせ、あちこちで論考を発表したり、実践に踏み出したりしている。「取材プロセスの可視化」はその1つであり、筆者も有効な手立てだと考えている。ただし、一歩間違うと、取材プロセスの可視化は取材と報道の命脈を絶ちかねない。
 SvetaZi/Shutterstock.com
SvetaZi/Shutterstock.com取材プロセスの可視化には、大別して2通りある。「ケース1」は、記事中で可能な限り取材源を明示する方法だ。事件報道を例にすれば、以下のようなスタイルである。もちろん、全くの空想記事である。
【従来型】
札幌大通署は2日、傷害の疑いで、札幌市中央区大通の公務員、山田太郎容疑者(40)を逮捕した。調べによると、山田容疑者は1日夜、札幌・ススキノの飲食店で、店員の態度が悪いと腹を立て、店員の顔を殴る蹴るなどして3カ月の大けがを負わせた疑いを持たれている。同署によると、山田容疑者は「カッとしてやった」と供述し、容疑を認めているという。
【可視化型】
札幌大通署は2日、傷害の疑いで、札幌市中央区大通の公務員、山田太郎容疑者(40)を逮捕したと同日夕に発表した。道警記者クラブ所属の各社に限って配布された「報道メモ」によると、山田容疑者は1日夜、札幌・ススキノの飲食店で、店員の態度が悪いと腹を立て、店員の顔を殴る蹴るなどして3カ月の大けがを負わせた疑いがあるという。同署広報担当の鈴木三郎副署長によると、山田容疑者は「カッとしてやった」と供述し、容疑を認めているという。しかし、本紙は容疑者本人や当番弁護士に接触できておらず、道警側の発表内容や容疑者の「カッとしてやった」という供述内容が事実かどうか、現時点では確認できてない。
報道の端緒が何であったか、報道側が事実をどこまで確認できているか。「従来型」では隠れていた取材行為が「可視化型」では見えてくる。この程度の可視化なら、すぐに実行できそうな感じである。
ただし、「可視化型」は当然、文字量が増える。短い文章が好まれるスマホ時代において、「可視化型」記事のスタイルが良いか悪いかは意見が分かれるだろう。文字の分量や丁寧すぎる説明に「うっとうしい」と感じる読者も多いはずだ。
それでも、取材がどのように行われたかを示し、組織名の陰に隠れた当局者の個人名を明示することは、歴史を記録するというジャーナリズムの役割から言っても無意味ではない。第三者による記事の検証も今よりは容易になる。
では、政治記事ではどんな想定が可能だろうか。これも空想記事で示してみよう。
【従来型】
懸案の日米経済交渉に関し、政府関係者は2日夜、このままでは妥結は難しく、日米関係は大きな曲がり角に立つとの認識を示し、「責任は米国にある」との見解を明らかにした、3日後に迫った日米首脳会談に向け、最大級の言葉で米国の対日姿勢に懸念を示した形だ。
【可視化型】
懸案の日米経済交渉に関し、匿名を希望する政府関係者は2日夜、首相官邸記者クラブ所属の複数の記者と懇談し、このままでは交渉の妥結は難しく、日米関係は大きな曲がり角に立つとの認識をマスコミの力で国民に伝えてほしいとの姿勢を示した。その中で政府関係者は「責任は米国にある」との言葉を用い、3日後に迫った日米首脳会談に向け、最大級の言葉で米国の対日姿勢に懸念を示したいとの意思を隠さなかった。
なお、懇談が開かれたのは東京・赤坂の中華料理店であり、記者5人が参加。冒頭、政府関係者は「この場での発言は引用していいが、私の名前は明らかにしないこと」と発言し、記者側も受け入れた。政府関係者は所属先の秘匿を求めていなかったが、本紙は今後も適切な取材を継続できる環境保持が重要と考え、記事で政府関係者の所属先を明らかにしないことにした。この政府関係者は今回の交渉内容を知りうる立場にある。懇談の飲食費は1人約5000円で、各自が支払った。
飲食を伴うオフレコ懇談は頻繁に行われており、そのこと自体は今や国民に隠すほどの事柄でもあるまい。
では、今も時々使用される「政府首脳」「政府高官」などの用語は誰を指しているのか。報道界では、「政府首脳=官房長官」「政府高官=官房副長官」などとされてきた。それが報道界の“常識”でもあった。しかし、そんな習わしをどの程度の国民が知っているだろうか。
取材源の明示がいかに重要であるか、それが記事やメディアの信頼醸成に大切かについては、元共同通信論説副委員長の藤田博司氏(故人)が早くから指摘し、『どうする情報源 報道改革の分水嶺』(リベルタ出版、2010年)で総括的にまとめている。
上に示した「可視化型」の政治(空想)記事は、そうした欠点を少しでも補おうと試みたものだ。実名を引用できない場合でも、工夫の方法はあるはず。さらに言えば、首相の動向も一定程度詳しく公表されているのだから、取材(懇談)が中華料理店で行われたことなどを記載しても、大きな不都合があるとは思えない。
ただし、「ケース1」では重要なことがある。それは、取材・報道の主導権は報道機関側にあるということだ。「何をどこまで書くか、何を秘すか」については、報道機関側が外部のなにもの(あるいは内部の他部署なども含めて)にも左右されず、独立して自主的に判断することに大きな意味がある。
重要なのは「なにものからも独立した判断」が「取材後」に行われる点だ。それが根幹だ。つまり、取材プロセスの可視化を記事上で実施するにしても、取材プロセスそのものには決して外部勢力(時には内部の他部署なども)に手を入れさせないという考え方である。
取材プロセスの可視化に関する「ケース2」とは、どんな形だろうか。それは、記事や番組という成果物が報道される前に、どんな取材をどう実施しているかを内外に発信し、場合によっては外部の“知恵”を取り入れるなどして、成果物の熟度や確度を上げるという考え方だ。SNSの発達と浸透により、この考え方は市民にも受け入れやすくなっていると感じる。
その関連で言えば、非常に気になる記事が過日、朝日新聞に掲載された。7月10日朝刊「メディア私評」欄の寄稿である。筆者は新井紀子氏(国立情報学研究所と総合研究大学院大学の教授)で、記事のタイトルは「新聞の既視感、その正体 データで見えた取材先の偏り」である。
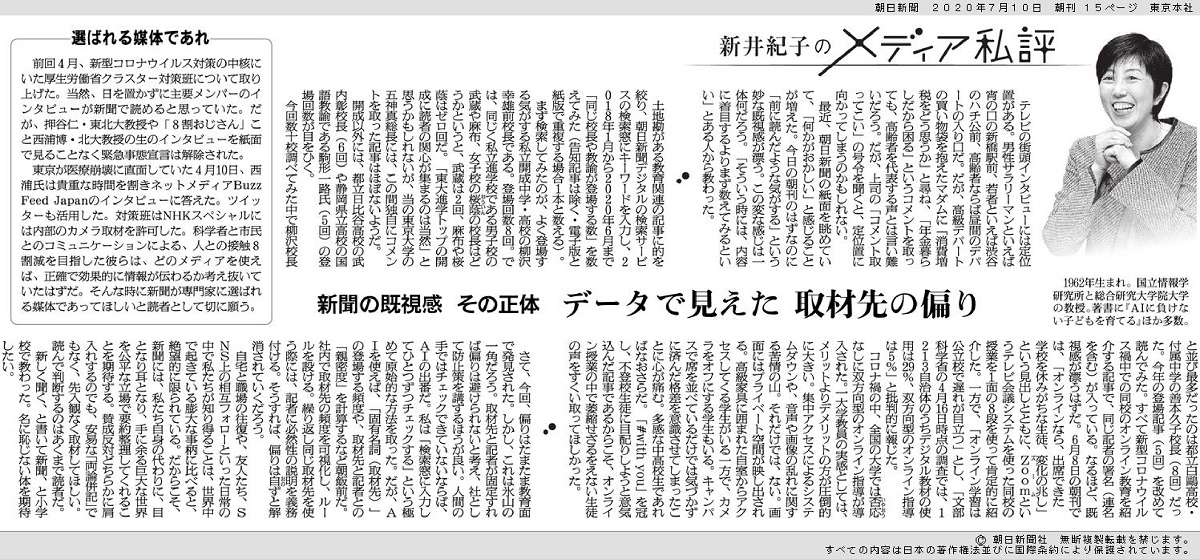
最近、朝日新聞の紙面を眺めていて、「何かがおかしい」と感じることが増えた。今日の朝刊のはずなのに「前に読んだような気がする」という妙な既視感が漂う。この変な感じは一体何だろう。「そういう時には、内容に着目するよりまず数えてみるといい」とある人から教わった。
新井氏はそう記しつつ、教育関連記事に絞って朝日新聞の過去記事を検索し、同じ校長や教諭が紙面に登場する回数を調べたと明かす。その結果、有名高校の校長らが何度も記事に登場しており、明らかに取材先が固定化していると指摘している。
取材先の固定化や偏在については、筆者も全く同意見である。教育面だけでなく、記事全体にその傾向があるとの推論も、その通りだと思う。問題はその先にある。新井氏はAI(人工知能)を使えば、「偏り」を事前にチェックできると指摘し、以下のように記述している。
AIを使えば、「固有名詞(取材先)」の登場する頻度や、取材先と記者との「親密度」を計算するなど朝飯前だ。社内で取材先の頻度を可視化し、ルールを設ける。繰り返し同じ取材先を使う際には、記者に必然性の説明を義務付ける。そうすれば、偏りは自(おの)ずと解消されていくだろう。
正直に言えば、筆者はこの発想に強烈な違和感を覚えた。取材の途中で、あるいは、取材の着手前に、過去の記事に登場する取材先の頻度を可視化して、それぞれの取材先に取材をかけてよいか、報道で使ってよいかなどを社内で「ルール化」せよ、というのだ。何度も取材している取材先であれば、またも取材する理由の説明を義務にすべきだとも言っている。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください