2020年09月19日
昨年の8月から連載を始めた「論座」、今年の3月から7月まではコロナ禍における学校現場の様子や全国の仲間からの声、世の中で話題になっていることへの意見、平常時・緊急時における私の考える学校づくりについて伝えてきた。
「学校の臨時休業があぶり出したことは何か?上/下」「臨時休業から1カ月半、学校は今」「9月入学って、本当にやるんですか?」「いま学校に取り戻さなければならないのは『子どもの楽しみ』だ」「『このままでは学校が危ない!』子どもの笑顔と未来のために考えるべきこと」
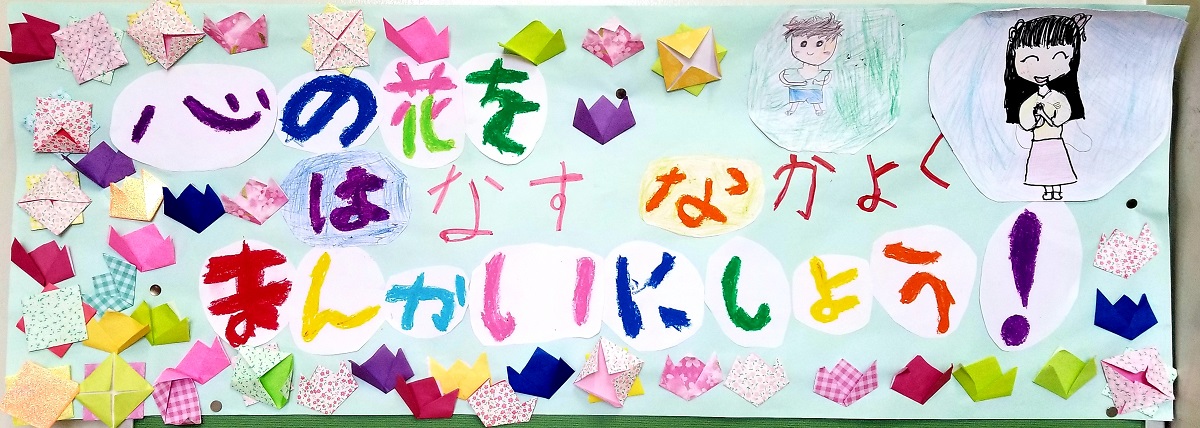 明るく、楽しく生きていこうとしている子どもたち
明るく、楽しく生きていこうとしている子どもたちそして、休校中から学校再開後の見えない圧力やストレス、学校現場の状況を無視した授業時間の確保や学習の遅れを取り戻すことを強いられる日々に疲弊していく子どもと教職員。「もう限界、このままだと倒れる」「イライラして子どもに当たってしまう。子どもの声を聞けなくなってしまった。」「こんな教え込み、詰込み授業をしたいわけではない」「学校現場を知らない人が表面的なことだけ見て決めていることが学校現場を苦しめている」「国は、人と予算を付けて学校現場に任せてほしい。余計なことを言ったり、したりしないでほしい」と、いくつかの自治体の仲間からの悲痛な声。その声に応えて、7月には緊急提言にも近い記事を「論座」に書き、そして、8月21日には、NPO法人「教育改革2020『共育の杜』」のアンケート調査結果公表と提言を行うために文部科学省での記者会見に同席した。
再任用校長の私が重い腰を上げてメディアを通して訴えなければならないほどに、学校現場は疲弊している。その様子は7月の論座記事「このままでは学校が危ない!」に詳しく書いているのでご覧いただきたい。と、ここまでは、教育評論家や専門家等ではなく、現職の校長が発信することに意味があると思ってやってきた。期待通り、反響もあったし、メディアを通して少しは社会に伝わったと思う。とにかく、コロナ禍において学校ではエッセンシャルワーカーである教職員が元気じゃないとこの危機は乗り切れない。国や自治体には、教職員のメンタルヘルス・健康を最優先する施策を考えてほしいし、学校現場でもお願いしたい。その思いは引き続き発信していきたい。
しかし、8月からこの「論座」の原稿を書く手が止まってしまった。それには、いくつかの原因があるが、実は、自分自身かなり無理をしていたのだと思う。
これまでいろいろ書きながら、「こういうことは、自分の学校では起こらないように考えてやっている」「教職員を追い込んだら、子どもためにならない」「教職員の元気が、子どもの元気、学校の元気につながる」「どうしてこんなことをするのだろう」「もっと、やり方を考えないと悪循環に入っていくのに」「優先順位を考えやってほしい」「結局、管理職の問題だなあ」と思うことが多かった。自分が代弁することで、現場の実態を分かってほしいと思うのだが、頭の片隅には、その解決策が常に動き続けていたわけだ。私は、教職員が疲弊しないように、子どもたちが安心して楽しく過ごせるようにと心がけてやってきたので、そちらの方を伝えるのが、本来の自分の在り方だった。それを抑えながら書いてきたので動けなくなってしまったのだと思う。自分を取り戻すことは大事なことだ。ESD(持続可能な開発のための教育)でいつも言っていたこと、「立ち止まって考え、再方向付けすること」が必要だった。
実は、3月、4月とテレビ取材も何度か受けて、放映されたが、その時にも同じような気持だった。学校の大変さを訴え、文部科学省や政府の対応の不十分さをニュースや報道番組で取り上げられたのだが、何か自分の伝えたいことと違った。
学校は大変状況な中、話し合い、工夫し、アイデアを出し合いながらやっている。感染症予防のための対策や準備も、そんなに突き詰めてやるのではなく、最低限のルールは作りながら、子どもが考えて行動できるように働きかけていた。なぜならば、学校は管理や監視の場でなく、教育の
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください