未経験の副作用発生の可能性。接種するかどうかを自分で決める自己決定権が大切
2020年11月10日
政府は10月27日、新型コロナウイルス感染症のワクチンを確保し、接種を進めるための「予防接種法改正案」を閣議決定し、国会に提出した。
政府はすでに、来年前半までにワクチンを国民全員に提供できる数量の確保をめざし、英米の3社と基本契約などを結んでおり、長引くコロナ禍に苦しむ人たちにワクチンへの期待が高まっているようだ。
しかし、ことはそれほど簡単ではない。
新型コロナワクチンの開発は異例のスピードで進められており、安全性も有効性も十分には確認されていない。しかも政府が購入を予定しているワクチンは従来にない新しいタイプのもので、これまで経験したことのないような副反応(副作用)が発生する可能性がある。
開発の実態を知った研究者やジャーナリストからは、「新型コロナの感染による被害より、ワクチンの副作用による被害の方が大きくなる可能性がある」という指摘が相次いでいる。]
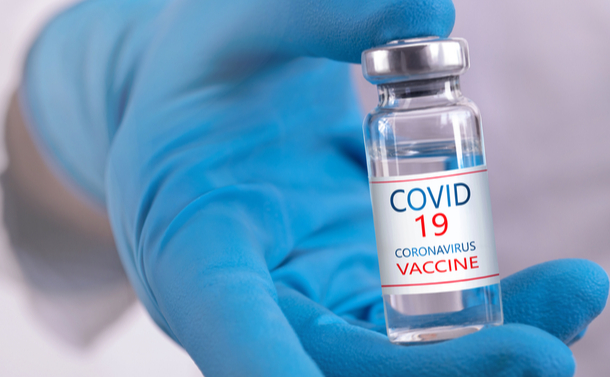 PalSand/shutterstock.com
PalSand/shutterstock.com予防接種法改正案の主な内容は、①国が買い上げたワクチンは接種費用を無料とし、個人や自治体に負担は求めない、②接種後に重い副作用による被害が出る場合に備え、患者の救済措置を整えるとともに、ワクチンメーカーが払う損害賠償金を政府が補償する契約を結べるようにする、③接種は国民の努力義務とするが、有効性や安全性が十分に確認できない場合は努力義務を適用しない――というものだ。
この改正案が成立すれば、ワクチン接種の法的枠組みが整うことになる。
厚生労働省は、開発の最終段階である「第3相臨床試験」に進んでいるワクチンの確保に動いており、米ファイザー社および英アストラゼネカ社と、開発が成功した場合それぞれ1億2000万回分の供給を受けることで基本合意している。
さらに10月29日、米モデルナ社から5000万回分の供給を受ける契約を結んだと発表した。
世界ではワクチンの開発競争が激しくなっており、ロシア政府は8月、国産第1号のワクチンを第3相試験前に承認・実用化した。また中国政府は国産ワクチンを第3相試験と並行して医療従事者などに緊急投与し、年内の実用化をめざしている。
日本国内では数社が開発中で、このうち創薬ベンチャー企業のアンジェスのワクチンは第1・2相試験を始めている。
以上六つのワクチンについて、製造企業・種類・接種回数をまとめておこう(ワクチンの種類については後に説明する)。
米・ファイザー=RNAワクチン、2回接種
英・アストラゼネカ=ウイルスベクターワクチン、1~2回接種
米・モデルナ=RNAワクチン、2回接種
ロシア・ガマレヤ研究所=ウイルスベクターワクチン、2回接種
中国・シノファーム=不活化ワクチン、2回接種
日・アンジェス=DNAワクチン、2回接種
開発が進む新型コロナワクチンについて、多くの研究者や医師が危険性を訴えているのはなぜだろうか。
第一の理由は、安全性の確認が不十分なことだ。
健康な人に接種するワクチンは治療薬より高い安全性・有効性が求められており、基礎研究・動物実験で安全性を確認した後、3段階の臨床試験(治験)をそれぞれ半年~1年かけて実施するのが普通だ。対象人員が少数の第1相試験、数十人以上の第2相試験、数千~数万規模の第3相試験だ。
「安全性の確認には少なくとも数年はかかる。とくに小児や妊婦に対する安全性の確認は難しい」と大島真・徳島大学名誉教授は言う。
ところが新型コロナの場合は、開発開始から1年足らずで承認されようとしている。米国をはじめとする先進国政府が多額の予算をつけ、必要な審査を短縮して開発を急がせているからだ。
日本政府も多額の予算をつけ、基礎研究と動物実験、治験を並行して進めることを認めている。これは、安全性も有効性もほとんど確認されないまま人間に接種して確認することを意味する。いわば治験参加者を使った人体実験だ。
また、ワクチンは人種によって差があるとされる免疫に作用するものだから、日本人での臨床試験が必須だが、新型コロナでは、海外で承認を得た医薬品について、国内での審査なしに承認する「特例承認」を認めている。
このような拙速な開発・承認には、ワクチンは必要と考える宮坂昌之・大阪大学招聘教授らからも「危険だ」との指摘が出ている。
 StaniG/shutterstock.ciom
StaniG/shutterstock.ciomワクチンは人類の健康を守るうえで大きな役割を果たしてきた一方、重篤な副作用を生んできた。なかでも心配なのは、ワクチンを打つことでかえって感染を全身に広げてしまう「抗体依存性感染増強(ADE)」だ。
ワクチンを打つと多くの場合、病原体(抗原)を攻撃する「抗体」(善玉抗体)がつくられる。だが、ときに逆の作用をする抗体(悪玉抗体)がつくられ、感染した免疫細胞が暴走して症状を悪化させることがある。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください