貸付が中心の政府の対応には限界。生活保護の利用も増えず。国は手厚い支援に乗り出せ
2021年01月10日
工場で派遣社員として働いてきた20代の男性Aさんは、新型コロナ禍の影響で昨年12月初めに雇い止めに遭い、寮を出ざるをえなくなった。友人宅やインターネットカフェで寝泊まりしていたが、職探しがうまくいかず、所持金が2000円になり、昨年の大みそか、たまらず東京・池袋の公園に出かけた。
そこでは市民団体の「新型コロナ災害緊急アクション」などが「年越し大人食堂」を開いていた。立ち寄った人たちの相談に応じ、食料品を配布する。住まいのない人は、東京都が一時宿泊先として確保したビジネスホテルに案内するといった支援をしていた。Aさんは年末年始を無事に超すめどがついた。
いまこの国では、Aさんのように「いつ路上生活に陥ってもおかしくない人。厳しい寒波の中で命を落としてもおかしくない人」が増えている。政府の緊急事態宣言再発動を受け、飲食業の営業時間短縮などが実施されれば、さらに増えるだろう。
しかし、生活困窮者に対する政府の支援はきわめてわずかだ。菅義偉首相のいう「公助」はまったく足りない。
 市民団体がひらいた困窮者支援の相談会でストーブにあたって食料の配布を待つ人たち=2020年12月31日午後、東京都豊島区の東池袋中央公園
市民団体がひらいた困窮者支援の相談会でストーブにあたって食料の配布を待つ人たち=2020年12月31日午後、東京都豊島区の東池袋中央公園新型コロナ災害緊急アクションは、新型コロナウイルスの感染が拡大した昨年3月、貧困問題などに取り組む30余りの団体が立ち上げた。「反貧困緊急ささえあい基金」を創設して寄付を募り。4月から「駆けつけ型の緊急支援」を始めた。
困っている人からのSOSが電話やネットで届くと、事務局長の瀬戸大作さんらスタッフが自動車で駆けつけ、事情を聞いて、携帯電話代や宿泊費など一時的な生活資金を手渡す。必要ならば、生活保護申請に同行し、保護を受けられるように手伝う。
12月末までに1億円近い寄付が寄せられ、1000人以上のSOSに対応し、5000万円以上を給付した。
このほか、連携している団体への助成や、施策の改善を求めて中央省庁との交渉もしている。すぐれた「共助」の例だろう。
この活動に参加している作家の雨宮処凛(かりん)氏によれば、SOSを寄せる人たちは多種多様だ(「国から『誰一人、困窮では死なせない』というメッセージを」HUFFPOST 2020年12月23日など)。
たとえば40代の男性Bさんは、20年ほど前の就職氷河期に社会に出た。正規雇用の道がなく、派遣の仕事に就いて以来、そこから抜け出せない。安い給料では民間のアパートに入ることも貯金もできず、派遣期間が切れても十分な求職活動をする余裕がない。このため「寮つき・日払い」の職を続けることになり、全国各地の工場を転々としてきた。
そんな生活を20年間続けてきたBさんは、コロナ禍で路上生活者になり、緊急アクションの支援で生活保護を申請し、自転車操業のような生活から脱出できた。これが「自助」を尽くした結果だ。
こんなSOSもあった。「息子と暮らしているが、2人とも仕事がなくなり、現金も尽き、わずかな米と漬物しかなくなった」(高齢の女性)。「仕事がなく、派遣会社の寮で待機を命じられたが、所持金も食料も尽き、10日以上ほぼ水だけで過ごした」(40代の男性)。「餓死か、自殺か、ホームレスか、刑務所か、迷いました」という人もいれば、ネットカフェで寝泊まりする生活を10年以上続けてきた人もいる。
職種も様々だ。製造派遣、警備、食品工場、居酒屋、コールセンター、風俗などなど。内定を取り消された若者、テレビ番組でAD(アシスタント・ディレクター)の仕事をしていた人もいる。
女性からのSOSも多い。飲食店や宿泊、小売、風俗、キャバクラ、ヨガやジムのインストラクターなど職種は幅広かった。
外国人も大打撃を受けている。とくに技能実習生や留学生の困窮が深刻だ。仕事がなくなった人。帰国したいのにできない人。飛行機のチケット代や帰国までの生活費を稼ぎたいのに、ビザが切れて働けない人も少なくない。
これまで、そんな一人一人の働きがこの社会を支え、私たちの「便利」を作ってくれていたのだが……。
 困窮者支援の相談会には長い列ができていた=2020年12月31日、東京都豊島区の東池袋中央公園
困窮者支援の相談会には長い列ができていた=2020年12月31日、東京都豊島区の東池袋中央公園やはり困窮者支援に取り組んでいる「認定NPO法人もやい」は、昨年4月から緊急体制をとっている。相談業務を充実させ、毎週土曜日に東京・新宿の都庁下で食料品配布と相談会を続けている。
大西連・理事長によれば、寄せられる相談は例年の1.5倍、食料品配布に訪れる人は毎回150人を下回ることはなく、例年の2倍だ(安藤道人・大西連「コロナ禍で生活困窮者への家賃補助と現金貸付が急増」2020年9月13日noteなど)
日雇い、週払いの仕事、派遣、契約社員、パート、アルバイトなど不安定な働き方をしていた人が圧倒的に多い。請負やフリーランス、業務委託など個人事業主として働いていた人からの相談も多い。
リーマン・ショック後(2008年秋以降)は単身男性からの相談が中心だったが、今回は女性も多く、非正規全般に影響が及んでいる。
コロナ禍前は月収20万円前後あり、裕福ではないが、たまには友人と食事をしたり旅行に行ったりしていた人が、急な失業や収入源で途方に暮れる。そんな人が何人もいた。
この国では、働く人の38%が非正規雇用で、その平均年収は179万円だ(2018年、国税庁発表)。なかでも女性は154万円にすぎない。
これでは貯金も難しく、単身所帯の38%が貯蓄ゼロである(金融広報中央委員会の2019年調査)。
そして、非正規の人は雇用の調整弁としてまず切られる。
このような生活困窮者に対して政府はどんな支援をしているか。
コロナ禍での個人や世帯に対する直接的な生活支援としては、2020年度第1次補正予算で総額13兆円が計上された10万円の「特別定額給付金」が注目を集めた。これはコロナ禍で大儲けした人にまで支給される一方、住民登録をしていないホームレスの人たちには支給されない。
生活困窮者支援に関する政府の対応は、既存の制度の要件緩和が中心で、主なものは「総合支援資金」と「緊急小口資金」という生活福祉資金の貸付制度と「住宅確保給付金」だ。企業やその従業員への支援が第2次補正予算で11兆6000億円も用意されたのに比べ、きわめて小規模といえる。
このうち総合支援資金は、生活再建に必要な資金を、2人以上の世帯なら月20万円まで原則3カ月、無利子・無担保で貸す制度だ(3カ月で60万円まで借りられる)。これについて政府はコロナ禍で減収になった人も対象にする特例措置を実施している。
また緊急小口資金は、一時的な資金が必要な人に最大10万円を無利子・無担保で貸す制度で、上限を20万円にするなどの特例措置が取られている。
生活に困った人たちは、利用要件が緩和された二つの貸付に走った。
全国社会福祉協議会(全社協)のまとめでは、総合支援資金の融資決定件数は昨年3月から12月19日までに約52万件、融資金額は約3853億円に達した。これまでの最高だったリーマン・ショック後の2010年度が約4万1000件、262億円だったのに比べ、件数で12倍、金額で14倍になっている。
また緊急小口資金は約86万件、約1581億円だった。いずれも12月になっても一週間当たり8000件程度の申請があり、収まる様子はないという。
一方、住宅確保給付金は、離職者・廃業者を対象とした家賃補助の仕組みで、原則3カ月(最長9カ月)、家賃相当額を自治体から家主に支給する。これについて政府は「休業などで収入が減少した人」に対象を広げ、「ハローワークへの求職申し込みをしないでもよい」などと要件を緩和した。
この結果、利用者が昨年4月以降に急増した。支給額は昨年1~3月が月5500万円程度だったのが、6月には34億円にもなった。
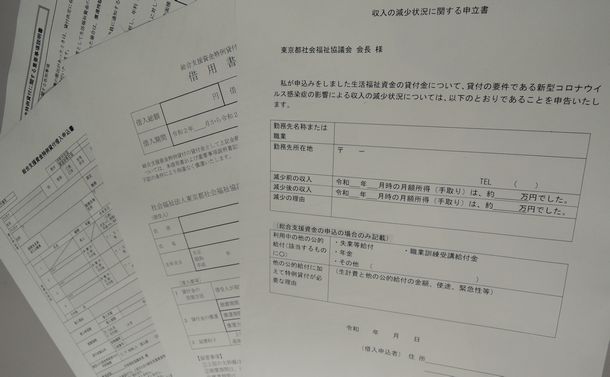 東京都社会福祉協議会が用意した総合支援資金の申請書類。
東京都社会福祉協議会が用意した総合支援資金の申請書類。以上のような政府の対応には問題が少なくない。
問題の第一は、支援の中心が現金給付でなく貸付であることだ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください