取材手法を市民と共有する仕組みをつくろう
2021年01月13日
新聞の発行部数減少が止まらない。日本新聞協会が2020年10月に発表したデータによると、全国の総発行部数は前年比7.9%減、実数にして約272万部も減った。時代の要請にかなっていない以上、新聞「紙」というメディアの衰退は致し方ない。新聞が担っていた取材・報道の役割を社会でどう引き継ぐか。そろそろ、この問題を真剣に検討すべき時期が来たのではないか。
まず、新聞協会の公表数値を見てみよう。
協会加盟の日刊116紙の総発行部数は2020年10月現在、3509万1944部で前年比7.2%減。減り幅は過去最大だ。部数は271万9304部の減少である。スポーツ紙も含んだデータであることなどから単純比較はできないが、日本経済新聞の朝刊が約223万6千部(今年1月、同社公表)、毎日新聞も200万部を少し上回る程度とされているから、計算上はこれらの新聞がわずか1年間で丸々消えてしまったというイメージだ。
全国の12の地区別では、近畿の減少幅が最も大きく8.8%減だった。続いて東京の8.7%減、大阪の8.0%減、関東と九州がともに7.8%減。さらに、四国7.5%減、中国6.4%減、中部6.1%減などの順で並んでいる。1世帯当たりの部数は0.61部になった。ほぼ2世帯に1部しか購読されていない。
地方での夕刊廃止を見ても、「紙」の衰退ぶりが際立つ。2020年には東奥日報(青森県)、山陽新聞(岡山県)、徳島新聞、高知新聞、大分合同新聞といった有力地方紙が夕刊発行を取りやめた。2019年以前にも沖縄タイムスと琉球新報の沖縄2紙、南日本日本新聞(鹿児島県)、中国新聞(広島県)、秋田魁新聞などが夕刊を廃止。全国紙も地方での夕刊をやめるケースが相次ぐ。徳島と高知両新聞の夕刊廃止で、四国は2021年から「夕刊空白区」になっている。
こうした事態は散々予測されてきたことであり、今後も「紙」の衰退は続く。それに伴って各新聞社の経営環境もさらに厳しくなるだろう。
そうは言っても、何かの出来事や時々の話題を取材・報道し、社会に伝えてきたのは新聞(テレビも)であり、その構図は今も続いている。網羅的、系統的、継続的にそれを担う主体としては、日本では新聞以外に確たるものは存在していない。事実確認の方法から用字用語の使用法まで一定程度の訓練を積み、短時間で的確な原稿を仕上げる記者とその集団。事件や事故、災害、議会の動向、首長らの発言、街の話題や風物詩などを継続的にウオッチする組織的な仕組み。豊富な人脈や取材ノウハウの蓄積。それらの多くは新聞社に内包されている。
古い組織体質やステレオタイプの記事など、新聞への批判がやまない現状も存在する。「ジャーナリズムの本旨は権力監視」という基本姿勢をベースに、筆者も厳しい指摘を繰り返してきた。しかし、現在も取材・報道の多くは新聞社が担っている。ネット全盛の時代とはいえ、それもまた事実である。
戦後長らく、「新聞は社会の公器」と言われ、新聞メディアが報道界の中心にあった。この言葉自体は、新聞が戦時の総力戦で翼賛体制の一翼を担うようになった際に盛んに使用されたらしいが、戦後も「社会の公器」としての役割を担ってきたことに異論はあるまい。
この場合の公器とは、新聞「社」ではなく、「紙」に印刷された取材の結果を指す。取材の結果が社会の公器であるならば、取材のノウハウや知恵の蓄積なども当然、社会の共有物としての性格を帯びているはずだ。
他の企業と同様、日本の新聞社も終身雇用制の下にあった。最近は人材の流動化も進んできたが、基本的に朝日新聞の記者はずっと朝日の記者であり、毎日新聞の記者はずっと毎日の記者だった。それに伴い、取材のノウハウや知恵の蓄積はそれぞれの新聞社内に閉じ込められ、他社と共有される機会も決して多くなかった。せいぜい、新聞協会や新聞労連などが主催する研修会やイベントで、難しい取材の成功譚が披露される程度だったと思う。
仮に、である。新聞社の経営が行き詰まったり、さらなる合理化で記者の数が減少を続けたりしたら、どうなるのか。それはつまるところ、新聞社の衰退や記者の離職などと共に、公共的な性格を持つ取材・報道ノウハウの多くが社会から消えてしまいかねないことを意味する。何をどう取材し、どのように伝えるか。その公共的な財産も失ってよいはずはない。
したがって、新聞の衰退がさらに加速している今こそ、取材ノウハウの共有を進める必要があるだろう。
筆者はかつて、日本ジャーナリスト会議(JCJ)やアジア記者クラブ(APC)などの協力を得ながら「調査報道セミナー」という催しを主宰していたことがある。新聞記者時代に調査報道にのめり込んだ筆者は、他者がどのような取材を実行しているのか、それをどうしても知りたくなり、せっかくなら大勢の記者たちと一緒に優れた取材のノウハウを聴き、議論しようと思ったからだ。
初回は2012年3月。東京や京都など場所を変えながら、2016年まで計7回開催した。毎回、50人前後の参加者があり、原発問題や政治資金、過疎化の問題など幅広い分野での取材ノウハウを共有してきた。
 「調査報道セミナー 2013 冬 in 京都」。マイクを握るのは京都新聞の大西祐資記者(現・京都新聞取締役)。この日は福井新聞の記者も登壇するなど、セミナーでは地方紙の調査報道も積極的に取り上げた=2013年2月16日、京都駅前の京都キャンパスプラザ
「調査報道セミナー 2013 冬 in 京都」。マイクを握るのは京都新聞の大西祐資記者(現・京都新聞取締役)。この日は福井新聞の記者も登壇するなど、セミナーでは地方紙の調査報道も積極的に取り上げた=2013年2月16日、京都駅前の京都キャンパスプラザもちろん、同様の試みは他にもある。活動領域の幅広さで言えば、NPO法人・報道実務家フォーラムが一番手だろう。新型コロナウィルスの影響で2020年はオンライン開催だったものの、それまでは早稲田大学を会場として多種多様な講座を実施し、取材ノウハウの共有を進めてきた。参加者には、現場の最前線で仕事する若い記者やディレクターが多い。
社団法人・日本記者クラブも「記者ゼミ」を毎月1回程度の割合で開いている。「調査報道」と「IT」の2講座に分かれ、それぞれの優れた事例を共有する試みだ。内容も非常に濃い(ただし、原則として日本記者クラブ加盟社の構成員でないと参加できない)。このほか、JCJや新聞労連なども随時、似たような場を設けている。
取材者と法曹界の関係者による「ほんとうの裁判公開プロジェクト」という集まりもある。第三者である記者や研究者らが裁判記録を閲覧するには、どうすればいいのか。その法的問題や実践的な手法を毎月の勉強会で積み重ねてきた。同プロジェクトは2020年末、『記者のための裁判記録閲覧ハンドブック』(公益財団法人・新聞通信調査会刊)を一般向けに出版した。執筆者は、会社の枠を超えた多彩な顔ぶれだ。取材ノウハウを広く共有する書物としては、画期的な1冊と言ってよい。
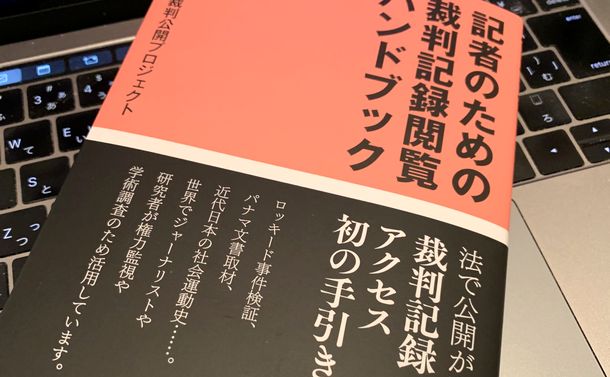 『記者のための裁判記録閲覧ハンドブック』。コンパクトな作りの中に実践例が詰まっている
『記者のための裁判記録閲覧ハンドブック』。コンパクトな作りの中に実践例が詰まっている取材手法の共有は、劣化の際立つ取材力の維持と向上に一定程度、寄与することは間違いないであろう。人材の流動も少なく、会社間の壁が分厚かった報道界において、その壁を乗り越える道にも通じる。
ただし、これらの試みは基本、参加者が「記者」「新聞社員」などに限られている。つまり、報道界の内側に向けての試みである。果たして、それだけでよいのだろうか。「取材のプロ」同士での共有は、新聞の衰退に追いつくのだろうか。
いま、地方紙では「オンデマンド調査報道」が盛んになっている。読者の取材依頼に基づいて記者が取材に動き、その結果を記事にするという試みだ。
皮切りは西日本新聞(福岡県)が2018年に始めた「あなたの特命取材班」(あな特)。LINEなどのSNSツールで読者とつながり、双方向性を維持しながら取材を進める仕組みだ。「あな特」は読者の関心を呼び、同様の枠組みを設ける地方紙が多数現われた。今では、北海道から沖縄まで25の地方紙が集結し、オンデマンド調査報道の「JODパートナーシップ」を結んでいる。参加紙の間では、共同取材や記事交換なども実施されている。
この取り組みも、取材ノウハウの共有に通じるだろう。地方紙の地理的な制約を取り払い、取材と記事の質を向上させる可能性も大きい。
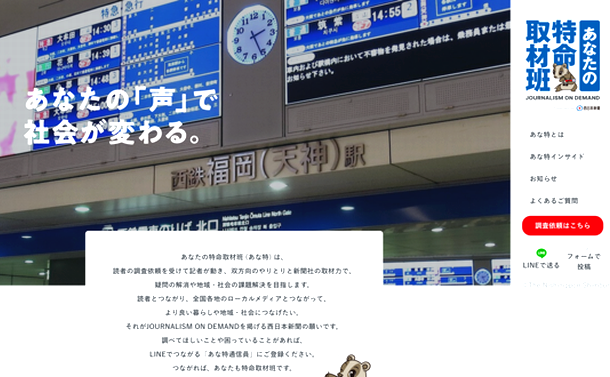 西日本新聞「あなたの特命取材班」のHP
西日本新聞「あなたの特命取材班」のHPしかしながら、社会の公共物とも言える取材手法や知恵の蓄積をきちんと次世代にバトンタッチしていくという意味から判断すれば、前述したような取り組みだけでは、新聞の衰退速度に追いつくまい。
では、不足しているものは何か。筆者の見立てでは、取材手法と知恵の蓄積に関し、その共有を「取材のプロ同士」にとどめず、広く市民にも開放することである。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください