2021年02月05日
新型コロナ禍の中、自宅で過ごす時間がながくなっている。そんな中、多くの人が感じるのは自宅の安全性と快適性だ。建築の耐震教育に携わっている人間の一人として、ステイホームの基本である住宅の地震に対する安全性について考えてみる。
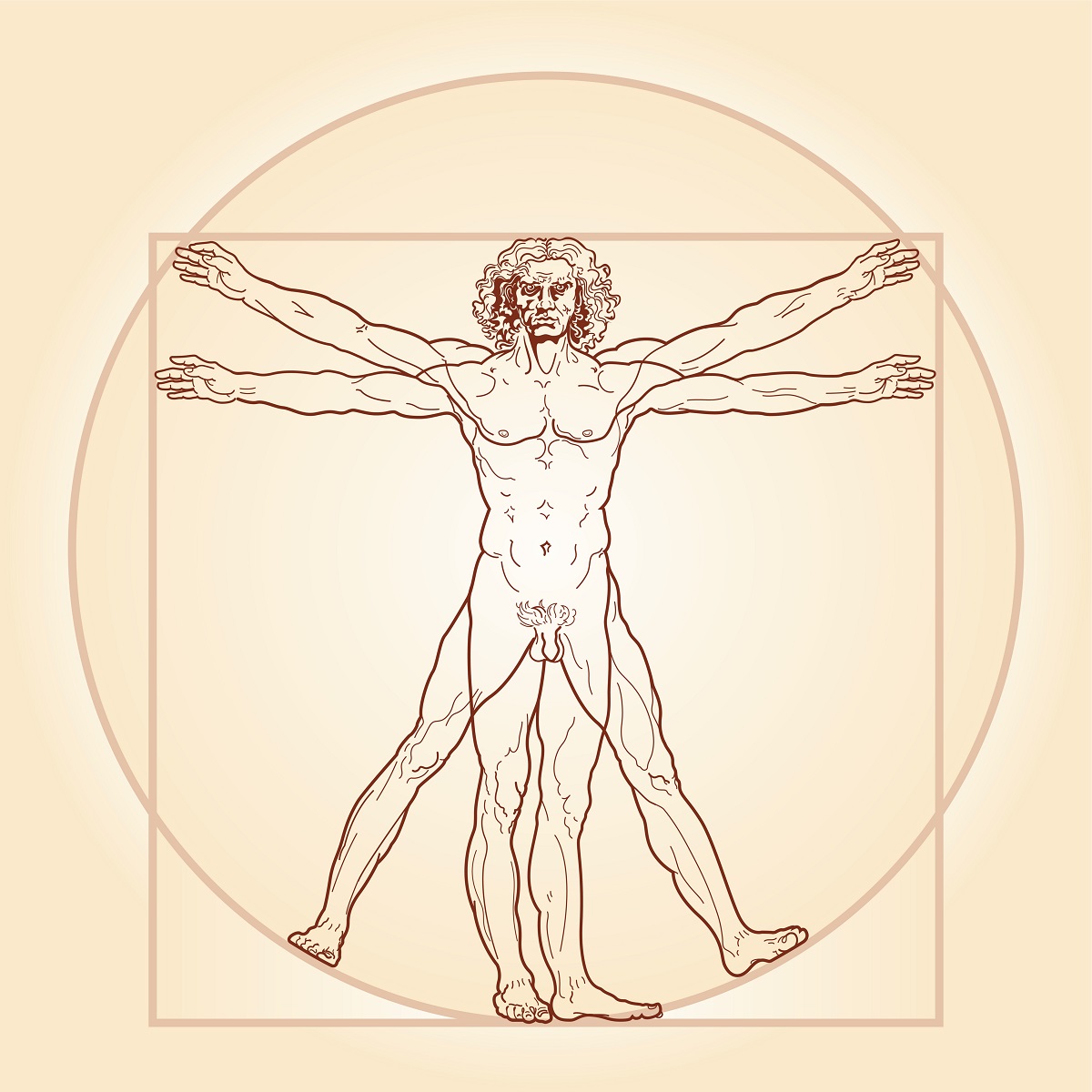 ウィトルウィウスの人体図 Shutterstock.com
ウィトルウィウスの人体図 Shutterstock.com自然の脅威から命を守るために作り始めた建築が、使い勝手を考えるようになり、さらに権力者が現れると荘厳さや美を尊ぶようになった。優先すべきは命と生活を守るシェルターとしての役割だ。一方で、現代人は、小規模な災害を抑える技術を手にし、人工空間に居住するようになった。このため、自然に対する畏れを感じなくなり、経済性や効率、見栄えを優先する社会となった。
多くの人は、便利で快適な格好いい家を安く作りたいと思っている。国は建築物の安全性を確保するように建築基準法で規定している。しかし、第1条に、「この法律は、建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と書いてあるように、あくまでも最低基準であり万全の安全性を保障しているものではない。このため、自らの安全に対する意識を高めないと安全な家を手に入れることはできない。「彼を知り己を知れば百戦あやうからず」が安全な家の基本である。
 震度6強の地震で道路が陥没し、傾いた住宅=2018年9月6日、札幌市
震度6強の地震で道路が陥没し、傾いた住宅=2018年9月6日、札幌市「君子危うきに近寄らず」というが、危険は避けた方が良い。地震が起こると、強い揺れ、液状化、土砂崩れなどの地盤災害、津波、地震火災などが複合して襲ってくる。これらの危険度が高い場所は避けるのが基本である。それが無理なら、危険度に応じた安全な家を作る必要がある。
地震規模が大きく、震源域に近く、地盤が軟弱であれば揺れは強い。強く揺れると、軟弱な地盤は液状化し、土砂崩れやがけ崩れが起きる。海の地震では、海辺を津波が襲い、海抜ゼロメートル地帯は堤防が壊れれば長期間浸水する。木造家屋密集地帯では、地震火災による延焼危険度が高い。斜面を切り盛りした場所や谷を埋めた所も危険である。活断層の近くも避けた方が良い。市町村が各種のハザードマップを作っているので、これらを確認して安全な場所を選びたい。昔の地図を調べるのも役に立つ。一般には平らな台地の上がお薦めだ。
地盤の揺れが同じでも、建物の硬さによって建物の揺れは異なり、柔らかい建物は強く揺れる。建物の硬さは壁の多さで決まる。
背の高い建物は低い建物よりも揺れやすい。建物は、強く揺れると大きな力を受ける。また、建物が重いほど力は大きくなる。この力に対抗するのが柱や壁だが、柱に比べて壁の方が強い。したがって、壁が多くて背の低い建物は揺れにくく、強度も大きい。
壁の多い低層の住宅は、ガラスが多い格好いい建物に比べ、はるかに安全だと思われる。最近の戸建て住宅は、壁が多く屋根も軽量なので、近年の地震災害では被害が微少に留まっている。
戸建て住宅は注文住宅の場合には、発注者がその安全性を決めることができる。一方、建売住宅や分譲された集合住宅、賃貸住宅の場合には設計図書などで安全性を判断するしかない。戸建て住宅は、庭があるので、災害時には様々に活用できる。また、太陽光発電や蓄電池(電気自動車などを含む)を活用した停電対策も容易だ。
これに対し、集合住宅は
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください