今こそ、「ナショナルミニマムの保障」の議論を。全ての人が安心して生きられるように
2021年10月25日
 NPO法人「TENOHASI」が実施した弁当配布と生活相談。炊き出しには長い列ができた=2021年9月25日、東京都豊島区の東池袋中央公園
NPO法人「TENOHASI」が実施した弁当配布と生活相談。炊き出しには長い列ができた=2021年9月25日、東京都豊島区の東池袋中央公園10月19日、衆議院総選挙が公示され、31日の投票に向けて選挙戦がスタートした。各党党首によるテレビ討論会が開催されたり、各党の政策比較ができるサイトが広く閲覧されたりと、政策をめぐる議論も活発になっているが、そこで頻出しているのが「分配」というキーワードである。
 岸田文雄首相の所信表明演説(10月8日)から作ったワードクラウド(WC)。多く使われた言葉ほど大きな文字になる。「新しい」「分配」という言葉が特徴的だ
岸田文雄首相の所信表明演説(10月8日)から作ったワードクラウド(WC)。多く使われた言葉ほど大きな文字になる。「新しい」「分配」という言葉が特徴的だそれは、「その政党の唱える『分配』は、抜けてしまった社会の『底』を再建することにつながるものなのかどうか。社会に暮らす全ての人の暮らしを下支えする政策が提示されているのかどうか」という評価軸だ。
昨年春以降、コロナ禍の経済的影響により仕事と住まいを失う人が増加し、貧困の拡大に歯止めがかからなくなっている状況を、私たち支援関係者は「社会の底が抜けている」という言葉で表現してきた。
東京都内の各ホームレス支援団体が定期的に実施している食料支援の場に集まる人の数は、今夏以降、さらに増加傾向が強まっており、9月25日にNPO法人TENOHASIが実施した池袋での弁当配布・生活相談には、416人が列をなした。400人を超えたのは、リーマンショックの影響が強かった2009年以来である。この連載で報告してきたように、支援を求めて集まる人の属性も、世代・性別・国籍を越えて多様化してきている。
感染対策のために経済活動を一定、制限すれば、生活に困窮する人が増加するということは容易に予想しえたことである。それでも「社会の底を抜ける」のを止められなかったのは、政府の姿勢が「自助・共助」頼みであり、「公助」が不充分だったからだ。
 NPO法人「TENOHASI」が実施した弁当配布と生活相談。日没後も相談が続いた=2021年9月25日、東京都豊島区の東池袋中央公園
NPO法人「TENOHASI」が実施した弁当配布と生活相談。日没後も相談が続いた=2021年9月25日、東京都豊島区の東池袋中央公園選挙戦では、多くの政党がコロナ禍での緊急対策として現金給付の提案をおこなっており、その対象をどう設定するのかという点に注目が集まっている。
私は、日本も他の先進国のように複数回の現金給付を実施すべきであり、迅速に支給するために支給は一律におこなうべきだと主張してきた。本来、特別定額給付金は一度限りではなく、緊急事態宣言が発出されるたびに支給されるべきだったと思う。
今回、遅まきながら現金給付の必要性が議論されていることは、一歩前進とも言えるが、テレビ討論等で貧困をテーマに議論が行われる際、現金給付だけが焦点化されているのを見ると、違和感を抱かざるをえない。
コロナ禍の貧困拡大によって露呈したのは、現金給付をはじめとする緊急対策が不足しているということだけではなく、従前から存在していたセーフティネットが充分に機能していない問題も大きいからだ。
 党首討論で議論する(左から)社民党の福島瑞穂党首、国民民主党の玉木雄一郎代表、共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の枝野幸男代表、自民党の岸田文雄総裁、公明党の山口那津男代表、日本維新の会の松井一郎代表、れいわ新選組の山本太郎代表、NHK党の立花孝志党首=2021年10月18日
党首討論で議論する(左から)社民党の福島瑞穂党首、国民民主党の玉木雄一郎代表、共産党の志位和夫委員長、立憲民主党の枝野幸男代表、自民党の岸田文雄総裁、公明党の山口那津男代表、日本維新の会の松井一郎代表、れいわ新選組の山本太郎代表、NHK党の立花孝志党首=2021年10月18日例えば、菅義偉前首相は今年1月に「政府には最終的には生活保護という仕組み(がある)」と発言したが、その生活保護の捕捉率(制度を利用できる要件のある人のうち、実際に利用している人の割合)は、2~3割にとどまっている。コロナ禍では生活保護の運用について一定の改善はあったが、一部自治体による「水際作戦」(相談に来た人を追い返すこと)も根絶されておらず、まだまだ利用しづらい制度であることは変わりない。
 参院予算委で答弁する菅義偉首相。コロナ禍で生活に苦しむ人たちへの対応を問われ、「政府には最終的には生活保護という仕組み」があると述べた=2021年1月27日
参院予算委で答弁する菅義偉首相。コロナ禍で生活に苦しむ人たちへの対応を問われ、「政府には最終的には生活保護という仕組み」があると述べた=2021年1月27日生活に困った人が活用できるはずの制度は存在しているものの、使い勝手の悪さから利用できない人が続出する。
社会の「底」の比喩を使うなら、そもそも「底」に穴が開いていたから、「底」が崩落してしまったのである。
政治家たちには、当面の緊急対策をどうするかということと同時に、社会の「底」をどう張り直すのか、という議論を闘わせてほしい。
そのために必要なのは、政策を議論する場から事実上、消えてしまった「ナショナルミニマム」という言葉を呼び戻すことだ。
ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき、全ての国民に対して保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の水準である。誰もが「健康で文化的な」生活をおくる上でのボトムライン(「底」)を示すものと言える。
民主党・鳩山政権時代の2009年12月、当時の長妻昭厚生労働大臣のもとで厚労省に「ナショナルミニマム研究会」が設置された。同研究会の委員には、貧困問題を専門とする研究者だけでなく、雨宮処凛氏や湯浅誠氏といった反貧困運動の活動家も選ばれていた。
「ナショナルミニマム研究会」は議論を重ね、2010年6月に「中間報告」が発表された。
 長妻昭厚生労働相と鳩山由紀夫首相=2010年3月25日
長妻昭厚生労働相と鳩山由紀夫首相=2010年3月25日「中間報告」では、「本研究会で議論してきたナショナルミニマムの考え方は、世界に例を見ない少子高齢社会を迎えている日本において、貧困や格差を縮小し、地域で安心して暮らせる豊かな社会を目指して、今後の社会保障や雇用のあり方を論じる際には、生活保護だけでなくあらゆる社会保障制度や雇用政策の設計の根幹となるべきものである。」と「ナショナルミニマム」概念の重要性が強調されており、「ナショナルミニマムの保障は、生活保護のみならず、最低保障年金等の所得保障制度、最低賃金、子ども手当や住宅手当、様々な雇用政策、負担の応能性の強化、低所得者の負担軽減等の包括的・整合的・重層的な仕組みを通じて、実質的に有効なセーフティネットを構築することにより、実現が図られる。」と、今後の方向性が示されていた。
しかし、この「中間報告」のとりまとめを最後に「ナショナルミニマム研究会」が招集されることはなくなり、事実上、解散状態に陥ってしまった。貧困対策に意欲的に取り組んできた長妻氏が2010年9月に退任したことが影響したと見られるが、政権が「ナショナルミニマムの保障」を打ち出すことは社会保障費の増加につながりかねないのでやめさせたい、という財務省の意向が働いたのではないかと私は推察している。
厚生労働省が毎年発行している「厚生労働白書」の2010年度版には「ナショナルミニマムの構築」という項目が設けられているが、2011年度版からはこの項目が消えてしまった。
 第1回「一人ひとりを包摂する社会」の会合であいさつする菅直人首相(右)=2011年1月18日、首相官邸
第1回「一人ひとりを包摂する社会」の会合であいさつする菅直人首相(右)=2011年1月18日、首相官邸2011年1月、内閣官房に「一人ひとりを包摂する社会」特命チームが設置され、同年5月には「社会的包摂政策を進めるための基本的考え方」という緊急政策提言が発表された。
「社会的包摂」に関する議論は、24時間365日の無料電話相談事業(2012年から始まった「よりそいホットライン」)や生活困窮者自立支援法の制定(2013年)につながっていったが、2012年12月に自民党が政権復帰すると、「社会的包摂」という言葉は使用されなくなり、第二次安倍政権下では「一億総活躍」という言葉に取って代わられることになる。
 1億総活躍推進室の看板を掛ける安倍晋三首相(左)と加藤勝信1億総活躍担当相=2015年10月15日
1億総活躍推進室の看板を掛ける安倍晋三首相(左)と加藤勝信1億総活躍担当相=2015年10月15日
 「孤独・孤立を防ぎ、不安に寄り添い、つながるための緊急フォーラム」で発言する菅義偉首相=2021年2月25日
「孤独・孤立を防ぎ、不安に寄り添い、つながるための緊急フォーラム」で発言する菅義偉首相=2021年2月25日政治力学が変化すれば、一つのキャッチフレーズが別のフレーズに取って代わられるのは、不可避なのかもしれないが、私が注目したいのは、「ナショナルミニマム」から「孤独・孤立対策」へと至る一連の流れの中で抜け落ちたものは何なのか、ということだ。
今年6月以降、政府は「孤独・孤立対策の検討にあたり、多様な現場の声を聴き、様々な課題によりきめ細かく対応していくため」として、子育て支援、子ども・若者支援、女性支援等、さまざまな分野で活動をしているNPO関係者との意見交換の会議を開催している。
 第2回「孤独・孤立に関するフォーラム」の出席者からのメッセージ(内閣官房の発表資料)
第2回「孤独・孤立に関するフォーラム」の出席者からのメッセージ(内閣官房の発表資料)この回では、生活困窮者への食料支援や住宅支援に取り組む各民間団体の関係者から、コロナ禍で深刻化する支援現場からの報告が行われたが、それらの報告を受けた坂本哲志孤独・孤立対策担当大臣(当時)の締めの発言は、以下の内容だった。
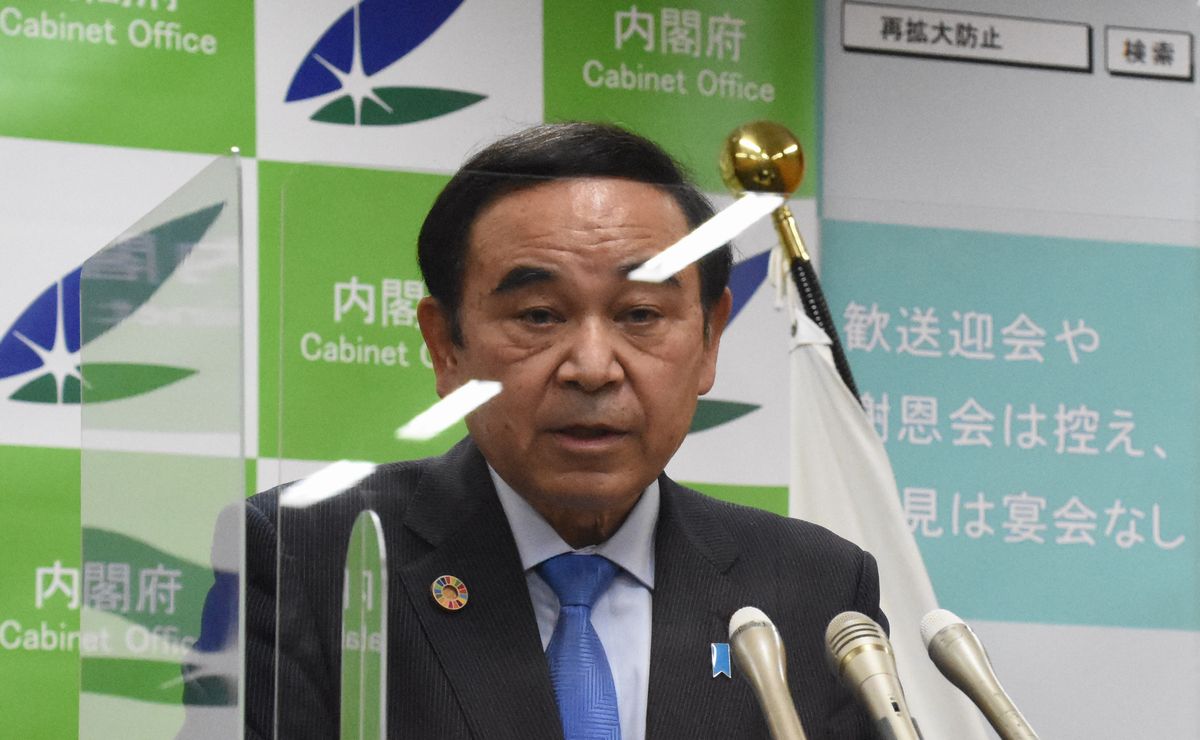 坂本哲志・地方創生相=2021年4月27日
坂本哲志・地方創生相=2021年4月27日「官民や民間同士」、「社会全体で」という言葉が示唆しているのは、政府が貧困問題に対して前面に立って対策を打つのではなく、民間と横並びで(あるいは、民間の後ろに立って)生活困窮者を支援するという姿勢である。
ここで完全に欠落しているのは、全ての人の暮らしを「健康で文化的な最低限度」のレベルまで下支えするのが政府の責任であるという「ナショナルミニマムの保障」という理念である。
公的責任による「保障」という考え方は、菅直人政権の「社会的包摂」の時点からすでに薄まっており、「保障」の代わりに「支援」という言葉が前面に出てくるのだが、「孤独・孤立対策」に至って、「支援」の主体は民間に移ってしまったようである。
私には、政府が社会の「底」を再建する責任から逃げ、「底が抜けた」状態を放置した上で、「共助」に丸投げしているようにしか見えない。
投票日に向けて有権者にお願いしたいのは、各政党、各候補者が語る「分配」に、「ナショナルミニマムの保障」という観点があるかどうか、慎重に見極めてほしいということだ。この観点のない「分配」政策は、貧困を放置し、格差を縮小させる効果も果たさないだろう。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください