加害企業として許されぬ姿勢、問われる適格性/私たち一人一人の問題ととらえ注視を
2021年12月25日
 会見冒頭、用意した文書を読み上げる東京電力の勝俣恒久会長(中央)。会長の左は藤本孝副社長兼電力流通本部長、右は武藤栄副社長兼原子力・立地本部長。清水正孝社長は出席していない=2011年3月30日、東京都千代田区内幸町の東京電力本店
会見冒頭、用意した文書を読み上げる東京電力の勝俣恒久会長(中央)。会長の左は藤本孝副社長兼電力流通本部長、右は武藤栄副社長兼原子力・立地本部長。清水正孝社長は出席していない=2011年3月30日、東京都千代田区内幸町の東京電力本店2011年の福島第一原発事故を受けて、東京電力(東電)は、①最後の一人まで賠償貫徹、②迅速かつきめ細やかな賠償の徹底、③和解仲介案の尊重という3つの誓いを公表してきました。
しかし、実際の東電の姿勢は、3つの誓いの精神からはおよそかけ離れたものでした。
そして、近時の東電の姿勢は、これまでにも増してより悪質なものになっています。
そこで、本稿では、東電の主張と狙いを紹介し、何が問題なのか、どう悪質なのかを2回に分けて明らかにしたいと思います。前号の「【上】被害者を被害者と思わぬ非道に拍車」では、賠償支払いの枠組みや、東電の主張内容を紹介しました。今号では、前号をふまえて、東電の主張の狙いや、これがどう批判されるべきなのかについて述べたいと思います。
 提訴の際の記者会見=2013年2月、福島市
提訴の際の記者会見=2013年2月、福島市しかし、こうした東電の主張には、2019年末頃から変化が表れ、「中間指針過払い論」とでも評されるべきものとなりました。前号で詳しく紹介しましたが、具体的には、次のような内容です。
 双葉厚生病院の患者らが避難した福島県男女共生センター。医療器具や点滴が運び込まれていた=2011年3月13日
双葉厚生病院の患者らが避難した福島県男女共生センター。医療器具や点滴が運び込まれていた=2011年3月13日①中間指針は、相当因果関係が認められる損害を上回る賠償額を定めている
②中間指針は、自主的な紛争解決の指針として機能してきており、本件事故の被害者から圧倒的に支持されている
③自主的避難等対象区域には、損害はない
④東電は賠償金を払いすぎている
さて、東電はなぜ主張を変化させたのでしょうか。
ここでは、東電のねらいを訴訟上の目標と訴訟外の目標という風に2つに分けて分析してみたいと思います。
訴訟上の目標についてですが、ここでのターゲットは、「共通損害」・「代表立証」・「一律賠償」という判決の判断手法に向けられています。少し難しい言葉が並んでいますので、若干用語の説明をしたいと思います。
*「共通損害」
「共通損害」とは、被害者が蒙っている損害のうち、共通する部分に着目し、共通する損害を括りだして認定するという手法です。原発事故の集団訴訟の場合では、地域ごとに区域分けして、その地域の被害者の慰謝料について、共通損害として扱うという手法が用いられています。
*「代表立証」
「代表立証」とは、一定数の被害者の尋問や検証などを通じ、共通損害を立証するという立証方法のことを指します。原告一人一人が蒙った損害の全てではなく、共通する損害部分についてのみ請求しているにすぎないことから、原告のなかから選定された一定数の原告の立証を通じて、原告全員に共通する損害を認定する手法です。
*「一律賠償」
「一律賠償」とは、地域ごとに区域分けしたうえで、それぞれの地域に属している原告について、共通損害として評価される損害に対して、一律の賠償額の支払いを命ずるという手法です。
 福島地裁の裁判官らの検証=2016年3月、浪江町
福島地裁の裁判官らの検証=2016年3月、浪江町原告らの損害を「共通損害」として括ることや、多数の原告の損害を「代表立証」によって証明すること、個々の原告の損害に対して、一定の属性に基づき「一律賠償」を命じることは、原発事故の集団訴訟が初めて実践したことではありません。水俣病や横田基地などの公害訴訟や、薬害訴訟など、日本の司法において歴史的に蓄積されてきた判断手法です。
そうした歴史もふまえて、この間、原発事故の被害者が起こした集団訴訟の判決では、区域ごとの損害を共通損害として、代表立証の方法による立証によって認定し、一律賠償として賠償額を一律に判断する手法が採用されてきました。
しかし、東電は、この手法に強く反発し、中間指針の賠償水準を上回る損害を個別に立証しなければならない、すでに損害額を上回る賠償を行っていることから既払い分を請求額に充当しなければならないと主張しているのです。
東電の主張は、訴訟上の判断手法に向けられたものではありますが、決してそれだけに尽きるものではありません。むしろ、訴訟外のターゲットこそが本丸というべきものです。
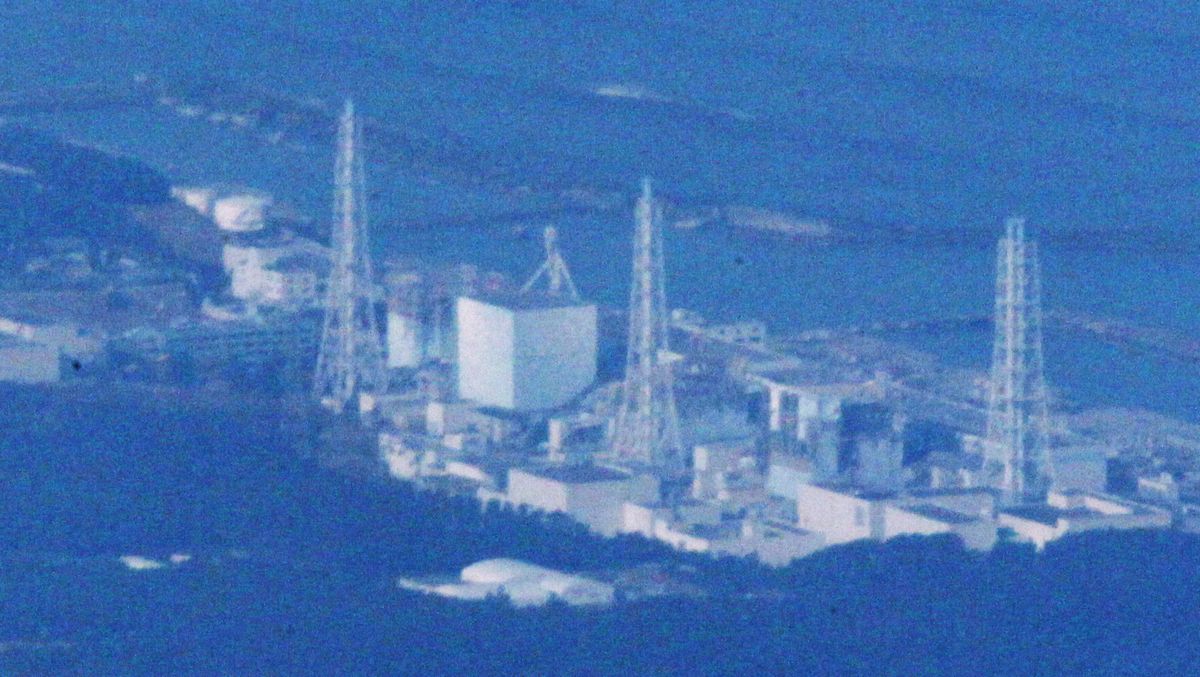 放水作業が始まった東京電力福島第一原発。左から1号機、2号機、3号機、4号機=2011年3月19日午後3時28分、福島県大熊町、30キロ以上離れた朝日新聞社機から撮影
放水作業が始まった東京電力福島第一原発。左から1号機、2号機、3号機、4号機=2011年3月19日午後3時28分、福島県大熊町、30キロ以上離れた朝日新聞社機から撮影
 桜並木が続くが、フェンスの向こうは帰還困難区域=2017年3月、富岡町
桜並木が続くが、フェンスの向こうは帰還困難区域=2017年3月、富岡町「中間指針過払い論」の究極的なねらいは、ズバリ中間指針の見直しの絶対阻止にあります。
私がかかわっている「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)第1陣は、現在、最高裁に係属していますが、控訴審判決の内容が妥当だと最高裁が判断し、確定することになった場合、控訴審判決である仙台高裁判決は、まさに「共通損害」・「代表立証」・「一律賠償」による判決でしたので、この控訴審の判断手法を最高裁も是認したことになります。
生業訴訟第1陣の原告には、中間指針が賠償対象区域と定めた全区域の被害者に加えて、賠償対象区域とされなかった区域の方々も含まれていますが、仙台高裁判決は、賠償対象区域とされなかった区域の方々に対しても賠償を命じ、賠償対象者の範囲を拡大させ、賠償額を上積みさせるものでした。
しかし、仙台高裁判決の意義は、それにとどまるものではありません。「共通損害」・「代表立証」・「一律賠償」という判断手法による判決は、ある地域に属している人であれば、原告であろうがなかろうが同等の損害を蒙っていると認定したことを意味します。いわば、仙台高裁が、原賠審に成り代わって、中間指針を見直したのと同じようなもので、そうすると、本当に中間指針を見直せという、中間指針見直し論を惹起しかねないものでもあるのです。
 仙台高裁での勝訴を伝える旗出し=2020年9月、仙台市
仙台高裁での勝訴を伝える旗出し=2020年9月、仙台市中間指針が見直されることになれば、さらに数千億円の賠償負担が課されることになります。東電としては、こうした議論が盛り上がることを最も恐れているのです。
東電がいかに恐れているのか、次の一文でもそのことがよくわかると思います。
「中間指針等は類型的に想定される被害を最大限に網羅した賠償額を定めるものとなっており、実際に提訴に至った被害者の割合はごくわずかなのである。それにもかかわらず、原判決が判断したように、中間指針等(及びそれを踏まえて策定された自主賠償基準)に定める賠償額が全体に不足しているかのように個々の居住者の個別事情によらずに『共通損害』を認めるとすれば、訴訟の乱発が懸念され、又は中間指針等見直しを余儀なくされる」(生業訴訟第1陣で最高裁に提出された東電の書面)
「訴訟の乱発が懸念され、又は中間指針等見直しを余儀なくされる」とありますが、何としても中間指針の見直しを阻止したいという確固たる意志が感じられます。しかし、中間指針が「中間」と銘打たれたものであり、見直されることを想定していることに照らしても、東電の主張がいかに不合理なものであるかは明確だと思われます。
 一面に広がるフレコンバッグ=2016年5月、楢葉町
一面に広がるフレコンバッグ=2016年5月、楢葉町こうした東電の主張は、法廷の場で展開されているものですが、そこで述べられている内容の射程は、訴訟当事者である原告にとどまるものではありません。
「中間指針は実際の損害よりも高い賠償額を定めている」、「福島市や郡山市、いわき市などのいわゆる自主的避難等対象区域には法的な意味での損害はない」、「多くの被害者は中間指針に納得していて、不満があるのは1%にも満たない原告にすぎない」、「東電はこれまで賠償を支払いすぎているから、費目に関係なく充当すべき、同一世帯内の他の家族の分も充当すべき」――東電は、福島県内や、あるいは国会の場で、こんな主張を公然とできるでしょうか。
 帰還困難区域に立ち入るゲート=2015年10月、浪江町
帰還困難区域に立ち入るゲート=2015年10月、浪江町東電の主張は、被害実態に見合った責任を取ることを拒否し、被害者が声をあげることがないよう威圧するものです。同時に、国や東電の責任を追及している原告を孤立化させ、新たな分断を被害者のなかに持ち込むものでもあります。とすれば、ことは原告のみにかかわるものではなく、被害者全体にかかわるものでもあります。
 東京電力ホールディングス本社の看板=2021年5月、東京都千代田区
東京電力ホールディングス本社の看板=2021年5月、東京都千代田区また、こうした主張を展開する東電に対しては、原発事故を起こした加害企業としてのありようとして、その姿勢が厳しく問われるべきです。たとえば、次のような一文を見るとき、東電が真摯な反省をしているといえるのか、大いに疑問をもたざるをえません。
「中間指針等に定める賠償額は『最低限』のものである(あるいは「最低限」にすら満たないものである)として、それを超える『共通損害』を認定するという原判決の判断が是認されるようなことがあれば、将来万一原子力事故が生じた場合に、当該事故を生じさせた原子力事業者は、当該事故についての『紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針』(原賠法18条2項2号)に従って賠償を行ったとしても、後に訴訟によって更なる請求が認められる可能性が高い以上、当該指針に従った賠償を実施せずに、訴訟が終了して賠償額が確定するまで支払を停止させるという判断をとりかねない」(東電が最高裁に提出した書面)
この一文は、中間指針を超える損害を共通損害として認定する判断が確定した場合には、将来事故が生じた際、原賠法に基づく指針に従った賠償支払いを原子力事業者は行わないことになるかもしれないと述べるものですが、裁判所に対する恫喝ともいえる内容となっています。自らの都合だけを述べ、被害者の有する権利や被害者の感情などには、全く配慮を欠いています。
 東京電力柏崎刈羽原発では今年、安全を根幹から揺るがす重大問題が続出し、信頼が崩れ続けた。写真は1月26日、中央制御室への不正侵入の発覚を受けて桜井雅浩・柏崎市長(左)に陳謝する橘田昌哉・東電新潟本社代表(中央)。その後も、立ち入り制限区域の不正侵入を検知する設備の故障と長期間の放置、行ったはずの安全対策工事76カ所の未完了、30カ所の配管溶接不備、火災感知器100個の設置工事の法令違反などが発覚した
東京電力柏崎刈羽原発では今年、安全を根幹から揺るがす重大問題が続出し、信頼が崩れ続けた。写真は1月26日、中央制御室への不正侵入の発覚を受けて桜井雅浩・柏崎市長(左)に陳謝する橘田昌哉・東電新潟本社代表(中央)。その後も、立ち入り制限区域の不正侵入を検知する設備の故障と長期間の放置、行ったはずの安全対策工事76カ所の未完了、30カ所の配管溶接不備、火災感知器100個の設置工事の法令違反などが発覚した政府は、原発事故による汚染水について、海洋放出とする方針を一方的に決め、「風評被害」対策に万全を期すと豪語していますが、肝心の東電のこうした姿勢を目の当たりにしては、「万全」という言葉も空虚でしかありません。
 脱原発とエネルギー政策の転換を訴える人たちが持つキャンドルで、国会議事堂が取り囲まれた=2012年3月11日
脱原発とエネルギー政策の転換を訴える人たちが持つキャンドルで、国会議事堂が取り囲まれた=2012年3月11日現在、生業訴訟はじめ、国と東電を被告とする被害者の訴訟は、4件(生業訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、えひめ訴訟)が最高裁に係属しています。
国と東電の原発事故に対する法的責任の存否について、最高裁の判断が示されるという意味で、「頂上決戦」とも称されていますが、損害との関係でも、東電は当然のこととして、国の責任が認められることには重要な意義があります。
 【左】法廷に先立つ集会。大友良英さんも駆けつけた【右】裁判所に向けた行進。想田和弘監督も駆けつけた
【左】法廷に先立つ集会。大友良英さんも駆けつけた【右】裁判所に向けた行進。想田和弘監督も駆けつけた有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください