どうやって稼ぐ? コメントとの付き合い方は? 国民の信頼は取り戻せるか?
2022年02月18日
 新谷学・月刊文藝春秋編集長=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学・月刊文藝春秋編集長=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)2010年夏にローンチした「論座」(ローンチ当時は「WEBRONZA」。2019年4月に「論座」に改称)がアップしてきた記事が2月18日、2万本に達しました。この11年半を振り返ると、ネットメディアをめぐる状況は劇的に変化し、進歩したと思う点もあれば、困った常態になっていると言わざるを得ない点もあります。
論座編集部ではこれを機に、サイトとしてのあり方をあらためて考え、より良い論座づくりを目指すこととしました。まずはそのための「考えるヒント」を得るべく、各界の様々な方にインタビューをします。
今回はなしを聞いたのは月刊文藝春秋の新谷学編集長。「週刊文春」の前編集長で、あの「文春砲」の生みの親です。編集長退任後、週刊文春編集局長としてデジタル時代のメディアの稼ぎ方を追求。昨年夏、かつて在籍した文藝春秋の編集長に戻りました。文藝春秋にかける思い、「論座」のこと、メディアの未来についてじっくり聞きました。新谷編集長の動画と合わせてぜひ、お読みください。
新谷学(しんたに・まなぶ) 月刊文藝春秋編集長
1964年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。1989年4月に㈱文藝春秋入社、
「スポーツ・グラフィック ナンバー」、「週刊文春」、月刊「文藝春秋」各編集部などを経て、2011年ノンフィクション局第一部部長。12年4月に「週刊文春」編集長に就任、6年間つとめた後、18年7月「週刊文春」編集局長。20年9月より執行役員として「スポーツ・グラフィック ナンバー」編集局長を兼務。21年7月、執行役員・月刊「文藝春秋」編集部。
著書に『「週刊文春」編集長の仕事術』(ダイヤモンド社)、『文春砲 スクープはいかにして生まれるのか? 文春編集部編』週刊文春編集部編(角川新書)、『獲る・守る・稼ぐ 週刊文春「危機突破」リーダー論』(光文社)
――文藝春秋は今年12月に創刊100年を迎えます。節目の時期に現場を任されたかたちですね。
新谷 文藝春秋の編集長を引き受けるにあたり、まず大事にしようと思ったのは、100年前に菊池寛が「創刊の辞」で述べている「原点」に帰るということです。菊池は、「自分は頼まれて物を言うことに飽きた。自分で考えていることを、読者や編集者に気兼ねなしに、自由な心持ちで言いたい。友人にも私と同感の人々が多いだろう」と述べ、創刊号には芥川龍之介や川端康成などの、自由にモノを言いたい“友人”が寄稿しています。
大正デモクラシーたけなわの1922年、28ページというペラペラの本からのスタートでしたが、昭和、平成を経て令和に至る今も、私は「自由な心持ちで物を言う」ということが、この雑誌が最も大切にするべき点だと思っています。
――なにより「自由」でいたいと。
新谷 今って自由にモノを言うことが、けっこう難しい世の中になっていますよね。コンプライアンス、「炎上」リスク、取材手法の是非、ポリティカル・コレクトネスなどの制約があるなかで、どうやって自由に発信をするか。考えるべきことは多いと思います。
もうひとつ力を入れていきたいのは、しっかり「稼ぐ」ことです。「貧すれば鈍する」ではないですが、収益が思うに任せないと、言いたくないことを言ったり、誰かにおもねったりしかねません。「自由に物を言う」ためにも「稼ぐ」ことが必要なのです。
――メディアの世界も、紙からデジタルへの移行が進んでいます。「論座」もその前身であった紙の「論座」が2008年に休刊になっています。そんななか、文藝春秋が「紙のメディア」を守り続けているのはすごいと思います。ずっと紙を続けるのでしょうか。
新谷 私は、菊池寛が「自由に物を言う」うえで最適なデバイスが、創刊当時はたまたま紙のメディアだったという風に思っています。もちろん、紙の文藝春秋をただちにやめることはまったく考えていませんが、その一方で紙に限定する理由はなくて、「自由に物を言う」のにもっと適した「場所」があれば、それを使わないという選択はありません。現状では、端的に言って、それはデジタル空間だと思っています。
――今は紙もあるしネットもある。今後はバーチャルも普及するでしょう。そういう様々なデバイスの中から、自由に物を言うために最適な方法を選ぶと言うことですか。
新谷 そうです。私はかねてから、「中身」と「入れ物」を分けて考えるべきだと言ってきました。「中身」とは記事やコンテンツ。「入れ物」はプラットフォームやデバイスです。われわれは、他に真似ができない素晴らしい記事やコンテンツを作るプロでありたい。そのうえで「入れ物」は、時代に応じて最適なものを選んでいけばいい。
その際に重要なのは、プラットフォーム事業者やデバイス企業と対等の立場でいることです。そのためにも、記事やコンテンツの質を上げることが、死活的に重要なのです。
 新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)――記事やコンテンツのプロでありたいというのは同感です。文藝春秋では何を目指しますか。週刊文春とは随分とテイストが違うと思いますが。
 新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
たとえば、総務省の谷脇康彦・総務審議官の接待問題です。谷脇さんは公務員として違法行為を犯し、だから退職されたのですが、他方、総務行政において谷脇さんが過去にやってきた仕事、今後期待されていた役割は非常に大きく、余人をもって代え難いということを、多くの人から言われました。もちろん、彼がしたことが免責されることはないし、記事を止めるという判断は絶対にありえない。それでも、国益という言葉は安易に使いたくはありませんが、複雑な気持ちになったのも確かですね。
週刊文春というのは、典型的な「スクラップ型メディア」です。権力者や巨大組織の問題点をえぐり出す。これには間違いなく意義があります。ただ、それだけでいいのか。「ダメなのは分かった。じゃあ、どうする」も必要ではないか。この国にはもう先送りできない難題が山積しています。こうした問題に向き合い、「どうすればいいのか」を伝えるビルド型のメディアも必要ではないか――。
そんなことを考えてモヤモヤしていた時に、文藝春秋の編集長というポストに就くことになりました。今度は「ビルド型メディア」をとことんやろうと思っています。
――昨年8月発売の9月号から新谷さんが編集長です。ビルド型は始まっていますか。
新谷 11月号の「矢野論文」は、この国の難問をテーブルに乗せ、当事者に説明してもらい、国民的な議論を喚起するという基本的な編集方針にかなり合う形で発信できたと思っています。
――財務省の現職財務次官による寄稿「財務次官、モノ申す」ですね。「このままでは国家財政は破綻する」とバラマキ政策を批判したもので、賛否両論が渦巻きました。
新谷 この国にとって財政問題は避けて通れません。国家財政の厳しい現状を国庫の管理責任者である財務省の事務次官につまびらかにしてもらう。そのうえで、彼、あるいは財務省が持っている問題意識を、広く国民に伝えてもらうということは、絶対にやるべきだと思いました。
賛否両論は承知のうえでしたが、やはり様々な意見がありました。批判で多かったのは、官僚のノリを超えているということ。安倍晋三・元総理もやり方が非常識とおっしゃっていました。だけど、非常識だからこそ、大きな反響を呼んだ。時にはそういう手法も必要だと思います。
1月号のトヨタの豊田章男社長への編集長インタビューも手応えがありました。カーボンニュートラルを目指すにあたり、EV(電気自動車)一本足でいいのかどうかを、当事者の豊田社長にかなり厳しい質問も含めて聞きました。
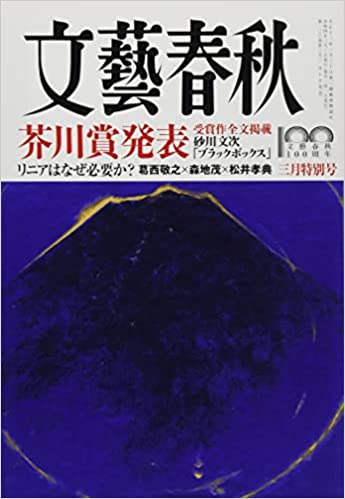 「リニアはなぜ必要か?」が掲載された文藝春秋3月号
「リニアはなぜ必要か?」が掲載された文藝春秋3月号このほかにも、今の日本には、面倒なので見て見ぬふりをしている難問が少なくありません。財政問題やエネルギー問題はもちろんのこと、象徴天皇制や教育問題もそうです。こうした問題、課題は繰り返し取り上げていくつもりです。
あと、この国の課題としてあえて申し上げたいのは、メディアの問題です。残念ながら、われわれ既存のメディアに対する国民の不信は大きい。メディアが信用されていない国は、非常に不幸だと思います。これは日本に限った話ではないかもしれませんが、この点についても手をこまねいていていいのだろうかという問題意識を持っています。
――最後の指摘は、われわれメディアにとって深刻な課題です。ネットの進展で、あらゆる人が「発信者」になれる時代になり、既存メディアが地盤沈下をしているという現状、取材手法への批判なども含めた既存メディアへの不信など、メディアをめぐる環境は厳しさを増している。メディアへの信頼をいかに取り戻すかは、「論座」も真剣に考えないといけません。
新谷 既存メディアが生き残る道は、究極的にはオピニオンと調査報道しかないと考えています。その意味で、オピニオンサイトである「論座」には大きな役割がある。ただ、文藝春秋同様、「論座」も商業ジャーナリズムという宿命を背負っています。収益をいかに上げて持続可能になるかについては、知恵を絞る必要があります。
――オピニオンを扱うという点では、文藝春秋と「論座」は共通します。あえて紙とデジタルの違いがあるとすれば、どういう点でしょうか。
新谷 最大の違いは一方通行か双方向かだと思います。紙の場合、読者は基本的に受け身です。だからこそ、集中して読めるという利点があるのは確かです。これに対し、デジタルは双方向で、読み手側も発信できる。この点で大いに可能性があると思います。技術的な面も含め、どうやって良い双方向の関係をつくるかが課題でしょうね。
問題は、紙のメディアで生きてきた人、原稿の書き手も編集者も、デジタルでの発信にあまり慣れていないということです。だから、面白くて、役に立って、分かりやすいコンテンツの発信が、十分できているとは言えません。逆に言うと、それができれば紙にはできない可能性が広がるわけで、そのための努力をメディアはしなくてはいけません。
――双方向性について言えば、「論座」にも記事へのコメント欄があり、「課題解決型論」論考については、コメント欄に応えるかたちで「論」を展開するようにもしていますが、必ずしもうまくいっていません。誹謗中傷やヘイトまがいのコメントが並び、対応に苦慮するケースもあります。コメント欄についてはどうお考えですか。
新谷 コメント欄はあったほうがいいと思います。批判的なコメントは「見たくない」という気持ちになるのも分かりますが、批判の中にも、一面の真実というか、痛いところを突いている点があります。そこから逃げてはダメだと思います。
とはいえ、中身をろくに読まず、誹謗中傷するためだけに書き込む人たちには、できればご遠慮願いたいですね。文藝春秋としては、この国の課題について、当事者を呼んでぶっちゃけどうだという話をする言論空間に、賛同してもらえるような人たちが集う場にできればベスト。賛否はあっていい。でも、異論には一切耳を傾けず、議論する前から何でもかんでも批判する人の相手をするのは、徒労感が大きい。見極めはなかなか難しいですが……。
――確かに見極めは難しいですが、われわれのコメント欄はこういう議論を期待していますと宣言することはありだと考えています。その趣旨に賛同する人は書き込んでくださいと。それでも色んなコメントはくるでしょうが、一定の議論の場をつくることはできるのではないか思います。
新谷 お金を払って読んでくれている人であれば、発言の権利はあると、私は思いますね。読んでもいない、お金も払ってないような人が、外から石投げるようなコメントにまで、すべて丁寧に対応するのは正直言って難しいです。開かれた空間ではありたいけれど、一定のフィルターは必要なんでしょうね。
昨年、東浩紀さんの「ゲンロンカフェ」に出ました。「シラス」というプラットフォームを使って、石戸諭さんと4時間ぐらい対談する「番組」だったのですが、このシステムはすごく良かったです。
対談のあいだ中、見ている人のコメントがずっと出るわけです。面白がって話を聞いてくれている人が、さらに深い部分に触れるような質問してくれると、議論がどんどん深まって、すごく面白い体験でした。これは、お金を払った人しか「番組」を見られないという、一種のフィルターを通してあるからこそ、成立するのだろうと思いますね。
 新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)――議論を深めるコメントは、筆者にとっても有意義です。ただ、ヘイトや誹謗中傷のコメントがつくと、当事者にとってはつらい。メンタルが強いとか弱いといった問題ではありません。
新谷 Zホールディングスに山本龍彦慶応大学教授を座長にした「デジタル時代における民主主義を考える有識者会議」があり、私も参加しています。フェイクニュースやデジタル時代における民主主義について議論をするなかで、繰り返し、次のように言っています。
Yahoo!ニュースのヤフコメで誹謗中傷に関しては削除されるようになると、憲法の定める言論の自由を侵害してるのではないかと声を上げる「ヤフコメ民」がいるけれど、これはおかしい。そもそも憲法はネットの登場を想定していない。ある表現が拡散するスピードや範囲は、憲法制定当時からは比べようもないぐらい大きい。誹謗中傷を受けた人に与えるダメージも計り知れないぐらい大きくなり、命を絶つ人まで出ている。新たなルール作りを考えるべきです、と。
ネットの時代には、デジタルにおける言論空間に照らした新たな「表現の自由」のルールをつくる必要があるのは間違いないと思います。
――次に、われわれ商業ジャーナリズムが発信し続けるために、どうやって収益を上げるのかという点について考えたい。新谷さんが文藝春秋で取り上げていきたとおっしゃる日本の課題であれ、「論座」の中核を占める政治・経済・社会問題にからむオピニオンであれ、ハードなテーマは正直あまり“集客”できないのも事実です。PVが増えない、読者や会員の獲得にもつながらないとなると、集客しやすいエンタメ系やスキャンダラスなものに頼りたくもなります。
新谷 いわゆるアテンション・エコノミーですよね。
――はい。情報の善し悪しよりも、注目を集めることが重視され、それが資源になっていくというアテンション・エコノミーです。課題解決や言論空間をめざすメディアとして、このジレンマをどう解消していけばいいと考えますか。
新谷 それは文藝春秋も抱えている難問です。最近、この手の話をするとき、よく渋沢栄一の「論語と算盤」を例に出します。メディアとして、守るべき理念、大切にしなければいけない見識がある一方で、収益も上げなければいけない。どうするかという「マニュアル」はなく、要はきちんとした道理、メディアとして貫くべき理念である「論語」と、経済的な利益である「算盤」のバランスをいかに保つか、なのだと。
ジャーナリズムを標榜する人たち、なかでもリベラル系の人たちに欠けているといつも思うのは、「稼ぐ」意識が弱すぎるところです。言っていることは立派だし、志も高いのですが、稼がなければ続けられない。そこから逃げてはいけないと思います。稼ぐことは卑しいことではない、大切なことです。そこは渋沢栄一の言う通りです。
ただ、稼げるなら何をやってもいいのかっていうと、それも違います。例えば文春オンラインの場合、芸能やスキャンダルに戦力を投入すれば、目先のPV、利益は伸びるでしょう。でも、「算盤」ばかりが先にたち、「論語」の部分がおろそかになると、文春というブランドは傷ついてしまう。それは持続可能ではありません。繰り返しますが、大切なのは、「論語」と「算盤」のバランスなのです。
もっと言えば、真面目なネタ、読者が少ないと思われているようなネタは、本当に数字を取れないのか、稼ぐことにつながらないのか。私はそういう「常識」を疑ってみてもいいと思っています。例えば、文藝春秋の「矢野論文」は硬く難しいテーマだけど、非常によく売れました。
スクープ性や当事者性、タイトルやタイミングといったもろもろの要素が相まって売れたとは思いますが、逆に言えば、売れるための条件づくりに努力すれば、難しくて読まれないと思われる論考だって、注目を集めるのではないか。さらに、デジタル技術を駆使すれば、より分かりやすく、面白く伝えられるのではないでしょうか。
 新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)――ところで、ネットサイトには今、「課金モデル」、いわゆるサブスクモデルと、「広告モデル」があります。どちらに可能性があると考えますか。それとも「第三の道」はあるのでしょうか。
新谷 サブスクモデルか広告モデルかのどちらかというのではなく、メディアの特性に合わせて双方をうまく使うべきでしょう。たとえば週刊文春は広告モデルに非常に向いています。スクープ、スキャンダルは、一本の記事でPVが1億を超えることもある。PVが物をいう広告モデルが合理的です。
週刊文春編集局長になって「文春オンライン」も統括するようになったとき、まずは週刊文春の力をフルに使ってPVを目一杯伸ばそうと考えました。サイトの存在感を高める目的で、最初の戦略としては正しかったと思います。ただ、文藝春秋も「文春オンライン」に一部の記事がアップされていますが、PVを最優先でいいかというと、そうではありません。
文藝春秋は、先ほど言ったように、この国の難問を解決するメディアを目指します。読者に問題のありかを知ってもらい、共に考えてもらいたい「ソリューション型のメディア」の場合、ワンショットでPVをガンと伸ばすよりも、この言論空間は自分たちのための空間だ、自分たちのメディアであると感じてもらうことが望ましい。それには、サブスクモデルが適しています。
――言論空間のコミュニティに加わるための参加費という感じですか。
 新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
――「論座」も従来型のオピニオンに加え、課題解決型の論考を増やそうと考えています。読者に連帯感を持ってもらうために、サブスクモデルの方のほうがいいのですね。
新谷 そうだと思います。コミュニティに関連して言うと、文藝春秋では今、ウェビナーに力を入れ始めています。私自身も今後、積極的に出ていって、我々の問題意識を直接読者にお伝えし、一緒に考えましょうという呼びかけをしようと考えています。
――「論座」も認知度を高めるためにオンラインイベントを開いているのですが、準備に時間がかかって、回数が限られています。
新谷 オンラインイベントは、「当たるも八卦」で数をこなし、知見を積んで練度を高めるしかないですね。何が会員増につながるかはわからないので、とりあえずやってみる。ネットビジネスは総じてそうですね。うまくいけば踏み込むし、ダメなら撤退する。まずはやってみることです。
――「論座」が11年半で公開した記事が2万本になりました。文藝春秋も100年間に膨大な記事を掲載してきたと思います。こうした記事。いわゆるデータアーカイブの使い方で考えていることはありますか。
新谷 過去記事はメディアにとって大きな財産です。遡ってつくることができないものには、すごく価値があります。とりわけ、サブスクモデルとデジタルメディアとは相性がいいと思いますね。
何か出来事があったとき、会員であれば、それに関連する過去記事に自由にアクセスできるのが理想的ですね。例えば、先日、石原慎太郎さんがお亡くなりになりましたが、「石原慎太郎」で検索すればサイトの中にある慎太郎さんに関わる論文や小説が出てきて、「会員はすべて読める」という仕組みができるとすごくいい。技術的にすぐにどこまでできるかは分かりませんが、これは絶対に大事だと思うんですね。
――文藝春秋は、それこそ時代を画した論文や記事がたくさんあるので、アーカイブの活用のしがいがあるのでは。
新谷 創刊100周年ということで様々な記念企画をやっていますが、過去のコンテンツを活かしたものもあります。例えば、「肉声シリーズ」。昨年12月号では文藝春秋に掲載された「皇族の肉声」の中から10本を、2月号ではやはり過去に掲載された「政治家の肉声」から11本を選んで、学者や記者に解説を書いてもらいました。今後もこのシリーズは続けてやっていきます。
よくぞこの人が、このタイミングで誌面に登場し、こんなことしゃべってくれたなっていうのが、面白いんです。文藝春秋がこの100年、日本と共に歩んで来た雑誌だということをアピールする意味でも、アーカイブの利用には価値があると思います。
 新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)
新谷学さん=2022年2月7日、東京都千代田区紀尾井町 文藝春秋本社(撮影・吉田貴文)――「論座」でもコンテンツ2万本を期して、再読してもらいたい論考をツイッターでアピールしていこうと考えています。ところで、先ほど「既存メディアに対する国民の不信は大きい」「手をこまねいていていいのかという問題意識を持っている」という指摘がありました。メディアをめぐる現状をどう見ていますか。
新谷 人がモノを言ったり考えたりする際には、本来、そのベースになる基本的な情報が必要です。行動を起こす時も、示唆を与えてくれる情報がいります。ただ、情報に対する意識が近年、大きく変わってきているのは確かです。
かつては、メディアが絶対的な存在で、優越的な立場から情報を提供する。あるいは、啓蒙的な上から目線で情報を伝えていましたが、そうした関係性がネットによって激変しました。メディアに頼らなくても、自分で情報が取れると多くの人が思うようになり、メディアの優越的な地位が失われたのです。
ただ、ネットの情報は玉石混交なうえ、自分にとって都合のよい情報ばかりを集めていると、フィルターバブルにはまって考えが偏り、間違った行動をとりかねない。自分をミスリードしない情報は何かを知ること。いわゆるメディアリテラシーが大切だということは、意識しておいたほうがいいと思います。
では、メディアリテラシーにおいて何が大事かといえば、信頼できるメディアと信頼できないメディアを、判断できることです。逆にメディアの側にすれば、どうすれば信頼されるメディアになれるかが問われます。
時によって主張や立場を変えるダブルスタンダードだったり、“大本営発表”しか書かなかったりするメディアでは、当然信頼されません。政治家や大手企業の代弁者ではなく、国民が知っておくべき情報を、リスクがあろうがコストがかかろうが、しっかりと伝えるメディアが、絶対に必要なんです。
――ネット上に情報があふれかえる時代だからこそ……
新谷 情報を整理して伝える「キュレーション」が必要です。きちんとキュレーションのできる、国民に選ばれるメディアにならないといけない。メディアが信用されていない国は、非常に不幸だと先ほど言いました。国民を不幸にしないためにも、信用できるメディアになりたいと思います。「論座」とも建設的な議論を戦わせるようなコラボレーションができるといいですね。
――「論座」もシン「論座」を目指して頑張ります。今回はありがとうございました。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください