昭和のマス・プロ式システムはすでにサンク・コスト化している
2022年04月01日
ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)日本版の参入による国内報道メディア業界への影響について今回は述べていきたい。
この事例はWSJ日本版のみならずその後ろに控えるニューズも考慮すると、国内報道メディア業界の代替勢力の大きな脅威といえよう。さらに、現実的には経済のグローバル化やIT革命によってWSJ日本版以外にも多くの代替メディアが国内報道メディア業界に参入してくる。
これらが本格参入した場合、国内報道メディア業界全体の平均的な収益率は低下する可能性があり、またそれによって業界内の競争は激化する。この場合、もっとも影響を受けるのが経営基盤の脆弱な報道メディアである。特に人件費など固定費比率が高く、報道記事の差別化が不明確で、販売力が弱い場合がこれに当てはまる。
国内新聞社の場合、一部を除いてこれらのほとんどが該当する。国内報道メディア業界の特徴として以下が挙げられる。給与水準が高い余剰人員を抱えつつも人件費が高止まりしている。記者の労働市場の流動性が乏しく、業界内の新陳代謝に乏しい。記者クラブ制度による速報的な横並び記事が大半で、独自性を押し出せる調査報道やオピニオン記事が少ない。オンライン上の記事の有料化で苦戦している。
WSJ日本版の投資規模からすると、これ自体は国内報道メディア業界の経過観察的な動向と考えられる。対する国内の各報道メディアの対抗戦略として、迎撃、協調・提携、差別化などがあり得る。これらについて見ていこう。
連載第1回と第2回もご覧下さい。
 Rawpixel.com/shutterstock
Rawpixel.com/shutterstockまず、外国報道メディアに対する国内報道メディア業界としての迎撃策として放送法による外資規制がある。ニューズによるテレビ朝日買収劇の後、外国報道メディアの国内進出を排除するかのような動きがあった。放送局の監督省庁である総務省は2011年、放送法を改正して放送事業者とこれらを傘下に持つ放送持ち株会社に対する外国資本の議決権比率が20%未満と定めた(総務省, 2021)。つまり、国内報道メディア業界が政府に圧力をかけ、あるいは政府と共謀して、外国報道メディアという代替勢力の参入に対する新たな参入障壁を設置したと解釈できる。
また、報道メディア個別の迎撃策として、日本経済新聞社によるデジタル・グローバル戦略が挙げられよう。これは外国報道メディアとの協調策としての側面もある。WSJ日本版の直接的な競合相手となるのは国内の代表的な経済紙『日本経済新聞』で、これを発行するのが日本経済新聞社である。同社はWSJ日本版発刊直後の2010年3月、インターネット媒体『日本経済新聞 電子版』」を創刊した(日本経済新聞社,2010)。これは基本的に有料サイトで日経新聞の定期購読者が月額1000円、電子版のみの購読者は月額4277円で、日経新聞の朝夕刊の記事と有料記事が読み放題である(日本経済新聞社, 2022)。
日本経済新聞社では2009年4月に電子新聞編集本部を発足させ、「コンテンツは無料」というネット界の慣習を覆す国内初の会員制有料課金サイトの構築を試みた。当時、喜多恒雄社長は報道メディア界にもインターネット時代が到来し、紙の新聞の大きな成長を期待することが困難であるとの危機感を示した。 IT革命によるデジタル化に迫られたのである。これが日本経済新聞社のデジタル戦略の一つである。
一方のグローバル戦略には国内新聞事業の限界を乗り越えるための外国報道メディアのM&Aがある。日本経済新聞社は2015年7月、英国出版・教育大手のピアソンから、1888年創刊の英国有力経済紙『フィナンシャル・タイムズ(以下、FT)』を発行するFTグループを1600億円で買収した(日本経済新聞社, 2015)。FTの有料購読者数は2019年3月末で100万人に達し、このうちデジタルの購読者が8割を占める。広告収入への依存度が50%を超えていたが、現在は購読料収入が大半だという。デジタル化で財・サービスの形態や収益構造が大きく変化したのである。2021年6月の『日本経済新聞』朝刊販売部数(日本ABC協会公査)が約185万部、2021年7月1日時点の『電子版』有料会員数が約81万人であった(日本経済新聞社, 2021)。
 日経によるフィナンシャル・タイムズ・グループの買収を伝える24日付両紙の1面 =2015年7月24日
日経によるフィナンシャル・タイムズ・グループの買収を伝える24日付両紙の1面 =2015年7月24日グローバル経済の中での経済報道の影響力という点を切り取れば、国内の経済報道では確固たる位置を築いた日経新聞社といえども単体ではWSJの前に立ちはだかることは、まず不可能である。これは日経新聞社の情報の収集力と提供力というよりも、日本語という言語的な障壁による。
日本語の報道記事の読者数は日本語人口に規定され、この市場規模は最大限で1億2千万人程度である。一方、WSJは英字紙であり、全世界人口約78億人のうち、英語人口はその約22.5%に当たる約17.5億人とされ、今や英語はグローバルなビジネス言語である(Neeley, 2012)。WSJはこの読者マーケットに向けて発信される。これが日本語の経済記事マーケットより遙かに大きいことは容易に想像できる。
ミクロ的に比較すれば、コスト競争力の格差が考えられる。WSJを発行するダウ・ジョーンズや親会社のニューズが十分な収益と規模の経済がある場合、WSJ日本版の原文記事の取材編集費用はサンク・コストで経営的に考慮する必要性は低い。日本語への翻訳だけが新たに発生するコストで、これが限界費用と考えられる。WSJ日本版は限界費用に従って価格設定すればよく、フルコスト的な価格設定を迫られる国内報道メディアとの価格競争を優位に進められる。WSJ日本版が月額2千円に対して、日経電子版はその倍額である。これらがWSJ日本版の競争優位の一つといえよう。
また、日本の経済的な地盤沈下が日本の経済報道メディアの影響力を減衰させる要因になる。英国のシンクタンクZ/Yenグループが2021年3月に発表した国際金融センターの競争力を示す指数では、1位ニューヨーク、2位ロンドン、3位上海、4位の香港、5位のシンガポール、6位の北京の順だった。東京は前回調査の2020年から順位を3つ下げて7位となった。かつて3大国際金融市場の一つとして東京は国際的な影響力を誇っていたが、現在ではニューヨークとロンドンとの差が開き、中国の台頭を許す結果となった(Z/Yen,2021)。つまり、国際金融センターとしての東京の衰退は、東京発の経済ニュース価値を減少させることにつながる。
日経新聞社によるFTの買収の背景には、日本の国際競争力の低下もあった。経済のグローバル化が世界中に拡がりつつある中、それに乗じてFTを発行するダウ・ジョーンズや、これを凌ぐロイターやブルームバーグのグローカル戦略による国内報道メディア業界への参入に対抗する奇策が日経新聞社のFT買収であった。つまり、これは積極的な迎撃策というよりも、むしろ防御に回った窮余の策といえよう。
しかも日本経済新聞社のFT買収には、日本と英国の間にある企業文化の融合が求められるため、その成り行きは茨の道だろう。その一つがジャーナリズムの倫理面である。欧米、特にアングロ・サクソン系の国・地域のジャーナリズムには、公権力など情報源に対する独立性が強く求められる。FT買収時にはAFPなど海外報道メディアからは、日本経済新聞社は日本の大手企業と利害関係にあるため、FTの独立性が損なわれると危惧する声が上がった(AFP 2015)。
2021年夏に開かれた東京五輪パラリンピック大会でも、日本経済新聞社のみならず、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社など国内大手の新聞社は大会組織委員会とスポンサー契約を結んだうえ、大会組織委員会の内部組織であるメディア委員会に五輪担当記者ら人材を派遣した。これは、情報源に対するジャーナリズムの独立性を毀損する行為である(小田, 2021)。
つまり、大会組織委員会というスポーツ界の公権力に対する第三者からの批判機能が失われ、その広報機関と化した状態であった。こうした事態は市民革命を経て公権力の監視を矜持とする欧米報道メディアにとっては受け入れがたい日本の報道メディア文化なのである。
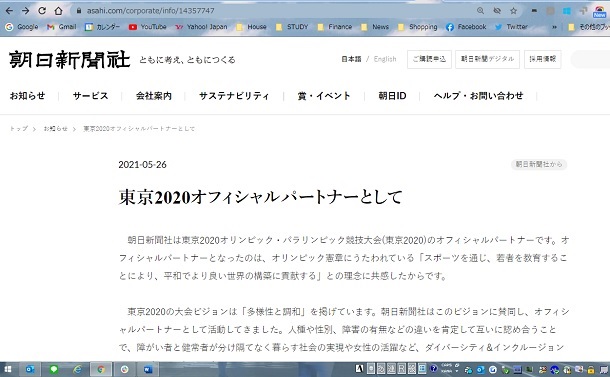 朝日新聞社が2021年5月26日にサイトで公開した社告
朝日新聞社が2021年5月26日にサイトで公開した社告また時差と提携を利用した対策もある。東京とロンドン、ニューヨークの時差はそれぞれ9時間と12時間ある。報道ニュースの需要時間帯は起床時間に限られるため、時差と外国報道メディアとの提携を利用して、WSJ日本版に掲載される記事と同等の翻訳記事を国内報道メディアに掲載することが可能である。国内報道メディアには海外拠点での取材活動のほか、本社に提携先の記事を翻訳する部署を置いて、世界中の動向を常にウォッチしている。
このため、日経新聞など日本の大手新聞の国際面は外国紙のそれと比べて充実している。例えば、共同通信と米AP通信は提携し相互の記事を配信しているが、国内報道メディアに掲載されるAP電の記事は相当な数にのぼる。特に海外の戦争・紛争に関する報道写真はAPやロイターなど国際通信社にほぼ依存している状況だ。人工知能(AI)技術の進歩で翻訳のスピードや質といった問題は消滅しつつある。これを国内報道メディアが上手く取り込めれば、時差と提携を利用してグローバル報道メディアにも対抗可能であろう。
次に、WSJ日本版など外国報道メディアの脅威に対する国内報道メディアの差別化戦略の一例を見てみよう。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください