パブリック・ジャーナリズムとの融合がもたらす効果とは?
2022年08月26日
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ(平家物語)
盛者必衰、邯鄲の夢。 日本国内ではあまりに有名な古典の一節だが、古今東西の報道メディアにもこれが重なり合う。
今回はIT革命後の一時期、新規参入勢力として世界的な報道メディア界の頂点を極めたものの、すぐさま衰退の道を辿ってしまった米国インターネット関連企業のAOL社の栄枯盛衰について考察していきたい。その後、これまで紹介した報道メディア業界への新規参入による市民社会への影響について述べたい。
IT革命後の報道メディア界への新規参入勢力として、連載第6回で「個人化」と「脱中心化」という構造転換を促した米国のTwitter社を取り上げた。これはジャーナリズムの世界に一般市民が主体的に参加することを可能にしたパブリック・ジャーナリズムの事例でもあった。
また、デジタル・トランスフォーメーション(DX)によって復活を遂げた米国の伝統的な報道メディア、ワシントン・ポスト (WP)社を取り上げた(連載第7・8・9回)。これは報道メディアの「グローバル化」と「デジタル化」の事例でもあった。
Amazon社のジェフ・ベゾス氏が買収したWP社はコア・コンピタンスとしてのジャーナリズムを継承しつつ、ビジネスモデルを一転させた。これらは現時点では報道メディア界への新規参入の成功例といえよう。
連載「市民メディア白書」の初回~第10回はこちら
一方で、当然ながら新規参入は成功例よりも失敗例のほうが数多くある。ここでその最たる事例として米国のAOL社を取り上げたい。
1990年代後半、IT革命時の寵児として知られたAOL社は21世紀初頭の一時期、高級誌の「Time」や一般誌の「People」、世界的な報道テレビ局の「CNN」、そして映画大手の「ワーナー・ブラザース」を傘下に収め、世界的に報道メディア界の頂点を極めた。それもつかの間、たった2年で凋落の道を歩むことになった。
 monticello/shutterstock
monticello/shutterstock報道メディア業界を含め米国経済社会のダイナミズムは弱肉強食の完全競争市場から生まれる。これは保護産業的な日本の新聞業界やテレビ業界には見られない特徴の一つである。AOL社はそこに果敢に挑んで勝者になり、飲み込まれて敗者にもなった。ここでまず、AOL社の事例について見ていきたい。
>>関連記事はこちら
インターネット接続サービスで知られる「America Online(AOL)」を運営した前身の企業を含めるとAOL社は1985年に創業した。1990年代になると米国でのインターネットとパソコンの普及と共に業績を伸ばした。そして1995年、Microsoft社が基本ソフト(OS)、「Windows 95」をリリースすると、市民社会のメディア環境が一転した。同時にインターネット回線の通信速度が飛躍的に高速化し、その利用人口も急速に拡大していった。
米国ではこれが報道メディア業界に破壊的な影響を与えた。ここで筆者が米国で経験した実例を紹介したい。
当事、筆者は米国南部のジョージア州アトランタで共同通信社の支局員として1996年アトランタ五輪の関連取材をしていた。共同通信社のアトランタ支局は月額3000ドルで米国のAP通信社と専用回線による総合ニュースとスポーツ・ニュースの配信契約を結んでいた。一方、この支局にインターネット回線を敷き、パソコンを設置した。そこで筆者はAOL社が提供する月額約10ドルのインターネット接続とコンテンツ閲覧の契約をした。
AOL社はポータルサイトの先駆けであった。そのホームページにはAP通信社が配信する総合ニュースやスポーツ・ニュースを含めたすべての分野の記事が掲載されていた。これらの記事が共同通信の契約額の300分の1の値段で閲覧できたのである。
共同通信の契約には記事の翻訳・転載の許可が含まれていたものの、AOL社によるAP通信の記事サービスはより充実し、しかもただ同然の安価であった。当時、支局長と二人で「こんなことはあり得ない。APも共同も潰れてしまう」とAOL社の暴力革命的な価格設定と、通信社の将来を懸念した。
また、アトランタ五輪では大会スポンサーでコンピューター大手の米IBM社が競技結果を大会組織委員会のホームページに、五輪の公式言語である英語、フランス語、スペイン語による無料で速報することを計画していた。つまり、マス・メディアを中抜きにして、オリンピックの競技結果を無料で読者に提供することを意味したのである。
大会組織委と五輪大会を取材する世界各国・地域の報道メディアとの協議がもたれたが、荒れに荒れた。この計画に猛烈に反対したのが米国のAP通信社と英国のロイター通信社であった。両社が五輪報道で競技結果を世界各国・地域の報道メディアに速報することで収益を上げていたからである。結局、速報サービスは大会を取材する報道メディアに限られたものになった。
「ドットコム・バブル」という時代の大きなうねりに乗って、AOL社は飛躍的に成長した。1990年代後半になるとAOL社は同業のCompuServe社や無料ブラウザのNetscape Communications社を買収して、その規模を爆発的に拡大させた。
そして2000年、「世紀の結婚」といわれたこの超巨大合併を成し遂げた。米国連邦取引委員会(FTC)や欧州委員会、そして米国連邦通信委員会(FCC)から市場独占や自由競争などで懸念されつつも、1922年創業の世界でもっとも影響力のあるメディア・エンタープライズ、「タイム・ワーナー」社を、AOL社は1110億ドル(約12兆4000億円)で買収したのである。これによって市場価値3500億ドル(約37兆8000億円)の「AOLタイム・ワーナー」社が誕生した。
AOL社の狙いは報道メディアとしての「Time」や「CNN」よりも、むしろタイム・ワーナー社が持つ規模全米2位のケーブル網にあった。これで全米にくまなく拡がる通信インフラを押さえ、メディア・プラットフォームの構築を目指した。これはTwitter社やWP社のプラットフォーム戦略と同様、基盤を確保して自社の規格をスタンダード化させる戦略である。
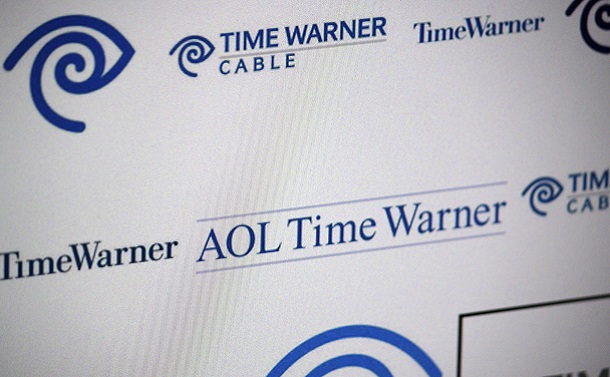 360b/shutterstock
360b/shutterstockこうして一介のITベンチャー企業がこの伝統的かつ超優良といわれたメディアを買収し、創業わずか15年で世界最大のメディア・コングロマリットにのし上がったのである。(Wired, 2000; FTC, 2000; VR Digest, 2001=2017)。
この急成長を支える仕組みが、買収する企業が自社の株式で相手企業を買収する「株式交換」による企業の合併・吸収(M&A)であった。この手法の最大のメリットは
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください