「余命宣告」を受けてから1年、闘病の記録
2022年09月30日
ジャーナリストの隈元信一さんが自身のがん闘病をつづる連載を始めます。題して「死を見つめる」。ドキリとする言葉ですが、朝日新聞の家庭面記者だった1980年代に手掛けた医療の連載記事と同じタイトルです。いきなりの余命宣告をどのように受け止め、そこからどう病と向き合ってきたか。どんな情報を集め、医療や介護関係者と話し合いながら、納得のいく治療を選んできたか。そして、できる限り自分らしい生活を続けてゆくにはーー。一人の患者として、報道記者として、考え続ける日々を記録します。
2人に1人が、がんになる時代。そう聞いても、自分だけは大丈夫と考えてしまいがちだ。ほかならぬ私がそうだった。70歳に近くなっても、全く無防備だった。
ところが昨夏、たちの悪い末期がんを告知され、「3カ月から半年」の命と診断された。約50日間の入院から介護施設を経て、現在は在宅ケアのサービスを受けながら自宅で闘病生活を続けている。告知から1年が過ぎ、ようやく手記を書く心の余裕ができた。
コロナ禍のさなか、がん治療の最前線で起きていることや自分自身の思いなどを報告したい。
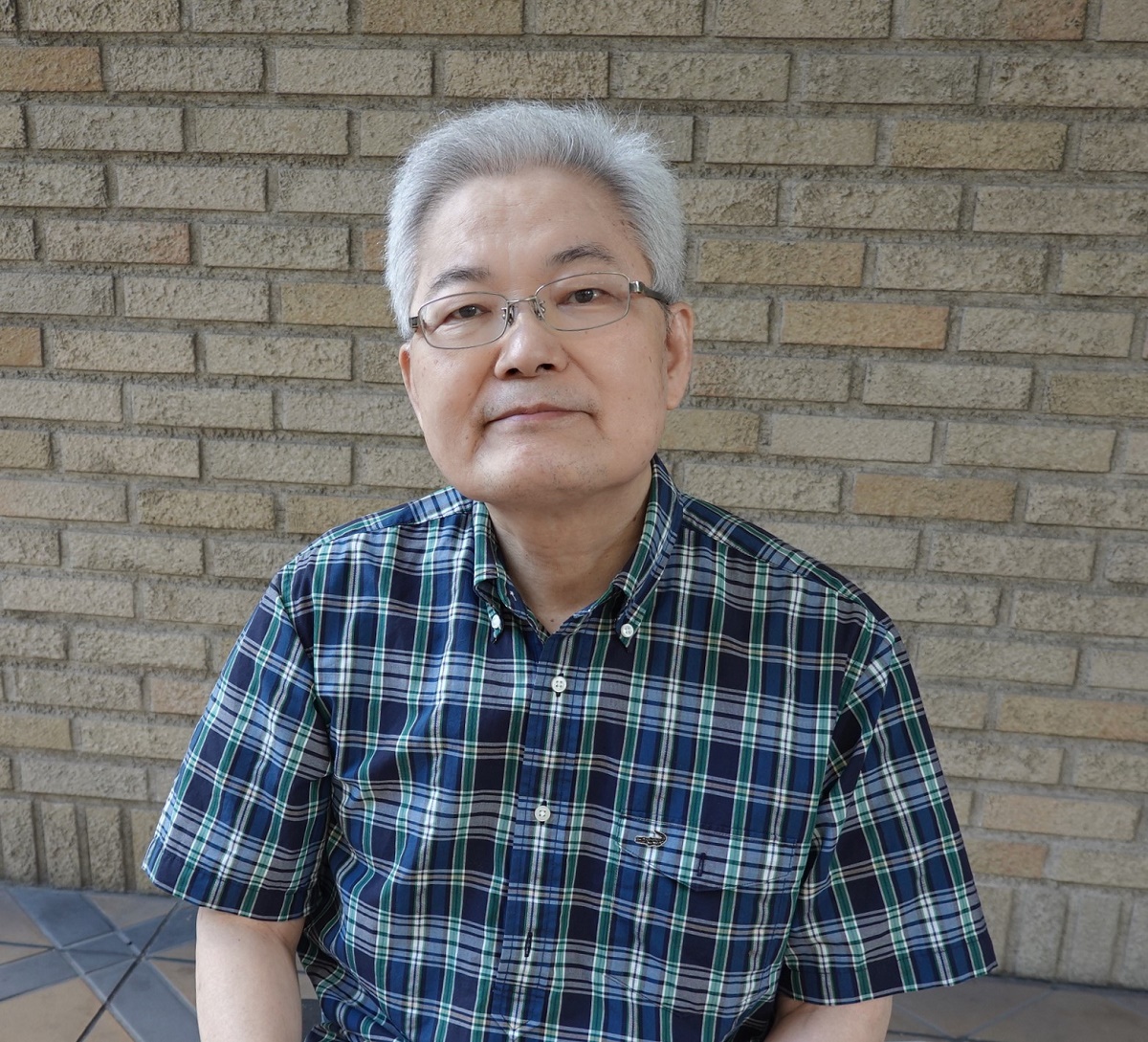 筆者・隈元信一近影
筆者・隈元信一近影最初に体の異変に気づいたのは、2021年3月のことだ。
尿意を催し、トイレに頻繁に行くようになり、排尿時に痛みを感じるようになった。「また石かな」。これまでに何度も胆石や尿路結石にかかった経験がある私はそう思い、自宅に近い泌尿器科のクリニックを訪ねた。
診断は「前立腺炎」だった。薬をもらい、それがなくなると通院を重ねた。
夏に入って、腰に激痛が走るようになった。結石の痛みとはどうも違う。
血中の腫瘍マーカーの値も高い。がんの疑いが一気に浮上した。紹介状を書いてもらって、私が住んでいる東京都大田区内にある大森赤十字病院ヘ。8月20日から1泊2日の検査入院、MRIや前立腺の細胞をとって調べる生検を受けた。
結果は、がん以外の何物でもなかった。前立腺がんだけならまだ良かったが、普通の腺がんとは違う神経内分泌がんとの混合がんで、すでに全身の骨や肺などに転移していた。
8月31日、腰から下肢にかけての痛みがひどく、体を動かせないほどになった。大森赤十字病院に電話すると「すぐに入院しましょう」。着の身着のままで直行して入院し、造影剤を使うCTや全身のMRIなどの精密検査を受けた。
「とにかく、この激痛を何とかしてください」
こちらの望みはただ一つだった。
すでに鎮痛剤(麻薬)は飲んでいたが、強烈ながんパワーの前に圧倒される感じだった。患部に放射線を照射すれば痛みの緩和が期待できるというが、この病院には、その武器がない。先端医療ができる専門病院か大学病院に移る必要があった。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください