虐待行為を正当化してしまう〈先生アイデンティティ〉という要因にどう対応するか……
2023年01月29日
2022年11月、静岡県裾野市の認可保育園さくら保育園において保育士3名による在園児への虐待事件が起きた。あってはならない虐待はなぜ起きてしまったのか? 「保育士はなぜ虐待をしてしまうのか?~保育士・研究者による体験的考察(前編)」に引き続いて考える。
前編でも記したが、筆者は保育士免許を取得して約8年認可保育園に勤務、数年前から保育士の傍ら大学院で保育学研究を始めた。昨年夏(2022年7月)に保育園を退職し、大学院での研究を続けながら、保育士養成の専門学校や大学で非常勤講師として学生の指導にあたっている。
前編の最後では、疲労困憊(こんぱい)するなか、保育士の心の中に湧き上がりがちな苛立ち、怒り、憤慨、腹立たしさといった感情(以下、〈ネガティブ感情〉)を子どもにぶつけてしまう前に、保育士同士の相互ケアを通してコントロールすることの重要性を指摘した。後編では、虐待行為を正当化してしまうもう一つの要因について説明するところから、さらに考察を深めてみたい。
 虐待事件があったさくら保育園=2022年12月6日、静岡県裾野市公文名
虐待事件があったさくら保育園=2022年12月6日、静岡県裾野市公文名正直言って、筆者もまた、プライドを守るために〈ネガティブ感情〉を誰にも相談できなかった一人である。そして、〈ネガティブ感情〉に突き動かされた行動が危うく虐待につながりかねなかったと反省した経験がある。
実はこうした行動の裏には、もう一つの要因が存在する。それは何か?
まだ、駆け出しの保育士だった頃、筆者は他児を叩いたり蹴ったり、物を投げてしまうAちゃんを担任した。ある日、繰り返されるこの問題行動をなんとか止めようとAちゃんの片腕を掴(つか)んだ。
余裕がなかった筆者の心は、怒りで満たされてしまっていた。そのためか、Aちゃんの腕を掴む手につい力が入ってしまった。次の瞬間、Aちゃんが体をすくめて萎縮するのがわかった。そして、大声で泣いた。
一見片腕に触れているだけなので、外からは虐待に見えない(監視カメラも役に立たない)。しかし、大人の大きな手では、僅(わず)かに力を入れただけで、その怒りがダイレクトに伝わってしまう。ハッと我にかえり、その手を離してAちゃんに謝った。
冷静に考えると、一連の問題行動はAちゃんの気持ちのSOSのようなもの(いわゆる注目行動)だったのだろう。注意や叱りではなく、Aちゃんはどのようにしてほしかったのか、もっとじっくり気持ちを聞き届けることが、保育士として筆者がやるべきことだったと今になると反省する。
★「保育士はなぜ虐待をしてしまうのか?~保育士・研究者による体験的考察(前編)」は「こちら」からお読みいただけます。
しかし、血気盛んだった当時の筆者は、子どもたちをしっかり躾(しつけ)なくてはいけないといった思い込みがあった。一方的に「その子のためを想って」という大義名分を掲げて自分を正当化し、「先生」としての振る舞いや発言を省察することもしないまま、自分が考える理想的な子ども像を目の前の子どもたちに押し付けていたように思う。
こうした独善的で自制心を欠いた教育欲求を携えたまま、常に正しい「先生」として過剰に振る舞いすぎてしまう様子を、皮肉を込めて〈先生アイデンティティ〉と名付けてみる。〈先生アイデンティティ〉は、その保育士の人格そのものと統合されながら、子どもたちと「先生」という圧倒的に差がある非対称的権力関係において暴走することがある。
次に、筆者の新人時代に出会った教育熱心だと保護者からの評価も高いベテラン保育士の事例を報告しよう。
給食が食べられないBちゃんは、毎日のように給食の時間が終わっても最後まで席に残っていた。ベテラン保育士は、Bちゃんの口に食べ物を無理矢理押し込んだ。Bちゃんは、頑張って咀嚼(そしゃく)するものの、飲み込むことができず、思わず口から食べ物を吐き出した。
しかし、ベテラン保育士はBちゃんを許さなかった。白飯に一度嘔吐したものを混ぜ合わせ、Bちゃんの口に運んで食べさせたのである。Bちゃんは嗚咽しながらなんとか飲み込んでいた。
新人(保育補助)だった筆者に対してもそのベテラン保育士は、子どもには給食を必ず残さす食べさせるよう指導していた。他にも、お昼寝からの目覚めの際にぐずるCちゃんを無理矢理洗面台に連れて行き、「いつまでも泣くんじゃない! 顔洗ってシャキッとしなさい!」といって、真冬の冷たい水道水を泣いている子どもの顔面に浴びせていた。というより、頬を叩いていた。
現在、このような行為が行われたら、即座に虐待事件である。だが当時、周囲の保育士たちは、そのベテラン保育士の虐待行為を知りながら、注意や意見をすることはなかった。保育士資格取得前の新人だったとはいえ、上に報告しなかった筆者にも責任がある。
ベテラン保育士は、まさに〈先生アイデンティティ〉そのものだったように思う。真剣な(いや、怒りに満ちた)眼差しで子どもたちを指導(いや、威圧だ)し、「その子のためをためを想って」という大義名分を疑いもしない。BちゃんもCちゃんも、気持ちは置き去りのまま反発する術もなく、ただ泣くしかなかった。
そこでは〈ネガティブ感情〉が〈先生アイデンティティ〉を加速させ、虐待行為に発展する。こうした虐待行為は教育や躾の一環として正当化されつつ、強烈な怒りに任せて行われる。
 milatas/shutterstock.com
milatas/shutterstock.comさくら保育園での虐待事件の報道を見た筆者が、「保育は虐待と隣り合わせだ」とSNSに呟いた話は前編に書いた。咄嗟(とっさ)に出たこの言葉は、教育社会学者である内田良氏の論考からヒントを得ていた。
「教育という名のもので、子どもの心身が大きく傷つけられる。教育は、人権侵害と隣り合わせになりうる。」(内田 2018、p.131)
内田氏は、部活動顧問の暴力的な指導が招いた子どもの自死、いわゆる「指導死」の事例から、子どもが自殺してもなおその暴力行為が「教師のなかではそれは正しい指導、すなわち教育であると理解されていた」ことを示し、教育という枠組みによって虐待が正当化されることを明らかにしている(同、p.131)。
「指導死」親の会の代表である大貫隆志氏(2018、p157)も、教師自身の「子どものためを思う善意が、本当に子どものためになっているのか」を教師たちでモニタリングし合う必要性を訴えている。子どもの自死という問題が含まれることや、学校と保育園という施設としての機能の違いから、単純に同列で論じることはできないが、教師や保育士という「先生」の立場にある人間が、〈先生アイデンティティ〉をどうモニタリングしていくかという点において、参考になるだろう。
〈先生アイデンティティ〉の出発点に悪意はない。もとより、「子どもが大好き」で保育士を目指したのだから、子どものより良い成長を願ってのことだ。しかし、いつの間にかそれが虐待行為にすり替わっていないか、省察的視点によるモニタリングは必要だと筆者は考える。
子どもたちは健気だ。そんな酷(ひど)いことをする保育士に対しても、「好かれたい、愛されたい」という欲求を持っている。ある意味、保育士は子どもから無条件に愛される権利を持っているようなものだ。だが、こうしたアンビバレントな権力勾配を含有してしまう人間関係のなかで、保育士は自分の教育欲求が間違っているのではないかと自省する感覚が鈍くなり、「先生」として尊大に振る舞いすぎる傾向に歯止めか効かなくなることもあるのだろう。
子どもの気持ちを置き去りにしていないか。威圧や暴力によって管理統制してしまっていないか。自分だけの常識に捉われすぎていないか――。保育士間でモニタリングし合う関係を構築し、個々の保育士が自身の〈先生アイデンティティ〉を振り返る機会を持つべきなのだ。
★「保育士はなぜ虐待をしてしまうのか?~保育士・研究者による体験的考察(前編)」は「こちら」からお読みいただけます。
とはいえ、〈先生アイデンティティ〉のモニタリングはとても難しい。「先生」という言葉は不思議な力を持っているからだ。
お互いを「先生」と呼び合う関係は、意地悪に見れば、「ポライトネス」をし合っているようなものである。ポライトネスとは、お互いの体裁やプライドを傷つけないように、人間関係の距離を調整するための戦略的言語実践を意味する。つまりは、お互い心地よく過ごすための気遣いや配慮だ。
新卒の「先生」であれば、まだまだ指導やアドバイスを受け入れる立場であるが、勤務10年以上のベテラン「先生」たちは、お互いの保育について行き過ぎた行為を指摘し合える関係が構築できているだろうか。お互いを「〇〇先生」と敬称をつけて呼び合う間柄が、お互いのメンツを保つ、お互いの領域に介入し合わない、といった暗黙の協定として機能していないだろうか。
事例に挙げたように、筆者を含め周囲の保育士たちは、ベテラン保育士の虐待行為を指摘できなかった。ベテラン「先生」の顔色を伺いすぎてしまい、子どもを守るという一番の使命を果たさなかったのだ。
これは筆者の憶測であるが、さくら保育園に勤務する他の保育士たちは、1歳児クラスの虐待を早い段階で気づいていたのではないか。1歳児クラスの保育活動に疑念や不審を抱いていても、ポライトネスによって30代のベテラン「先生」たちのメンツに配慮し、踏み込んだ指摘ができない。すなわち、モニタリング機能が欠如したのではないか。その結果、早期に指摘されて改善する段階を逃し、告発という形になってしまったのではないかと想像する。
実践的に〈先生アイデンティティ〉をどのようにモニタリングするのか。この難しい問題への回答には至っていない。今後の課題とし、筆者自身も引き続き検討していきたい。
 APChanel/shutterstock.com
APChanel/shutterstock.com前編で触れた「てぃ先生」(YouTubeや各メディアで活躍するカリスマ保育士)は、出演した番組で監視カメラの設置に賛同している。今後、監視カメラ設置への賛同意見は多くなっていくだろう。しかし、これは保育士にとってはかなりつらいのも事実だ。ただでさえ逼迫(ひっぱく)している業務量に加え、カメラの向こう側の視線も感じながら働くなくてはならないからだ。
とはいえ、保育士は監視カメラに少しずつ慣れていく必要もあると思われる。保護者や子どもの安心感のためだけでなく、保育士自身の真っ当な仕事を証明するためにも、である。
監視カメラが虐待への一定の抑止力になることに異論はない。しかし、レジ操作や万引きを監視することとは、わけが違うとも思う。保育は、子どもにとっても保育士にとっても生活そのものであり、非定型な日常コミュニケーションの場である。そこには冗談や笑いから、涙を流すような場面もある。子どもたちとの対話を通じて、保育士は創意工夫を凝らした豊かなコミュニケーションを展開する。
そんな保育の専門的コミュニケーションが、監視カメラによって公にされ、適切かどうかの判断が下されようとしているわけだが、それが保育の営みそのものの萎縮を引き起こすことはないだろうか。
例えば、泣いている子どもがいるのに、保育士がすぐに駆け付けなかった映像を見た人は、子どもを放置しているとして、虐待や不適切な保育を疑うかもしれない。だが、現実の保育現場では、保育士が少し離れて泣いている子どもを見守りつつ、子どもが自分で気持ちを切り替えられるタイミングを見計らっていることはしばしばある。保育士は、その子が泣き止んだら、笑顔いっぱいに抱きしめてやろうと心の中で計画している。
虐待だと疑われないためには、こうした現場感覚に即した保育支援は避けられ、「泣いている子どもには、すぐさま駆けつけるように」などとマニュアル化されるだろう。これが子どもにとって本当にいいことなのか、そうでないのか、保育観・教育観ともからみ、判断は難しい。
筆者は、子どもたちには、表情豊かで人間味の溢れる優しい保育士に囲まれて育ってほしいと感じている。監視カメラを意識したマニュアル化された対応や、画一化された人格の保育士ばかりになるなら、それこそAIやロボットに保育を任せても変わらない。言い過ぎかもしれないが、そう思っている。
★「保育士はなぜ虐待をしてしまうのか?~保育士・研究者による体験的考察(前編)」は「こちら」からお読みいただけます。
昨年の虐待報道の後、「不適切な保育」という言葉を散見するようになった。虐待には至らなくても、子どもの人権侵害になりそうな予兆を取り出して、「不適切な保育」と言っているようだ。いかにも保育にありがちな、柔らかい言葉への変換である。
しかし、「不適切な保育」として保育士の行為を精査するとき、どこか逃げ道をつくっているかのように筆者には聞こえる。虐待になる手前は、本当にセーフだろうか。不適切を適切に改善していくことは当然として、その「不適切な保育」を行なった保育士を免罪する機能がうっすらとあるように思えてならない。
被害を被った子どもたちがいるのに、なかったことにしてしまう可能性もある。今、保育士たちは、保護者からも地域社会からも「あの保育園は大丈夫か?」「あの保育士は虐待していないか?」という疑惑の視線を背中に感じながらも、地道な保育活動を連綿とつなげている。保護者たちにしても、我が子の安全について不安を払拭(ふっしょく)したいという想いであろう。
とはいえ、疑惑の払拭はなかなか簡単なことではない。そんな最中、「不適切な保育」などと曖昧な言葉で自分たちの仕事についての査証をぼかしてしまっては逆に不信感を招きかねない。
これは、保育に携わる者として、自分たちの仕事を批判的に自省的に振り返り、明確な改善を図るべきチャンスかもしれない。そのためにはやはり「不適切な保育」などと柔らかく曖昧な言葉を使うのではなく、あえて「虐待」という厳しい言葉で保育を再検討するべきであろう。
前編で挙げた4つの要因は、日本の保育に前に横たわる大きな課題だ。これらの改善も進めつつ、まずは保育士自らが自分たちの内面について向きあってほしい。
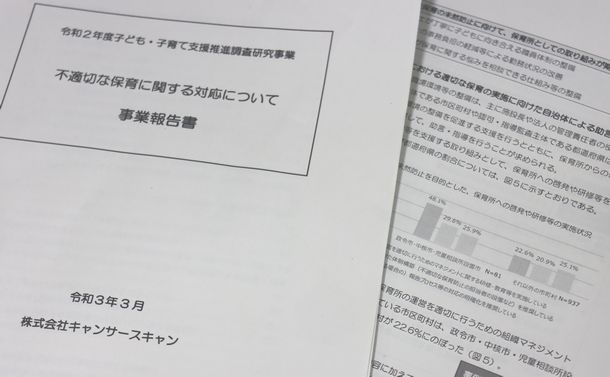 「不適切保育」への自治体の対応を調べた厚労省の調査研究= 2022年12月6日
「不適切保育」への自治体の対応を調べた厚労省の調査研究= 2022年12月6日本稿を「保育士はなぜ虐待をしてしまうのか?」というタイトルをつけたのには意図がある。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください