基礎を大切に、傲慢にならず、自分が変わることを怖れずに
2023年04月17日
東大〈宇野ゼミ〉の学生が、進路に悩む同世代の若者たちに向けて発信するインタビュー企画の第2弾は、「空想科学研究所」主任研究員の柳田理科雄さんにご登場いただく。マンガやアニメ、ゲーム、昔話の世界にあふれる「オドロキの現象」を読み解き、子どもたちを科学の世界にいざなってきた。1996年に刊行した『空想科学読本』は大ベストセラーとなり、YouTubeの番組「空想科学研究所KUSOLAB」の登録者は20万人を超える。そんな柳田さんだが、若い頃は挫折の繰り返しだったという。その果てに刻み込んだという「未来を空想する重要性」を、若者たちに向けてあらためて語っていただいた。
 柳田理科雄さん
柳田理科雄さん〈やなぎた・りかお〉1961年、鹿児島県種子島生まれ。東京大学理科Ⅰ類中退。明治大学理工学部の兼任講師。さまざまな学習塾の講師を経て、1999年、メディアファクトリーの編集者だった友人の近藤隆史さんと共に空想科学研究所を設立。アニメやマンガや昔話などの世界を科学的に検証し、各地での講演、メディアへの出演などを精力的に行っている。これまでの空想科学の検証事例は1千を超える。主な著作に『空想科学読本』『ジュニア空想科学読本』『ポケモン空想科学読本』シリーズなどがある。2007年からは全国の学校図書館向けに「空想科学 図書館通信」を週1回、無料配信している。「理科雄」は本名。
——まず科学に関心を持った背景についてお聞きしたいのですが、「理科雄」という名前はやはり最初のきっかけになったのでしょうか。
鹿児島県の種子島で生まれましたので、自然に囲まれた環境でずっと過ごしてきました。そんな故郷で5歳のときに、ロケット基地の建設が始まったんです。同じ頃に「ウルトラマン」のテレビ放送も始まりました。ごく自然に自然とか宇宙に対する興味が開かれていきました。名前が「理科雄」だから理科に興味を持った、ということはなく、理科に興味を持った後で、学校の科目に「理科」というものがあることを知った記憶があります。
——その後、小中高と進む中で科学に対する気持ちは変わっていきましたか?
科学者になりたいと思ったきっかけは、小学校5年生ぐらいのときに湯川秀樹博士と朝永振一郎博士を知ったことでした。鹿児島市内の高校に進むためには、中学から鹿児島に行くというという選択肢が現実的でした。だから中学入学のために島を出たのは、大きなトピックでした。人生がガラッと変わったので。
高校に入って、京都大学の佐藤文隆先生が書いた宇宙論の本に出合いました。これが、科学への思いが非常に確固たるものになったきっかけです。「僕は京大に入ってこの先生の下で学ぶんだ」って決意したわけです。
当時は京都大学の理学部はボーダーラインの偏差値が69、一方僕自身の偏差値が52で、無茶な受験でしたけれども、僕は「そんなの関係ない」と。「俺の根性で、1年のうちに絶対に偏差値17上げてやる」と1日6時間の勉強をしました。高2の秋にそういう勉強を始めて、高3の冬、いよいよもう入試が近いというところで最後の模試を受けたら、偏差値は52、まったく変わっていなかった。
その原因ははっきりしています。例えば英語で言うと、僕は5文型の存在を知らなかった。それは文法のテストに形式的に出るだけのもので英語の本質には関係ない、という捉え方をしていました。数学も同じで、公式は知っているんだけど、なぜその公式が成立するのかには興味がなかった。英語はとにかく長文を読んで、数学はとにかく難しい問題を解いて、という勉強をしていました。先生からは「基礎からちゃんとやらんか」と言われたけれども、僕は「京都大学に基礎は出ません」と言って難問ばっかり解いていた。そういう生徒の成績が伸びるはずがないんです(笑)。それでも京大を受験して、当時は「絶対受かった」と思ったんですね。
けれども、合格発表を見にいくと不合格だった。肩を落として帰路についた新幹線の中で、ふと網棚に置いたままの新聞を見つけたんです。そこには「京都大学の佐藤文隆教授が退官」と書いてあったんです。これで京大に行く理由が完全になくなってしまった。
そこからどうしたのかというと、受験世代の子どもらしく、「だったら東大に行ってやる」という発想をしました。京大は純粋な科学への憧れで選んだわけですけども、東大の方は京大より上だからという理由で受験したわけです。
それで、予備校が始まるまでの2週間に何をしようかと考えた時に、そういえば高校の先生が基礎をやれと言っていたなと思い出し、書店に行って問題集を買いました。そこで、英語なら「5文型ってこういうことだったのか」とか、古典なら「助詞助動詞ってそういうことだったのか」というふうに気がつきました。6月の最初の模試で偏差値77が出て、そこから成績が下がることはなく、もう当然のように合格したと(笑)。そこまでは良かったんです。
——と言いますと?
いまでも人生最大の後悔なんですが、「自分は頭が良い」と思ってしまったんですね。しかも「生まれつき良いんじゃない、努力でここまで頭を良くしてきたんだ」という絶大な自信を持った。
だから、大学の数学や物理、化学は、高校時代とはまったく違う勉強法が必要なのに、自分は「俺にわからないということは、教え方が悪い」と思ってしまったたんです。東大には多分100人に1人ぐらいはこんなことを思う奴がいると思うんですけど(笑)。僕は見事にそれにはまって、授業がまったくわからなくなってしまった。
それで結局どうするかっていうと、もういわゆる東大生っていう名前だけが僕に残ったわけで、それを使って一番生きていける場所って言ったら学習塾の先生だった。東大っていうだけで実力も何にも見ないでいい仕事をくれるわけですから、僕も飛びつきました。
——それは何年生の時ですか?
アルバイトは入学直後からやっていましたが、塾に就職したのは5年目の2年生のとき5年目の2年生です。
——5年目の2年生!?
1年生を3年、2年生を2年やったので。
——なんと! そうだったんですね。
大学にはもう本当に何の用もないんだけど、籍だけを置いていたわけです。やっぱり「せっかく東大に入ったのに辞めるのはもったいない」という頭があった。その間ずっと学習塾でアルバイトして、23歳で大学を辞めると同時に学習塾に正式採用されたって感じですね。
——大学を辞めるうえで葛藤や抵抗感はありましたか。
ありました。僕を大学に出すために、両親はもちろん、祖母2人も鹿児島へ出てきて僕の生活の面倒を見てくれたりしていました。だから僕の場合は僕が大学へ行って卒業して偉い人になるっていうのは柳田家の一族をかけた野望だったわけです。それを潰えさせてはならないっていう思いもありました。でも大学を中退し、「自分はこれで完全に科学と縁が切れたな」っていう感じでした。科学をやるために学者を目指して入った大学で、一歩も進めなくなってしまったことは、大きなショックでした。もう自分の人生は前に進まない、と思ってしまいました。
だから、僕が若い人に言いたいことは二つしかないですね。一つは「基礎を大切に」。もう一つは「絶対に傲慢になってはいけない」。何かうまくいったときに自分を過大評価したり、過信したりしてはいけない。あるいは、人生において何かと衝突したときに「これは自分が変われるチャンスだ」と思って、自分の側が変わっていって、その先に進む、という姿勢を持ってほしいですね。ここで「俺は正しい、お前が間違っている」という発想は絶対だめですね。それはもう相手が法律であっても、昔からの風習であっても、わがままな社長の発言であっても、そうだと思います。
——塾講師という仕事は、当時ご自身はどのように感じていたのでしょうか。
僕は天職だと思いました。要するに子どもたちが塾に来る理由は勉強ができないからなんですね。塾には色々ありまして、すごく勉強できるやつがもっとできるようになりたいと思って行くこともあれば、学校の勉強がうまくいかないから行く、という場合もあれば、親に言われたからという理由で来る子どもとか、色々いるわけですね。
僕が見ていたのは、どちらかというと勉強が苦手な子どもたちのグループでした。「勉強ができない」というのにも、理由は色々あるんですよね。そもそも勉強をやろうとしないケース、頑張っているのにできないケース、あるいは勉強の方法がよくわからない……とさまざまあるんです。子どもたちがそれぞれ勉強できない理由はじっと見ていると分かってきます。それに手を差し伸べると、成績って伸びるんです。この子には数学も暗記科目と同じように教えよう、とかその子に合わせた教え方は色々とあるわけですね。
でも、この教え方について根源的な悩みを抱くようになりました。本当に生徒のためになっているのだろうか、と。つまり、僕が近くにいて教えてあげると、この子の成績は伸びる。けれども、僕がいなくなったらどうするんだろう。もしかしたら僕はその場その場で喜ぶことはやってあげているけれども、教育としては間違ったことをしているのかもしれない。そんな風に思い始めたんです。30歳ぐらいのときでした。
そこで自分の学習塾を作りました。その名も「天下無敵塾」。「誰だって自分自身の道を突き進めば、その道の中で日本一、世界一になれるんだ」という意味です。授業の内容は「徹底的に自分の頭で考える人間になりなさい」です。「どの公式を覚えればいいですか」って聞かれたら「公式は自分で作りなさい」。「先生これのコツは何ですか」「それを考えるのが勉強だ」……そんな授業をしていました。
それで賛同してくれる保護者もいたんですけども、当然ながら、そういう勉強のさせ方は、中間テスト、期末テストで良い点数を取らせられないわけですね。目先の成績アップにはなかなかつながらないです。だから、段々と「あの先生は言っていることは立派だけど、あの塾に行っても成績は上がらない」というのがその地域の共通認識になってきて、生徒も来なくなっていきました。
当時すでに結婚していたんですけども、収入がないので、最後は妻の実家に転がり込んでいましたね。34、5歳の時、もう長男も生まれているような時でしたが。だから、うまくいっては未来が見えなくなる、ってことをこれまでに2回経験したっていうことですかね。
 インタビュアーの柳澤岳と吉村綾乃
インタビュアーの柳澤岳と吉村綾乃——そうした挫折を乗り越えて次の行動を起こそうとするモチベーションや情熱を、どうやって回復したのでしょうか。
情熱というよりも、「またどこかで雇ってもらえれば、自分の絶好調時代が始まる」と信じていたということだと思います。
大学を中退したとき、大学に跳ね返されたときは、完全に僕がただただ馬鹿でした。高校時代の同級生がいて、当時は成績も何もかもまったく及ばなかったんですが、彼と同じ東大に合格した瞬間に「よし、俺はアイツに並んだ」と思ったんですね。でも、自分が壁にぶつかった時に、安いプライドが邪魔をして、彼に相談することができなかった。
塾の失敗については、完全に自分のせいですね。いま振り返っても、これだけは幸いだったと思うのは、「俺は正しい。評価しない周りが悪い」という発想だけはしなかったことだと思います。わかってもらえなかったっていう無念があっても、相手が悪いという発想にはならなかった。大学時代の挫折とは、そこが違いました。
そんなときに、中学校の同級生で当時宝島社の編集者だった近藤隆史君(現・空想科学研究所所長)が「本を書かないか」と声をかけてくれたんです。印税として96万円をくれるということでした。これは1200円の本を印税8%で1万部刷るという計算です。まったく無名の新人に打診する話としてはあり得ない話です。困窮していた僕を救済するために企画を強引に会社に通してくれたんだろうと思います。
——そこで初めていざ本を書いてみるとなったときに、どんなことに苦労しましたか。
最初は、物理の答案のような原稿になってしまいました。例えば、ウルトラマンが空を飛ぶと何が起きるのかを、物理法則を並べて説明する。漏れのない完璧な説明をしようということしか頭にない。読む人のことを何も考えていなかった。バーッて書いて、それに近藤君が手書きでワーッとそれ以上に分かりにくい点などを書き込んで、それを僕がまた直して、また修正が大量にきてということを4回やったと思います。
——そして、出版されると大きな反響があり、ベストセラーになりました。
もうびっくりしましたね。まったく予想していないので。多分、誰も予想しなかったことだと思います。発売の段階でもう重版が決まったと聞いて、信じられない思いでした。
——その後執筆を重ねる中で、「書く」ということへの意識に変化はありましたか。
自分が何を書きたいかよりも、読者が何を読みたいかの方が大事なんだ、というのが時間をかけて分かってきたということだと思います。
最初はどうしても塾の先生の性分で「ここまで説明したのなら完璧に説明したい」っていう思いがあるわけです。でも、そこは読者はべつに知りたくはないわけですよね。不要なところを削って読者の興味を保たせながら、先へ先へと引っ張って、楽しい結論に導く。それが理想なんですが、そんなことは最初は全然できない。ひどい場合には「この文章を入れなかったら、自分がこの現象を勘違いしていると思われる」と考え、自分の評価を下げたくないがゆえに、読者にとっては読みづらくなる文章を入れるなんてことをやっていましたから。
それが段々と変わることができたのは、『ジョジョの奇妙な冒険』のキャラクター岸辺露伴の言葉に出会ったのも大きかったかもしれない。「ぼくは『読んでもらうため』にマンガを描いている!」。荒木飛呂彦先生もそう思っていらっしゃるんでしょうね。
——お話を伺っていると、大学受験や、塾講師の仕事における努力の形と、この本の執筆活動における努力の形を比べたときに少し変化があるな、と思いました。塾講師までは自分で試行錯誤していく、自分なりのやり方を一生懸命突き進んでいく、というのが軸としてあった。一方、本の執筆活動においては、徐々にではありながらも読者に寄り添うようになっていく。著者にとっての読者は講師にとっての生徒のようなもので、自分の発信した内容の評価者じゃないですか。その評価者からのリアクションを自分の発信の活動にフィードバックする発想が、塾時代と本の執筆時とは大きな違いとしてあるように感じます。
そうですね、そこが明確に違いますよね。でも、これはどの職業でも言えることだと思います。最終的な受け手のことを考えて、自分は精一杯商品を作る。自分ではなく受け手のことをまず第一に考える。これが成功の秘訣なのかもしれません。
執筆活動も、所長で編集者でもある近藤君に、ここを変えろとか直せと指示されると、最初は「いや、そこは俺の個性だから。そこを削ったら俺じゃなくなっちゃうから」というふうに思っていました。ところが、そんなふうに思っていることは個性でも何でもないんですね。自分が自分に対して「俺の方が良い」と思っているだけで。それに気づいてからは、余計なものを削って削って、最後に残るのが個性なんだと思うようになりました。本質と言ってもよいかもしれません。
——いま個性についてのお話がありましたが、若者の中には「自分らしさを出したい」とか「自分にしかできないことをしたい」と考える人も多いと思います。柳田さんはどういうふうに自分らしさを出しているのでしょうか。
人間はどこに個性が表れるかっていうと、やっぱり「面白いな」という気持ちだと思います。面白いと思う道を進んでいけば、それこそ自分の個性を発揮していけることになるんじゃないかと僕は思います。
昔はそういう選択ができなかった。大学卒業したらすぐ働くのが常識でした。いまは「YouTuberになりたいです」と言っても「しばらくヨーロッパを放浪します」言っても異端視されないし、そういう生き方も十分認められますよね。大学の序列も人気企業のランキングも、あまり重要でなくなっている。そういう意味では自由に生きられる時代だと思います。こういう自由な時代、どんな選択してもよい時代だからこそ、何を面白いと思うのか、どんな道を突き進むかというところに、自分らしさが出ると思います。
ただ、「面白い」っていうのもただ単に楽しい、ウハウハ笑えるということでなく、自分が「面白い」と思ってそれに向かって行動することによって何かが生み出される、そういう種類の「面白い」でないと意味はない。「私は〜が面白い」というだけで生きていける人っていないですからね。
——やっていることの面白さに加えて、やったことによる喜び、あるいはやったことで自分が生み出したことに反応が返ってきたりして得られた喜びの二つが反応し合って、エンジンになっていくということでしょうか。
そういう考えもあるでしょうけどね。だから何を面白いと思い、何を自分は嬉しいと思うか。それは人それぞれ違う。でも、自分が面白いと思うものだけに触れていたいということでは、生活ができない。だから、「何が面白いか」じゃなくて、「どういうことをやって生きていったら面白いか」というふうに考えたほうがよいと思います。
学生時代の悩みは、誰かの言葉を聞いたから「よし、生きる道が見つかった」というようなタイプの悩みではないんですよね。だから、僕は今日、こうして色々と話していますが、他の人の言葉も聞いていくうちに、自分だけにしか見つからない答えが出てくると思います。どこかにいる誰かが自分の求める正解を持っていて、それを与えてくれるなどということはないと思います。複数の人の言葉を聞いて、その組み合わせの中から色々と考えてみると、自分だけの正解が見つかる。こんな感じが人生の選択の仕方じゃないかなと思います。
 柳田理科雄さん
柳田理科雄さん——柳田さんご自身が「面白い」を発見したきっかけは何でしたか。
『空想科学読本』の第1巻は、お話ししたとおり、ただひたすらお金のために書いていました。本を書くことが楽しいかどうかなんて考える暇がなかった。でも、本を書くこと自体の面白さを、4冊目ぐらいのときに見つけたと思います。日本中に広がって、色々なところで、自分が考えもしなかった読まれ方をしている。これは結構すごいことなんじゃないか、と思い始めた。だから、最初から「これって面白いんじゃないかな」と思って始めてみて「やっぱり面白かった」なんてことはないですね。最初は苦労の面の方を誰もが感じるんじゃないでしょうかね。それでもやっていけば、その苦労が面白い、ということに気がつく。だから、簡単にできることってやっぱり面白くないんですね。
——最初の苦労の段階で諦めてしまったり、力が尽きてしまったりする人もいると思うのですが。
やってみたけれどもうまくいかず「これは自分には向いてない」と思ってしまう人も多いでしょう。でも、そういう人に対しては、もうちょっと頑張ってみたらいいんじゃないかなと思いますよ。「最初の3日を頑張る。3日頑張れれば3週間頑張れる。3週間頑張れば3ヶ月頑張れる。3ヶ月、3年、30年とやり続けて、気がついてみれば定年さ」なんていう、昭和の頃のサラリーマンたちが言っていた言葉があったと思いますけど、そのままの素の自分がすっかり向いている世界なんてないんですよね。必ずどこかに引っかかりがある。その時に、相手を変えるという手段もあるけども、自分が変わるという方法もあり得る。それによってどんどん楽しいことになっていくケースもたくさんあるわけですから。
——最後に、自分は何が向いているのか、自分は何をして生きていったらよいのか、悩んでいる若者に向けてメッセージをいただけますでしょうか。
最初に自分が面白いと思ったことをやってみる。すると意外に苦労しますから。苦労したら、そこで自分自身が変わってみるということを試してみたらどうでしょう。もちろん、初めから絶対的に向いてなかった世界というものも当然あります。そういうときには、また別の世界を探せばいい。
昔は、この1本道を進まない限り人生に幸せはない、という発想をする人が多かったんです。いまはそんなことはない。これが面白そうだと思ったからやってみたけど、どうしても最後の頑張りができないと思ったら別の方向に行ってみる。生き方も、世の評価軸も、どんどん多様化しています。頑張ってみて、ダメだったら、気楽に他のことをやってみる。それでいいと思います
【後記】取材ノートを見返すと、柳田さんの人生には「科学」や「教育・啓蒙」という軸がありつつも、その根本には「熱中・努力・一生懸命」と表現できるものがあるように思える。その根っこが、小学生時代の理科の勉強から、2度の大学受験、塾の自営業、そして本の執筆から現在の活動に至るまでを一貫して支えている。苦労をもろともせず、また挫折にも打ちひしがれることなく突き進むエネルギーが、決して成功ばかりではない半生を経て「空想科学」というライフワークに辿り着く原動力になったのだろう。柳田さんから頂いた「苦労の先に本当の喜びがある」という言葉には強い説得力があった。(柳澤 岳)
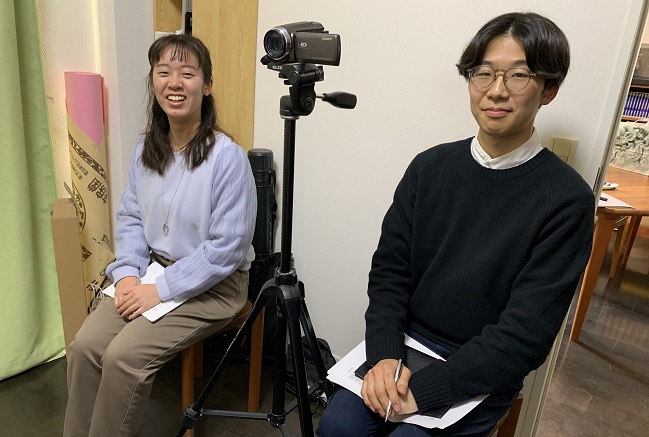 インタビュアーの柳澤岳(右)と吉村綾乃
インタビュアーの柳澤岳(右)と吉村綾乃有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください