WEBRONZA編集部×AAN(朝日新聞アジアネットワーク)提携
2010年10月27日
※初出は、朝日新聞アジアネットワーク(AAN)(2010年10月6日、肩書は当時)
世界経済や環境問題で重要さを増す大国インド。G20の中心メンバーでもあり、核・軍縮不拡散の矢面にも立っています。日本とインドの交流は盛んになってきましたが、長い歴史と複雑な社会を持つこの国について、私たちのイメージを再検討し、中国や米国との関係、南アジアの可能性などを議論しました。

◆報告
(1)日印関係とアジア ブリッジ・タンカ(Brij Tankha)デリー大教授(日本近代史)
(2)インドを見る目 すれ違いの日印関係 小川忠(国際交流基金日本研究・知的交流部長)
司会=藤原帰一(東大教授)
◆討論と参加者
■(1)日印関係とアジア
ブリッジ・タンカ(Brij Tankha) インド・デリー大学教授
交流の規模がやっと大きくなってきた
【司会(藤原帰一・東大教授)】 皆様、今晩は。本日のタイトルは、「インドへの道」。フォスターの小説みたいですが、このタイトルで、インドについて考えるセッションを企画いたしました。

申し上げますが、「アジアフェロー・フォーラム」といっても、アジアというとき、実は大半が中国。その次に韓国があって、その次はないんじゃないかなというくらい、企画が北東アジアに偏っておりました。実際、本日お越しいただいた方はそれほど多くありません。インドの企画では人数がこうなるという教訓です。念のために言いますが、これは朝日新聞社の問題ではありません。朝日から多くの皆さんがおいでになったのに、フェローの皆さんの出席率が低いからです。
これは嘆かわしいと思います。「われわれにとってインドとは何か」というタイトルにしても、いつもはインドのことをろくに考えてない証拠ですね。そして、関心がようやく向かってきたのもたまたま経済成長が著しくなってきたから、今度はインドにでも投資するかという理由。いかにも了見が狭い見方です。
でも、今日は違う。本日お願いしました報告者3名は、こんな狭い見方ではなく、インドについていろいろな視点から考えてこられたみなさんです。
最初にお話しいただきますブリッジ・タンカさん。タンカさんはもう日本でも多くの方がご存じでしょうが、日印関係の現場に立って、「インドで日本について語り、日本ではインドについて語らされる」という苦しい立場に、過去30年にわたって身を置かれてきた。日本とインドの両方に通じた、文字通りのかけ橋のような方です。
続いてお話しいただきますのは小川忠さん。いまは国際交流基金の日本研究・知的交流部長として日米の文化交流に関するお仕事に携わっていらっしゃいますが、実は国際交流基金のアジアに関する事業の中心で活躍された方です。インドネシアにも、またインドにも駐在され、インドのヒンドゥー・ファンダメンタリズムを中心とした『原理主義とは何か』(中公新書)という、非常に優れた、しかもタイムリーな本を発表されました。
3人目は、インド政治がご専門の、竹中千春さん。竹中さんはインド研究を続けてきた立教大学の先生で、そして、つい最近、『盗賊のインド史』という本を書き上げたばかりで、まもなく有志舎から発売されます。タイトルから見ても、ビジネスチャンスとしてのインドという視点とはかなり違った視点になりますね。
先生方のお話をいただく前に、一つご注意を申し上げます。このセッションでのご発言はオン・ザ・レコードです。お話の内容は、編集の上、インターネットのウェブサイトに掲載する予定でして、発言された皆様には原稿をご検討いただきますが、基本的にはオン・ザ・レコードでのセッションであることをお断りいたします。
時間配分は、タンカ先生が20分、小川さん15分、竹中さん15分ということで進めたいと思います。では、最初にタンカ先生、お願いいたします。
でも、アジアはもっと広いです。どう見ても
【ブリッジ・タンカさん=デリー大学教授(日本近代史)】 どうもありがとうございます。紹介されたように、私の専門は日本近代の歴史です。でも、時々インドのことも話しているから、だんだん「インドの研究者にもなろうかな」と思っているところでもあります。

私は70年代の半ばに最初に日本に来たんですけれど、その後、インドと日本の関係は大分変わってきましたが、まだまだ規模では、思うほど変わってないという気持ちもあります。
今日の話として、私はアジアから考えたいんです。
アジアを考えるとき、例えば60、70、80年代だったら、基本的にみんな日本の経済成長を中心にアジアを考えていました。そして、中国の改革以降の80年代以降、中国の経済成長が中心になってきました。
でも、アジアはもっと広いです。どう見ても。
旧ソ連とロシアがあります。また、中央アジアと西アジア。インドの視点から見ると、東南アジア、東アジアと西アジアも重要です。今の世界の歴史から見ると、経済の変化はもちろん重要な一つの特徴です。アジアの国々の経済成長が強くなっていること。しかし、片方で西アジア、つまりイランや中央アジアにかなり革命的な変化も起こっているんです。経済だけではなく、やはり社会的な変化を含めて。アジアを考えるとき、あるいは、日印関係を考えるとき、その両方を考えるべきだと思います。
インドから考えると、1947年の独立以降、60、70年代はソ連との政治的な関係が強かったです。例えば学生や民間の交流では、やはりアメリカが重要でした。アメリカとかイギリス。でも、ソ連に行った学生もかなり多かったんです。それは、ソ連が崩壊するまで、90年代まで、かなり多くのインドの学生が留学して、特に医学や自然科学、技術の研究をしました。まだ続いていますが、もちろん、数は減ってきています。
もう一つ。60年代、または独立から恐らく80年代まで、アジアの中の交流はかなり制限されていました。インドの場合は外国に行く予算がかなり低かった。あまり自由に行けないし、中国との関係が悪くなって、60年代以降、交流はほとんどわずかで限られていました。
しかし、80年代から、インドと中国の交流は増えてきました。インドと西アジアは60、70年代からすごく増えました。
日本との交流は80年代の半ばから、学生ではなく、企業関係が増えました。そうすると、インドの公務員とか新聞関係とか企業関係の人がよく日本に来るようになった。また、オーストラリアとの関係も、特にインドの留学生がアメリカやイギリスよりオーストラリアに行くようになった。もちろん、中国の企業もインドに入るようになってきた。
独立以降、初めて、アジアの交流の規模がかなり大きくなって、その中でお互いの知識が増えていったと思います。インドの場合は、60、70年代、多分80年代にも、例えば新聞を見ても日本の情報はほとんどなかったと思います。でも、最近はあらゆるところに、中国の情報、あるいは日本の情報が出てきています。
天心とタゴールの関係:大正時代までインドのイメージは強かった
日本とインドの関係を考えるとき、日本のイメージとして私が理解していることは、私は歴史家だからそこから始まるのですが、幕末から大正時代まで、大正時代あたりまで、インドのイメージは日本の知識人に大変強かったし、日本の教科書にインドがよく取りあげられていました。
一つはインドが植民地にされていたから、その植民地の危険性が重点でした。だから、幕末から中国で書かれた本、あるいは、ヨーロッパで書かれた本がだんだん日本で翻訳されて、そこで、イギリスのインド政策が注目されたんです。特に明治初期から末期までの教科書を見ると、大分日本にインドのことが教えられたんです。
その環境から、岡倉天心とタゴールの関係ができてきたと思うんです。それは美術とか仏教を中心にして、一つの何か西洋というか西洋文明に対するいろいろな試みでした。
当時は岡倉だけでなく、例えばこの近くの築地本願寺を設計した建築家の伊東忠太は、インドへ行って、新しい建築の言葉、スタイルをつくろうとしていたんです。アジア的表現を探しました。
あるいは、西本願寺の大谷光瑞は中央アジアに探検隊を送って仏教のルーツをたどろうとして、いろいろ研究して、インドにも行って、中央アジアだけじゃなくて、もっと広い意味でアジアを考えていったわけです。彼は仏教の立場に立っていた人でしたけれど、近代的な考え方もあったんです。だから、宗教だけじゃなくて、やはりいろんな企業のことや経済を検討して、彼の弟子がつくった工場を見にトルコまで行って調べています。
また、インド側でもよく知られたチャンドラ・ボースとインド国民軍(INA)の話があります。そういうインドの独立運動家が日本に来て、活動していたんですね。
そういうつながりは、日露戦争以降、だんだん薄くなって消えていったんです。
ソ連かスウェーデンが選択肢:インドが戦闘機を買う場合
80年代以降、特に2000年以降、そういう可能性がまたもう一度見えていると思います。交流のベースがだんだん厚くなってきた。その上に、知識もだんだん増えてきています。まだ欠点もありますが、日本とインドの関係が希望を持つような状態になっている。
インドから今のアジアを考えると、ロシアとの関係はまだ重要だと思います。90年代にはいろいろな問題があって、ソ連時代からロシアにかけて経済はかなり乱れていたし、両国関係もいろいろ問題があったんですけれど、だんだん整理されてきました。
例えば今度、インドは戦闘機を買う予定です、アメリカが売りたいと思っており、米印関係もよくなっているのに、インドは戦闘機を恐らくスウェーデンかロシアから買うとみられています。来年までに決まります。
それはソ連かスウェーデンから戦闘機を買ったら、値段はもっと安いし、アメリカよりもっと技術移転が認められると考えるのです。アメリカはあまりそれをしない。日本は次期戦闘機(FX)をアメリカから買うと報道されています。100億ドルで日本は40機か50機の戦闘機を買うつもりです。インドは同じ値段で126機の戦闘機をロシアから買う予定です。だから、インドと日本の外交を考えるとき、交渉のやり方にちょっと差があると思うんです。
もう一つは、政治的、経済的にもロシアや中国との関係はトラック2でした。88年頃から私のいたシンクタンクを中心に、知識人や外交官レベルの交流があった。当時のロシア駐在のインド大使が活発だった。今、外務省レベルで話が続いているんです。ロシアの場合は、やはりイラン問題やタリバンの問題でインド政府とかなり共通な利害があると思うんです。
中国への対抗軸としての日本/グローバルな枠組で日印交流を
中国との関係では二つの問題があります。経済的には順調に伸びているんですけれど、2年前からその経済、企業関係にも少し問題が出てきました。

大きな問題は、2007年から北東のアルナチャルプラデシュ州の領有権を中国が主張している問題です。飛行機が国境を超えたりするなど、2006、7年はかなり問題でした。今は少し落ち着いていますが、インドの政府機関の人が中国に行くとき、ビザがもらえないから行けないとか、そういうビザの問題があります。
もう一つは、やはり中国の海軍政策です。インド洋各地で港をつくったりするなど。だから、インドは今ソ連から潜水艦を買う話をしているらしいのです。
インドとアメリカとの関係は原子力協力合意の後、大分よくなりました。オバマ大統領は就任直後は、そんなに強くインドを注目していないように見えていたんです。
オバマ米大統領は11月にインドを訪問する予定です。新聞によると、再処理についての合意などの協定にサインする予定ですが、事故についての責任問題などの問題は残っており、調印されるかどうか注目されています。
さらに対アフガニスタン政策で、インド政府はアメリカの「よいタリバン」「悪いタリバン」と分けるやり方に賛成ではありません。それはいろんなテロの問題とつながってくるからです。
そうした情勢で、これからインドと日本の関係が、インド政府側から見ると重要になってきて、だから、この間、経済連携協定(EPA)、自由貿易協定(FTA)の交渉が終わって、今度サインされるかもしれません。それができると、日本の企業がもっとインドに入るかもしない。特に自動車部品とかジェネリック医薬品の場合はかなり重要になると思うんです。例えば日本の会社がインドのランバクシー社など製薬会社を買っていたし、インドのザイダスグループなどが日本の会社を買うなど、そういう交流が増えると思います。
韓国とは1年か2年前にそういうFTAをつくっていたから、もっと前に行っています。
インドがFTAをつくる理由は、経済交流だけじゃなくて、多分政治的な側面を持っていると思うんです。今の中国の事情などを考えると、やはり日本とインドの関係を強くしたいんです。
私は外交政策は専門ではないけれど、これからの世界にはいろんな地域的な、あるいは、グローバルな問題があるから、インドと日本の交流や関係が、二国間だけじゃなくて、グローバルの枠に機能しなければいけないと思います。それがすごく一番重要なことです。
そういう関係を支えるために、お互いに交流、知識を増やさなければいけない。それを増やすためには、文化交流、学生の交流が重要です。日本の大学では、ほとんどインドが教えられてない。社会科学の科目を見ると、インドの歴史とか経済は、ほとんど教えられていません。
日本の大学では、どこへ行っても、ヨーロッパとかアメリカなど外国人の先生がたくさんいるし、韓国、中国の先生も増えてきました。でも、インド人はほとんど見えない。移民政策の問題もあるのかもしれませんが、やはりそれを考えなければいけないと私は思っています。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 タンカ先生、ありがとうございました。インドと日本の関係を、インドとほかの国、ロシア、中国、アメリカなどとの関係を踏まえながら、長いパースペクティブの中で見てくださいました。
■(2)インドを見る目 すれ違いの日印関係
小川 忠(国際交流基金日本研究・知的交流部長)
お互いをステレオタイプで見ている両国
【小川忠・国際交流基金日本研究・知的交流部長】 国際交流基金は、外務省所管の独立行政法人で、日本と諸外国の間の文化交流を通じて、海外における日本理解を広め、また、日本の諸外国理解を深めて、相互理解を達成していくのがわれわれのミッションです。

われわれの仕事をやっていく上で、三つの要素のバランスをとって向上させていくことが大事だということを、国際交流基金在勤の28年間、先輩から言われてきました。
一つは、日本そのものの存在感というものを増していく、プレゼンスを向上させていくということです。それから、2番目の要素として、日本のことを好きになってもらう、好感度を上げていくという要素があります。3番目の要素としては、より深い知識、認識を持っていただく。この存在感、好感度、それから認識度というものをバランスよく向上させていくというのが我々の仕事だというふうに教えられてきました。
国際交流の現場にいて常に感じるのは、往々にして人は先入観を持っていて、その先入観を満たすような文化交流をやったほうが喜ばれるケースが多いということです。何か先入観を壊すようなことをすると、観客は混乱して、事業終了後にアンケートをとっても不評であったということが多い。そんなことを経験してきています。
そういう意味で、今日はこの日印の相互理解ということをお話しさせていただきますが、日印双方とも非常に先入観というか、ステレオタイプされたイメージでもってお互いを見ていて、そのステレオタイプされたイメージからなかなか脱却できない状況にあるんじゃないかということを感じます。それで、「すれちがいの日印関係」というようなタイトルを考えてきました。
統計を見ると、先ほどの三つの要素の中では、インドは日本に対する好感度は非常に高い。しかし、その日本に関するプレゼンスと知識の度合いはどうかというと、必ずしも十分じゃないというのが一つの特徴なのかなと思います。これが例えば中国、韓国と比べてみると、中国や韓国はご存じのとおり、日本に対する好感度は低いです。かなり低い。ちょうどインドと逆のような状態になるかと思いますが、インドと比べると少なくとも日本に関する知識とかプレゼンスは高い。パターンが逆転した状態にあるというふうに理解しています。
最近、外務省が対日世論調査というのをインドの主要都市12都市で2,000名ぐらいの有識者をターゲットにやりました。2009年2月の調査です。
それによると、76%の人々が日印関係を「非常に良好」、もしくは「良好」というふうに回答しています。中国だとこれはほとんど逆になってしまうのではないですか。70%ぐらいが「良好でない」と答えると思います。
また、インドにとって重要なパートナーはという質問に対して、アメリカ48%、ロシア30%、その次にちょっと開きがありますけど、日本が14%で3番目にランクされています。「インドにとって日本は信頼するに足る友邦か」という質問に関しては、92%が肯定的な回答をしています。
それでは、「日本に関するイメージは」という質問をしたところ、回答が一番多かったのは「先進技術を有する国」、2番目が「経済力がある国」、3番目に「平和を愛する国」。科学技術立国、経済大国、そういうイメージが結構強い。それから、日本人のイメージということでは、「勤勉である」とか、「能率的な経営慣行を持っている」とか、創造的というイメージがあります。それから、日本語学習に関しては、6割以上の人が「日本語学習に関心がある」というふうに回答していますし、「多くの若者が日本に留学すべき」というふうな点に関しても肯定的な回答があったと。ということで、日本、日本人に対するイメージは非常によい。
では、その日本に対する好感がより深い日本理解につながっているかというと、これは残念ながらそうでもない。多分、インドを旅行された方は経験されたことがあるかと思うのですけども、中国との混同、非常に初歩的な混同が結構あります。
それから、もう一つは、欧米のメディアであるとか欧米の学会でつくられたイメージ、認識というのが、そのまま無批判でインドの有識者の中で受け入れられている。いわゆるフジヤマ・ゲイシャ的な異国情緒をそそる本やハリウッドの映画なんかが欧米で流行ると、もうそれが即、インドに伝わってくるという状態にあります。
「日本とインドで大きいのはどちら?」
最近、国際交流基金ニューデリー事務所の職員がインドの小学校に行って講演をしたことがあるそうです。そこで、「日本とインド、どっちの面積が大きいでしょう」という質問を小学生にしたら、みんなが手を挙げて日本と答えたそうです。それから、「日本とインド、どっちの人口が多いでしょう」というと、これも日本というふうに小学生たちは一斉に答えたと聞きました。
つまり、これというのは大人の意識が子供に反映していて、日本のことはあんまりよくわかってないけども、ある種のあこがれというか尊敬みたいなものがインドの中にあるということだと思うのですね。
じゃあ、振り返ってみれば、じゃあ、日本人が現代インドのことをどれぐらい理解しているのだろうという点で考えると、われわれも反省すべき点が多いのではないでしょうか。今までの話の中にもありましたけど、ある古典的なインドイメージとか古典的なインド知識は持っていても、現代インド、非常に大きく変化を遂げている複雑なインドという国の多様性とか多重性というものをどれだけわれわれは、理解しているのか。ともすれば、文化の違いばかりが強調されて、非常に異質な国、異質な他者としてのインドということが強調され、インドに対する共感とか相互理解というものが欠けているという気がいたします。
誤解のきっかけは「宗教とカースト」
インドに駐在していて、日本人がインドを誤解するつまずきのもとというのは大きく2つあるかなと思っています。それは宗教とカーストです。いまだにインドは仏教国、というイメージを持っている人が多いです。

インドは人口でいうとヒンドゥー教徒が8割です。イスラム教徒が1割ぐらいで、仏教徒は実は1%にも満たない。さらに人口の1割がイスラム教徒ということですから、実は中東のイスラム大国、イランとかサウジアラビアと比べてもイスラム教徒の数は多い。ある意味、インドはイスラム大国でもあるわけです。そういった認識を日本人はどれだけもっているでしょうか。
それから、これもよく言われるのですけども、ヒンドゥーとイスラムの宗派間対立というのは何か多神教対一神教の対決で、必然的なものであるというような認識が持たれがちです。これも宗派間対立とか宗派間暴動をつぶさに見ていくと、その中には政治的な勢力が宗教を使って、ある種の政治的な利益を得るために宗派間対立をあおるという要素がありますし、必ずしも宗教、教義のせいでヒンドゥー、イスラムが対立しているのではない。そういったところをわれわれは見落としがちです。
カーストの問題ですが、これはこの後、竹中先生がお話しされるように(今レジュメを見たんですけれども)、これもつまずきのもとなのです。インドの場合、カーストというと4つの階級、プラス、カースト外カーストがあって、古代からそういうカースト制度が強固に存在して、下位カーストの人々は人生あきらめてるといったイメージを持たれがちなんです。しかし、インドの現代政治の中で今起きていることは、そういった下層カーストの人々の政治的な参加とか発言力が増しているという現象があります。
カースト意識そのものも、例えば都市部と村落部でかなり違ってきているし、また、都市部でも世代によってこのカースト意識の持ち方も変わってきている。カーストの実態に関していえば、インドのカーストは実際には「ジャーティ」という非常に細分化されたサブカーストがインド人の中では意識されています。この中で時代を経てこの下位のカースト(ジャーティ)が上位カースト化するということもありますし、それから、ジャーティは地域によってその位置づけが違っているというのがあります。同じジャーティでも、ある地域では最下層なのに、他の地域では中の下あたりに位置づけられるといったようなことです。それから、カーストは低いけども経済力はある富裕層が存在します。そうすると、階級とカーストのねじれ現象みたいものが発生しているということになります。カースト理解はなかなか一筋縄じゃいかないということなのですね。そういった問題というのを常日ごろ、考えておく必要があるのではないかと思います。
下層カーストの人々は人生をあきらめていて、無気力であると言う人がいるのですが、私がインドへ行ったときに、西インドで大地震が起きました。2001年です。あのときに、いろんなインドのNGOの人々とともに救援活動をお手伝いしていて感じたのは、インドの地域の住民、特に下位カーストの人同士が助け合っているということです。、国際的に注目を集める大災害では欧米のNGOが華々しくマスコミに報道されたりするのですが、実は災害のときの救援活動の主役になっているのはそういった地域に生きる下層カーストの人々なのだということを実際私自身も実感して、報道と実態の乖離みたいなものを考えたりしました。
さらにデータ的なものも紹介させていただくと、国際交流基金は海外での日本語教育の普及というのをやっていまして、海外の日本語教育に関するデータをとっているんですけれども、2006年と2009年で比べてみると、日本語学習者は11,011人から18,372人ということで67%ぐらい増えている。
日本語機関数も106機関から170機関ということで60%ぐらい増えています。それから、われわれは海外で日本語能力試験という英語のTOEICに当たるような試験を実施しているのですが、2003年時点では3,897人だったのが、2008年には6,669人ということで、これも非常に増えてきています。
ということで、この日本語学習に関しては次第にインドで拡大しつつあることが見てとれますが、しかし、抜本的な日印関係、日印交流を強化していかなければいけないと考えます。
現在私は日米センターという部署で、アメリカとの交流を担当しており、ワシントンとかニューヨークに行って、そこの議会関係者であるとか、シンクタンクであるとか、大学の先生方とか、いわゆるアメリカの外交政策にかかわる有識者の人々と会うことが多いのですが、かなりのインド系の知識人がアメリカで活躍されていると感じます。
その代表格というのがルイジアナ州の知事のジンダル知事でしょう。彼は共和党のホープで、次の副大統領候補なんて言われています。インド系のアメリカ人は今アメリカには257万人ぐらいいて、世代交代が起きている中で、かつてカースト意識ゆえに団結しなかったような人々が、インド系アメリカ人ということで団結しつつあるという事態が進行しています。彼らはインターネットを駆使して、様々なファンドレイジングとかネットワーキングというのを進めている。
米国で存在感増すインド人社会
アメリカの外国人留学生のなかで最大のグループを形成しているのがインド人です。これが10万人ぐらいいると言われています。こういった10万人のインド人留学生のなかにはそのままアメリカに残る人もいて、彼らがアメリカの大学でインド研究をしたり、議会、シンクタンクでアメリカの対インド政策の形成に関与しているという状況にあります。
ひるがえって、日本はどうかというと、今、在日インド人の数というのが2万人強、アメリカの100分の1以下。それから、文部省の統計で見ると、日本の大学で学んでいるインド人の留学生は543人、アメリカの大学在籍者の200分の1ですね。それから、さっき話しましたけど、インドの日本語学習者というのは1万人強ということで、アメリカとインドとの関係と比べると、この日本とインドの関係というのはほんとうに貧相なものです。
これを、中国、韓国と比較してみたいのですが、中国の日本語学習者というのは今68万人、それから、韓国は91万人、インドは1.1万人。それから、日本の大学で学んでいる中国の学生というのが7万9,000人、韓国の学生が1万9,000人。全体の留学生の数が13万人ということですから、これで考えた場合も、インドの543人というのはあまりにも数が少な過ぎるのではないでしょうか。
先ほど、藤原先生やタンカ先生の話にもあったように、日本の大学で現代インドを教えている大学というのはほんとに皆無に近いと言っていいんじゃないかと思いますね。近藤正規先生のように社会科学系学部や教養系学部で教えられている方がいますが、現代インドを研究するセンター、現代インド研究所のような本格的なものが日本の中に存在してない。現代インドをもっとわれわれは理解する必要があるし、そのための抜本的な交流の強化が今求められているというふうなことを感じます。あと、また質疑応答の中でお話ししたいと思います。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 日本とインドの文化交流の現場でお仕事をされてきた経験をもとにしたお話をいただきました。で、「どうもまだまだだな」というようなことになりそうですね。最後になりましたが、竹中千春さんにお話をお伺いしたいと思います。
■(3)グローバルなインドとローカルなインド
竹中千春・立教大学教授
転換期のインド社会
【竹中千春・立教大学教授】 1980年にデリー大学に行ったときに、最初にお会いしたインドの研究者のタンカさんとご一緒できて、大変光栄です。それから、1999年、インドの核保有が問題となっていた時期に、デリーの会議に招いていただき、国際交流基金の小川さんにお会いしました。そのお二人の後にお話しできることを大変光栄に思います。

今日は「インドへの道」ということで、「われわれにとってインドとは何か」という題をいただきましたが、私自身は30年ぐらい、「私にとってインドって何?」 みたいな感じで生きてきました。そこで、今日はその問いへの答えの2010年バージョンとして、タイトルの「転換期のインド社会」に関して、三つの柱を立ててお話ししたいと思います。
今日、レジュメをつくろうと思ったら、学生が迷い込んできてしまい、ちょっと中途半端になってしまいました。あまりきれいではないレジュメですが、1番目に冷戦後のインドについての特徴、次にレジュメで3番目としたインドの民主主義、最後にレジュメで2番目としたインドの外交について話したいと思います。
1番目でございます。
すでにいろいろなお話が出ましたが、現在のインドはどういう国なのか。どうとらえるかについては、いろいろな観点があると思いますが、まだ世界大国になっているとはどうも言えないだろう、と。でも、なりつつあるのかもしれない。
とはいえ、確実に地域大国ではあります。けれども、じゃあ、インドのものすごくローカルな社会というのはどうなっているのか、という疑問も湧いてきます。とりあえずここでは、現在のインドには二つの顔がある。グローバルなインドとローカルなインド、この両方の顔を持ちながら、それに挟まれてナショナルなインドが内政や外交を展開してきているのではないか、という議論をご紹介したいと思います。
そこで三つの見方を挙げてみます。
一つは、90年代のインドです。社会主義国家の幕をおろしてから、ポスト社会主義国家として、例えばロシアとか中国と同じように、どうにか国家として生き延びた。それをインド自身が模索した時代が90年代だったと思っております。
ポスト社会主義期の孤立から抜け出した00年代
ポスト社会主義国家の動揺とともに孤立ですね。要するに、同盟を組んで後ろから支えてくれたソ連がなくなってしまった。新しいロシアとどういう関係を築くか、まだ確定していない。中国はものすごい成長をしている。アメリカとはそれまで対立とまではいかなくても、常に緊張関係を持っていた。したがって、非常に孤立した形で冷戦後の時代を迎えた。ことに核問題についても、日本とは異なり、「核の傘」などない。つまり、超大国には守られていない。そういう孤立の中で隣の核保有大国と対峙しているという安全保障上の焦燥感があり、同時に、経済がどん底であると認識されていた。インドはこの苦境からどう脱出するのか。これが90年代の最初から後半までの、インドの深刻な危機意識だったと思っています。
二つ目ですけれども、そうしたインドが現在、安全保障の面でも安心感を得、そして、経済成長を遂げて、ここまで来たよという状態になっているのではないか、と思います。大体それがはっきりしてきたのが2003、2004年ぐらい、第1期目のブッシュ・ジュニアの政権の後半くらいからですね。世界的には、対イラク戦争の時期あたりからではないかと思います。
「10%成長を続ける核保有大国」が国民的コンセンサス
さて、現在のインドでは、核を保有している大国であるという柱と、経済成長10%を目指して走っていくぞという柱は、さまざまな政党の違いを超えて、国民的なコンセンサスになっていると言っても間違いではないと思います。ですから、どのような政権ができても、この2つの柱を維持していくということは明らかだと思います。ですから、日本の外交が、経済成長については問題ないですが、核の問題で厳しい条件を突きつけますと、政権与党だけではなく、全インドの反発を招く可能性もあるということになります。

3番目ですが、そういうインドの外交上の国益というものは、今何なのかということですね。いわゆるナショナル・インタレストです。けれども実は、ナショナルなインドというもの自体が、先ほどお話ししたグローバルなインドとローカルなインドの両方向に引っ張られている。一方ではグローバルなインド、先ほど小川さんもお話しされましたように、世界で活躍しているインド人が増えていて、その中には非常にお金持ちのインド人たちもいる。そして、グローバルなインド人のメディアが力を発揮している。
アカデミズムやメディアの世界でさまざまな言説を創造するインド人はアメリカやヨーロッパに数多くいて、インドの国益とは何かを論じ考える上でも、こうしたグローバルに活躍するインド人の声が大きな力を持っている。インド政府も、経済成長をめざすがゆえに、海外で展開するインド系の資本を本国にどのように還流させるか、あるいは、インド系移民をどのように本国につなぎとめるかに、大きな関心を払っています。
一方では、次にお話しします民主主義の面で、ローカルな草の根の、つまりナショナルというよりは州、さらに州よりも小さな単位での地元社会のインドを主張する担い手もまた、力を伸ばしてきています。
要するに、グローバルなインドとローカルなインドの両方向へ国民国家であるはずのインドが引っ張られて、それまでにあったナショナルなインドの形がかなり崩されたのが90年代だったと思います。けれども、経済成長と核保有する大国への道を辿って、もう一回ぎゅっとナショナルなインドをまとめ上げる方向に、国民を引っ張っていこうと努力しているのが現在のインド国民会議派(以下、会議派)政権かなと考えています。
次に、3番目ですが、まず、インドの民主主義の現在についてお話しして、最後の結論に持って行きたいと思います。
レジュメの図を見てください。先ほど小川さんが指摘されたように、宗教やカーストや民族などがインド政治の中でどう機能しているのかを、手短に説明してみたいと思います。
要するに、皆さんがよくご存じのジャワーハルラール・ネルーの時代のインド国民会議派、これは一党優位の政党システムとされます。たとえば、日本の自民党が安定していた時代のようなイメージを持っていただければと思います。それを、インドの政治学者は「会議派システム」と呼んできました。
そういう時代、インドは工業化がまだ進んでいない農村社会でしたから、民主主義の基礎は農村ということになります。村の選挙区では、どういう選挙が展開され、会議派が与党の地位を維持したのか。図を見ていただければと思いますが、会議派システムの下では、高カーストで、多くはブラーフマンの地主さんが会議派の候補者になることが多かった。ある人が会議派の公認になったら、その人と対立する地主さんは無所属になります。こうした形の選挙が1950年代とか60年初めぐらいまで、あるいは地域によってはその後も続き、会議派の支配を支えました。地主さん同士が戦って、一方が会議派与党、公認を得られなかったら無所属で、無所属が勝った暁には会議派へ入るといった、そういう政治の世界ですね。
こうした一党優位の基礎が壊れ続けてきたのが、この40年ぐらいです。 政党制の変化は、一党優位から多党制へという流れになります。まず、与党会議派が分裂した。自民党が分裂した、みたいな話ですけれど、与党が分裂した。これが1967年から77年の危機の時代に起こります。会議派が、より若い世代のインディラ・ガンジー派と、古い政治家の側の会議派の組織派に分かれたわけです。そういう危機を抑制するために、75年から77年、インディラ・ガンジーは議会を停止して、非常事態体制を敷きます。危機の原因には、大与党の分裂、政府のガバナンス能力の低下、世代交代、その他さまざまな問題がはらまれていましたが、その結果、会議派の一党優位体制が壊れていきました。
農村社会のカースト・地主支配が崩れて多党化へ
さて、一方では、先ほど説明しました、伝統的な農村社会のカースト的な支配に基づいた地主の支配そのものが崩れてくる。なぜかというと、開発政策、国民統合政策、教育政策、さまざまなものの影響によって、古い社会のあり方が崩れ始めたからなのです。
その後は現在まで、傾向として多党化が展開してきました。77年から90年代初め、つまり社会主義の時代が終わるまでが、一つの時代です。ジャナタ、つまり人民、ピープルですが、その連合がインディラ・ガンジーの強権政治を倒すと訴えて選挙を戦って勝ったのが77年で、それ以降、会議派ではない非会議派の政党に加えて、会議派を割って出たおじいさんの政治家たちが一緒になって組んだジャナタ連合が、会議派陣営と対抗する時代が始まります。
このとき、ジャナタ連合として、もちろん会議派を割って出たおじいさんたちもいるんですけれども、地域からさまざまな政党が出てきました。民族とかカーストを掲げたさまざまな政党が出てきました。宗教を掲げた政党も出てきました。したがって、諸政党の連合や分裂が繰り返され、会議派が復活したり、再びジャナタ連合が勝ったり、国政のレベルでも政権交代が展開します。州のレベルでも、こうした政権交代が展開したところが多いです。
この構図が、91年以降は再び変わってきます。ジャナタ連合の中から割れて、インド人民党勢力というヒンドゥー至上主義勢力が登場し、国民的な支持を得ます。その結果、90年代は擬似的な3大政党というべきか、3大勢力の交代あるいは拮抗という時代が始まります。会議派政権が96年まで続きましたが、その後、96年総選挙ではインド人民党が勝って第1党になったにもかかわらず、他党との連合が組めず13日で下野した。そして、他のジャナタ連合勢力を基軸にし、会議派の閣外協力を得て統一戦線内閣が成立した。けれども、内閣が任期満了まで持たず、98年に総選挙が行われ、さらに多くの議席を取ったインド人民党が勝利して、このときは諸政党の合意を取り付けて、連合政権を成立させます。そして、核実験、核保有を行います。
したがって、90年代のインドはポスト社会主義国家の深刻な危機、孤立の中で模索の時代を経験し、それは同時に、不安感を反映したナショナリズムの動揺を招きました。ヒンドゥー至上主義を核とした国家主義的な右翼勢力が民衆の支持を得て、会議派やジャナタ連合を凌ぐように台頭したのが90年代ということになります。
要するに、ポスト社会主義国家が動揺したとき、国家に対する不信、経済的な危機、安全保障上の孤立など、さまざまな不安が攻撃的なナショナリズムの形を取り、厳しい対外政策や国内のマイノリティへの迫害として現れました。したがって、そうした問題が解消してきた時代、つまり2000年代には、むしろ猛々しいナショナリズムの人気は低下し、2004年総選挙でインド人民党と諸政党の連合勢力は、予想外の敗北を喫しました。
こういう動きの中で作られてきた多党制的な状況とは何か。図の三角形を見てください。かつては会議派が、階層的な農村社会、つまり図の三角形の全体を、地主というトップをつかむことで抱えていたのですが、今は、ガラガラポンというか、色の違う階層あるいはカーストの積み木に割れて、それぞれ別の政党を支持しているという形になっています。こうした多党化は、下克上といいましょうか、下のカーストからの静かなる革命であり、民主主義の政治体制の中で草の根からの力を出すしくみとなっています。
ですので、カーストといいますと、さっき小川さんがおっしゃったように伝統的なイメージがありますが、いまや明確な利益集団であり、アイデンティティ集団であり、それは政党の票田となっています。それぞれのカーストを基盤とした固い政党の票田が形成されているので、当然、多党化が推進されることになります。つまり、これが、インド民主主義における下からの強い動きであり、内政的なダイナミズムの源となっています。
外交に内政の縛り:中国と異なる民主主義のダイナミズム
最後に、こうした内政に縛られる外交ということを考えていきたいと思います。
インドの外交を見ると、一党優位の時代には、ある意味、ネルー首相は独壇場でいわゆるネルー外交を展開した。要するに、外交は内政の問題とは切り離されていた。非同盟、社会主義というスターのような外交でしたが、それが次第に変わってきました。与党分裂の時代、インディラ・ガンジーは、結局アメリカには受け入れられず、模索の中からソ連と同盟する方向を選択した。そして、70年代には、南アジアの冷戦構造が強化されることになります。

その後、77年以降多党化の時代を迎え、80年代には緩やかな経済自由化を試み、さらに90年代から2000年代初めまでは、ヒンドゥー至上主義の怖いナショナリズムを経験しました。けれども、2000年代に入ると、急速にアメリカに信用されるパートナーの地位を獲得し、地域大国から世界大国に上り詰めようとする外交の時代を迎えました。
最後に、結論的になりますが、民主的な内政の縛り、つまりインドの外交が内政に拘束されるという点について、指摘したいと思います。インドと中国とを比較したとき、インドには民主主義の強いダイナミズムがあるという点をおさえておく必要があります。
まず、経済成長の問題です。これは、内政的には利益配分の課題となります。政策的に考えれば、新自由主義的な市場経済志向を強めた姿勢でいくのか、あるいは、国内の弱い階層への保護主義的な分配を確保するという姿勢でいくのか、というバランスの問題です。
2004年に成立したインド国民会議派政権においては、分配を保障する保護主義的な政策を出さざるを得ないところがありました。どうしてかというと、先ほど説明したように、下層の貧しいカーストを代表する政党が数多く連合政権に参加しており、さらに閣外からの共産党勢力の協力も必要だったので、政権を維持するためにも分配への志向を示す必要があったわけです。けれども、2009年に樹立された会議派政権では、会議派は十分に多数の議席を取ったために、より少数の諸党との連合で事足り、しかも共産党勢力は後退して、それらの勢力配置の結果、分配への圧力は弱まる政権の構造になりました。とはいえ、国民的なコンセンサスは高度経済成長ですから、ある程度の分配を見える形で保障しながら成長を維持するという、落としどころで政策を実現していくと思います。
安全保障の面では、核問題でアメリカとインドの協力が成立し、国際的にはほぼ核大国として認められたという状況にあります。現在では、アメリカと協力して国際的な融和の中で国益を伸ばすという会議派の現実路線のほうが、国民的に支持されているのではないかと思います。インド人民党は、2009年の総選挙で国防や治安の強化、対テロ戦争の推進をナショナリスティックに訴えましたが、勝利したのは会議派でした。
外交のナショナリズムカード:「アメリカ帝国主義」と中国
最後に、外交上のナショナリズム・カードについて述べます。流動的な世論が外交に影響を及ぼすという条件があると、野党が一番切りやすい、あるいは、与党の中の反対派が切りやすいカードはナショナリズムだということになります。
インドの場合、別にナショナリズムの対象が日本ではないので、東アジアとは違って、日本が意味もなくバッシングをされることはありません。インドのナショナリズムのアキレス腱は、まずアメリカ。「アメリカ帝国主義」というのはすごく批判しやすいので、みんなすぐアメリカ帝国主義を叩く声を出しやすい。でも、今は、アメリカ批判はしたくないというグループが、先ほどから指摘してきたように、政財界の中では強くなっています。
あと、中国。これは先ほどタンカさんもおっしゃいましたように、これから少し問題になってくる可能性はあるかなと思います。領土問題もあるし、それから、経済的な拮抗も……。もう時間がないので、話を止めなきゃいけないですね。
最後に、パキスタンです。パキスタンに対しては圧倒的にインドのほうが力が強いので、負けるとは思っていない。けれども、パキスタンの問題はすぐ内政に関わってくるので、ナショナリズム・カードになりやすい。インドの治安はどうするんだと、野党やメディアが政権批判を行い、与党はそれに応えなければならない。けれども、すでに述べたように、現在のインドには90年代のような不安定性は少ないので、ナショナリズムのカードは切られにくくなっていると言えると思います。アメリカとの核取引のときには、他国の人々には理解できないほど、反米的なナショナリズムが政界を揺るがし、マンモハン・シン内閣は下野しそうになりましたが、何とか乗り切りました。それを見ても、現在のインドはわりとリーズナブルに付き合いやすい相手になってきたのではないか、というのが私の結論でございます。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 竹中先生、ありがとうございました。15分ですべてがわかるインド政治。実に情報量が多いお話をいただいたと思います。
三つ、盛りだくさんなお話をいただいた後ですので、ここで10分ぐらいコーヒーブレークを入れて、それから再開します。
■全体討論(1)南アジアで増す中国の存在感をどう受け止めるか
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ご着席をお願いします。ご発言をされる方は名札を立ててください。特に手を挙げる必要も何もありません。立ててくだされば、順番にうかがっていきたいと思います。では、トップバッター、宮田さん。
【宮田謙一・朝日新聞ジャーナリスト学校事務局長】 それでは、アイスブレーカーとして質問させていただきます。タンカさんがアジアから見たインドという視点でお話をされて、大変印象深かったです。実は今日たまたま、南アジアから来たジャーナリストたちと話をする機会がありました。スリランカ、バングラデシュ、パキスタン、ネパールからの人たちでした。この人たちと話していて、やはり南アジア地域における中国の存在感というのが非常に大きくなっているなということを感じました。

一例を挙げますと、例えばスリランカ。スリランカで例の反政府勢力タミル・タイガー(LTTE:「タミル・イーラム解放のトラ」)をスリランカ政権が激しい戦闘でけ散らした。その際に、中国政府が物心ともにあつい支援をして、スリランカ政府と中国との関係が非常によくなっている。スリランカ世論も中国に大変好印象を持っているそうです。
パキスタンはもう言うに及びません。つまり、アメリカやヨーロッパ、日本がインドと原子力協定を結んだその反射的な動きとして、中国とパキスタンが原子力協力を進め、場合によっては原発がそろそろ輸出されるのかなというぐらいになっていますね。
ことほどさように、インドの周辺諸国の間で中国の存在感が大きくなっている。これはインドにとって必ずしもハッピーな状況ではないんだろうなと。インドはこういう中国の存在感が増していることに、どういう考え方でいるんでしょうか、あるいは、どう対応しようとしているんでしょうか。竹中さんにも同じ質問をさせていただきたいと思います。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 これはすぐお返事をいただいたほうがいいですね。まず、タンカさんから。
警戒強める軍、平静装う政府首脳
【ブリッジ・タンカさん(デリー大教授)】 インドでは防衛問題や国際関係を論じている人たちの意見がかなり分かれていることがあります。
一つは、中国の外交がインドに危機感を起こしているから、それに対応しなければいけないという軍事関係の人々。例えば海軍の場合は潜水艦がすごく足りないから、増やさなければいけないとか、あるいは、戦闘機を近代化しなければいけない、そういう議論がかなり強いと思います。

でも、政府の発言は、それほど強くない。例えば、string of pearl(真珠の数珠)といいますね。パキスタン、スリランカ、ミャンマーがインドの首を絞める形になる数珠です。国家安全保障担当の政府高官が言ったのです。「string of pearl is not a tool of assassination(真珠の数珠は暗殺の道具ではない)」。だからそんなに心配しない方がいいんじゃないか。中国はこの地域での貿易が増えているから、そういう心配でいろいろ港を開発しているということがあるというのです。
でも、私から見ると、やはりどう見てもそれは外交の一部です。パキスタンの場合はもっとずっと前からです。中国、パキスタンと北朝鮮とのつながりが核兵器開発であったし、パキスタンの物理学者、カーンがネットワークをつくって、今までいろいろ交換していたんです。
だから、中国の動きはインドでかなり注目されていると思います。大きな問題になる可能性があると。これから南インド、太平洋、あるいは、マラッカ海峡までインドと中国の対立が強くなるということを、去年書いた人がいました。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ありがとうございます。次に、竹中さん。
核でも経済でも「かなわない隣人」中国
【竹中千春・立教大教授】 そうですね。インドは中国を「かなわない隣人」だとずっと考えてきたという歴史が根っこにあります。
もう一つは、他の南アジア諸国にとってのインドは、威張っていて、どうにかしてくれという相手です。じゃあ、どうするかというときに、小国にとっては、中国に接近し、中国の力をバランスに使って自国の立場を確保する外交政策が合理的です。こうした二つの外交的ダイナミズムが、今のお話に含まれているかなと思います。
たとえば、ネパール。ネパールは、伝統的に中国とインドの間でバランスを取ってきました。ネパールでは武装勢力が展開し、チベット側から逃げてきた人たちもいる。中国側の軍隊がネパール側に入ってきてチベットの反政府勢力を捜索したりしていても、インド側は無視してるというか、見て見ぬふりをしている。つまり、チベットは中国だけど、ネパールはインドという現状のバランスの中で、小国や武装勢力も、大国を使っているという構図があります。
今おっしゃったパキスタンも、そういう構図の中で中国と手を組んできました。
また、ミャンマーと中国も近い。そのために、ベンガル湾の海上に中国が進出してくるという脅威がある。それに対抗して、タンカさんがおっしゃったように、インドは海軍力の強化を課題として考えており、潜水艦の購入などをロシアと交渉したりしています。要するに、軍事的にももちろん中国を非常に意識しています。

「かなわない隣人」なので、インドは中国に負けてきた。ネルー時代の最後の領土紛争で負けますし、核実験も中国が先にして核保有国となる。それには負けちゃいけないというので一生懸命核開発をして、ずいぶん経って核保有しました。そうしてみると、核武装の連鎖で、中国を追ってインドは核保有国になったと思います。このように、インドにとって中国というのは常に気にせざるを得ない隣人です。
ともかく、今までのところはかなわないと思ってきた。核でもかなわないし、経済でもかなわない。だから、何とか中国ともめないようにしながら、東南アジアや東アジアの市場にインドも進出しようとしてきたと思います。
時々かんしゃくを起こすので、98年の核保有のときには、中国が悪いと非難して核実験、核保有を強行する理由にしました。中国にとっては「えっ?」という反応だったと思いますが、ありがたいことに、そのときはけんかを買ってくれなかったのでよかったなあと思います。これまで、中国は冷静にけんかを買っていませんが、それでも国境地帯では軍事経済的に明確なプレゼンスを拡大している。チベット地方からカシミール地方に伸びる幹線道路を建設したり、ネパールの向こう側のチベットで急速な開発を進め、大きな空港を設置している。インド側から見ると、中国の進出は冗談ではない脅威に見えてきます。
でも、今までは、インドは、中国の逆鱗に触れても許してもらったこともあって、なるべく両国間の紛争を避けて大きくなろうとしてきたのかなと思います。
中ロ印の大国関係がこれからうまく続くか
ただ、先ほど言いましたように、これからもこうした関係がずっと続くかどうかは、ちょっとよくわからない。中国、ロシア、インドが仲良くすると、アメリカは嫌いますが、これらの地域大国が今後も仲良くするのかどうかについては、保証がない。もちろん、そのほうが好ましいとは思いますが。
そのあたり、今後の展開は未定ですが、今のところ、インドの政権は経済優先で、多国間主義と言いましょうか、全方位的な外交を選好しており、中国に対しても対立を回避する努力をするのだろうとは思っています。そんな感じです。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 さて、ここは少し踏みとどまってみましょう。インドで国際関係の会合に出席すると、中国のことばかり議論されるんですね。そこでは、「日本は中国の再軍備力の増強をどう考えているか」なんてお話ばかりです。中国での国際関係の会合では、インドがどうこうという話は僕はろくに聞いたことないです。そこで、国分さんに、中国から見たインドの話をうかがいたいんです。どうなんでしょう?
近隣関係の重要性を認識し始めた中国
【国分良成・慶応大法学部長】 インドが中国を考えるときに、日本ファクターというのはどういう働きをするのかなというのに関心があります。日本では、中国を考えて難しくなったときにインドに助けを考えがちなわけですよね。よくあるパターンです。それと同じような対象がインドで成り立つのかどうかということですね。おそらくインドにとってみると、むしろ日本でなくアメリカが浮かぶのかなとも思いますし。その辺がちょっとよくわからないんですけれども、インドでの日本の位置づけというのはどういうふうになるのかなと。

中国は国際関係の議論をするときに、これまでは多国間で考えることを非常に嫌ってきました。つまり、中印は中印でという発想だけれども、日中のときは日中だけでということになります。中国にとってみると、日本とインドが組んだときには、当然に自分がテーマになりやすいことがわかっていますから、だからその辺は避けたいという傾向が非常に強いですね。
確かにインドのいない国際会議の中で、中国は大体大国関係中心に議論する傾向が強いですが、そのときにインドというファクターが正直言うとあまり出てこない。どうしてもやはりアメリカ、日本、そして、ヨーロッパという、こういう枠が多いですね。
ただ、やはり今、中国にとってみると、そう言いながらも、最も重要な関係になりつつあるのは、だんだん近隣の関係になってきているわけですね。隣国に嫌われたら、これは難しいことになるということは相当理解し始めていると思います。最近では、もともとは北朝鮮の仕業と思われる韓国哨戒艦の爆発事件で、中国は北朝鮮の肩をもちすぎて米韓から嫌われ、その後、東南アジアに広がって南シナ海の紛争となり、また各国から批判され、それがまずいと思って、日本に接近して東シナ海の資源開発問題をどうにかしたいということを言ってきた瞬間に、尖閣沖の問題が起こったわけですよね。
振り返ると、中国の隣国との関係というのもあまり丁寧でなかったというところがあって、それはやはりインドとの関係もそうでしょう。これはもちろんチベットやパキスタンの問題があるので非常に微妙なんですけども、そういう周辺との関係というのが中国にとっては非常に重要な意味を持ちつつあるということが、ようやく認識されつつあるということじゃないかなという感じはします。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 タンカさん、はい。
中印関係の重要性には疑問がない
【ブリッジ・タンカさん(デリー大教授)】 インドと中国の関係はインドにとって重要です。それには疑問がない。例えば、インドの外務省には中国専門家が圧倒的に多いです。ほとんどの中国のインド外交使節に中国語ができるなど、そういう背景がある人がもちろんいます。
二つ考えてみます。
一つは、中国からデリー(インド)の例えば国際会議に出てくる人がだんだん変わってきたことです。80、90年代には、ほとんど中国のインド専門家が来て議論していました。しかし、2000年代から、例えばアメリカ担当とか、日本研究者とか、そういうような人たちも来ているから、やはり見方が変わってきたと思うんですね。
中国の成都に南アジア研究所があります。もちろん北京、上海にもありますけれど、成都の研究所では、3年ほど前からだんだんパキスタンに重点を移して研究しているらしいです。それも今の外交を反映してると思います。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 乱暴な補足をすると、インドが強く安全保障政策で協力している国は伝統的にはソ連であって、ソ連はもちろん解体に向かう。また、政策の重点がどんどんヨーロッパに移っていくということで、中国が強くなることに対する懸念をインドが持ったときに、友邦というのはあんまりなかったわけですね。
言うまでもなく、アメリカとの関係が悪かったわけですけれども、それが近年非常に変わって、やっぱり原子力協定が大きな転機だと思いますけれども。
だから、日本人に向かって、「もっと中国に怒れよ」とたきつけるような姿勢がちょっと和らいでいて、むしろ日本人のほうが中国の脅威について大声で言いたがる人がインドに行くといったパターンに、麻生政権のころからちょっと変わりつつあるような気がしてました。
さて、王敏さん、中国の話題とつながりで。
インド転換期における危機はどういうものか?
【王敏・法政大教授】 インド大好きな中国人です。
小川さんに一つ教えていただきたいのですが、インドには日本語教師志望者はほとんどいないというようなことを言われたのですが、なぜ日本語教師志望者がほとんどいないのでしょうか。その背景と、そして、他言語の教員になりたい志望者はどうでしょうか。あるかどうか、小川さんに教えていただきたいと思います。

それから、小川さんの文章で、岡倉天心とタゴールの交流に関して書かれているんですが、タンカさんにお聞きしたいと思います。一般のインド人にとって、タゴールの存在とイメージは、どんなものなのでしょうか。そして、一般のインド人が物事を考える、判断する価値基準は何によるものでしょうか。もちろん、さまざまだと思いますけれども、大ざっぱにもしまとめられるようなものがあれば、教えていただきたいと思います。
それから、竹中先生のご報告を聞きますと、とてもバランスがとれた感じのインド社会のイメージを受けております。うらやましいぐらいバランスがとれているようですが、そうしますと、転換期における危機といったものはどんなものがあるのでしょうか。
お三方に教えていただきたいと思います。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 王先生からはお三方それぞれにご質問がありましたので、これもすぐお返事をいただきましょう。まず、小川さんに、日本語教育の現状ですね。
給料がよくないので日本語教師になりたがらない
【小川忠・国際交流基金日本研究・知的交流部長】 インドで日本語学習者が何で日本語教師になりたがらないかということなのですが、この回答はタンカさんのほうがいいかなと思うのですが。私が聞いているところでは、今、日本の企業がインドにどんどん進出してきていて、かなり高給で日本語学習者を雇っていただけるということです。日本語を学習した人は大体日本の企業に就職していく。なかなか日本語教師は大学の専任ポストでもあまり給料がよくないから、日本語を勉強した人は日本の企業に就職したがって、日本語教師にはなりたがらないというふうに聞いております。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ありがとうございます。次に、タンカさん、すごい難しい問題。一つはタゴール、二つ目はインド人の価値観、これは僕も聞きたい。ぜひ。
ベンガルではタゴールは神様みたいな存在
【ブリッジ・タンカさん(デリー大教授)】 タゴールは簡単です。彼の存在は神様みたいです。特にベンガル地方だったら、彼はやはり文学者で美術家、思想家としてベンガル語の近代文学をつくったぐらいの人です。

文学だけじゃなくて、歌も書いています。彼の歌はベンガルの村では、どこでもみんなが覚えています。だから、田舎でも、「ラビンドラ・サンギート」(ラビンドラの歌)といいます、ラビンドラはラビンドラナート・タゴールの名前ですけれども、サンギートは歌。だから、ベンガルで彼を批判することはあり得ない。それは大変危険です。
もちろん、インド全土で彼は思想家として高く評価されています。
すごく現実的なインド人の価値観
インド人の価値観は一言ではいえない。インドは宗教的と強調されていますが、インドの歴史を見ても、どんな地方を見ても、インドの人々はすごく現実的で、今の世界との関係が強いと思います。だから、インドの神秘的なイメージはほとんど外国のイメージだと思うんです。あるいは、植民地時代につくられたイメージの側面が強いと思います。ないというわけではないのですが。例えば、僧侶階級とされるバラモンでも高利貸しがいた。バラモンがお寺のお坊さんというわけでもない。そしてそういうことは時代によって変わっている。
インドにはあらゆる価値観がありますけれど、一つ言えるのは多分、権力に対して自立性が強いことだと思います。それを利用する側面もありますけれど。そこから出てくる国家意識は多分日本や中国とまた違います。
3番目は、日本語の学生。例えばデリー大学の私の学部では日本語の授業は60年代の半ばから始まったんです。卒業生は70年代はほとんど旅行会社に就職したり、会社をつくったりしていました。70、80年代は先生になったり、また、時々通訳をしたりとか、そういう仕事があって、90年代からほとんど企業に入りました。
今は日本語だけでも難しくなっている。だから、企業だったら、言葉よりそういう専門知識が重要です。学部としても大学の先生になる人が少ないけれど、企業とかそういう仕事をやめて大学に戻る日本語を勉強した人が少し出てきます。ただ、奨学金やそういう職が少ない。例えば、PhDを取っても就職はすごく難しいです。だから、それが一つの限界だと思うんですね。だから、そういう仕事や研究所ができれば、そういう人が企業から戻るかもしれない。
今はむしろ、韓国語や中国語を学ぶインド人学生が増えています。仕事もすごく増えているから、韓国の企業がかなり活動しています。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 仕事がないから民間に行くんだという、大変非常に率直なお話です。転換期だけど、危機はないじゃないかという抜本的な問題を、竹中さん。
不幸な90年代が終わり、ちょっとうれしかった
【竹中千春・立教大教授】 はい、すいません。ちょっと能天気な話をしたかもしれません。ともかく90年代のインドがあまりにも不幸だったので、最近のインドがつい良く見えてしまいます。2000年代初めにも、先ほど小川さんもおっしゃいましたが、大地震がグジャラート地域で起こり、翌年には大規模な反ムスリム暴動があって何千人も殺されました。悲しい事件が続き、パキスタンと核戦争になるかもしれないとも怖れられ、この国はどうなっちゃうのと思ってばかりいたので、最近ちょっとうれしいというのが正直な気持ちです。もちろん、問題は山のようにありますが、先ほど言いましたように、結構リーズナブルなインドに変わってきています。これからどうなるかは保証の限りではありませんが、結構うれしい気持ちがあります。それが学問的にも反映されて、バラ色ではないけれど、明るいインド像になっているかもしれません。お許しください。
ただ、一つだけ言えば、インド人ってどういう人という質問は、なかなか答えにくいものです。小川さんやニューデリー支局長を務められた竹内さんとか中島泰さんのほうがよくご存じだと思います。私自身は、タゴールとまた違いますが、ガンジーを勉強したくてインド研究を始めたのですが、実際にインドに行ってみると、インド人ってもう全然想像したのと違うよ、非暴力主義って一体どこにあるの、みたいな経験をし、最初は衝撃を受けて、あまりこの国を好きになれませんでした。
貧しくても自由、正しいことは言う人権意識強い
でも、だんだん理解できて、最近この国の人たちをやっぱり好きだな、そして尊敬できるなと思うようになりました。インドの人々は何十年も独立後に苦労してきましたが、さっきタンカさんがおっしゃったように、貧しいけれども非常に自由な人たちです。いろいろなところでおつき合いするインド人って、もう言いたいことを言う人たちなので、私もだんだん似てきて、言いたいこと言う人になっているかもしれません。

それに加えて、貧しくてもカーストが低くてもマイノリティでも、つまり弱い立場に立っていても、正しいことは言わなければならないという人権意識は非常に強いです。そうした人権意識を支えているのは、民主主義の制度です。いろいろな工夫を重ね、法・制度・政策を生み出し、改変し、政党自体も民主主義のツールとして使っている。政党をつくって主張していく、権力をとって、あるいは、連合をつくって権力の中に入ることで、金をとってくる、権利を保障する。いろんな意味で、こうした民主主義の運用がインド人の強みになっているのではないか。国際社会のインド人は、マイナスのイメージだけでなく、こうした多元主義的な民主主義の一面をも体現しているような気がします。
問題は山のようにあります。一つはやっぱり国内の格差社会。日本では「悠久のインド」とか、ゆったりしたインド人というイメージがまだまだ強いですが、そういう古きよきインドはもうない、少なくともあんまり残っていない。デリーとかムンバイではみんな走っている。農村でも一緒に走らなきゃいけないんじゃないかという話になっている。例えばブッシュ大統領が植物から燃料を作るという政策を謳うと、インドの農家が来年の作付けを考えて、多国籍企業から種籾を買って作り、結局、借金を返済できなくなる。自殺する農民という問題が、インドでは最近の深刻な問題です。
国内の格差と、不安定な周辺諸国という危機要因
ですから、格差社会、これが政権変動ともかかわっているわけですが、格差社会をどうするか。つまり、さっきの話で言えばグローバル・インディアについていけるインド人が天国にいるとして、そこから蜘蛛の糸が下まで垂れているけれど、下にはいっぱい貧しい苦しい人たちがいる。芥川龍之介の小説じゃないですけど、みんな蓮の花のある池へ上りたいんだけど、上れない。途中で蜘蛛の糸がぶちっと切られて落ちていくインド人が、今でもやっぱりたくさんいる。でも、こうした人々をも上に連れていけるインドになるのかどうか。これは、国家の体制が崩れるとか、民主主義が壊れるとかいう問題じゃないんですが、何億の人たちの運命がどっちへ行くのかということは、やはり大きな危機、国民社会の分かれ目であろうと思っています。
2番目の点ですが、南アジアの中でインドだけが格段に強く豊かになっている。先ほどお話があったように、周辺諸国との格差が拡大している。スリランカやバングラデシュも経済成長していますが、そうした状態を考えても、格差が地域的に拡大している。
そこで、インドの大国主義が一方で現れるとともに、紛争は周りにあって、インドだけある意味では「輝くインド」になっているみたいな構図があるので、それをどうするのかという問題が指摘できます。これは、例えば日本とインドの外交的な協力を考える際、南アジアとその周辺地域における人間の安全保障政策、紛争解決、平和構築などのテーマになると思います。
インドの周辺との矛盾が現れているところが、例えばカシミールという地域です。そういう紛争をきちんと解決していくことができるのか、それがクライシス2というか、二つ目の危機、問題です。
3番目は、インドのナショナリズムと大国主義について。90年代には自信のなかったインドで、タカ派のナショナリズムがわっと登場して国家を揺らしました。けれども今は自信を持つインドに戻りつつあるんですね。私からすると、昔の社会主義インドは自己中心的なナショナリズムがすごく強くて、プライドが高くてつき合いにくい国だったと思いますが、最近のインドはちょっとモデレートになっていて、官僚の方とかビジネスの方も前よりずっとつき合いやすくなり、インド人英語もやや聞きやすくなったと思うんですが、いかがでしょうか。けれども逆に、成功し始めているからこそ、最近の中国じゃないですけれど、大国主義的なインドになり始めているかなという懸念もあります。
ですから、危機の3番目は、インドにとっての危機かどうかわからないんですが、インドが自国中心的な大国主義で行動する場面、中国などの競合する相手国との緊張を高める場面が、今後出てくる恐れがあるかなと考えています。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 大国としての自信を深めつつあるインドというお話です。竹内さん、お待たせしました。
7人の首相で何も変わらなかった日本:「インドへの道」は遠い
【竹内幸史・朝日新聞「ニッポン人脈記」班記者(元ニューデリー支局長)】 私は2001年から3年半、ニューデリー支局長をやって、東京でもインドをウォッチし続けてきました。コメントと、質問を一つさせていただきます。

今回のテーマは「インドへの道」ということですが、記者としてインド、日印関係を見てきた経験では、これは引き続き「道は遠い」、あるいは「さらに遠くなっている」というような感じがあります。
「われわれにとってインドとは何か」というときと、「インド人とは何か」というときはちょっと違うんですが、「インド人は」で言えば、国際社会における非常にユニークなおもしろい経営資源だと思います。すぐれたIT頭脳やネットワーク力があって、これを日本がうまく使って成長のかてに取り込んでいけば、非常におもしろい展開ができる。けれども、「インドへの道は遠いな」というのは、やっぱり日本にその能力も、その余裕もない。
新聞社としても紙面的余裕がどうしても不十分ですね。つまり、東アジアでこれだけ中国の問題が出てくれば、そっちに紙面を割かざるを得ない。そういう中で、インドというのはどういう国なのかということを新聞もメディアも頑張って報道してやりたいけれども、なかなかその余裕がないのです。
私が赴任する前の年に、森喜朗首相がインドに行き、そのときに「グローバル・パートナーシップ」を日印で表明しました。このグローバル・パートナーシップ宣言から今年で10年ということで、その間に何が変わったかというと、「思ったほどやっぱり勢いがつかなかったね」ということをよく言っています。
それ以降、小泉、安倍、福田、麻生、鳩山、菅と、みんなインド重視だと言っています。10年間に7人の首相が「共通の価値観の国だから」と言い続けていますが、結局、「価値観のどこが共通しているんだろうね」ということを皆いつも自問しているところです。
やっぱり、まだまだ社会の問題、カーストの問題など、インドは分かりにくい国なので、メディアも学者も努力するべきでしょう。
インドにとって日本とは何か?
そこで特にタンカさんへの質問です。インド関係の民間外交をやっている人で、ビバウ・カント・ウパデアーエ(Vibhav Kant Upadhyay)という人がいます。この人はこの10年間、7人の首相を全員インド通になるように仕向けてやってきたのですが、インド国内では、「日本のサポートをしているなんて、労多くして実りが少ないだろう」という声があるようです。
インドでは、首相もいずれこの数年で若返るわけですが、さっき竹中先生が言われたように大国志向、強国志向をどんどん強めていくでしょう。その中で、「日本みたいにぐじゃぐじゃ言っている国とはもういいじゃないか、もう日本と時間かけてつき合うよりも、大国の仲間入りの方が大事だ」という方向で動いていくのではないかなという懸念があります。そのあたりを、どうお考えになりますか。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 わ、一気に暗くなりました。
【ブリッジ・タンカ(デリー大教授)】 どういうご質問かちょっとわからなかったんですけど。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 インドが日本を卒業して、大国として大国とのつき合いを重視するようになるんじゃないかという含みでした。
【ブリッジ・タンカさん(デリー大教授)】 私はそう思いますけれど(笑)。
いや、というのは、日本の外交は、戦後、ほとんどアメリカとの条約のもとでいろいろ活動してきました。今の例えば普天間問題とか、先日の尖閣問題をみても、何かリアクティブ(reactive、反応的)です。

僕は別にイスラエルを支持していませんが、イスラエルはアメリカとの条約はあるけれど、自分のやりたいことをいろいろ勝手にやっていて、リアクティブというわけではない。
インドの場合、90年代から、アメリカとの関係が一番重要になっているみたいです。もちろん、国内では議論がありますが、今の政府だけを考えると、アメリカが重要になる。それに次いで日本が重要です。
日本は重要だが、重要性が変化してきた
日本との、特に経済関係が重要と思っているんですけれど、少なくとも90年代から毎年日本から何とか財団や何とか企業団体が来て、いろいろな宣言をしています。まあ順調に伸びているのですけれど、ほとんどの経済関係がインド側から見るとそれほど大きくなってない。その間に、例えば中国との関係は経済的に進歩したし、あるいは、韓国もそうです。
またインドの経済事情も変わっているんです。インドはまだ、中国ほどじゃない、もちろん。しかし、やはり世界の市場を考えれば、その中に政治もそういうグローバル的なものにしようとこれから考えてくると思います。
だから、日本はこれからも重要だと思いますが、日本の重要さが少し変化するかもしれない。変化の傾向をとってくると思います、インドに対して。
インドの現在の問題はエネルギーの問題や、近隣のテロの問題です。そうすると、例えばロシアとか中国とかイランがもっと重要になります。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 インドのジャパン・パッシング、ですね。畠山さん、どうぞ。
■全体討論(2)インドはAPECに加わりたいのか、FTAを結びたいのか
【畠山襄・国際経済交流財団会長】 日本で来月、菅首相の主宰のもとで大きな国際会議が開かれるわけですね。これはインド抜きで開かれる。APEC(アジア太平洋経済協力会議)ですね。
それで、APECにはインドが入ってないわけですけども、日本のねらいは、APECにインドを入れて、そのメンバーでFTA(自由貿易協定)をつくりたい。さっきお話の中に、日本とインドのFTAができたらという話がありましたけど、そういう希望が出ているんですが、インド側が果たしてそれを希望しているのかどうかはよくわからない。

インドがAPECに入りたいのかとか、ここについて、もしご意見があればぜひ伺いたいというのが第1点です。
第2点は、そういうことをアメリカで私が当時のUSTRのスーザン・シュワブという代表に聞きましたらば、「インドを入れて自由貿易協定?、冗談でしょう」とか、「インドを入れたら非自由貿易協定になるわ」と、まあ、ちょっとインドの方の前で恐縮ですけど、そう言われたんですが、それのみならず当時、ASEANとインドは自由貿易協定の交渉をしていましたが、ASEANの人たちも口をそろえて、「インドとの交渉は大変だよと」、今、暗い話になったので、暗い話のついでに申し上げると、そう言われました。さっき竹中先生の話だと、2009年からの国民会議派になって、市場経済になって、「それは変わったよ」ということだったような気もしますが、ほんとうに変わっているんでしょうか、というのが第2問です。
第3問もありまして、私が通産省にいてインドといろいろやっていたころの日本人ビジネスマンのインド観は、例えばインドネシアに赴任した人に対して、「インドネシアにもう一回行きたいか」と聞くと、「行きたい」と答える。インドに赴任した人に、「もう一回行きたいか」と聞くと、「行きたくない」と答えるということだったんですが、その理由は、インド人は非常に何ていうかlitigiousというのか、論争好きで理屈っぽいと、それで、話が長くて。まあ、よく冗談で、国際会議の名司会者は、インド人は黙らせて日本人はしゃべらせることだと言われるぐらい、波長が合わないというのです。日本は和をたっとぶわけですから、そう言いたいことを全部言うようなのは合わないと言われますが、そういうことでしょうか。
最後は小さい問題ですが、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想ですが、これによって、日本はインドの経済発展に大きく貢献していると言っていてマンモハン・シン首相が見えたりすると、その問題を出したりしているわけですけれども、そういう話はデリー大学の教授などのお耳にも達するものなんですか。聞いておられますか。
APECには入りたい。でもFTAがいいのかわからない
【ブリッジ・タンカさん(デリー大学教授)】 APECには入りたいと思っています。しかし、インドの新聞でFTAはインドの経済にあんまり役に立たないという議論が出ていました。東南アジアや韓国のFTAを利用して中国のいろんなものが入ってくるという議論でした。それは、交渉を厳しくすれば別にそれは問題ないと思うんです。

現在行っている戦闘機買い入れの交渉も同じです。アメリカとボーイングより、スウェーデンのサーブとかロシアのミグを使おうとしている。
インドで活動しているほかの外国の企業は、同じような問題をイメージしていると私は思わない。印象は全然違います。だから、もしかしたら、それは日本人の問題、独自な問題だし、交渉の問題だと思います。
【畠山襄・国際経済交流財団会長】 あるいは変わっているかもしれませんけどね。
【ブリッジ・タンカさん(デリー大教授)】 いや、変わってない。ただ、同じ状況なのに、ほかの国の企業、あるいは、インドで活動している外国人は日本人と同じように問題を考えてない、それを問題にしてない。彼らの印象は違います。だから、それを深く研究をすれば、多分何か答えが出てくるんじゃないかと思います。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ええ。問題は単純で、英語でまくしたてられる、こっちは英語が話せない、何だ英語がしゃべるからって威張りやがってという憤懣をデリーでは感じるけどジャカルタではあんまり感じないで済むというお話ですね。
日本にはインドの特派員がいません
【川崎剛・朝日新聞アジアネットワーク事務局長】 報告をひとつ、質問をひとつします。
朝日新聞アジアネットワーク(AAN)はアジアの途上国の記者を毎年招いてきたのですが、今年度、インドから記者を招こうと思っていたところ、というのは、大学教授や学生どころか、日本にはインドの記者がいません。特派員がいません、今の今、一人もいません。昔いたかもしれませんけど、もうかなり長く、インドのメディアの記者は日本に駐在していません。

ということで、ぜひインドの記者を招いて、東京発で日本のことを書いてもらう手助けをしようと思ったわけです。
これは朝日新聞のプロジェクトですから、生活費と家賃は出しますよということで、朝日新聞の昔からのつき合いがあるタイムズ・オブ・インディア(Times of India)に話をした。「よし行こう、出すぞ」といい返事がきた。
しばらくしてから、「滞在は5カ月ぐらい」と言っていたのが、「ちょっと忙しいので3カ月にしてくれ」。この間、「欠員が出て忙しい、4週間ではどうだ」。「それでは出張と同じじゃないか」というと、「では6週間」。バナナのたたき売りみたいになり、その後、申請に入りたくても名前を言ってこないわけです。
ひょっとして、彼らはそれほど日本に来たくはないのではないか、インドのメディアにとって日本はそんなに魅力はないのではないか。英語のメディアで日本の情報は得ているでしょうし。
日本のメディアの記者はインドにたくさんおります。
インドの経済は本当によくなるのか
質問です。朝日アジアフェロー・フォーラムでインドをやるということになったので、気にしていたら、やっぱり日本のインドへの関心と欧米のインドへの関心は全然違うのではないかということを最近感じました。
『エコノミスト』は、8月21日号ですけれども、「中国対インドの世紀の対決」という特集をやっていました。『エコノミスト』の今週号(10月2日号)では、インドは中国の経済力をどのように追い抜くかという考証をしている。これが表紙です。トラが走っている。
これは先週の『ニューズウィーク日本語版』ですが、「インド経済黄信号」という特集です。表紙では、トラが困っている。
中国の経済のように私たちに少しイメージができるといいのですが、インドの経済はほんとうによくなるのか、長い目でも、中期的にも。その感じを何かお持ちでしたら、教えていただきたい。以上です。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 タンカさん、インド、よくなるんでしょうか。
よくなっているが、不均衡も拡大している。バランスが取れるか。
【ブリッジ・タンカさん(デリー大教授)】 二つ。まず、最初のコメントは、新聞記者の問題。インドの新聞の事情を見ると、国内の記事が多い。国内から外交関係の記事はそんなに書かないから、多分そういうわけで離れたくない一つの理由かもしれない。
インド経済の問題では、前のBJP政権が「インディア・シャイニング(India Shining、輝くインド)」というスローガンを立てたんですけれど、私はそれをあまり好まない。国全体がまだ満足する状態ではない。もちろん、経済が急速に変化して、経済だけじゃなくて、社会の変化の速度が早くなっているから、あらゆるところがよくなっている。生活もよくなっています。
ただ、格差はもっと大きくなっているから、今の国民会議派の政権を見ると、内閣はかなり経済成長を中心にしてやっていると思います。政党としては、左翼的なセーフティネットを中心にしており、それで、この間の選挙に勝ったので、そういうことはすごく重要になります。
だから、これからの一番の問題は、そのバランスをとらなければいけないということです。今日の話では出てこなかったけれど、インドの真ん中あたり、今、毛沢東主義のゲリラが活動している問題があります。政党としては、インド共産党の毛沢東主義派ですけれど、基本はほとんどいわゆる部族(トライブズ)です。だから、必ずしも一致してないと思います。その政党と部族の問題。でも、それがそういう不均衡、アンバランスを表現していると思います。
米英の対インド観は微妙に違う
【司会(藤原帰一・東大教授)】 補足すれば、『エコノミスト』はインド特集をたくさん組んで、しかも、インドが次の経済大国だ、投資先だということをよく記事にするんですね。『ニューズウィーク』はインドについて記事を書きますけれども、やや消極的で、インドが中国になるわけないじゃないかという形です。これは要するにアメリカの雑誌、イギリスの雑誌という違いでしょう。イギリスはもともとインドの市場とのかかわりが非常に強く、イギリス国内にインド系住民がたくさんいます。イギリス国内のインド系住民がインドに投資をするという仕掛けもあるわけで、インドの成長とイギリス経済の成長と密接な関係があるわけです。でも、インドとアメリカとの関係はそれほどじゃない。ということは、インドが大きくなるからといってそこまでの期待はないわけです。

ただ、実態から見れば、中国の場合には実物経済が成長しますけれども、インドの場合には、実物経済の成長よりも、それに対する期待のために流れているお金がまだ高い状況だと思います。これが将来もそのままで終わるかどうかというのは全く別の問題です。
次に国分さん。
インドが描く自画像は
【国分良成・慶応大法学部長】 ありがとうございます。二つ質問がありまして、これはどなたでもいいですけど、今日の3人の報告者の方にお答えをいただければと思います。
一つは、インド自身が今、自画像をどういうふうに描くのかという、こういう話です。もちろん他人がインドをどう見たかという他者が描く像がまずあるんだと思いますけれども、インド人が今のインドをどう見るのかという点です。

われわれの像からすると、先ほど竹中さんの報告にありました、50年代は非同盟のリーダーみたいな、そういうインド像みたいなのがあったわけですが、それが、特に時代を経るに従って、非同盟と同時にアジアの中のインド、あるいは冷戦中のソ連寄りのインドという、こういう像みたいなものがあったと思うんです。
それが、その後、やがて南アジアの中のインドというような、こういうイメージみたいなものができ、自画像としてもそうだったんじゃないかと思います。しかし、南アジアって非常に単純にまとめちゃうけれども、相当に多様なわけですよね。もちろん、パキスタンもバングラデシュもあり、スリランカもあり、さらには、南アジア、プラス、中央アジアみたいな概念も最近出てきたと。それにプラスして、インドということを論ずるときに民主主義とか、こういうイメージも出てくると思うんですね。
南アジアとか中央アジアという枠の中では、核問題とか民族問題、こんなような議論が、特に冷戦以後、大きかったような気がするんです。
ところが、特に21世紀に入ってから、まさにBRICsの時代のインドということになってきた。G7やG8じゃなくて、もうG20だと言われたときに、インドがその中心をなしているということですね。中国やブラジルと肩を並べたときに、世界の像をどういうふうに描いて、さらにそこに自身をどう位置づけていくかという点ですね。多分インドにとってみると、多極化というこういう時代に入っていくというのは、おそらく中国と相当に利益を共有できる部分ができていく感じがするんです。
だから、日本がいくら中国に向き合うためにインドを使おうとしても、実際には難しいのではないか。その前に、ちゃんと日本は中国ときちんと対面しないといけないわけですけれども、別にインドを使ったから何ができるというわけでも必ずしもないと思うんですけれども。インドと中国の間の交流も相当に多いですから。
そういうときに、インド自身が自画像を考えたときに、今のG20とかBRICsなどと言われ、どのように対応していくのか。もしインドはもうむしろ大国のほうに主として目が向き始めたとしたら、元気のでない日本が一体どこに位置づけられるのかと思うのです。
いずれにしても、インドが今考える世界像というのは、多極化とかG20の世界で、成長している国家の一つのダイナミズムというか、そこが働いているのかなという感じが、お話を聞いているとするということがひとつ。ちょっと長くなってすみません。
民主主義でインドはどうしてばらけないのか
それから、もう一点は、これは竹中さんにお聞きしたほうがいいと思うんですけども、われわれ、中国研究をやっていると、民主化したら中国は大変なことになるという議論があります。民主化で中国はばらばらになって混乱するというのですが、インドがどうしてばらけないのかなということです。
そのときに、インドがどうして大きく三つや四つの主要政党でもっているかということですね。つまり、いろんな利益がたくさんあるにもかかわらず、その利益を吸収していく代表政党がこれで済んでるというのは、どうしてそうなのか。その利益の集約がそういう形で済むというのは、中国の将来の民主化を考えたときに、何か参考になるんではないかと思ってお聞きしたということであります。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ありがとうございます。今すぐお答えをお聞きしたいところなんですが、ちょっと時間の関係がありますので、国分さんの最初のご質問、「インドとそれから世界の中のインド」というお話と、それから、「インドが何で3つの政党でもつのか」、ちょっと頭の中にとめておいてください。質問を束ねていきたいと思います。次に、近藤さん、お待たせしました。
日印経済関係を活性化するためには具体的に何を
【近藤正規・国際基督教大学上級准教授】 これまでのお話の中であまり出なかったこととしては、日印経済関係があると思います。
インドは2003年度以降日本にとって最大のODA受取国であり、インドにとっても日本は最大の二国間ドナーとなっています。さらに2008年度の日本の対外直接投資は、対印が対中を抜いて第1位になっています。最近では、先ほどお話があったEPAの大筋合意もなされ、原子力協定に向けた交渉も始まっています。ただし現実問題としては、日本の企業におけるインドビジネスの位置づけは、まだまだ対中や対ASEANとは比べものにならないようです。小川さんのお話しにもありましたように、人的交流も限られています。

そういう状況を踏まえましてお伺いしたいのですが、日印経済関係を今後さらに活性化するために具体的に何をすればいいのか、非常にざっくりした質問で申し訳ないですが、どなたかお話いただけると有難いです。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 建設的な提案をというお話ですね。次に竹田さん。
大国化するインドの国家資本主義的な動き:政府と民間企業の関係は?
【竹田いさみ・獨協大教授】 ひとつ質問がございます。キーワードを申し上げますと、インドの大国化、国家資本主義、政府と企業の連携――これが三つのキーワードです。先ほどからインドの大国化というお話がありますが、例えば大国化していくプロセスで、政府と民間企業がどのようにタイアップしていくのでしょうか。

民間主導のグローバリゼーションの世の中で、やはり国家資本主義的な動きが加速されているわけです。韓国が、「韓国株式会社」として、例えばアブダビの原発を落とす、それから、ロシアがベトナムの原発を落とす。ロシアの場合は武器輸出とセットです。というように、売り込みに政府と企業が一体化するという例が見られるわけです。イギリスの銀行は大半は国有化されていますから、イギリスは金融は政府主導型ということになります。
そうすると、政府の役割というのはものすごく大きくなっています。
経済危機が訪れるとやはり政府が介入しますから、そこでさらに政府の役割が大きくなります。また、その民間市場に関しても政府が介入すると。こういう国際環境の下で、日本はどのような状況に置かれているのかという問題意識があります。
しかし、インドの場合、大国化ということを将来描いた場合、政府と民間企業がどういう形で現在タイアップしているのか、もしくはしてないのか、将来的に政府はどういう形で民間企業を後押しするのか、大きな問題だと思います。
中東湾岸諸国、サウジアラビアには中国資本が相当進出しています。中国の場合は民間企業の後ろに中国政府が控えているわけです。中国政府、もしくは市政府の存在感を見て取ることができるようです。
それでは、インドはどうなのでしょうか。インドの場合は、政府の影がそれほどちらつかない。だから、安心してつき合えるという意見もあるそうです。
インドの大国化、国家資本主義の台頭、政府と民間企業のタイアップについて、ぜひ先生方からご意見をうかがいたいと思います。ありがとうございました。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 政府と企業の関係についてのお話ですね。崔相龍先生。
大国の中身――極端な貧富の格差とカースト
【崔相龍・法政大特任教授(元韓国駐日大使)】 国分さんの問題意識とちょっと重なりますが、私はインドの自画像、未来像について、特に日本の専門家である竹中教授とタンカさんにお聞きしたいと思うんです。
私にとってインドというのは二つの顔が見えるんです。

一つは、何十年前だと思いますが、平和研究、特に平和思想研究でガンジーの思想をかなり地道に調べたことがあります。私にとって一つの顔はガンジーの顔ですね。私は最近かの有名なマイケル・サンデルの講義録、『JUSTICE』(邦訳『これからの「正義」の話をしよう:いまを生き延びるための哲学』)。そこに私にとってショックを受けた一つのインドの例が出ています。
インドの西の地域だと覚えておりますが、いわゆる代理出産の問題ですね。代理母を志願するインドの女性が増えつつあるという。それで、1回代理母で4,500ドル、ないし、7,500ドルを金をもらう。これはほかの仕事で15年かけて稼ぐ金額なんですね。私は大変ショックを受けました。韓国もかなり悲しい、非常に貧しい女性がいますけれども、韓国では考えられないと思いますね、私は。だから、こういう顔。簡単に言えば、極端な貧富の格差、それからまた、カーストの差別を含んだインドの社会ですね。そういう一つの顔。
もう一つは、ほんとの神のような、神の化身のような偉大な指導者がいるわけですね。タゴールもそうですし、ガンジーもそうでありますね。そういう人類の救済に貢献し得るそういう偉大な指導者が出ている、そういうインドの社会ですね。
こういう社会は、今さっき未来像の一つとして大国ということが出ましたけれども、問題は大国の内容、中身ですね。どういう大国になるか。アメリカも大国、日本も大国、中国も大国、インドの大国の中身はどうなる。
私は非常に疑問に思っているのは、こういう極端な貧富の格差を伴う経済成長、その延長線でのインド大国の未来像はどうなのか。その似たようなものは中国にも起こっています。中国はまぎれもない大国ですね。だけど、専門家によりますと、いずれ中国はアメリカをしのぐ可能性があると。インドは少なくとも日本をしのぐかもしれないという展望があるんです。
それも含めて、格差というインドの病気というか、インド病というか、それを伴う大国インドの未来像について、漠然でもいいですから、その専門家、竹中教授と、インド自身の代表とも言えるタンカ先生にお聞きしたいと思います。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 今、4人の方からご質問いただいたものをまとめてというのはいかにも失礼なんですが、残された時間が2分、それを1分延長したとして、一人1分という大変な短時間で恐縮ですけれども、最後のお言葉をいただきたいと思います。まず、タンカさん。
インドの人々に大国の自覚はまだない
【ブリッジ・タンカさん(デリー大学教授)】 まず、インド大国論という議論は一部で話されていますが、普通はそんなには重要な議論と思われていない。

社会に幾つも問題があるから、それを解決しなければいけないと考えていて、自分がもう大国になってるとはそんなにインド人は考えていないと思うんです。「インドが大国だ」というのは、むしろ外国から見ている議論の中にもっと大きい。もちろん、一部の企業などではそんな議論がされている。
もう一つは、格差やカーストなどいろいろあると思いますが、ある意味で、カーストは忘れたほうがいいと思います。あまりにもそれにとらわれている。重要かもしれないけれど、今は差別とは違うように機能している。
活発化する社会運動
今のところ、インドのいろんな問題に対して、社会運動がかなり活動しています。そうすると、その格差あるいは不平等な条件を解決しようとしているというところに注目しなければいけないと思います。もちろん、失敗する可能性はあります。でも、今すごくポジティブな面が機能していると思います。
企業と政府の関係についても、かなり議論があると思うんですね。大企業が外国で活動するために、そういう援助とかバックアップが必要になっていると。でも、国内で民間企業を少し制限する動きもかなりあります。だから、国の経済はそういう大企業をもとにして語るんじゃなくて、やはり民間の生活から考えるべきなんです。
ちょっと違う経済制度をつくりたいという気持ちがある。同じように、ナショナリズムも近代的な統一ナショナリズムじゃなくて、違うような多様的なナショナリズムをつくりたい。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ありがとうございます。続いて、小川さん。
日本の英語発信力がやはり必要
【小川忠・国際交流基金日本研究・知的交流部長】 先ほど、畠山先生がインドネシアに赴任した企業マンはもう一度駐在を希望し、インドに赴任した人は二度と戻りたくないという傾向があるとおっしゃいました。私、両方の国に駐在していたのですが、ぜひもう一回、どっちの国にも戻りたい。

今の話と、川崎さんと近藤先生の話をちょっとまとめて、日印交流の活性化ということを考えてみたいと思います。インドネシア人と日本人で共通するのは英語が下手だということですね。藤原先生がおっしゃっていたように、これからは英語で発信していくことが大事だと思います。インドの大学とかジャーナリズムとか官僚たちで構成される知的世界は、英米の知的世界との中で形成されていったという歴史的経緯から、今でもロンドンとかニューヨークでどういう議論をやっているかということに非常に関心を持っている。
ということは、インドに日本への関心を持たせるようにするためには、ロンドンとかニューヨークで日本のことをもっと議論させる状況を作り出していく必要がある。そのためには、英語で日本国外に向かって発信できる人をつくっていくということは大事です。それから、日本の大学において英語で教育する大学も最近少しずつ増えてきて、そういう大学にインドからの留学生が増えつつあるということを考えると、やはり英語でもって高等教育が行われるというシステムをもっと日本の中でできればいいんじゃないかなというのが1点です。
中産階級が増え、歴史認識の対立が起き始めた
それから、2点目として、大国意識とインドの自画像という話の中で、ちょっと一つ論点として入れておきたいのは、今インドの中で中産階級が急速に増えてきているという事実です。一握りの大富豪と大多数の貧者だけではない、ミドルクラスの人々が拡大していて、そういう人たちがインドの自画像とかインドの未来ということを語り始めている。
その中で非常に深刻な問題として、インド人同士の中での歴史認識の対立という問題があります。私がインドにいた90年代末ごろ。イスラムの位置とか、ガンジーの評価ということに対しても、あまりにも神格化されたガンジー像に疲れたミドルクラスがチャンドラ・ボースとか、いわゆるヒンドゥーナショナリズム的な議論に結びつくというような現象がありました。対外的な大国意識を語る前に、インド人自身のインド自画像が非常に90年代から2000年代にかけて揺れていたというのが私の印象です。 以上です。
【司会(藤原帰一・東大教授)】 最後トリです、竹中さん。
インドも中国も資本主義に向いた人々ではなかったか
【竹中千春・立教大教授】 1分はたぶん超えますが、頑張ります。
竹田先生がおっしゃった政府。そうですね。社会主義をやめた後は、政府の規制をどんどん取っ払おうということになりました。そうすると、保護されてきたインドの資本は負けちゃうんじゃないかと危惧されましたが、今やタタ財閥などグローバルなインド系の資本が伸び、世界のミリオネア・トップリストにインド系の人が何人も入る状態に変わっています。ですから、方向性としては政府からの自由を拡大し、政府がアジャストの機能、つまり利益の調整機能を果たすということがより期待されていると思います。

崔先生が、ガンジーとかタゴールとかネルーとか、インドの生んだ偉大な人々について指摘されました。確かにそういう英雄の時代がありました。けれども、見方を変えると、偉大な人が出てくるのは少し不幸な社会ではないかとも言えるかもしれません。普通の社会、幸福な人々の多い社会には、あまり偉大な人は登場できない。
この点から言うと、中国もやっぱりかなり不幸な社会だったのかもしれません。逆に、社会主義的な大きな政府は要らない、偉大な指導者も要らないという時代になってくると、インド人ってずいぶん資本主義に向いた人たちだなと思えてきます。たぶん中国人も。世界中、印僑と華僑の大きなネットワークが動いているみたいな時代になっていますね。
ですので、ポスト社会主義のインドでは、ガンジーの顔が印刷された1,000ルピーの高額紙幣が出回っていますが、すごく屈折した感じがします。ガンジーが説いたのは清貧といいましょうか、日本にも伝統的にそういう価値観がありましたが、農民の清い貧しさを尊いとする価値観でした。それが、市場経済の開放によってある意味で否定され、豊かなものを目指せ、お金儲けした者が勝ち残るという価値観に変わっている。しかも、それを象徴する高額紙幣に微笑んだガンジーの顔が載っているというわけです。
それでは、大国化するインドはどういう自画像を描いているか。「墜ちた偶像」の1990年代の後、どうなったか。2004年総選挙でインド国民会議派が勝ったときのキャンペーンは「普通の人」でした。「輝くインド」という宣伝文句を掲げたインド人民党に対して、今や普通の人が主人公の時代だという主張です。2009年総選挙では、国際的に有名になった映画『スラムドッグ・ミリオネア』の主題歌を使う権利を会議派陣営が獲得し、選挙のキャンペーンに使いました。そして、会議派のほうが若い世代や女性にアピールしたと言われています。裏を返せば、会議派のおじさん、おじいさんたちがみんな90年代の選挙で落ちちゃったんで、その息子とか娘、ハリウッドスターで若い人材などが候補者になったのですが。こうして、より若く、ミドルクラス的な人たち、人口の二、三割を占める成長するインドを体現する人々が会議派の候補者となり、農村の人たちもバックアップしている。政界から見ると、そうしたインドの自画像になっているのではないかと思います。
「普通の人」のインドへ
もう少し具体的にイメージを描くと、選挙で選ばれる自画像の条件の一つは普通の人、その次の条件は、都会のミドルクラスでちょっとかっこいい。だから、選挙遊説のときにはインドの民族衣裳を着ているけど、投票所に行くときはラルフローレンのTシャツを来ている、そういう若々しい人が会議派の議員に当選した、みたいな感じですね。
このように、国民的な自画像が選挙戦の中でも試されている。その結果、国民、つまりナショナルなインドは、グローバルなインドを求めつつ、グラスルーツというか、草の根のローカルなインドもくっつけていく、みたいイメージになっているかなと思います。
終わりに、国分先生のご質問の政党制についてですが、3党とか4党とかではなく、三つの政党勢力、四つの政党勢力といった形でお話したつもりでした。たとえば、会議派陣営といえば、会議派という一つの党にもう10も20もくっついて連合を作り、選挙戦を戦います。インド人民党側もそうです。2009年選挙では、360ぐらいの政党が登録され、全国政党は7、州政党が34にすぎず、その他は1人1党のような政党で、ほとんど議席が取れません。そういう単位の多党制ですから、3党とか4党とかいう状態ではありません。
でも、それでもまとまっているというか、ばらばらではないところが、おもしろい。さっきの畠山さんのご質問に対して答えれば、みんな言いたいことが言えるからこそ、一緒の船に乗っている。嫌だったら降りて出ていけるから安心して一緒にいるという発想ですね。はっきり言うと、国連の安全保障理事会の拒否権と同じ発想です。「出ていけるので一緒にいるよ」、「反対しても一緒のほうがいいから一緒にいよう」という形のデモクラシーなんですね。
最後になりますが、日本とインドの関係、これはもっと強化していけると思います。インド、平均の年齢が20代ですので、要するに若い。歴史問題なんて成立しない。社会主義を全然知らない人が今のインドを動かそうとしている。ガンジーも社会主義も知らないけど、頑張るぞインド、みたいな感じの人たちがパソコンを動かしているという世界です。ですから、そういう人たちとものごとを一緒にやるということになると、必要なのはスピード、国際人としての力、たとえば英語能力、それから若さ、軽さですね。
ですから、日本のほうが悩み過ぎ、かもしれません。大国主義が匂いすぎる。大国だから援助しなければ、なんて思わなくていいと思います。あっちは儲けようと思っているんですから、こっちも何とか儲けよう、みたいな感じで投資や技術協力を交渉すればよいと思います。
インド人は、まずあらかじめノーと言って、いろいろ主張を述べてから、あっちがこう言ったら、そうですねとか譲歩して、何とか妥結しようとします。しかも、すでに述べたように、あちらにも内政の縛りとかいろいろあります。だから、そこであんまり悩まない。もう要するに言いたいことは言うぞという姿勢でつきあえばよいと思います。
「日本対インド」やめ、グローバル企業で多くのインド人雇え
最後ですが、経済的にもっとつながりを強化すべきです。そのためには、「日本対インド」という図式で考えないことが必要ではないでしょうか。例えば、日本企業の多くはグローバル企業なので、もっとたくさんのインド人を雇うべきではないか。すでにかなり多くの中国人を雇っていますけれど、まだまだ足りない。ですから、企業の中に国籍や文化の異なる人々を採用して多様性を作り出し、そうした人たちがグローバル企業のメンバーとして活躍する。インドの企業のインド人と日本の企業のインド人が交渉すれば、心配されているようなカルチュラルギャップは発生せず、こちらの利益を十分主張して妥当な契約が結べるのではないか。そう思います。

今、日本のグローバル企業には、他の諸国に比べでも国際的な人材が少ないと言われます。日本人だけでやろうとしたら無理な時代です。そうした組織的な変化を生み出せば、若さや軽さ、ずうずうしさや押しの強さも、日本の企業が獲得し、より力強く前進できるのではないでしょうか。すいません、1分、たくさん超えてしまって。
インドへの好奇心、知的関心が育ってきた
【司会(藤原帰一・東大教授)】 ありがとうございました。
ギャップの多い会合でした。大国となったインドをわれわれがどう迎え入れるのか、大国インドとどう向き合うのかという視点から、インドの外からのお話、質問が繰り広げられました。他方、インドにかかわっていらっしゃった方々からは、インドにとってインドとは何かというお話があって、これも大国かどうかという以前の問題なんですね。
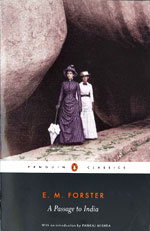
このギャップからわかってくるのは、やはりインドへの道が遠いということです。かつてイギリスの作家フォースターは、イギリスの植民地であったインドとのかかわりを長編小説『インドへの道』に描いたわけですけれども、そこにも距離の認識がありました。イギリス人が考えているよりインドは遠いところにあるという隔たりの認識が、独特な植民地支配への批判になっていました。日本も、インドはアジアだから距離が近いと考えるのは間違いなんでしょう。
もし、本日の会合に少しの意味があるとすれば、その距離の大きさと、それを埋めようとする好奇心、知的な関心がわれわれの中にさらに育ってきたということなのではないかと思います。本日はお忙しい中、3人の先生方、また、お集まりいただきました皆様に深く感謝したいと思います。(拍手)(写真:家老芳美)
■【第13回朝日アジアフェロー・フォーラム】参加者一覧
〈報告者〉
ブリッジ・タンカ インド・デリー大学教授(日本近代史)
小川忠 国際交流基金 日本研究・知的交流部長
竹中千春 立教大学教授(インド現代政治)
〈司会〉
藤原帰一 東京大学教授(国際政治・東南アジア政治)
〈フェロー&ゲスト〉
今西淳子 渥美国際交流奨学財団常務理事
国分良成 慶應義塾大学法学部長
近藤正規 国際基督教大学上級准教授(開発経済学、インド経済)
佐藤幸人 アジア経済研究所研究主任(台湾政治、経済)
竹田いさみ 獨協大学教授(国際政治、東南アジア広域研究)
崔相龍 法政大特任教授(元韓国駐日大使)
畠山襄 国際経済交流財団会長
王敏 法政大学国際日本学研究所教授(比較文化)
〈朝日新聞からの主な出席者〉
伊藤重人 ジャーナリスト学校主任研究員
大軒由敬 論説主幹
太田啓之 オピニオン編集グループ
大野正美 論説委員
岡田健冶郎 オピニオン編集グループ
金重秀幸 オピニオン編集グループ
川崎剛 朝日新聞アジアネットワーク(AAN)事務局長
金順姫 国際報道グループ
柴田直治 特報センター長
杉浦信之 ゼネラルマネジャー、東京本社報道局長
竹内幸史 ニッポン人脈記班記者
刀祢館正明 編集委員
中島泰 論説副主幹
中野渉 国際報道グループ
奈良部健 編集センター
西村陽一 ゼネラルエディター、東京本社編成局長
野村彰男 ジャーナリスト学校長
原真人 論説委員
藤原秀人 論説委員
宮田謙一 ジャーナリスト学校事務局長
村山正司 オピニオン編集長代理
山田理恵 大阪生活文化グループ
遊佐美恵子 論説委員室
若宮啓文 コラムニスト
脇阪紀行 論説委員
渡辺勉 政治エディター
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください