WEBRONZA編集長 矢田義一
2012年07月06日
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所(G-SEC,Global Security Research Institute)が、東日本大震災からの復興支援を意図するプロジェクト「復興リーダー会議」が着実な歩みを続けている。被災地での支援活動で試行錯誤を重ねながら実績を積んだリーダー的存在の人たちや、今後の復興を担う人々らが集まり、現地の復旧から復興に向けた情報交換や、対話と議論、研究などに取り組んでいる。
スタートしたのは、2012年4月。13年3月ごろまでの1年間程度の期間で、月に1度、慶応義塾大学三田キャンパスにあるG-SEC Labに、様々なジャンルから講師を招いて話を聞き、参加しているリーダーらが質疑応答や討議を重ねている。
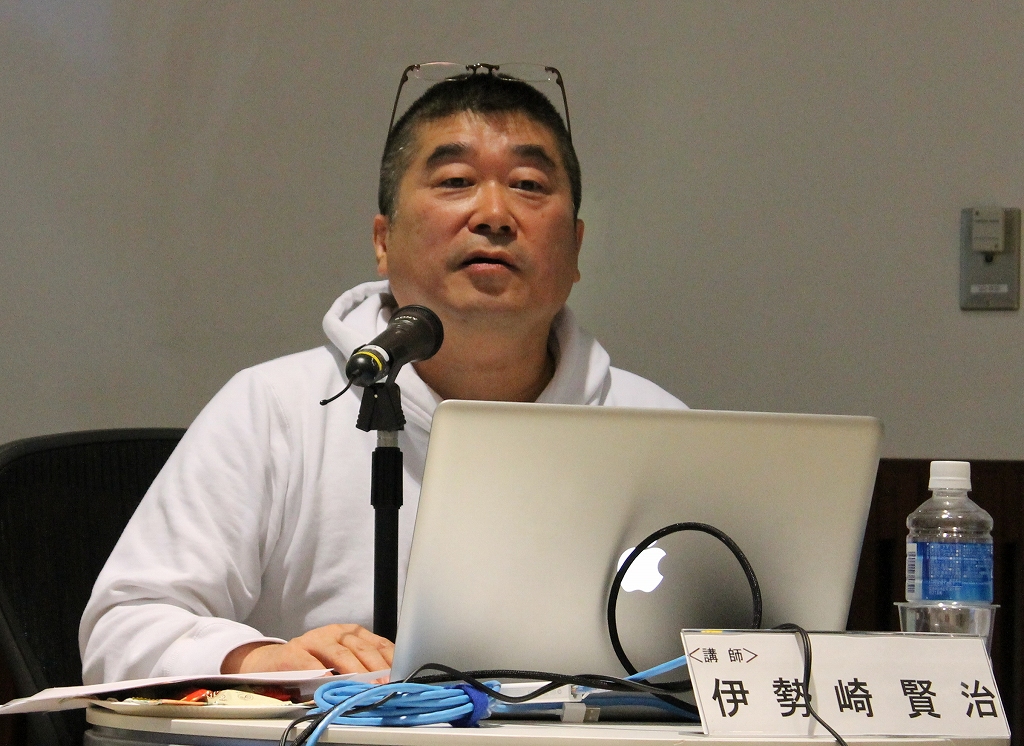 「人間はどんな状況からも復興できる」と語る伊勢崎賢治氏=写真はいずれも2012年6月16日、慶応大学G-SEC、矢田撮影
「人間はどんな状況からも復興できる」と語る伊勢崎賢治氏=写真はいずれも2012年6月16日、慶応大学G-SEC、矢田撮影ここでは、6月16日にあったセッションのうち、伊勢崎*賢治氏の基調講演の一部をご紹介したい。伊勢崎氏は、国際NGOや国連職員として、アフリカや東チモールなど世界各地で紛争処理にかかわってきた。とりわけ、日本政府特別顧問として、アフガニスタンにおいて武装解除を成し遂げたことは有名だ。
東日本大震災や原発事故に向き合い、復興への歩みを続けるにあたり、国際紛争の最前線に立ってきた伊勢崎氏が強調することは何か。以下はその抄録――。
*伊勢崎氏の崎の字は、正しくはつくりの上の部分が「立」ですが、ブラウザで表示できない場合があるので、「崎」の文字をあてています。
.......................................................................................
■放射能差別を許すな
僕は、福島と特別な関係はありませんでしたが、福島第一原発の事故が起きてから3週間目に南相馬市に入りました。ピースビルダーズという広島のNGOの代表理事をしている関係で行きました。
広島が福島を救えないか――。とっさにそう考えたのです。その根底には、日本人は福島を絶対に差別するようになるという思いがありました。仮に、放射能差別というものがあるとしたら、それを一番理解し、息の長い支援をできるのは、広島しかないのではないか。そういう観点で考えた結果です。
 アフガニスタンでの武装解除について具体的に説明する
アフガニスタンでの武装解除について具体的に説明する当時はまだ、南相馬の市長がユーチューブで有名になりかけたころです。物資も届き始めたが十分じゃない。みんな、福島を通り越して行ってしまう。それを仕分けるボランティアも誰もいない。みんな放射能が怖いから。仙台などはボランティア銀座みたいになっていましたが、ボランティアお断わりを言うような市町村も出始めていた。一方で、福島にはボランティアはまったく入っていませんでした。
僕の専門である国際紛争の処理という現場では、その現場が危険であればあるほど、初動調査をまず行います。援助を必要としている人がいる限り、細心の準備と注意を払って、現場に近づくことをします。
そして、いかなる点に気をつければ、どのような人道援助が可能なのかを考えます。このような発想で、広島大学の協力を得て線量計を調達して、車をチャーターし、現地に向かいました。もしもの時に速やかに退避できるように、南相馬の市会議員に同乗してもらいました。
ルートは福島市を出発し、北へ向かい、飯館村のうしろ側の国道を通ります。さらに、相馬市を通って南下し、南相馬に入りました。あの当時、場所によっては福島市内の方が放射線量が高く、2マイクロシーベルト・パー・アワーのところも数多くありました。どんどん南相馬市に近づき、これからもっと高くなるのかなと思っていたら、逆にぐっと下がった。市内に入ると本当にどんどん下がってきて、市会議員の案内で、裏道から原発から20キロ圏内に入り、さらに9キロ圏内くらいまで行ったのですが、0.4マイクロシーベルトくらいしかないのです。
その頃は、放射能の影響は風任せだろうというような認識しかなかったんですが、実際に体験してみると、半径50キロを警戒区域にして画一的に避難しろという政府の言い方は全然あてにならないということがすぐ分かりました。逆に言うと、危険だといわれる場所でも、線量計を使って気をつけてやっていけば、人道援助は可能であるということが分かったのです。
その結果を踏まえ、広島から南相馬市にボランティアを入れるようにしました。その後は普通にボランティアがやってくれるようになったのですが、この広島のピースビルダーが先陣を切ることになりました。
■線量計という武器を
国際紛争の現場では、戦闘の難を逃れて、難民が発生します。難民を助けるのは国際社会の仕事ですが、すべての人間が難民化するわけではありません。違います。難民は自ら脱出できる余裕のある人です。そうじゃない人たちがたくさんいるのです。
 参加者は熱心に耳を傾け、活発な討議を繰り広げた
参加者は熱心に耳を傾け、活発な討議を繰り広げたたとえ、その可能性がわずかであっても、自分たちをとりまく情勢が改善することに一縷の望みをかける人たちがいます。残るか残らないかでぎりぎりの選択があるはずで、どんな危険な状況でも生活を捨てないという選択をする人たちがいる。家族は逃がして、俺だけはということもある。
難民支援は難民キャンプをつくって支援すればいいわけですが、僕はどちらかというと、人がとどまった社会をどうするか、どう復興するか、ということに関与してきました。
まず、戦争やめさせる。それから、壊れた社会をどう再建するかということをやってきましたので、その経験をそのまま、今回被災したところにあてはめるわけではないですけれども、ある意味、福島ではそういう構図がなりたつのではないかと思いました。
国際紛争の現場では、国家が提供できない安全を住民らが自らがつくりだすしかない。銃をとるわけです。自警団を組織します。その崩壊していた国家が提供できない安全を自ら確保するということは、自然と起きてきます。住民ら自らが銃をとるといった、こういうオプションは、国際社会はさすがにできません。国連もがそれを支援することはありません。しかし、現実です。
福島の場合には武器に相当するものは何でしょう。線量計です。当時、線量計はオークションでも高値がついて、入手が困難、不可能な状況でした。それを大量に入手して、使い方などを訓練し、各家庭に1台くらいもたせられないかと思い頑張りました。
政府がやらないなら、残ろうと決意した市民を同じ市民が支援しなくてはならない。放射能とつきあって生きるというのは非常に悲しいことです。 悲しい、しかし、新しいライフスタイルの確立を支援できないかと真剣に考えました。
■政府の失策は歴史的に糾弾されるべき
僕は、原子力の専門家ではありませんが、国際紛争の現場での危機管理というのは、体に染みています。その観点からいうと、福島第一原発で水素爆発が起こったのだから、とにかく逃げるしかなかったでしょう。
そして、的確に逃げるためには放射線量の細かい測定とその情報の伝達が決定的に重要だったのに、政府はまったく逆のことをやった。水素爆発の直後は情報を隠蔽し、その後は雑に半径で区切るという、場当たり的な避難しかさせられなかった。この点では、政府の失策がもたらした被爆として歴史的に糾弾されるべきではないかと思います。
■人間は必ず復興する
国際紛争の現場に長く身を置いていると、戦争やっているところに地震、津波が来るというダブルパンチという例も見聞します。ミンダナオやハイチがその例です。前者では、20万人犠牲になった。人口200万人のハイチでは30万人亡くなった。
しかし、そんなところでも人間は復興します。NGOなども殺到するが、人間の極限のところでの底力を見せつけられます。社会が焦土と化しても、がれきから、難民キャンプから、細々ではあるけれど社会活動が始まるのです。誰に言われるのでもなく。日常品の単純な売買、闇市のようなものは、焼け跡では必ず始まります。
何の支援なくても、誰でもやります。ましてや、日本人です。政府がアホでも、無政府状態でも、政府がいようがいまいが、日本人は市民として自力で復興するに決まっています。だから、東北の復興そのものを心配する必要はありません。問題は復興のやり方によってもたらされる国の在り方です。そっちの方が問題です。
■困難から踏み出す上位概念を
不謹慎のそしりをおそれずに言えば、大災害は国家体制を根底から変革する大きなチャンスです。インドネシアのアチェでは、28年間続いたアチェの独立派と、インドネシア人との内戦を津波が終結させました。ハイチでは一部の裕福な権力者とマフィアが内戦を続け、ほとんど破たん国家でした。復興は困難を極めますが、地震で、悪い奴らも同時に基盤を失った。
ただ、大きな困難のなかから復興に踏み出すには、そのための上位概念が決定的に大切です。
少子高齢化、過疎化、不況、失業、政治と金、財政はたん、無駄な公共事業、民主主義というよりもほとんどポピュリズムに堕した政治……。震災前から停滞していた日本を表すこれらのキーワードのどれを足がかりに、これからの復興を構想する際の上位概念を導きだせるのか、まだ分かりません。
少なくとも、単なる復旧がそれになることはないでしょう。少子高齢化、財政難などが進むことは必至です。以前のように、拡散していた住居を集合化して、インフラ整備を集約化、軽微なものにする。その結果、市町村の合併が進むことになるのではないでしょうか。
また、復興断念、もしくは、無居住地化、これを進める地域が出てくる
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください