選択肢のなさが支える安倍支持率。カギを握る保守層を取り込める国民民主党の今後
2018年08月13日
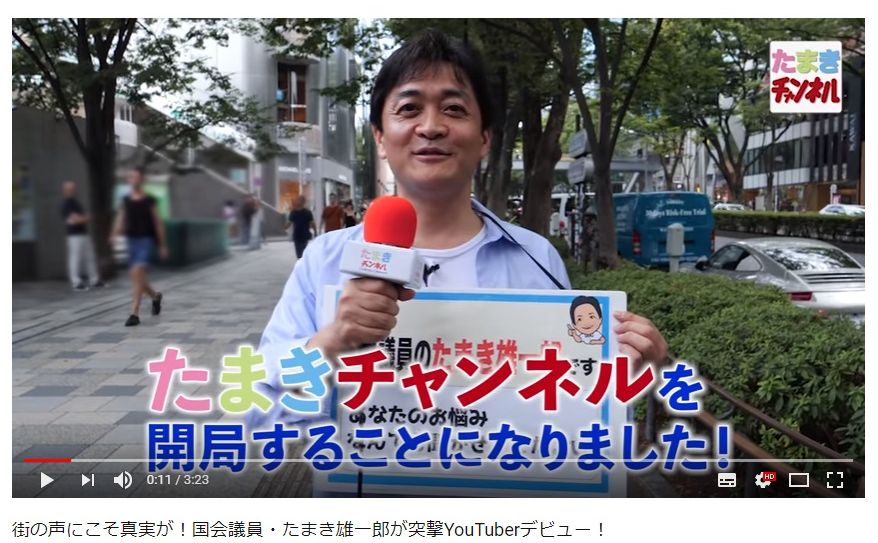 国民民主党の玉木雄一郎共同代表が配信した「たまきチャンネル」の動画=ユーチューブから
国民民主党の玉木雄一郎共同代表が配信した「たまきチャンネル」の動画=ユーチューブから 朝日新聞が8月4、5日に実施した世論調査において、国民民主党は、またしても支持率が1%だった。兄弟政党とも言える立憲民主党は6%で、前回の調査から2ポイント落とした。一方、自民党は36%で、前回よりも2ポイントアップしている。
国民民主党は、5月7日現在、衆議院議員39人、参議院議員23人の計62人であり、国会議員の数が4人になってしまった社民党と同じ支持率というのは、情けないとしか言いようがない。来年(2019年)の統一地方選挙まで、あと8ヶ月程度しかなくなってきて、参院選までも1年を切っている。候補者は気が気じゃないだろう。
私のまわりでは、立憲民主党に公認願いを出したという話はよく聞くが、国民民主党に公認願いを出したという話は聞かない。それはそうだろう。支持率1%の政党に好き好んで公認願いを出すとは思えない。
しかし、事態は、国民民主党の支持率を笑ってすむほど甘くはない。立憲民主党もまた、支持が伸びていないのだ。
今回の支持率6%は、昨年の衆院選前にゴタゴタが起きていたころの民進党並みとなってきている。原因として考えられるのは、一部で強い支持層がいるものの、国民に支持が広がっておらず、衆院選のころの熱気が冷めてきていることだ。
もともと、立憲民主党の支持者は中高年層に多いと言われているが、そこから広がりがない。さらに、共産党から流れてきた支持者の一部も共産党に戻ってしまっている。立憲民主党の支持者を広げるには、無党派層を取り込んでいくしかないのだが、今のところ、うまくいっていない。
振り返れば、かつての民主党は右から左まで様々な意見を持つ政治家の集まりだった。そのため、「まとまりがない」と言われ、実際、“内ゲバ”が起きてしまったのが、存続することができなくなった理由でもある。
そのうち、「左」の立場に近い議員が中心となり結党されたので、立憲民主党はどうしても共産党や社民党に近くなってしまう。その結果、保守的な考えを持つ国民の「行き場」にはならない。
確かに原発には反対だ。でも、憲法改正については、検討してもよいのではないか。そう考える国民もいる。与党に対して反対ばかりではなく、もっと議論を尽くせないかと考える国民も多いだろう。
「まともな議論も避けるような与党自民党が、強行採決によってゴリ押しで欠陥法案を通そうとするなら、こちらも強硬な手段を取る必要がある」という立憲民主党の言い分は、理解できないわけではない。だが、そもそも数の上で圧倒的な差をつけられている以上、強硬手段に打って出たところで、法案は可決されてしまう。そうであれば、少しでも修正し、国民にとってよりよい法案をつくるよう議論を進められないかというのも、また理のあるころではないか。
「実は、反対しているのは一部の法案である。それが目立つので、すべてに反対しているように見えるかもしれないが、多くの法案には賛成して成立させている」という言い分もあるが、そういう姿は残念ながら国民には見えない。自らの情報発信チャンネルを育てずに、マスメディアに頼っていては、「いつも反対して文句を言っている」政党というイメージしか、国民には発信できない。
 党首討論に臨む立憲民主党の枝野幸男代表(右)。安倍晋三首相に論戦を挑んだが……=2018年6月27日
党首討論に臨む立憲民主党の枝野幸男代表(右)。安倍晋三首相に論戦を挑んだが……=2018年6月27日国民民主党の共同代表の玉木雄一郎衆議院議員は、党の独自性を出すため、与党との「対決」を前提とした国会運営ではなく、議論を尽くしてより良い「解決」に向けて進めることを主張している。これは、昨秋、分裂した民進党の中でも、より現実路線を取ろうとした長島昭久氏や細野豪志氏らに近い考え方だ。長島氏も細野氏も国民民主党に参加しなかったというのは皮肉な現実ではあるが、それでも玉木氏は議論を尽くす現実路線が最善だと考えている。
これに対して、野党共闘を進めることを前提に、立憲民主党他の野党とも連携し、与党と対決していくべきだと考える議員もいる。国民民主党の前身である希望の党や民進党を想起すれば、そのような構成になるのもうなづける。
野党共闘を重視し、与党との対決路線で行くべきだと考える議員は、将来的には立憲民主党との合流を目指しているのかもしれない。しかし、立憲民主党の支持率が決して上昇機運にないことを考えると、それが最善なのか疑問は残る。今のままでは、保守層の取り込みは覚束(おぼつか)ない。
先日(7月25日)、私は自分が配信しているネット番組『ヨロンブス』で、国民民主党共同代表の大塚耕平参議院議員と対談した。「国民民主党というのは、何を目指す政党なんですか」と質問をなげかけると、次のように答えた。
「国民民主党は『改革中道政党』であって、『正直な政治、偏らない政治、現実的な政治』を目指します。政策を進める『お作法』が大事なんです」
つまり、たとえ与党案であっても、「否定から入らず、現実を見据えた上で、決められた時間内で十分に議論を重ね、決まったことには従い、権力は抑制的に運営する」という民主主義そのものを目指すというのだ。
ある程度政治を知っている人であれば、「それは理想であって、現実には難しいことだよ」と言うだろう。前の国会で焦点となったIR法案を見ても、働き方改革法案を見ても、政府側に熟議を重ねる姿勢がないのは明白であり、そのうえで民主主義の理想を追うのは困難かもしれない。また、国民側にこうした路線を理解できるだけの度量があるかというと、いささか心もとない。
大塚氏は、「国民民主党がIR法案に賛成したという誤報が流れましたけど、我々は働き方改革法案もIR法案も反対しているんですよ。そのうえで働き方改革で47項目、IR法案で31項目の附帯決議を入れて縛りを付けているんです。これだけ附帯決議を付けるということは、別の法案を作るのに等しいんです」と語った。
現在の国会の構成からすると、政府与党案が賛成多数で可決されるのは厳然たる事実だる。多くの法案の中には、ロクに議論をされずに通るものもあるだろう。
ただ、とりわけ今後の国民生活に大きく関わってくるような法案については、政府与党案がほとんど修正のないまま通ってしまうのは危険である。日本がほんとうに民主主義国家というのであれば、熟議を通して、法案はより良いものにする努力が必要ではないだろうか。
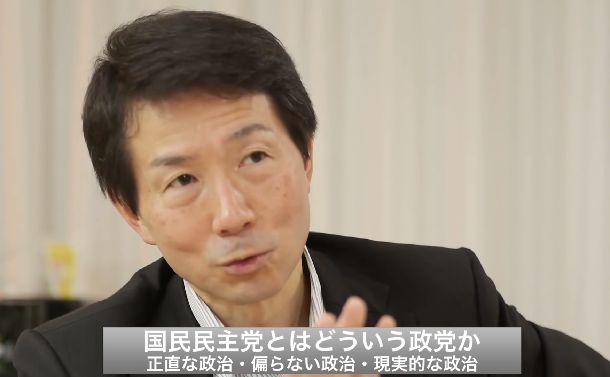 ネット番組「ヨロンブス」で語る国民民主党共同代表の大塚耕平参議院議員
ネット番組「ヨロンブス」で語る国民民主党共同代表の大塚耕平参議院議員現在の安倍晋三内閣支持者に支持の理由を聞くと、「他に任せられる政権がないから」という答えが半数近くある。森友・加計学園問題など、これまでなら内閣が吹っ飛びかねない大きな「不祥事」が続いても、安倍内閣が高い支持率を維持できるのは、「他に選択肢が見えない」からに他ならない。もし別の選択肢があれば、支持率が15~20%程度になってしまうのではないか。
国民民主党が、大塚氏や玉木氏らの目指す政党として活動し、それが国民にも伝わるようになれば、保守層の中に国民民主党の支持にまわる人も出てくるだろう。難しいのは、その大前提として「国民に伝わる」ことが不可欠である点である。
世間を見渡すと、「国民民主党は第二自民党のようになる」と言う人が少なからず存在する。議論のプロセスが可視化され、広く示されなければ、結果だけを見て、マスメディアまでもが「国民民主党は政府案に賛成した」と報道するおそれがある。要するに、「わかってもらってなんぼ」なのだ。
ここで2019年の参議院選挙を視野に野党のあり方を考えてみよう。
それまでに立憲民主党の支持率が倍増するのは容易ではないだろう。国民民主党が今後、分党状態になり、立憲民主党に議員が移籍する可能性もゼロではないが、そもそも野党の中で立憲民主党が一人勝ち状態となることは、国民の選択肢を狭めるという意味からも望ましくない。
「改革中道」「中道保守」「リベラル保守」の立場をとる政党が野党として存在し、選挙のときには協力しあえるような関係を構築できてはじめて、国民にとって選択肢が広がるのではないか。そして、それは安倍内閣の支持率にも影響を及ぼすはずだ。
今はそれぞれ単独での政権獲得を目指していると聞いているが、仮に、立憲民主党と国民民主党の支持率を足して20%を超えるようなことになってくると、連立政権も視野に入れた「戦略」が可能になる。選挙の結果、自民党が政権を維持したとしても、国会に緊張感がもたらされ、現在のような驕(おご)り高ぶった政権運営とはならないだろう。
国民民主党の支持率は1%。確かに低い。だが、やりようによって、支持率を上げることは意外と難しくないと私は考えている。議員の数も少なくないし、政策力もある。議論を尽くしてより良い「解決」を求める姿勢は、保守層も取り込める絶妙の立ち位置である。伸びしろはあるのである。
支持率アップのために、まずやるべきは「広報」の充実に他ならない。マスメディアに頼らず、自らの情報発信チャンネルを育て、質量ともに充実した広報を展開することが必要だ。ネットの発展でやり方はさまざまある。さらに、60人以上いる国会議員が、自ら地元や関連団体を足を使って回り、党の理念や目指すものを丁寧に説明する。いわばネットとリアルの両面で、ひたすら宣伝につとめるのである。
国民民主党が何を目ざそうとしているのかが浸透すれば、支持率が上がらないはずはない。国民民主党の支持率が上がると、その反照として立憲民主党の立ち位置も明確になり、支持率アップにつながるはずだ。国民民主党は保守層から、立憲民主党は左からの支持が期待されるので、互いに大きく食い合うことはない。
このように進むためには、国民民主党はまずは代表選挙(22日告示、9月4日投開票)を乗り切らなくてはならない。大塚氏の主張した「民主主義」を実行できる政党になるのか、野党共闘を最重要と捉えて立憲民主党との同化を目指すのか、代表選挙では難しい選択を迫られる。
硬直化した一強多弱の国会運営が続くのか、国民に政権選択の可能性を示すことができるのか。国民民主党の今後の活動が、カギを握ると私は見ている。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください