2018年10月06日
 選挙に関するアンケートを「ビッグフェス」で公表する高校生たち=愛知県(本文とは関係ありません)
選挙に関するアンケートを「ビッグフェス」で公表する高校生たち=愛知県(本文とは関係ありません)先日、『未来をはじめる−「人と一緒にいること」の政治学』(東京大学大学出版会)という本を刊行した。東京都内にある私立の女子中学・高校で行った政治学の講義をもとに、政治についてじっくりと考えようとする一冊である。
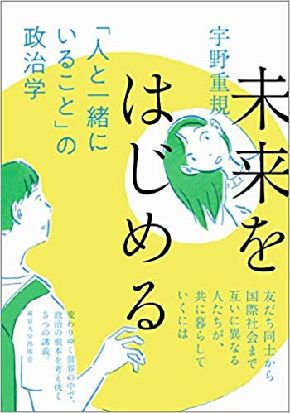 『未来をはじめる−「人と一緒にいること」の政治学』(東京大学大学出版会)
『未来をはじめる−「人と一緒にいること」の政治学』(東京大学大学出版会)女子校で政治学の講義を行うことには、それなりの「ねらい」があったつもりだ。
政治学の入門講義というと、かつてであれば、およそ「権力」とは何か、「国家」とは何かという話からスタートしたものである。昨今の講義では、「本人-代理人理論」や「合理的選択論」など、政治学に固有な「考え方」をていねいに解説するものも多い。それぞれに特色があり、身近な具体例をあげるなどして、政治に親しみを感じられるように工夫されている。
とは言っても、なかなか政治を身近に感じることは容易ではないだろう。政治とは多様な人々が集まって意思決定をすることだ、といくら解説したところで、「集合的意思決定」などという言葉を使った瞬間、多くの人は「難しそう」、「自分とは縁のない話だ」と思ってしまう。
今回の講義ではもう少し手前のところから話をはじめたい。それがそもそもの企画の出発点であった。
「政治」だからといって、何もそんな難しい議論をしなくてもいい。人が何人か集まれば、当然その「違い」が目につくはずだ。その「違い」が面白いし、楽しいのだけれど、ちょっとつらく感じることもある。世の中には自分と趣味や価値観の違う人もいるけれど、互いにどう距離を取り、ともに過ごしていくべきか。きっと多くの人が日常の中で嫌というほど、実感している話のはずだ。同世代の仲間と、教室という狭い空間で日々過ごしている中高生ならなおさらだろう。
そんな話を振ったら、女子校の中高生たちは即座に、「ちょっと、心が疲れる…的な」(本書、259ページ)と表現してくれた。
そうそう、そういう感じ。クラスで何かを決めるときもそうだよね。そのあたりから政治を考えてみたいと話したところ、いいノリで反応してくれた。知識主導型でない政治学の講義をしたいというこちらの思いを、彼女たちのノリの良さと表現力が大いに手助けしてくれたと思う。
しかしながら、女子校で政治学の話をしたのは、それだけが理由ではない。
この本の元になる講義を行ったのは2017年の5月から9月にかけてである。女子校で講義をするにあたって、念頭にあったのはやはり、高橋まつりさんの事件だ。
 高橋まつりさん
高橋まつりさんこの事件をどのように理解すべきか――。その答えは、いまだに出ていない。事件の直後から、職場環境や上司の対応を批判する声が上がる一方、「その程度の残業は珍しくない」「労働時間だけが問題なのではない」という意見も見られた。
だが、いずれにせよ、問題を高橋さん個人の問題にしたり、あるいは個別の企業だけの問題にしたりしてはいけない、それだけは間違いないだろう。
そう、これは政治の問題なのだ。
人がいかに生き、働くかは、どれだけ個人の問題に見えても、そこには必ず社会全体の仕組みや制度の問題が関わっている。だとしたら、そのような仕組みや制度を変えることもまた可能なはずだ。それこそ政治の働きなのだと、女子高生たちに語りかけてみた。
もちろん、まだ企業などで働いたことのほとんどない彼女たちである。なかなか実感のこもった議論は難しいとは思っていたが、なかなかどうして、彼女たちなりに正直な感想を述べてくれた。結論は出なかったけれど、やはりこういう問題を早くから議論しておくことは意味があると、あらためて感じた。
税と社会保障に関して、サービスと負担のバランスはどのようにとるべきか。「機会の平等」と言うけれど、「恵まれない人」の境遇のいかなる部分を、どの程度まで社会は補償すべきか。これらは、いずれも容易に答えの出ない問題であるが、彼女たちは真剣に考えてくれた。
「努力が報われないのはおかしい」という声があれば、「そもそもスタートが違っているのはフェアでない」といった意見も出た。いずれも、現在受験のプレッシャーに晒(さら)されている彼女たちなりの正直な意見だろう。
そう、彼女たちはすでに十分に考えているのだ。「まだ中高生だから」と決めつけるのは、大人の勝手な思い込みにすぎない。実際の彼女たちは、現実の社会を彼女たちなりに観察し、自分たちなりの実感に基づいて生きていこうとしている。それをいわゆる「政治」にうまく結びつけていけないなら、それは「政治」の側に問題があるのだ。
講義の後の話になってしまうが、今年になって東京医科大学の入試における「差別」が問題になった。入試の採点が意図的に操作され、女子受験者の合格数が抑制されていたとの報道は、現在受験のプレッシャーに晒されている彼女たちにしてみれば、そもそもの土台をひっくり返すような話であろう。
 東京医科大学の入試不正をめぐる会見を終え、頭を下げる東京医科大の行岡哲男常務理事(左)と宮沢啓介副学長(学長職務代理)=2018年8月7日、東京都新宿区
東京医科大学の入試不正をめぐる会見を終え、頭を下げる東京医科大の行岡哲男常務理事(左)と宮沢啓介副学長(学長職務代理)=2018年8月7日、東京都新宿区しかも、その後の議論は、さらに深刻であった。いわく、大学の医学部には付属病院があり、そこで働く医師の確保のためには、ある程度入試段階での操作があったとしても仕方がない、そんな説明がもっともらしくメディアで流通した。要するに、病院は「一生フルタイムで働かせることのできる男子が欲しい」と言っているようなものである。
結局、男性を含めた働き方の改革をしない限り、女性差別もまた続くのであろう。問題の根深さは明らかになったが、それでは働き方をいかに変え、社会をどのように変えていくか。改革に向けての議論は曖昧(あいまい)なままだ。このような状況を放置している限り、いくら政治を語ってみても、虚しいばかりであろう。政治をこのままにしていいのかという本書の思いは、この事件によって不幸な形で裏書きされたことになる。
もちろん、世の中に根深い問題がたくさんあるということは世の常識だ。中高生といえども、そのことを十分に意識している。問題はそこからだ。
世間のさまざまな問題は、一時的に騒がれることがあっても、いつかは忘れ去られてしまうものなのか。「根深い問題」は「根深い問題」のまま放置されるのか。このような諦念(ていねん)が世の中で支配的な限り、「文句を言っても始まらない」「ともかく、なんとか自分だけでも地雷を踏まないように」というのが、人々の基本的な態度になってしまう。
そうではなく、最終的な解決にただちに到達するかはわからないけれども、問題は問題として直視し、どこに原因があるのかをみんなで議論する。どのような解決策が考えられて、それに誰が賛成して、反対するかを、誰の目にも見えるところ検討する。なかなか一足飛びに解決とはならないが、少しでも状況をよくするためににじり寄っていく。それこそが政治の基本のはずだ。
こうした当たり前が当たり前でないとしたら、何かがおかしい。今の日本社会に必要なのは、このような当たり前の感覚である。
興味深いことに、講義を通じて、筆者は受講者である女子中高生からこのような「当たり前の感覚」を再確認したように思う。
聞いてみると、彼女たちは、政治や社会の問題について、自分たちなりに話しているようだ。そのうえで、議論が加熱し過ぎたときには、意図的にテンションを下げる術を彼女たちは心得ている。「違い」が先鋭化したときは、とりあえずそれぞれの代表者を選び、議論することで解決を目指す知恵も持っている。彼女たちは自然に「政治」を理解しているのだ。
講義ではさらに「実験としての民主主義」の話もした。
世の中を変えるのに、国民全体を巻き込む必要は必ずしもない。自分の身の回りで、できることから実験をしてみる。実験がうまく行けば、誰かがそれを見て、自分たちでもそれをやってみるだろう。気づいてみたら、社会が変わっているということもありうるのではないか。
筆者のこのような話を、女子中高生たちは自然に受け止めてくれたように感じた。
 民主主義を考えるトークイベント で話す若者たち=都内
民主主義を考えるトークイベント で話す若者たち=都内講義の締めくくりとして、女性の政治哲学者であるハンナ・アーレントの言葉を引用した。「人間が生まれてきたのは始めるためである」という言葉である。
彼女たちは、間違いなく何かを「始める」ことだろう。それは必ずしも目立つものではないかもしれない。しかし、そんな一人ひとりによる「始まり」が、やがては確実に社会を変えていく。そんなビジョンを筆者は実感している。
もちろん、「始める」のは彼女たちだけではない。何歳であれ、いかなる性であれ、誰もが「始める」権利を持っている。誰もが自分の生のなかで何事かを「始める」ことのできる社会――。これこそが民主主義の社会である。民主主義をめぐるこのような思いを、いまの日本社会において筆者が口にできるのは、彼女たちのおかげである。
『未来をはじめる−「人と一緒にいること」の政治学』(東京大学大学出版会)は09月25日発刊されました。詳しくはこちら。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください