5市の不参加表明、指南書、ハンスト、県議会迷走…私たちは民主主義の未熟な担い手だ
2019年02月03日
 玉城知事と不参加を表明した5市の市長=琉球朝日放送提供
玉城知事と不参加を表明した5市の市長=琉球朝日放送提供沖縄は「民主主義の学校」だ。
そんな記事を読んだとき、ちょっと美化しすぎだろうと思った。けれど今は、良い意味でも、悪い意味でも、そうかもしれないと考える。
県民投票では、辺野古埋め立てに「賛成」か「反対」か、明確な意思を問うことに意義があるとされていた。しかし5市が、不参加を表明したことで、波紋が広がった。
5市の市長たちは、自民党に近い面々だ。
5市の不参加により、約36万7000人、有権者の3割以上が投票できなくなる事態に陥ってしまった。
どうすれば、全県で実施できるのか。
投票日の2月24日まで、あと1カ月のタイミングで、「選択肢」を巡る議論が再燃した。それは県民の分断と、うんざりするような政治的駆け引きの毎日、まるで、県民投票劇場だった。
この国の民主主義を問うていると注目されている沖縄の挑戦だが、民主主義を実践するには、とてつもない忍耐と、エネルギーが必要だということを、私たちは学んでいる。
不参加を表明した市長たちの主張はこうだった。
沖縄市の桑江朝千夫市長「賛成、反対の二者択一では、多様な民意を推し量れない」
うるま市の島袋俊夫市長「賛成か反対かの2択では多様な市民の考えが反映されない」
それなりに理屈が通ってはいるが、去年の県知事選挙で「誰一人取り残さない」「多様性を認める」と訴えた玉城知事の言葉を、逆手に取った印象が否めない。
玉城知事の足を引っ張るような、あからさまな言動もあった。
「これは県民の意思というよりも、知事が進めている政策を後押しするというような形にしかならない」
これまでも歯に衣着せぬ発言が波紋を広げてきた宮古島市の下地敏彦市長だ。
もはや有権者の姿は見えなくなっていた。県民投票は「政争の具」になっていたのである。
批判は当初、不参加を決めた市長たちへと向けられていた。しかし、刻一刻と投票日が迫るにつれて、風向きが変わっていた。投票できない県民の、非難の矛先は、うまく調整できない玉城県政にも向けられたのだ。
全県で実施できなければ、県民投票の意義が薄れる。そうなれば、玉城知事にとっても痛手だ。とはいえ、県議会で議論を積み上げ、議決したことを安易に翻すこともできない。
県民のために汗をかけないのは野党か、不参加を決めた5市の市長か、それとも玉城知事か。どちらが先に折れるか、「まるでチキンレースだ」という人もいた。
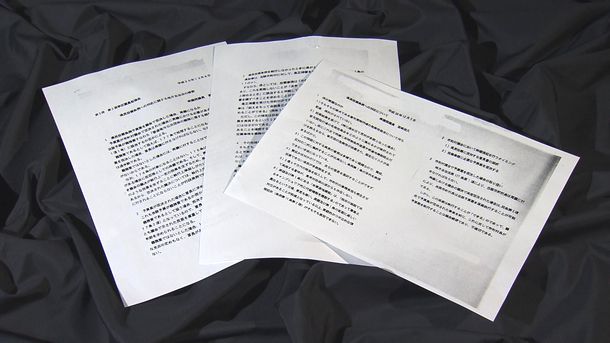 宮﨑議員作成の文書=琉球朝日放送提供
宮﨑議員作成の文書=琉球朝日放送提供「指南書」だと指摘された文書を作成したのは、宮﨑政久衆議院議員だ。宮﨑議員は、弁護士でもある。文書には、詳しい法令の解釈や見解が記されていた。
文書では、県民投票関連の補正予算案が、市町村議会で2度否決された場合、「市町村長が予算案を執行することが可能」としつつ、議会で否決されたのに反して市町村長が予算案を執行することは「議会軽視であり、不適切である」と結論づけていた。
5市の議会で補正予算案が通らず、市長たちが不参加に回ったのは、宮﨑議員の文書が影響したからか。記者の追及が相次いだが、宮﨑議員は「県民投票を否定するために、説いて回っているわけではない」と釈明を繰り返した。
とはいえ、弁護士の言葉には力がある。私は、「不適切である」という考えは、どういう立場で発言したのかと質問した。
宮﨑議員は、それは「議会人としての考え」だと答えた。
別の文書では、「県民投票の不適切さを訴えて、予算案を否決することに全力を尽くすべきである。議員が損害賠償などの法的な責任を負うことはない」とも述べていた。それらも「議会人としての考え」らしい。
舞台は、宮﨑議員のペースのまま幕を閉じた。
 宮﨑議員と自民党県連が会見=2019年1月16日、琉球朝日放送提供
宮﨑議員と自民党県連が会見=2019年1月16日、琉球朝日放送提供予算案が否決されても首長が専決処分で予算を執行できる、というのは法律家としての建前。執行は不適切だ、というのは政治家としての本音。
宮崎議員は「弁護士」と「議会人」と立場を使い分け、言い逃れをしている。私はそう感じ、会見終了後に追いかけて、こう聞いた。
「宮﨑さんの発言は、弁護士の見解か、議会人の見解かわかりにくいのでは」
すると宮﨑議員はこういった。
「私は、話すたびに、今から弁護士として言います、とか、議会人として言います、とか、断りを入れて話さなくてはならないのですか」
県民の3割以上が投票できないという局面に、27歳の青年が、ハンガーストライキを始めて話題になった。おじさんたちが筋論や、メンツにこだわり、身動きが取れなくなっている中、身を挺して「全県での県民投票実施」を訴えたのだ。
彼の姿は、計算がなく、真っすぐに映り、予想以上に共感が広がった。そして、なかなか一歩を踏み出せない政治家たちの背中を押した。県政で中立の立場にある公明党が、仲介役に名乗りを上げたのだ。
公明党も、県議会では県民投票に反対していた。しかし、支持者からの声が無視できなくなったのだという。
確かに、沖縄の公明党は、悩ましい状況にある。中央では、安倍政権と共同歩調をとっているが、沖縄では平和の党を自負し、辺野古埋め立てにはどうしても反対だという支持者も根強い。
投票日まで約1カ月に迫った先月末、公明党と県議会議長が話し合い、予定していた「賛成」「反対」に、「どちらでもない」を加えた3択案で、野党と再調整することになった。
ところが、それでも与野党の話し合いはこじれた。
自民党は「賛成」という選択肢を、「やむを得ない」に変更するよう迫ってきた。そして投票日も含めて、仕切り直しだとまで言ってきたのだ。
2択のままか、3択にするか。忍耐の、長い一日だった。
話し合いと休憩を繰り返した夜9時すぎ、議長たちが疲れ切った表情で会場に現れた。議長提案の「賛成」「反対」「どちらでもない」の3択案が合意されたのだ。
公明党が、どうやって自民党と交渉したのか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください