安田菜津紀さん連載関連イベント、100人が参加し真摯に語り合う
2019年02月09日
 会場では連載の写真も映し出された(写真はいずれも吉永考宏撮影)
会場では連載の写真も映し出された(写真はいずれも吉永考宏撮影)フォトジャーナリストの安田菜津紀さんがWEBRONZAで執筆している連載「記憶を宿す故郷の味―日本で生きる難民の人々―」の関連イベントが、1月31日に開催されました。日本で暮らす難民の人々が置かれた状況などについて話し合うトークセッションに続き、参加者のみなさんが難民の方の故郷の味を楽しみながら懇親を深めました。
 安田菜津紀さん
安田菜津紀さん毎月1回の連載では,安田さんが撮影した難民の方の故郷の料理を大きく掲載してきました。思わずお腹が鳴るような、おいしそうな写真が並びます。これまで、シリア、カメルーン、ネパール、バングラデシュ、ミャンマーの料理を取り上げてきました。
日本に逃れてくるまでの状況は、それぞれに厳しいものがあり、日本で難民認定を受けるまでの苦労も並大抵のものではありません。ネパール出身のケーシーさんの場合は、日本で路上生活も経験し、交通費がないため、入国管理局まで片道6~7時間かけて歩いて通ったこともあったといいます。難民の人々にとって、日本語の言葉の壁は高く、困難を抱えながら日本語の習得に努力する姿も描かれています。連載には、日本で暮らす難民の相談活動などに取り組んでいる民間の認定NPO法人・難民支援協会の全面的な協力を得ています。
今回のイベントは、日本で暮らす難民の方々の状況を多くの人に知ってもらい、「故郷の味」を楽しんでもらうことで五感を通してこの問題を考えてほしいとの思いから、企画されました。
当日は強い雨の降るあいにくの天候でしたが、会場のパルシステム東京新宿本部会議室には約100人の参加者が集まりました。
 野津美由紀さん
野津美由紀さん安田さんは2017年のデータとして、日本で難民申請をした19623人のうち、正式に難民認定されたのはわずか20人だったことを紹介。「どうしてここまで日本の認定は厳しいのか」と問いかけました。
これに対し、野津さんは「法務省の入国管理局が難民の審査を担当していることに、構造的な限界がある。入管のメインの業務は、日本に悪い人が入ってこないように未然に防ぐ、仮に日本に入ってきている場合は追い出す。そういう形で日本の社会の治安を守っていく。悪い人かどうかを見極めるために必要な知識・経験と、この人をどれくらい日本で保護する必要があるかを判断する知識・経験は、本来、全く別の専門性のはず。多くの国では、入国管理と難民保護は全く別の機関がやっている」と、日本の制度の問題点を指摘しました。
日本の難民審査の現状について、安田さんは「『あなたが難民であることの客観的証拠を示して』と言われる、証拠を求められることはかなりハードルが高い」と発言。野津さんは「国を逃げるという人が、証拠を持ち出せるかというと、すごく難しい。客観的な証拠がないと難民認定されないという制度の在り方は、本当に保護しなければならない人たちを落としてしまうことになる」と述べました。
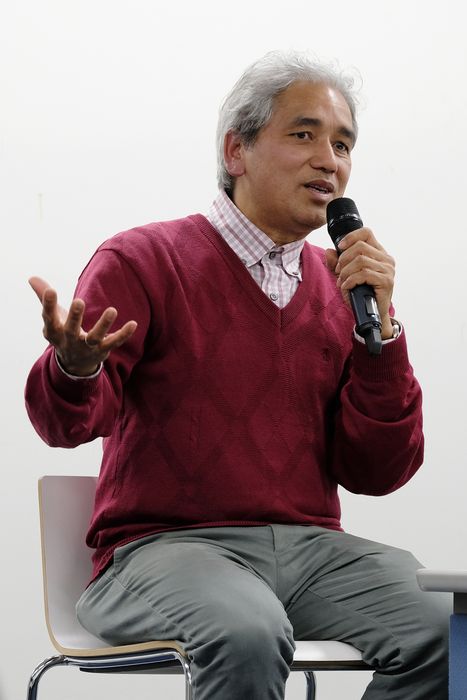 チョウチョウソーさん
チョウチョウソーさん日本で住んだのは大久保のアパート。4畳半が二つ、6畳が一つのスペースに14人のミャンマー人が住んでいました。日雇いの建設現場での仕事をした後、チョウチョウソーさんは口コミで千葉県の市川に電気工事の仕事の口があるのを知り、そこで4年間働きました。この会社の社長は図面の読み方など、いろいろなことを教えてくれたそうです。
日本で難民申請ができるとは全く知らなかったチョウチョウソーさんですが、ミャンマーの軍事政権が出している雑誌の中で「チョウチョウソーは英語も知らないくせに、アウンサンスーチーが書いたものを翻訳して、他のビルマ人に配っている悪い人間だ」などと
名指しで批判されているのを知りました。ミャンマーに帰れば迫害されることは確実だと考えて97年2月に難民申請を行い、98年10月に認定されました。
日本での活動も忙しく、「自営業であれば、スケジュールの調整も楽にできる。そして、ミャンマーの料理を日本人に紹介したい」という思いからお店を始めたということです。「ミャンマー料理の魅力」について問われたチョウチョウソーさんは「店では子どもの時に食べて『いい』と思った料理を出している。ビルマ人は白いご飯をたくさん食べる。煮物が多く、タマネギ・ニンニク・ショウガは必ず入る。だからインフルエンザにはならない。心をこめて、みなさんに食べてもらっている。『お客さん』というより『家族』だという気持ちで料理を出している」と語りました。
 トークセッションに真剣に耳を傾ける人たち
トークセッションに真剣に耳を傾ける人たち会場との質疑応答の時間では、参加者の女性が「オーバーステイの人に対して厳しくなった政策の背景は何か」と質問。野津さんが「2020年の東京五輪に向けて、オーバーステイの人を減らしていこうというスローガンを、入管が大々的に打ち出している。政府が認めた条件では外国人労働者を積極的に受け入れていくが、日本に自力で逃れてきてオーバーステイになってしまっている人たちが定住していく道を開いていくという考え方は、政府にはないのかなと思う。五輪が終わるまでは厳しい状況が続くと考えている」と答えました。
トークセッションの最後に野津さんは「ぜひ難民の問題に関心を持ち続けていただきたい。すぐに改善するという問題ではなく、多くの方に関心を持ち続けていただくことが状況を変えていくプレッシャーになる。もう一つ、可能な時に寄付という形で私たちの活動を応援していただければと思う」と参加者に呼びかけました。
チョウチョウソーさんは「難民問題が生まれてくるルーツを考えてほしい。問題のルーツを解決しないと世界中に難民が増えていく。ミャンマーは民政になったが、状況は一晩では変わらない。難しい問題がたくさん残っている。解決には日本を含めた国際社会のサポートが重要だ」と訴えました。
安田さんは「新しい社会は一日でつくることはできない。だからこそ、私たちが心を寄せていきたいのはむしろこれからだということを、会場に来てくださったみなさんと分かち合いたい」と呼びかけてトークセッションを締めくくりました。
 「ビリヤニ」などを小皿に盛り分ける参加者たち
「ビリヤニ」などを小皿に盛り分ける参加者たちイベント後半は、難民の故郷の味を楽しみながら、参加者が交流。ネパール流ピリ辛漬物「アツァ」、ミャンマーの「鶏肉とジャガイモのスパイス煮込み」、パキスタン風多炊き込みご飯「ビリヤニ」などの料理に舌鼓を打ちながら、会話が盛り上がっていました。
安田さんの連載は毎月第4土曜日の掲載で、今後も続きます。連載をまとめた出版の計画もあります。WEBRONZA編集部では、今回のように五感を生かして様々な問題を考えていくイベントを、今後も開催していく予定です。ご期待ください。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください