文章術を指南する前に、新聞記者にはやるべきことがある
2019年02月17日
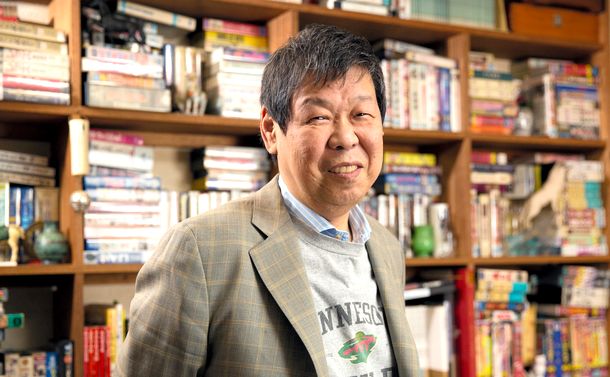 橋本治さん
橋本治さん1月29日の訃報に接して以来、橋本治の作品を読み返している。
女子高生のおしゃべり言葉が延々と続く1977年のデビュー作『桃尻娘』が当時の文壇に与えた衝撃は、ちょうどその頃に生まれた私でもおおよそ想像できる。
枕草子や徒然草、平家物語の現代俗語訳は、千年近く前の物語の登場人物をまるで会社の同僚や近所のオッサンオバサンかのように身近に立ち上がらせた。読んでいてついつい「いるいる~。そんな人~」と相槌を打ってしまう。
一方で『小林秀雄の恵み』『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』といった批評や、最新長編『草薙の剣』は、端正で緻密な建築物のような作品だった。その博覧強記ぶりとジャンルを越境する自由さは、まさに「才人」と呼ぶにふさわしい。
型を身につけていてこその型破り、縦に筋が通っていてこその横紙破りであるのはわかっていても、その縦横無尽のスタイルは、同じように物書き稼業をやりながら一向に筆の冴えぬ我が身を「好きに書けばいいんだ」と励ましてくれているような気がしたものだ。
その多彩な著作群のなかで特に好きだったのが『よくない文章ドク本』だ。
これは、いわゆる「文章読本」と総称されるジャンル(文章作法、文章術、作文指南など名称は様々)の書物に対する痛烈な批判、挑発であり、ひとさまに文章の上達を説こうという傲慢な輩への痛快な「あかんべえ」だった。生真面目な教科書や参考書にお尻ペンペンして逃げるような軽妙な姿勢を装いながら、その底流は、他の作品同様、「日本語」に対する深遠で真摯な考察に貫かれていた。
いまのように文章を書く仕事に就く前、まだ純情で殊勝だったころだが、何冊もの「文章読本」を読んだ。ちまたにはなお様々な作文指南書があふれているが、文章を生業とする人だけでなく、サラリーマンや大学生なども必要に駆られ、あるいは上司や指導教授などに勧められ、手にするのかもしれない。
いま誰にともなく堅く誓うのだが、仮にどんなに文筆家として名声を得ようとも、自分は決してこうしたものは書くまい、と思う。
斎藤美奈子が喝破しているとおり、文章読本をものする者はなべて男であり、圧倒的に男のディスクールだった。すれっからしになってしまったいまの自分にとってどれも読むに耐えないのは、基本的に、娘に口うるさく注意するお父さんの姿勢で書かれているからだろう。
「分かりやすく書け」「導入で引きつけろ」「紋切り型を使うな」「外来語を使うな」「品位を保て」「短文を重ねろ」「体言止めを多用するな」「起承転結を意識しろ」「ちょっと気取った表現を挟め」……小姑の小言のごとく神経質で、揚げ句には「名文を読め」「巧みな表現を書き写せ」「毎日書け」だのと生活態度にまで踏み込み、究極の殺し文句が、でました! 「文は人なり」。
いやはや、である。
脱力してしまうのが、文章読本ではよく野口英世の母シカの手紙が究極の名文かのように引用されていることだ。
学校にほとんど通えず綴り方の手ほどきを受けられなかったシカがアメリカの英世に宛てた「おまイの○ しせにわ○ みなたまけました○ わたくしもよろこんでをりまする○」で始まる手紙について、井上ひさしは「文間の余白は猪苗代湖ほども深く広い」と絶賛している。高橋玄洋も「判読に苦しむほどの字で間違いや脱字もありますが、何と温かい手紙でしょう。母親の子供を思う心情がひしひしと響いてきます。/他人の借り着や、型通りの文章では、あなたの顔など見えてくるわけがありません」と称えている。
字もろくに書けないなか息子への叫ばんばかりの心情を何とかしたためようとしたこの手紙の文面を読んで感動しない者はいないだろう。添削してやろうなどとも思わないだろう。しかしこれを達意の文かのように理想視するなら、そもそも技術を教える文章読本など要らない、と思うのは私がひねくれているからだろうか。
人に文章の書き方を教えてやろうという人は、ホントにこの「文は人なり」が好きだ(元になったビュフォンの格言は正確には「文体は人(le style est l'homme même.)」らしいが)。この根性論や精神論にも結びつく人文一致信仰は、笑ってしまうことにいまだに強く生き残っている。
橋本治が『よくない文章ドク本』を書いたのは1980年代初頭で、軽薄体や饒舌体、パンク体、新言文一致体など様々な文学テクストが繚乱し「なんでもあり」かのようになった時代だったが、一方でまだまだ規範主義者は残っており、だからこその文体の挑戦だったのだろう。
「一体なんだってまた文章読本なんてもんがあるんでありましょうか? なんだってそんなものを一般人が必要とするんでありましょうか? というのが私の一般人だったときからの疑問でありました」「要するに、文章書いて他人に取り入りたいわけネ」
橋本は当時読まれていた文章読本の数々を俎上に載せ、こき下ろした。
「この威張り方って、ちょっと尋常じゃないと思わない?」「あのネ、僕たちはネ、あなた達とはコミュニケーションを拒否しているわけ。だから、あなた達のいう分かりやすい文章は無内容な文章なわけ。僕達の文章は、あなた達にとっては文章作法や作文技術が必要だと思えるような文章に見えるわけ。それだけなの」「困ったもんだよ中年は」
文章読本はかつては谷崎潤一郎や三島由紀夫、丸谷才一など作家が書いたものが権威をもっていたが、昭和末期以降に幅を利かせたのは新聞記者系だ。それもほとんどが朝日新聞の記者もしくはOBで、天声人語を担当した論説委員か編集委員クラスの「大物」ばかり。文章読本を著すというのは記者として栄達を究めた証しであり、たいへん名誉なことと受け止められていたのだろう。
そして、彼らは、新聞界のお家芸として培われてきた文章の作法を、伝達を目的とする文章一般に敷衍し、新聞記事をその模範か鏡鑑かのように取り扱う。
新聞界には固有の用字用語体系があり、特に事件や裁判、経済記事などでは制度的文体、いわば文法がある。
新聞記事には「毅然」も「破綻」も「蠢動」も「韜晦」も「惻隠」も居場所はない。「饒舌」は「冗舌」、「逍遥」は「散歩」あるいは「散策」と言い換えねばならない。現政権になってあれほど人口に膾炙した「忖度」も「隠蔽」も「改竄」も「噓」もルビなしでは使えない(む、膾炙もダメだ)。間の抜けたことに、かつては蛇行も「だ行」、暗闇も「暗やみ」と書かねばならなかった。「姦淫」も「放屁」も新聞では棲息を、もとい生息を許されていない。
こういう軛は恐ろしい。私も記者になってしばらくの間は、自分の言葉がどんどん細り思考法まで束縛されていくような不安に常に駆られたものだ。いまでも記事を書いていると「熟語は大和言葉に開け」「センテンスは短く」という強迫観念に襲われる。読点がやたら多くなる悪癖からもなかなか抜け出せない。
さらにやっかいなのは、デスクやキャップ役になって他人の原稿を直すうちに、検閲官のように文章表現に狭量になり、新聞的でない文を腐し、やがて自分たちの言語圏を至上と錯覚し始めることだ。その自意識肥大の一例が、記者あがりの文章読本なるものではないか。
斎藤美奈子はキッパリという。「文は服なり」。衣装が身体の包み紙なら文章は思想の包み紙であり、女も男も見てくれのよさにこだわってきた、と。いわく、どうりで新聞記者系の文章には色気がないはずだ。彼らの念頭には人前に出ても恥ずかしくない服(文)のことしかない。だから彼らの教えに従ってしまうと、文章はどれもドブネズミ色した吊しのスーツみたいになる。記者系の文章作法は「正しいドブネズミ・ルックのすすめ」。そういう人がたまに気張って軽い文章を書こうとすると、カジュアルフライデーに妙な格好で現れるお父さんみたいな感じになる――。ホントにその通りだ。
 斎藤美奈子さん
斎藤美奈子さん橋本治の言葉をさらに引けば、「この世には、分かりやすい文章なんてありはしない」「文章というものは、必ずや読者を選ぶんだよッ!」。
おそらく、文章読本の類いをすすんで書く人たちには、この「文章は必ず読者を選ぶ」という視点が決定的に欠けている。だから、万人に受け入れられる文章が存在しそれが良きものだという、ある意味傲慢な勘違いをする(彼らからすれば、読者を選ぶ文章という発想こそが不遜だということになるのだろう)。
新聞の文章についてつけ加えるなら、伝承文学の時代ならいざしらず、近代以降の文章は必ず個人が呻吟しながら一字一句選び取って書く。したがって分担執筆はあり得ても、無人称あるいは複数主語の文章というものは存在しない。だが新聞記事や社説は、役所の文書同様、書き手個人の責任が組織に融解した集団主語の文章という体裁をながくとってきた。
辺見庸は、共同通信記者を辞めて作家専業になる際、とにかく新聞言語圏から脱出したかったという趣旨のことを書いている。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください