国際協力NGOの現在と日本のNGOが抱える課題を考える
2019年03月03日
 Rawpixel.com/shutterstock.com
Rawpixel.com/shutterstock.com危機的な世界で「不可欠な存在」になるために・下 日本の国際協力NGOが目指すべき方向性と行動について考える
いま、子どもたちを取り巻く状況は苛酷(かこく)である。東京都目黒区や千葉県野田市の痛ましい悲劇は記憶に新しいが、日本では、年間80人近くの子どもが虐待により死亡、メディアで取り上げられる事件は氷山の一角に過ぎない。子どもたちを苦しめるのは、虐待だけではない。7人に1人の子どもが貧困に陥り、学ぶこともままならない。
世界に目を転じると、状況はさらに厳しい。年間540万人の5歳未満の子どもが予防可能な原因で命を落とす。6歳~17歳の子どもの5人に1人が学校に通えず、5人に1人が武力紛争下で暮らしている。
私が子ども支援のNGOであるセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンで働いて17年になるが、子どもたちをめぐる窮状は苛酷さを増している。
しかし、私たちには、こうした窮状に対してできることも多くある。
世界はいまや、「戦後最悪の人道危機」にあるといわれている。
いたるところで紛争が起き、長期化し、約7000万人の難民・国内避難民が発生している。その約半数は子どもである。気候変動も深刻さを増し、自然災害による被災者数は2016年には5億人を超えた。貧富の格差は、かつてないほど拡大している。
こうした厳しい局面で、日本の国際協力NGO は人道・開発支援の活動において、しっかりとその役割を果たすことができているのか。世界情勢が著しく変化していく中で、日本の NGO が積極的に打ち出すべき点や課題は何なのか。課題を克服するためには、どのような施策が必要とされるのか――。
こうした問いを探求するため、私たち有志グループは「NGO2030」を立ち上げ、外務省の委託事業「NGO研究会」として、調査・検討作業を続けた。日本の国際協力NGOが目指すべき大きな方向性とそのために必要なアクションを示すことを目的に活動し、3月1日には成果発表のシンポジウムを開催した。
これを機に、国際協力NGOの現状と、日本の国際協力NGOの役割と課題について、2回にわたって考えてみたい。
 ⽇本国際交流センター主催のワシン トンDC訪問団に参加した筆者(右から 2⼈⽬)=2017年3月3日
⽇本国際交流センター主催のワシン トンDC訪問団に参加した筆者(右から 2⼈⽬)=2017年3月3日日本のNGOの組織基盤や政府との関係性の強化を目的とするこの訪問に、私も2017年、他のNGOのメンバーらと参加。米国国際開発援助庁(USAID:US Agency for International Development)や国務省をはじめ、政府高官や議会職員、影響力のあるシンクタンクなどを訪問した。
どこでも率直な対話が交わされたが、なかでも衝撃を受けたのは、「NGOは戦略的パートナーである」「NGOなしには仕事は成り立たない」という認識が一貫して共有されたことだった。
アメリカでは、1970年代後半から政府がNGOによる人道・開発支援の「費用対効果」に着目し、組織基盤を強化するべく投資をおこなってきたという。90年代になると、援助の持続可能性や民主主義や多様性の推進という名目も加わり、NGOの専門性の向上に政府がより積極的な投資をした。その結果、NGOセクターが飛躍的に成長。具体的には、1990年に政府の組織基盤強化支援を受けた資金規模が1000万USドルの10団体のうち、8団体が2010年には1億USドルの規模に拡大している。
訪問先の多くでNGOの強みとして挙げられたのは、現地の事情や情報に精通していることからくる専門性や機動性、効率性、より革新的なアプローチによる支援活動などだった。ある上級議会スタッフは、「開発援助の複雑な課題に関して、もっとも精通した専門家であるNGOスタッフに、政策の素案作りを依頼することもある」と言った。
政府高官の一人は「議会に対して、行政が人道支援や難民支援のための予算増額などの意見を示すことは難しいが、NGOはそうしたアドボカシーを展開できる存在として重要なパートナーだ」とも強調した。NGOが一般市民から支持されているという背景がある。
さらに印象に残ったのは、アメリカで最大のNGOネットワークであるインターアクション(InterAction)の代表と対話した際に聞いた話だ。
――アメリカ政府が助成事業に対して特定の活動を認めないという要件を付けたことがあった。NGO側はこれを表現の自由の侵害だとして訴訟を起こした。だが政府は裁判の間もNGOへの助成を保留することはなく、インターアクションやその他のNGOもまた、政府機関のUSAIDへの情報共有を続け、緊密な関係を維持した(訴訟は最終的に勝訴した)。
「非政府組織」であるNGOの独立性を確保するためには、政府の政策に反対する自由がなければならない。政府の公的資金を受け取ることでNGOには一定の責任が生じるのは当然だが、真の「戦略的パートナーシップ」を築くには、NGOの独立性が確保されたうえで信頼関係が構築される必要があると、あらためて感じ入ったのを覚えている。
ワシントンでの「学び」は強烈だった。私を含めて訪米団に参加したNGOの代表者やシニアスタッフは帰国後、「自分たち日本のNGOははたして開発・人道支援における戦略的パートナーになり得ているのか?」という自問を繰り返した。
 シンポジウムで発表する「NGO2030」のメンバーで、 ジャパン・プラットフォーム共同代表/CWS Japan 事務局長の小美野剛氏(右)=2019年3月1日
シンポジウムで発表する「NGO2030」のメンバーで、 ジャパン・プラットフォーム共同代表/CWS Japan 事務局長の小美野剛氏(右)=2019年3月1日強力な“援軍”もできた。訪米団に参加した国会議員が中心となって発足した「NGO・NPO の戦略的あり方を検討する議員連盟」である。2018年6月には、シンポジウム「開発援助・人道支援における戦略的パートナーとしての NGO」を開き、アメリカの経験を参考に、NGO と政府に何ができるか議論をおこない、ODAの改革やNGOとの連携促進、能力強化などについて外務省に提言した。
日本のNGO自身が自らを変革する必要がある考えた私たちは、2030年に向けて目指すべき方向性、あるべき姿を指針としてまとめることにした。外務省のNGO能力強化策の一環である「NGO研究会」の事業として提案したところ、前向きに受け入れられ、外務省の委託事業として活動がスタートした。
外務省とNGOはこれまでも、「NGO・外務省定期協議会」でODAやNGOとの連携に関して対話してきたが、長期的な視点からNGOのあり方を議論することはあまりなかったように思う。この活動が、NGO間の、さらに外務省やその他ステークホルダーとの議論につながればとの期待が膨らんだ。
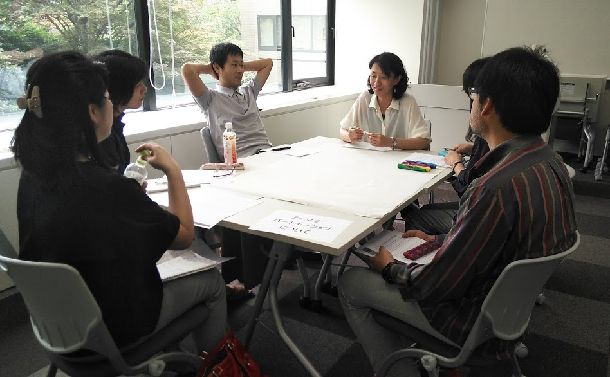 コンサルテーションではNGOに対 する様々な意⾒が出された=2018年6月22日
コンサルテーションではNGOに対 する様々な意⾒が出された=2018年6月22日コンサルテーションの結果はどうだったか。NGOに対する高い期待は示されたものの、専門性や提案力、発信力などの面が弱いこと、国際社会および日本社会の中で存在感が薄いこと、などが指摘された。これをもとに、日本の国際協力NGOが目指すべき大きな方向性、あるべき姿の指針をまとめ、3月1日に成果発表のシンポジウムを行った。
国際協力に関わるNGOは今、どのような状況に置かれているのか。
 「仙台防災枠組み」を採択した第3回国連防災世界会議の開会式=2015年3月14日、仙台市
「仙台防災枠組み」を採択した第3回国連防災世界会議の開会式=2015年3月14日、仙台市背景にあったのは、社会、経済、環境がかつてないほどバランスを崩し、「このままでは地球はもたない」という世界的な危機感だった。
2016年5月の世界人道サミットでは、「戦後最悪の人道危機」のなかで、これまでのあり方を見直し、効果的に対処するための新しいアプローチや仕組みに関する議論がおこなわれた。現地の政府やNGOにリーダーシップや権限・リソースを移譲し、先進国のNGOを含む国際社会はそれを後方から支えるという「ローカライゼーション」の重要性も確認された。
現在は、地球温暖化や貧富の格差といった課題が国境を超えてボーダーレス化し、先進国と開発途上国という関係だけでなく、すべての国やアクターが課題に向き合い、協働することが不可欠な時代となっている。課題が複雑に連鎖し、ひとつのセクターのみで解決できない。政府、国際機関、NGO、企業、学術界など、あらゆるセクタ―が連携を深め、英知を結集しなければ、解決は覚束ない。
にもかかわらず、最近はこうした地球規模の課題解決を妨げる事態も目立つ。
ひとつは、アメリカのトランプ政権に代表される自国第一主義、単独行動主義の拡大である。国際協調により平和や安定を維持しようとする多国間主義は揺らいでいる。
政府の戦略的投資により、強い影響力を持つまでに成長したアメリカのNGOが、とりわけアドボカシー活動において、かつてのような政府との信頼関係を土台としたインパクトのある活動を行うことが難しい状況に陥っている。
くわえて、民主主義が危機に瀕し、社会課題の解決に取り組むNGOなどの活動を制限する「市民社会スペースの狭まり」が世界中で広がっている。昨年の人権擁護者世界サミットでの発表では、2017年に少なくとも312人の人権活動家が殺害され、2015年から倍増しているという。
日本の状況はどうだろうか?
ひとつは、国際協力に関わるアクターが多様化したことが挙げられる。従来の政府・JICAやNGOのみならず、NPOや企業、地方自治体、大学等が国際協力を担うようになってきた。
甚大な災害、貧困、虐待、労働問題などが深刻化し、これまで開発途上国での国際協力を主たる活動としていたNGOが、国内の活動に取り組むことも増えている。国際協力はNGO、国内課題はNPO、といった境界線は薄れつつある。
欧米諸国などでは、NGOが政府の機能を補完し、公を担う存在として定着している国が多いのに対し、日本では「公を担うのは官」という考え方が根強く、NGOは公を担う存在として認知されていないのが現状だ。被援助国やアジア諸国のNGOも成長しているなか、世界の人道・開発支援に関する議論やそこでNGOが果たしている役割と、日本国内における議論やNGOに対する認識とのギャップは大きい。
日本のNGOはその存在意義をどのように捉え、また訴求すべきなのか。
 chrupka/shutterstock.com
chrupka/shutterstock.comしかし、こうした役割を果たすうえで、日本の国際協力NGOのキャパシティーは概して不足している。残念ながら、それが現実だ。
ただ規模を拡大すれば良いというわけではないが、私が所属するセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの本部スタッフ数は現在約60人、米国セーブ・ザ・チルドレンは約600人、英国セーブ・ザ・チルドレンは約800と本部のスタッフ数ひとつとっても10倍以上の差がある。活動範囲やもたらせるインパクトにも大きな差がある。
日本のNGOが日本および国際社会から不可欠な存在として認知されるため、組織基盤や専門性と共に発信力を磨くこともまた、喫緊の課題である。(続く)
※「下」は9日に「公開」する予定です。日本の国際協力NGOが目指すべき大きな方向性と行動を提示します。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください