安全保障だけでなく民主主義、環境、人権といった世界の「共通語」で語られる沖縄問題
2019年04月30日
 辺野古移転に抗議し、 「ジュゴンを守れ、海を守れ」と書かれた横断幕を掲げて声をあげる参加者=2019年4月22日、ニューヨーク
辺野古移転に抗議し、 「ジュゴンを守れ、海を守れ」と書かれた横断幕を掲げて声をあげる参加者=2019年4月22日、ニューヨーク
玉城デニー知事が抜けた穴を埋める衆院3区補選(4月21日投開票)では、玉城知事を支える「オール沖縄」の後継候補屋良朝博氏が、自民公認、公明・維新の推薦で、元沖縄北方担当相の島尻安伊子氏を、7万7千票対5万9千票で破り、初当選した。玉城知事の誕生(昨年9月)、県民投票の結果(今年2月)の流れに乗ったうえでの勝利といえる。
紆余曲折の末、実現した辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票には、有権者の52.5%(60万5千人)が参加し、投票総数の約72%が反対票だった。この43万4273票は、玉城デニー知事を誕生させた39万6632票を上回っており、知事選で玉城知事に投票しなかった人たちも「反対」に「マル」をつけたかたちだ。さらに全市町村で反対が多数となった。沖縄の声は誰の耳にもハッキリと聞こえたはずだ。
だが、安倍晋三首相は「全力で対話を」と言いながら、「粛々」と工事を強行し、駐日米大使も「辺野古が唯一」を繰り返す。沖縄の声が聞こえないふりをするのに懸命だ。本土のメディアも、もう県民投票のことなど忘れ去ってしまったかのようだ。
本稿では、まずこの県民投票を海外のメディアがどう報じたのか振り返ることで、辺野古米軍基地をはじめとする沖縄の基地問題について、国際社会がどうみているかをつまびらかにしたい。さらに、世界の有識者やNGO、国連がこの問題をどう見ているかも概括したい。辺野古基地推進・反対の対立のなかで、硬直化しているようにみえる辺野古の基地問題への視点を広げ、世界共通の言葉で考え直す契機になればうれしい。
県民投票に関する海外メディアの報道について、沖縄タイムスの米国特約記者・平安名純代氏は、「埋め立てに反対する民意が明示されたなどと報じるメディアがある一方、新基地建設を進める日本政府の方針を強調する報道も目立った」と要約している。
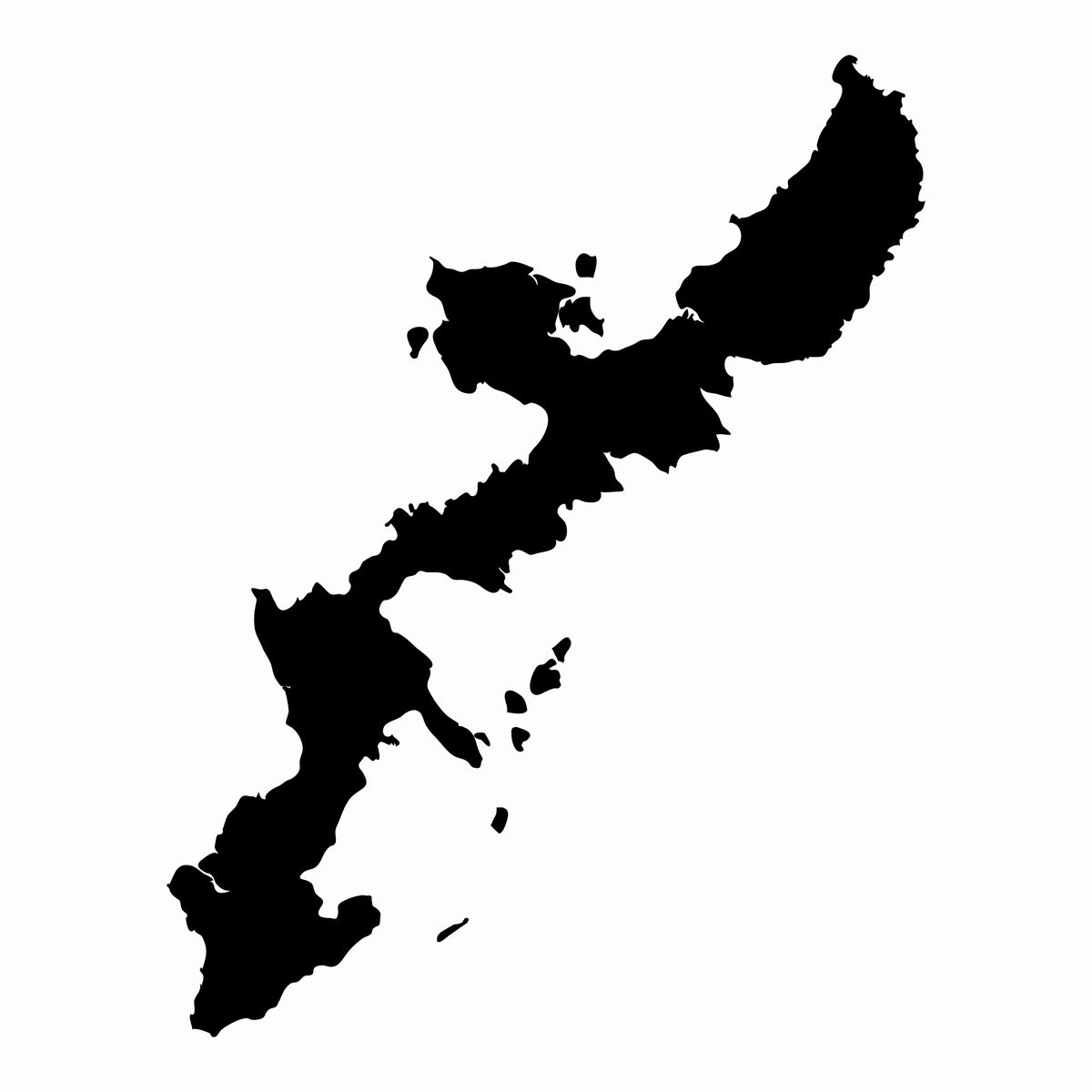 Eugene Ga/shutterstock.com
Eugene Ga/shutterstock.com1996年の県民投票や今回の県民投票の実施や選択肢など細かな点も押さえて、「沖縄の有権者は県民投票で新たな米軍基地の建設に明確な拒否を示し、日本政府と在日米軍に新たな頭痛の種をもたらした」とし、最後は菅官房長官のフラストレーションで締めくくっている。
「民意が示された」とまでは述べていないが、米軍準機関紙「星条旗」(2月24日、Okinawa voters say no to US base relocation plan in prefecture-wide referendum)は、日本政府が沖縄の一貫した反対にも拘わらず、このプロジェクトを推し進めていることを指摘し、投票結果が日本政府にとって問題をさらに複雑なものにしたと述べている。
安倍首相の「我々は長い間沖縄の人びとと対話してきたし、これからも理解を求めていく」との発言を引用しているが、海兵隊事務所や沖縄防衛局からはコメントを得られなかったとの記述を並べているためか、首相発言が軽々しく聞こえてくる。岩屋防衛相の戦略的重要性の指摘を紹介しつつも、玉城知事の「辺野古が唯一の選択肢との考えを再検討すべきだ」との発言で締めくくっているため、それが全体の論調に影響を与えている。
 住宅街に囲まれた米軍普天間飛行場=2019年3月12日、沖縄県
住宅街に囲まれた米軍普天間飛行場=2019年3月12日、沖縄県事実誤認というか、厳密ではない情報が気になったのが、ロイター通信の記事による米紙「ニューヨーク・タイムズ」(4月8日、Outnumbered and Elderly, Okinawa Protesters Oppose U.S. Military Runway)の報道だ。「基地は5年以内に完成する」「多くの日本人は海兵隊全部に出て言って欲しいと思っている」など根拠の怪しい記述もあるが、中国の脅威があるため、米軍はすぐには出て行かないし、日本政府は県民投票の結果にかかわらず工事を続けるという風に読める。若い人にとっては騒音が深刻な問題だ(野球をしていても球を打った音が聞こえない!)という締めくくり方は、基地被害のほんとうの深刻さを和らげている印象だ。
AP通信による英紙「フィナンシャル・タイムズ」の記事(2月25日、Referendum highlights attempt by US and Japan to push base through with no local consent)は玉城知事を「反基地闘争のリーダー」と形容するなど心配な記述もあるが、県民投票の目的が「政府が地域の声を無視している」ことを照らし出すところにあると、的確に指摘している。新基地建設の問題点は書かれてはいるが、投票結果が中国を利することになるおそれがあるとし、「結果にかかわらず方針は変わらない」という県民投票以前の菅義偉官房長官の言葉で締めている。
英紙「ガーディアン」の記事(2月22日、Okinawa referendum: everything you need to know、Residents of Japanese island will vote on Sunday about controversial plan to move US military base)は投票前のものだ。辺野古の新基地建設に対する批判の概要が書かれているが、絶滅危惧種であるジュゴンと2千人の住民の安全に焦点があたっている印象で、「多くの沖縄人は普天間を閉鎖し、代替施設は日本のどこか他所に作ることを望んでいる」との書きぶりは、沖縄の「NIMBY」(他所ならいいがウチの裏庭にはごめんこうむる)が強調されているようにも感じられる。
基地が沖縄に集中していることについても書いているが、南シナ海・東シナ海での緊急事態や北朝鮮の核にも言及していて、安全保障の方が重要だと言っているようにも聞こえる。最後は菅官房長官の「沖縄の人びとにはっきりわかる仕方での負担軽減を」という言葉で締めくられており、日本政府寄りの記事だと言える。
アジアの報道はどうだろう。
シンガポール紙「ストレイツ・タイムズ」は投票前の記事(2月22日、Abe to ignore controversial Okinawa referendum on US base move)だが、安倍政権が裁判にまで持ち込んで沖縄に言うことを聞かせようとしている点にふれ、日本政府が県民投票の結果を無視しようとしているとも伝えている。
 ホワイトハウス前で辺野古移設に対し抗議運動をするロバート・カジワラ氏=2019年1月7日、ワシントン
ホワイトハウス前で辺野古移設に対し抗議運動をするロバート・カジワラ氏=2019年1月7日、ワシントンマレーシア紙「ザ・スター」はAFP通信による記事(2月24日、Japan's Okinawa votes on controversial US base move)だが、「これは日本の民主主義が機能しているかどうかのテストケースだ」との専門家の発言を紹介している。最後は、日米安保と沖縄の地政学的な重要性にふれて締めくくっているが、「政府は沖縄をバカにしている」との発言や、朝日新聞の世論調査で「政府は県民投票の結果を尊重せよ」が80%にのぼるとの結果も紹介している。香港紙「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」(2月24日、Okinawa votes ‘no’ in referendum on US military base move)やカタールの国営TV「アルジャジーラ」(2月24日、'Test of democracy': Okinawa votes in referendum on US base)も基本的に同じ内容だ。
話がそれるが、「アルジャジーラ」が紹介している在日米軍報道官の発言、「我々は沖縄の人々と良い関係を維持しようと努力している。毎日、彼らの関心事と我々の準備態勢を維持する必要とのバランスをとるようできる限りのことをしている」は、中東の人々にどう受け止められるか気になった。イラクやアフガニスタンの米軍に対して人々がそうは見えないと感じるなら、沖縄における米軍の対応も大同小異だろうと、報道官の言葉を眉につばを付けて聞くのではないだろうか。
話を戻す。
中国の英字紙「チャイナ・デイリー」(2月24日、Okinawa votes in referendum on US military base relocation)はAP通信によるニュースだが、その扱いに特色がみられた。まず、県民投票に対し、日本本土だけでなく世界の平和運動家からも関心が寄せられているとの記述があり、新基地建設についても建設費用が膨らみ続けていること、滑走路が短いため普天間が返還されないかもしれない可能性にもふれている。さらに、県外移設の話が出ては消えることについて、沖縄の人々に差別(second-class treatment)されているとの思いを持たせているとも書いている。
以上、県民投票をめぐる海外のメディアを渉猟してみると、「民意は示されたが、政府は建設を進める方針である」という「筋」の話だけでなく、沖縄の基地問題にからみ、「沖縄の人々が民主主義のテストケースを提供している」「政府が非民主的であることを照らし出している」「沖縄の人々は差別され、バカにされている」「沖縄のNIMBY的主張もある」など、さまざまな見方が示されていることがわかる。この問題をめぐっては、米軍基地の事情、沖縄の主張、民主主義のあり方など、重層的な論点があることが、あらためて浮かび上がって興味深い。
ついでなので、アメリカのメディアに限るが、昨秋の玉城デニー知事誕生に関わる記事もみておこう。
米紙「ワシントン・ポスト」(2018年9月29日、Whatever the result in Okinawa election, US troops are there to stay)は、安全保障上の理由での新基地建設とそれへの沖縄の反発を紹介し、玉城知事が誕生すれば両政府にはさらなる頭痛の種だが、いずれにせよ、基地は存続すると報じている。
対立候補だった佐喜真氏については、政府からの資金が建設業などを潤すことを示唆していると指摘する一方で、高齢者が多い玉城支持者たちの文化的・歴史的背景(deeper cultural, historical sentiments)にも言及している。玉城知事の父親が海兵隊員であること、沖縄の人々の声に耳を傾けることが民主主義だとの信念を知事が持っていることを紹介し、「私の父の国の民主主義が、その息子の言っていることを拒否できるはずがありません」との知事の言葉も引用している。
この記事は、香港紙「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」でも紹介されているが、日本政府は安全保障問題は国が決めることだとし、新基地建設を前に進める決意であると締めている。
 衆院沖縄3区補選で当選した屋良朝博氏(中央)とカチャーシーを踊る玉城デニー沖縄県知事(右)=2019年4月21日、沖縄県沖縄市
衆院沖縄3区補選で当選した屋良朝博氏(中央)とカチャーシーを踊る玉城デニー沖縄県知事(右)=2019年4月21日、沖縄県沖縄市翌日の社説「沖縄の負担軽減に向けて(Toward a Smaller American Footprint on Okinawa)」では、沖縄の拒否は明確であり、この不公平な安全保障負担は、国家の安全保障といえどもこれを正当化できないとしたうえで、日米両政府は立ち止まって妥協点を探すべきだと主張した。
米誌「ネーション」(2018年12月13日)は、「米国は地元の圧倒的な反対にも拘わらず新基地建設を進めている(The United States Is Building a New Military Base in Okinawa, Despite Overwhelming Local Opposition)」との見出しで、これは民主主義の問題であると指摘する。さらに一歩進め、もしアメリカが民主主義を尊重しないのであれば、「日米同盟は脆弱なものになる」とする玉城新知事の発言も紹介している。
次に、世界の著名人の沖縄に関する発信をみてみよう。彼らが繰り返し、沖縄の状況を世界に発信し、沖縄の「軍事植民地的状況」を終わらせるよう訴えていることは、沖縄に住む者としては心強い。
2014年1月の最初の有識者声明は、前年末の仲井真弘多知事による埋め立て承認を受けて、オリバー・ストーン、ノーム・チョムスキー、ジョン・ダワーら103人が、新基地建設の中止と普天間飛行場の返還を訴えたものだ。
昨年2018年9月の4回目の声明は、「(最初の声明の)当時懸念していた状況は良くなるどころか悪化しているので、今再び私たちは声を上げる」として、ヨハン・ガルトゥング、シンシア・エンローらも含む133人が、沖縄の平和、人権、環境保護のための闘いと、県の埋め立て承認撤回への支持を表明し、日米両政府は新基地建設を中止するよう主張している。この声明を取り上げた「琉球新報」社説(2018年9月8日)は「米国の独立宣言や公民権運動を沖縄に重ねたことは、新鮮な驚きだった」と、沖縄の運動が普遍的な理念に結び付いていることを強調している。
 死んで引き揚げられたジュゴン=2019年3月19日、沖縄県今帰仁村の運天漁港
死んで引き揚げられたジュゴン=2019年3月19日、沖縄県今帰仁村の運天漁港県民投票との関連では、県民投票が実施されるまでの間、工事を停止するよう求めるオンライン署名の活動が注目を浴びた。「We the People」というホワイトハウスの請願サイトで昨年12月8日にオンライン署名を始めたのは、先述のロブ・カジワラ氏だが、タレントのローラさんや、いま日本でも話題の「Queen」のブライアン・メイさんが署名に賛同したこともあり、1カ月で約20万筆が集まった。
ただ、米誌「ネイション」の記者のティム・ショロック氏はこの署名活動について、「アメリカでは話題になっておらず、米市民は知らない。工事が進む状況下で、どんな効果が見込めるかは未知数だ」と語った。(『沖縄タイムス』1月9日)
アジアの市民運動の受け止めはどうだろうか。新崎盛暉氏はかつて、沖縄にとってはアジア、特に韓国との関係が重要だと言っていた。
「1995年以降の沖縄の反戦反基地闘争に非常に関心を持っていたのは、まず韓国だったんですね。(中略)現在では、普天間、高江の問題と、済州島の江汀村の基地建設問題が、一緒に語られる場面も出てきている」(注)と、「若い人たちの国境を越える感覚」が政府の基地押し付け政策との闘いを切り開く手がかりになるのではないかと指摘している。実際、名護市辺野古の新基地建設に抗議してキャンプシュワブのゲート前に座り込む市民を、韓国の平和団体「平和の風」の沖縄訪問団が激励したり(『沖縄タイムス』2018年2月20日)、北東アジアの平和や軍事基地について考えるシンポジウム「沖縄・韓国民衆会議」が開かれたりしている(『琉球新報』2月11日)。
(注)大田昌秀、新川明、稲嶺恵一、新崎盛暉「座談会 沖縄の自立と日本の自立を考える」大田昌秀他『沖縄の自立と日本:「復帰」40年の問いかけ』岩波書店、2013年、208~209頁。
市民社会の領域でのこれら一つ一つの事例は、単体としては大きなインパクトを持っていないかもしれないし、注目されていないかもしれない。だが、先の「琉球新報」社説にあったように、沖縄の基地問題に携わる人々の運動が普遍的な理念に結び付いていることは、国連の人権理事会での議論にも反映している。
たとえば2018年8月、人種差別撤廃委員会は、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください