「家族」に過大な負担を強いてきた結果、立ちゆかなくなっているこの国
2019年07月11日
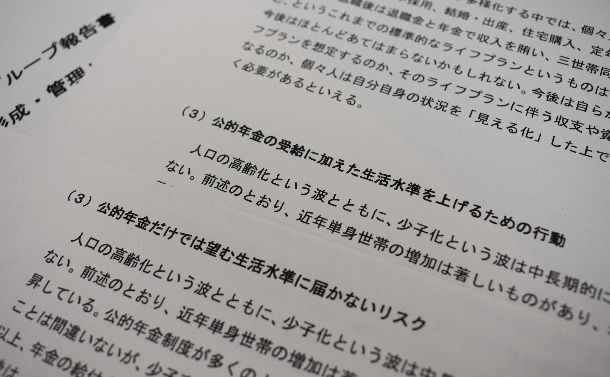 金融庁の審議会がまとめた報告書「高齢社会における資産形成・管理」
金融庁の審議会がまとめた報告書「高齢社会における資産形成・管理」
この参院選で最大の争点といえば、老後の暮らしに必要な資金の問題だろう。
「年金だけだと2千万円不足する」という金融庁の審議会の報告書は、多くの人の心の中でくすぶっていた不安に火をつけた。
ただ、これは選挙権を行使する大切な機会だ。不安にあおられるよりも、その正体を見極め、しっかりと考えたうえで投票したほうが一票は生きる。
不安を一皮めくったとき、そこにみえてくるのは、「家族」に過大な負担を強いてきた結果、立ちゆかなくなっている「家族国家・日本」の姿ではないか。
この報告書で注目すべきは、そこに書かれていること以上に、消されてしまった文章だろう。
報告書の原案には「公的年金の水準については、中長期的に実質的な低下が見込まれている」「今後は、公的年金だけでは満足な生活水準に届かない可能性がある」とあったが、最終稿では「公的年金の水準については、今後調整されていくことが見込まれている」などと丸められた。そして、これは最後まで残ったけれど、「『自助』の充実を行っていく必要がある」と資産形成を促した。
年金はこの先、大丈夫なのか? そんな不安を認めた表現だった。
「自助のすすめ」は、社会保障の意味を疑わせる内容になっていた。
社会保障は、何のためにあるのか?
社会保障の中でも、年金や介護、医療は社会保険に分類される。その存在理由のひとつは、人の一生は不確実性に満ちていて、個人で備えるのがなかなか難しいことにある。
年金でいえば、何歳まで生きるか予測がつかないから、自分で貯蓄しろ、投資しろといわれても、どれだけ蓄えればよいのかわからない(2千万円不足というのは、65歳の夫と60歳の妻が、あと30年生きると仮定した場合の話だ)。けれども1万人の寿命を足せば、合計は「平均寿命×1万」に近づく。みんなで老後に備えれば、必要な額のおおよその見当がつくから過剰な蓄えをせずに済み、ずっと合理的なのだ。
それなのに、年金だけでは満足に暮らせなくなるから自分で備えよと、報告書はいう。
そういわれても、ぎりぎりの生活をしている人はどうしようもない。多少は蓄えることができたとしても、「思っていた以上に長生きしたら、どうしよう」という心配を抱え続ける。長生きを喜べない、悲しい社会になってしまう。
それで社会保障といえるのか。保障していないじゃないか……。そうした疑問がわかないほうが、私には不思議に思える。
そんなことをいったって、年金は先細らざるをえない。いまと同じ額を給付していたら、若い世代が耐えきれないよ……。
そういう指摘もまた、否定しがたい事実だろう。
私たちは年金の保険料を納めているけれど、それを積み立てて老後に給付するわけではない。お年寄りの年金の原資は、現役世代の保険料や、税金などでまかなっている。息子や娘が年老いた親を養うのと同じことを、社会全体に広げておこなっているのだ。だから「減らすのはけしからん。とにかく出せ」というばかりでは、いまのお年寄りはよくとも、現役世代の負担が重くなり、年老いたあとに受け取る年金も減りかねない。
この問題に簡単な解決策はない。だからこそ、年金の土台である社会の構造から考えなければならない。
年金はなぜ先細るのか。いうまでもなく、原因は少子高齢化だ。
高齢化は長寿化だから、悪いことではない。問題は、なぜ少子化が進んだのかにある。
 Trueffelpix/shutterstock.com
Trueffelpix/shutterstock.com国立社会保障・人口問題研究所による2015年の出生動向基本調査では、夫婦が理想とする「理想子ども数」は2.32人。これに対し、実際に生むつもりの「予定子ども数」は2.01人にとどまる。なぜ「理想」まで生もうとしないのか。その理由としてもっとも多くの人が挙げたのは、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」(56.3%、複数回答)だった。
内閣府が昨年実施した少子化社会対策に関する意識調査では、国や自治体の少子化対策のうち「質が十分でない」「量が十分でない」と思うのは、そのどちらも「待機児童の解消」(質52.9%、量42.8%、複数回答)が最多で、次が「教育費負担の軽減」(質43.4%、量38.6%)だった。
「お金がかかりすぎる」と感じる理由ははっきりしている。ほかの先進国に比べて教育に投じる公費が少なく、私費負担が多いのだ。経済協力開発機構(OECD)の「図表でみる教育 2018」によれば、日本では高等教育のための支出の68%が私費で賄われ、OECD平均の倍以上にのぼる。
待機児童は、なぜ解消できないのか。理由はいろいろ挙げられるけれど、要は「本気度」が足りないのだろう。何をおいてもとりくむと腹をくくれば、解消できないわけがない。この社会では「3歳までは母親の手で育てるべきだ」といった意識が根強い。だから心の底で納得できず、本腰が入らないのではないか。
社会としての支援を怠り、家族に自助を強いれば、子どもを生むのを諦める人が増える。日本の少子化は、「しかたがない」という諦めが積もり積もった結果のように思える。
日本の社会保障は、主にお年寄りを対象としてきた。安倍晋三政権は、子育て世代を含む「全世代型」の社会保障への転換を掲げ、教育無償化などにとりくむ。具体策にはいろんな問題があるものの、子育てを支援し、教育費の負担を軽くするという方向性じたいは間違っていないと思う。
それは子どもたちや、子育て世代のためであると同時に、お年寄りのためでもある。子どもたちがしっかりと育ち、税や保険料を納められるようにならないと、年金を給付できない。若者にしかるべき賃金を払い、結婚して子どもをもうけられるように支えることも含め、全力で支援すべきだ。
しかし、である。
政権や自民党は、どこまで本気になれるだろうか?
自民党は野党時代、「子どもは社会で育てる」と唱える民主党政権に対して「子どもは家庭で育てる」と食ってかかり、その看板政策だった子ども手当も高校無償化も徹底的に批判した。2012年にまとめた日本国憲法改正草案には「家族は互いに助け合わなければならない」と記し、家族の自助を掲げた。この草案は党の公式なもので、いまも修正や撤回はされていない。
こういう意識をもったままで、「全世代型」の社会保障への転換が進むだろうか? 本気でとりくむというのであれば、安倍首相はみずから党内を説得し、改憲草案も修正・撤回すべきではないか。
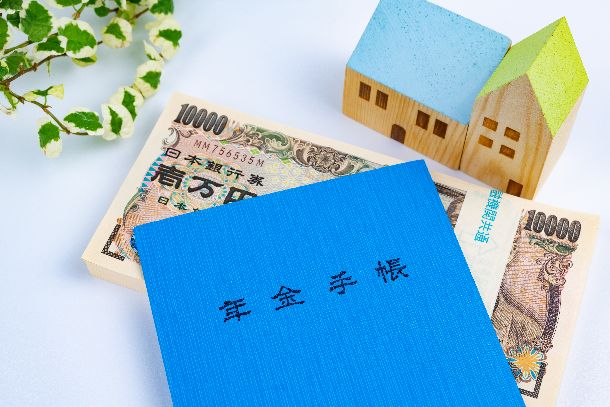 Princess_Anmitsu/shutterstock.com
Princess_Anmitsu/shutterstock.com1973年、田中角栄首相が社会保障を拡充し、「福祉元年」と呼ばれた。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください