「福祉国家」の根本に関わる問題。政党はこれを一度の選挙の争点ですませるな
2019年07月16日
 Princess_Anmitsu/shutterstock.com
Princess_Anmitsu/shutterstock.com7月21日の参院選が近づく。この選挙での争点は何だろうか。
有権者の側は明確だ。6月末の世論調査(日本経済新聞社・テレビ東京)では、重視する政策として「年金・福祉などの社会保障政策」が54%にのぼり、首相の掲げる「憲法改正」は13%に過ぎない。外交や安全保障よりも、社会保障や雇用といった生活にまつわる争点が重視されるのは、今回も例外ではない。
突如浮上した「老後資金2000万円」問題は、こうした態度に影響を与えたのは間違いないだろう。年金は、老若男女を問わず、国民の懐に直接に関係する問題であり、「2000万円」という数字は、憲法問題などと比べてリアリティを持ちものだけに、関心が高くなるのは当然だ。ここから各党とも、年金問題に関する公約を盛り込だ。
しかし、年金は「金額」以上の意味を持つ争点でもある。もっと言えば、三重の意味で「フェイクな争点」である。すなわち、①問題の根源は「2000万円」という金額にあるのではなく、②各党が掲げる公約は非現実的なものであり、③年金はそもそも選挙で問うべきはないはずのものだ。
本稿では、「2000万円問題」がなぜ、「フェイクな争点」なのか、各党の公約にも言及しつつ、ミクロ(問題の在り処)、メゾ(政策の争点)、マクロ(年金制度のあり方)の3層にまたがって論じてみたい。
まず、年金問題がクローズアップされた経緯を確認しておこう。「2000万円問題」が注目されたのは、金融庁の「金融審議会 市場ワーキング・グループ」の報告書「高齢社会における資産形成・管理」で「夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの無職の世帯では毎月の不足額の平均は約5万円であり、まだ 20~30 年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で 1300 万円~2000 万円になる」(同21頁)とされたことに端を発する。
 「老後2千万円不足」問題についての野党合同ヒアリングで、金融庁や厚生労働省の担当者に質問する野党議員ら=2019年6月13日、国会内
「老後2千万円不足」問題についての野党合同ヒアリングで、金融庁や厚生労働省の担当者に質問する野党議員ら=2019年6月13日、国会内ただし、同様の試算は、金融庁のみならず、例えば朝日新聞社が2019年1月に発行した「AERA with Money」という資産形成特集でも取り上げられている。労働力が減少し、65歳以上の高齢者のいる夫婦世帯は、1980年の16%から2017年には32%へと倍増、高齢者が2030年に32%、2060年には40%となることが予測される中で、年金給付額の増大には限界があり、これに長寿化が加われば、減少傾向にある退職給付金ならびに年金生活には困難が伴うことは、いわば常識の類に属する。
すでに社会保障給付はGDPの23%占め(2016年度予算ベース)、年金はその約半分を占めている。年金給付のシェアは1980年に4割程度だったが今後、年金給付額が増え続けていくことを考えれば、財源不足に陥るのは当然だ。
ただし、「2000万円不足」という文言が一人歩きしたこともあって、メディアは「100年安心年金」という、小泉政権時代のキャッチフレーズを逆手に、公約違反であるとのニュアンスを含めて報道し、これが有権者の不安を煽(あお)ることになった。金融庁の報告書は年金制度の持続可能性を議論しているわけではない一方、年金だけに頼って生活することが難しいことは多くの人が知っている。
つまり、年金問題は人為的に作られた争点でもあった。
もちろん、有権者が感じた不安はリアルなものだ。上に書いたように、現役世代の減少と高齢者の増加は、年金制度の維持を難しくする。
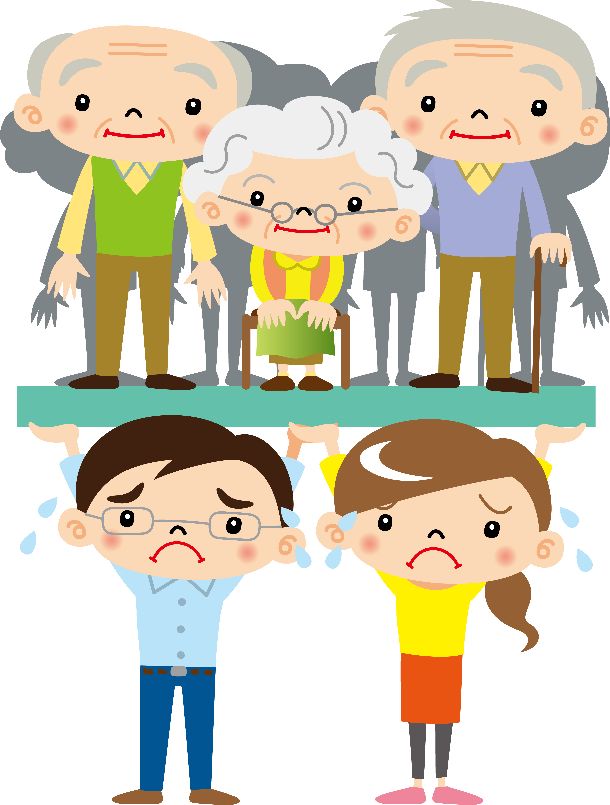 HIRO-Lab/shutterstock.com
HIRO-Lab/shutterstock.com
これは、財源維持と負担増加抑止のため、それまでのように物価・賃金の上昇と並行しての年金額増額を止め、被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を適用するという、実際には年金額を減少させるための仕組みだ。特定の計算式によって年金額を減額するこの制度は、年金財政の負担と給付が均衡するまで続くことが想定されるが、いずれにしても高齢化が進めば、年金額はさらに減ることになる。
「マクロ経済スライド」には複数のシナリオが含まれ、その土台となる財政検証は5年に1度であるため、導入当時は余り注目を集めなかった。また、デフレ下で年金給付を下げて年金制度維持可能性を高めることができたものの、本来ならば給付減となった2001-2年度にはこれが政治判断で見送られた時も、今回ほどの議論はなかった。
つまり「2000万円問題」の真の姿は、マクロ経済スライドの是非にも関わっているが、そうした争点をおざなりにしている政治家やメディアの責任は重い。今年が財政検証の年であるにも係らず、作業の結果がいまだ公表されていないことも、真の争点をみえにくくしていることは、政権の責任でもある。
参院選に際して、この問題を可視化したのは、マクロ経済スライドの廃止を公約としている共産党だ。同党は、マクロ経済スライドによって、2040年に金給付額が全体で7兆円減額されるとした上で、不足する年金財源は、所得に係らず一律の支払額となっている保険料を高所得者に対して引き上げ、さらに年金積立金を取り崩して給付にまわすことを提案している。こうした具体的な制度的提案は、共産党の面目躍如といったところだ。
もっとも、共産党は年収1000万で据え置きとなっている年金保険料を、それ以上の高所得者に相応の負担を求めるとしているが、日本で1000万以上の所得を得ている個人は5%にも満たないため、十分な代替財源となるかという疑問は残る。それ以上に、所得と保険料を連動させてよいのかという問題は残る。国民年金はもちろん、医療・福祉も、憲法第25条が規定する生存権(「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」)に関わるものであって、万人に保障されるもので、その権利は収入や所得の多寡に関係なく、国民であれば誰もが等しく享受できるものでなければならない。
同様に、幼保無償化に際しても、無償化が金持ち優遇策だとの批判が野党から出されたが、しかし就学前支援は国民が等しく享受すべき権利だと考えれば、社会権保障の観点からは疑問なしとはいえない。ユニバーサルな社会保障とは、裕福な者であっても明日は貧乏人となるかもしれないといった人生のリスクを皆で緩和するものだとすれば、高所得者だからといって、その負担分を負わせるのは、公平とはいえない。これは、年金が各人の所得に応じて比例させて配分するのか(配分的正義)、それとも全員に等しく配分すべきなのか(矯正的正義)という論点にも関わってくる。
さらに、年金積立金の取り崩しは、共産党が指摘するように、諸外国と比べても多額の200兆円という膨大な額になっていることは事実だ。しかし、年金給付額が年間60兆円にのぼり、給付総額が今後増加することを考えれば、十分な額とはいえない。それ以上に、GPIFの運用額がアベノミクス(異例の金融緩和策)と日本株価の上昇と一体不可分の関係にある以上(160兆円を運用するGPIFによって、日経平均株価は1000円ほど上昇したとされる)、年金財源は全体のマクロ経済政策とセットで考えなければならない。
それでは、高所得者負担と積立金切り崩し以外に、年金額確保の方策はあるのか。それに共産党とは対照的な形で具体的に応えているのが日本維新の会だ。同党は、公約にある「働き方・社会保障制度改革」の中で、「公的年金を社会保険として受益と負担を均衡させるため賦課方式から積立方式に移行」と、そっけなく掲げている。
つまり、現在の年金給付額の逼迫は、現役世代が高齢者に対する「仕送り」である「給付建て賦課制度」を原因としている。年金額が人口構成に条件付けられているためだ。老後に備えてあらかじめ自分で自分の年金の「貯金」をする「積立方式」に変えれば、人口動態に関係なく年金制度を運用できることになる。
実は日本も国民皆保険制度が1961年に導入されるまで、年金はこの積立方式で運用されていた。とすれば、年金を社会連帯ではなく、自己責任へと移行する「逆コース」といえる。
もっとも、賦課方式から積立方式への移行には困難が伴う。単純にいって、制度の過渡期に保険料負担が二重となるためだ。従って、積立式の部分的な組み入れを数世代にわたって保障する以降措置が必要となり、それに応じてどのような給付と負担になるかも大きく変わってくる。また、積立方式では、原則的に運用が個人に任されることになり、金融市場の影響を直に受けやすいという負の側面がある。
なによりも、公的年金制度という、戦後日本の福祉国家としてのあり方を大きく変化させることになり、世代間の分断や世代内の分断をさらに加速させることになりかねない。少なくとも、具体的な移行措置(拠出建てなのか拠出建てなのか)やこうした負の側面への緩和措置のない公約は、議論しようがない。
他の主な政党はどうか。立憲民主党は参院選公約「立憲ビジョン」で「安心して医療や介護がうけられるよう年金の最低保証機能を強化します」としか謳っておらず、国民民主党は「低所得の年金給付者の方に最低月5000円を給付」としか書いていない。与党では、自民党が同じく、収入の少ない年金生活者に「最大6万円の福祉給付金」を支給する、公明党も国民民主党と同じく「月額最大5000円」を上乗せするとしている。しかし、給付の上乗せがいつまで続けられるのかも明記せず、単に月数千円を配ることが「2000万円」という数字のリアリティを帳消しにできるとは到底思えない。
 ankomando/shutterstock.com
ankomando/shutterstock.com中でも年金問題は、冒頭に記したように、個人の懐に絡む問題であるものの、しかし人口減と高齢化という構造的問題であるゆえに、各党とも及び腰になり勝ちとなる争点だ。政権が年金額見通しの基本となる財政検証の結果を先延ばししたとされるのも、こうした事情があるだろう。
年金改革は、世代や職域をまたぐ全国民に関わる問題であると同時に、長期でなければならない課題であるゆえ、特定政党というよりも、党派を超えて、数年以上をかけて議論しなければならない課題だ。
70年代から議論を始めたイギリスでは、基礎的な公的年金の拡充に加えて、私的年金や賦課年金の導入などを、政権の党派問わず、90年代まで改革が断続的に続けられた。少子化に苦しむスウェーデンやドイツでも、賦課方式を維持しながら、部分的に拠出建て(掛け金の拠出と運用)を導入し、年金財政の安定化を図る大改革を90年代に行っている(詳細は、伊藤武「日欧年金改革における福祉改革と福祉政治」『事例比較からみる福祉政治』ミネルヴァ書房、新川敏光編『福祉レジーム』ミネルヴァ書房を参照)。
言い換えれば、年金問題は選挙の争点に馴染まず、もっと言えば、特定の政権や政党だけで解決できるような問題ではない。それは戦後先進国が完成させた「福祉国家」という国家のあり方の根本に関わるものなのだ。敷衍してみよう。
「労働の奨励としての飢餓の恐怖と、懲罰の道具としての経済の鞭と、この両者に対して広範な反抗が起こったのは、ここようやく20年ばかりのことで、私たちはいま、正にこの成果の意義、そこから生まれる新しい問題の意義を知り始めているところです」。歴史家として名高いE・H・カーは、1951年にこう語っている(清水幾多郎訳『新しい社会』岩波新書)。
工業国で、年金を含む社会保障制度が整備されていったのは19世紀末から20世初頭にかけてのことだ。福祉先進国として知られるスウェーデンでも国民年金が生まれたのは1913年、「ビスマルク型福祉国家」という類型で有名なドイツでは1889年のことだ。ほぼ100年前には、そもそも年金制度は存在せず、権利ですらなかった。
健康保険や雇用保険、公営住宅などを含む社会保障制度が飛躍的な拡充を見たのは戦後になってからで、1930年代にGDP比の5%を超えることのなかった工業国の社会保障費は戦後、1960年には10%前後となり、現在では3割程度と、着実に増大していった。
「福祉国家」という言葉が流通するようになったのは1940年代のことだとされているが、国家が「所得保障や社会サービスを用いて、出生から死亡までの生活上のリスクに対応し、国民の生活を安定させるために資源の再配分を行う」(鎮目真人・近藤正基編『比較福祉国家』ミネルヴァ書房)ようになったのは、ナショナリズムのもとで国民国家の制度化が進み、大量生産と大量消費による工業社会のもとで労働者が生まれ、人口が増加して高度成長が実現したことによるものだった。
日本でも一般的な年金制度が整ったのは太平洋戦争の時であり、現在のような国民年金制度が完成したのは1985年のことに過ぎないのだ。言い換えれば、人口増と経済成長を前提にしていたのが、今の年金制度なのだ。
しかし、こうした前提はもはや崩壊の憂き目にある。経済的なグローバル化は国家の財政的基盤を揺るがし、社会的なグローバル化は社会保障の受給権の範囲を難しいものとしている。日本でも外国人の医療保険の不正利用が、(おそらく過度に)問題視されたことは象徴的だ。
また、フルタイム雇用を前提とした社会保障は、非正規雇用(労働者の約40%)や個人事業主の増大(約13%)によってもはや通用しなくなり、ライフコースやキャリアの多様化は、個人のリスクを多様化させ、どのようなセーフティネットを必要とするかを制度的に決めることが難しくなっている。大企業で働く家庭を持つ男性にとって失業保険や児童手当ては重要かもしれないが、個人で働く独身女性が必要とする社会保障はそれとは異なるものだろう。現役世代の減少と高齢者人口の増大は、そもそも年金制度を維持しにくくなることは前に述べた通りだ。
問題は、20世紀を通じて作り上げてきた「高度成長・福祉国家・終身雇用」という――戦後日本の成功体験でもあった――三位一体が崩壊して、社会保障が歪(いびつ)になってきていることだ。
福祉国家に限っていえば、その利益は労働市場での「勝ち組」(例えば職能給で雇用される大企業正社員)に限定されるのに、負担は社会保険料を同じように支払う「負け組」(例えば職務給にある非正規社員やアルバイト、個人事業主)も分かち合っている。企業年金のある法人は全部で4割程度でしかない。非正規や障がい者、若年層などの福祉受給権を厳しくしていくことで、こうした「勝ち組」の社会保障水準を維持することは、社会での分断(水平的分断)や世代間対立(垂直的分断)を煽(あお)ることになる。
 Aksabir/shutterstock.com
Aksabir/shutterstock.comこうした矛盾をどのように乗り越えていくべきか?
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください