中国の高い映像技術の現状とカリフォルニア州の消費者プライバシー法
2019年08月09日
 Akarat Phasura/shutterstock.com
Akarat Phasura/shutterstock.com中国での遺失物が監視カメラによって探し出されて戻ってきたとの話が最近、ウェブに2回掲載された。
一つは、深圳の日本人ブロガーが書いた、ホテルで財布を落とした友人の話。もう一つは、元伊藤忠社長で中国大使もつとめた丹羽宇一郎氏が紹介した、中国のある省都でカメラを紛失した現地社員の話だ。
前者は監視されているから誰も財布を拾わないという点で、後者は路上で置き忘れたカメラを持ち去った中国人を捕まえて回収したという点で、中国社会の監視力のすごさを物語る。
NY(ニューヨーク)市警が中国企業の開発したカメラを犯罪予防捜査に使っていることは、前回「AIを使った犯罪捜査で人種差別はなくせるか?」で説明した。このカメラは、NY市警によると世界最先端技術を持つ多焦点型で、撮影範囲内のすべての人間の特徴を分析でき、撮影対象者の持ち物も分かる。
この二つの事例も踏まえ、筆者自身の経験も交え、現在の中国の監視・捜査レベルをもう少し具体的に考えてみよう。
筆者は今年3月に北京市内で財布を紛失した。気づいたのは翌朝のホテルのチェックアウト時で、ホテルに探してもらったが見つからず、そのまま朝のフライトで東京に戻った。ところが、羽田空港に着くなり、財布が出てきたとの電話連絡を受けたのである。
筆者が財布を落としてから手元に届くまでの経緯はこうだ。
チェックアウトの前日に筆者は二つの大学を訪問していたが、そのうちの一つで筆者の関係する学部のビルの向かいにある別の学部のビルで財布を落とした。財布を拾得したのはその大学の学部生で、彼は副学部長に届けた。その後、学内の監視カメラを見ると、私が財布を落とした様子とともに、私の顔が映っており、財布の中にあったIDカードの写真と、落とし主が符合。
副学部長はその事実を確認後、日本大使館、科学技術振興機構の北京支部等に問い合わせ、日本に関係していた中国人のネットワークを通して、私の居所を突き止め、国際宅急便で送ってくれたというわけだ。
この事実には我々が理解しておくべき三つの示唆がある。
一つ目は、ホテルは自社の監視カメラや従業員への確認等で顧客から届け出のあった遺失物を確認するが、そこで見つからないからと言って、それを警察に通報することは普通はないという点だ。ちなみに、ホテルのカメラは静止カメラで、技術もさほど高いものではない。
また、大学等の公的機関でも、監視カメラに映った結果を公安に連絡することは普通はない。要は、いくら中国であっても、ホテルや学校などの普通の場所では、日本と同じように、すぐさま当局に報告することはないということだ。
二つ目は、落とした瞬間がカメラで撮影されていない限り、拾得物の持ち主だとは確認は出来ないという点だ。ホテル内であれ、路上であれ、24時間カメラで撮影している場合、一日分でも膨大な量となる。従って、筆者もそうだったが、落とし主であることの最終確認は、日本で警察やJRの遺失物係が行うのと同様に、あくまでも人間が行う。
ただし、6月からの香港のデモ参加者が顔を隠すのにはわけがある。最初から身元の割出しを対象とする撮影であれば、それはかなりの程度、実現可能だからだ。
三つ目は、人間の動きを撮影する監視カメラはあくまで人間に焦点を当てているため、持ち主が路上に置き忘れた物や落とした物は焦点から外れ、一定の時間が経過した後に別の人間が持ち去ったとしても、それが真の持ち主なのかどうかを特定することは容易ではないという点だ。
また、現段階では、その拾得者がどこの誰かを特定するほどまでAI監視システムは先端化していないうえ、監視カメラの設置は全都市の全道路を隈なくカバーしているわけではない。よって、カメラを紛失した現地社員の例では、公安が捜査する理由が別にあったのではないかという可能性も考えられる。
要するに、人権やプライバシーのなさが批判される中国であっても、屋外での人間の活動を、事前に特定することなく、その持ち物までわかるほど、100%監視するほどの技術もなければ、そのような発想もない。さらに、中国に限らず日本やアメリカでも、なんらかの理由がないと、さすがに一般人の落とし物や忘れ物を探してもらうことを期待できないし、それが達成されるほどの能力で監視されるまでにはなっていない。
しかし、都市での落とし物が出てくるという事例は、カメラ技術のみならず、中国のAIが非常に優れたレベルにまで進化していることの証左でもある。中国以外で、これほどの結果が出る国はいまだ他にないだろう。
故ホーキンス博士はかつて「AIは人間を超える」と予想した。この場合の前提は、世界中で一つの目的に向かって多くの学者が切磋琢磨し、また発明された技術は世界中の全ての人間が利用できる、ということである。
 shuttersv/shutterstock.com
shuttersv/shutterstock.com確かにその頃は、米ソの冷戦が終わり、パックス・アメリカーナのもと、世界中が様々な科学の進歩の恩恵を受けることができると信じられた時代であった。だが、今や米中で技術覇権競争が始まっており、米国で開発された技術と、中国で開発された技術が、別々の研究として発展する状況になる可能性がある。さらに、ロシアもこの競争に加わっている。あえて言えば、日本や欧州諸国が米国とともにあり、そこに中国とロシアが協調する形で競争を挑むという「三つ巴」の競合状態にあるのだ。
それゆえ、幸か不幸か、故ホーキンス博士の「AIが人間を超える時代が到来する」という予想が実現するには、まだ時間がかかるかもしれない。とはいえ、これまで2回にわたって書いた米国の警察の例「AIを使った予測捜査で貴方は丸裸にされる」、「AIを使った犯罪捜査で人種差別はなくせるか?」や、上述の中国の監視カメラの例を見れば、AIが人間を超えるにはまだ幾つかの壁があるものの、その達成時期がかなり目前まで迫ってきているとも感じる。
また、民主党の大統領候補でもあるデブラシオNY市長は、NY市警のAI捜査のために中国製のカメラを導入し続けている。トランプ政権や、民主党が多数を占める下院から、中国は危険な競争相手と批判されても、どこ吹く風だ。米国や中国といった国家ベースで技術の協調開発を阻害しようとしても、地方公共団体の首長らが完全にこれに従うとは限らないのである。
1990年代、韓国のサムソンは、東芝や日立の技術者を高い給与で雇い、半導体の技術を日本から実質的に盗んだ。技術者の頭の中にあるものに壁はつくれなかったのだ。米中の技術覇権競争だといかに政治家が騒いだところで、技術者たちが協力を続け、彼らを支援する者がいる限り、情報の往来を止めることは不可能である。
そう考えると、AIの進化スピードは、妨害された恋人同士が一段と恋の炎を燃やすように、逆にスピードアップするのかも知れない。
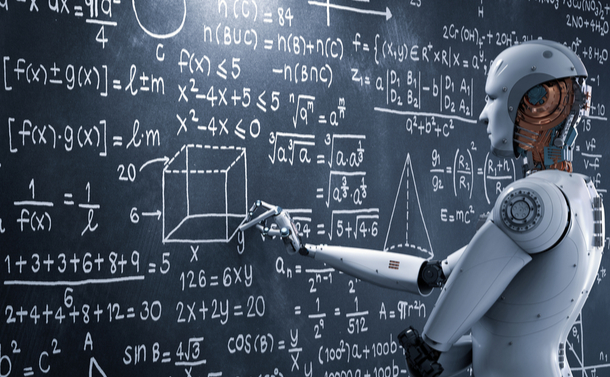 Phonlamai Photo/shutterstock.com
Phonlamai Photo/shutterstock.comしかし、現段階でAIを人間の求める通りに動かすためには、それを実現するための技術開発のみならず、感情のないシステムが勝手に課題達成に向かってしまうことで起こる副作用を防ぐ法的整備も必要になる。換言すれば、AIを使った捜査が行き過ぎることで起こる情報の乱用を止める、技術的・法的整備は絶対に必要なのである。
とはいえ、一義的には犯罪防止のための技術の進展を損ねるかもしれない法律を作るのは容易ではない。
こうした状況下、昨年、カリフォルニア州で通った二つの法案に注目したい。
一つは、昨年8月に知事がサインしていったん成立した、保釈金をゼロにする法案である(前回「AIを使った犯罪捜査で人種差別はなくせるのか?」でも触れている)。AIの活用で逮捕される者の数が増える可能性を意識したもので、法案はいったんは成立したもの、保釈金の廃止または引き下げを求めていた側、保釈金に絡んだ産業に従事していて導入に反対する側の双方に不満があり、結局、来年の大統領選挙時にあわせて、その可否について改めて住民投票をすることとなっている。
もう一つは、昨年6月に知事がサインした情報取得者の権利を守る法律で、日本ではJETROや法律事務所などによって「消費者プライバシー法」として説明されているものだ。
 MONOPOLY919/shutterstock.com
MONOPOLY919/shutterstock.com有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください