危険なレベルにまで低下した投票率と「政党の座標軸」の融解が示す危うい実情
2019年09月01日
 Niyazz/shutterstock.com
Niyazz/shutterstock.com参議院選からひと月以上がたった。その記憶は多くの人にとって、すでに過去のものなっているかもしれないが、筆者はまだその意義をうまくのみ込めずにいる。
改選議席数は下回ったが、改選定数の半数を超える議席を獲得した以上、与党が勝利したのは間違いない。とはいえ、野党も共闘の結果、32ある1人区のうち10の選挙区で勝利している。事前には苦戦が予測されていた選挙区も多く、それなりに健闘したと言える。結果として、与党と野党のうち改憲に前向きなグループを合わせた改憲勢力は、発議に必要な三分の二の議席を獲得できず、反改憲の野党側にも一定の手応えのあった選挙でもあった。
こうみてくると、今回の選挙の意義を勝ち負けという観点から読み解くのは容易でない。むしろ、この選挙の焦点は議席数ではなく、5割を切った投票率の低さにあるのではないか。そこに見え隠れするのは、令和の日本政治が陥りつつある危うい実情である。
今回の参院選の投票率は、選挙区で48.80%、比例区で48.79%しかなかった。過去二番目の低さである。5割を切るということは、2人に1人は投票していないことになる。はたして2人に1人しか投票していない選挙を、民主的な意思の表明と呼ぶことができるだろうか。人々はそれほどまでに政治に対して関心を失っているのだろうか。
「政治不信」ならば、まだ回復の可能性がある。政治にマイナスの目を向けているとはいえ、政治に対する関心が残っているからである。が、事態がここまで来ると、政治不信という以上に「政治不在」と言わざるをえない。
 参院選開票日、テレビのインタビューに答える安倍晋三首相=2019年7月21日、東京・永田町の自民党本部
参院選開票日、テレビのインタビューに答える安倍晋三首相=2019年7月21日、東京・永田町の自民党本部言論NPOが参議院選前に行った世論調査によれば、「日本の代表制民主主義の仕組みを信頼しているか」という問いに「信頼している」と回答した人は(「どちらかといえば信頼している」を含む)、32.5%に過ぎない。実に三分の一の人しか、自らの選んだ代表による民主主義のあり方を評価していないことになる。
20代と30代はさらに深刻である。現状の代議制民主主義を「信頼している」という人は、それぞれ20.2%、14.2%で、「信頼していない」を下回っている。「日本は民主主義の国か」という問いに肯定的な回答をした人の割合も、他の世代に比べて低い。20代、30代が日本の代議制民主主義に対して懐疑的、あるいは日本の政治や民主主義にリアリティーを感じていない様子が鮮明に浮かぶ。
実際、筆者の身の回りの若者の声を聞いても、政治不信という以前に、そもそも「どこに投票していいかわからない」「政治と言われても、何も思いつかない」といった反応が目立つ。そこにあるのは、ある種の戸惑いや政治への絶対的な「距離」の感覚に思えてならない。
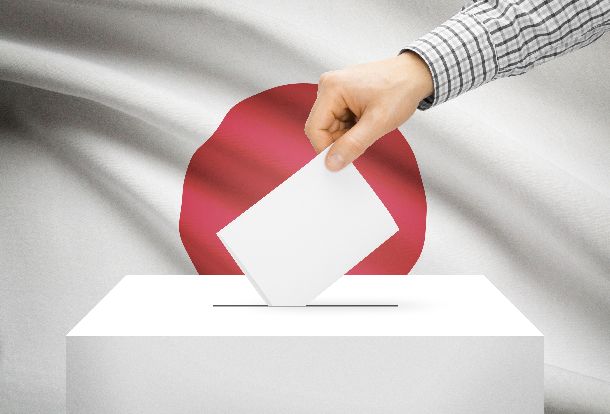 Niyazz/shutterstock.com
Niyazz/shutterstock.com50代以上の有権者にとって、「保守」といえば自民党、「革新」といえば共産党を想像するのが一般的であろう。だが、50代未満、とくに20代や30代にとっては、これが完全に逆になる。各種の世論調査によれば、現在の若者にとって、「保守」といえば共産党、「革新」といえば自民党や公明党、あるいは維新の党を意味するという。
考えてみれば、共産党が憲法擁護を掲げ、戦後民主主義の維持を訴えているのに対し、既存の枠組みの打破を訴えるのはむしろ、自民党や維新の党である。その限りにおいては理解できなくもないが、政治を語る基本的な語彙(ごい)においてすら、世代を超えた共通の理解が難しくなっていることを暗示している。
興味深いのは、こうした変化が50代を境に生じていることである。その原因を想像すれば、思春期を1989年のベルリンの壁崩壊以前に迎えた世代と、それ以降に迎えた世代の違いであろう。米ソ両大国による核戦争の脅威や、冷戦を反映した世界各地の政治状況を当たり前に耳にしてきた世代と、冷戦が終わり、「社会主義」と言われても実感を持って理解できない世代とでは、“常識”が大きく異なっても不思議ではない。肌感覚における政治体験が違うのである。
くわえて1990年代以降、日本社会において「時代の言葉」になったのは「改革」であった。戦後社会の基本的なあり方は打されるべきであり、現状維持を主張する人間は「守旧派」であって否定されなければならない、という時代の空気は、その時代の若者に「つねに変化しなければならない」というプレッシャーとして感じられたはずである。
その時期の若者にとって上の世代は、「日本型雇用」に守られ、年金をはじめとする社会保障においても有利な位置を占める「既得権者」に他ならない。その意味で、戦後社会の基本的なあり方の変更を阻む政党を指して「保守」と呼ぶ理解が次第に増していったのは、時代の空気の反映であったのかもしれない。
それでは、今回の参院選は、このような政党をめぐる座標軸の混乱にどのような影響を与えたであろうか。はたして、座標軸は回復されたのか、あるいは新たな座標軸が浮上したのか、はたまた座標軸をめぐる混乱が助長されただけなのか。
各党の公約を比較してみる。かつて「マニフェスト(選挙公約)」が活発に論じられた頃には、しばしば「数値や目標を具体的に示す」ことが強調された。だが、いまや数値目標や達成時期を示した公約はきわめて少なく、公約の多くは実現性を党内できちんと議論しているのかさえ疑われる水準である。「マニフェスト」選挙の理念をこのまま葬り去っていいのか、真剣に問い直されなければならない。
具体的な中身に目を転じれば、たしかに消費税増税や憲法改正に関しては、与野党の対立が明確なように見える。しかしながら、消費税増税に反対する野党の主張をみると、ではいかなる方法で財政を立て直すのか、さらに増大する社会補償費の負担を、誰がどのような形で担うのか、具体像を示せてはいない。
憲法改正についても、与党の一角を占める公明党は否定こそしないものの、現行憲法の基本を維持したうえで必要な規定を加える(加憲)を主張するのみ。自衛隊の明記や緊急条項などを訴える自民党との温度差は明らかであり、与党としての本気度は伝わってこない。
国民の多くが関心を持つ少子高齢化や人口減少についてはどうだろうか。抽象的な理念はあっても具体的な対策を示す政党は少なく、どこまでこの問題に真剣に向き合う覚悟があるのか、国民の間には疑念がいっそう深まったのではないか。参院選前にあれだけ盛り上がった「老後における2千万円不足」問題についても、議論が深められることはなかった。これだと、日本社会の未来像をいかに描くのか、具体的な提案に乏しい参院選であったと総括されても仕方がない。
こう見てくると、選挙を通じて政党間の対立の座標軸は表面的には維持されているとしても、もう一歩突っ込んで考えてみれば、その実質はむしろ空洞化がさらに進んだというのが現実であろう。このような選挙戦を付き合わされた有権者にしてみれば、政治に対する距離感が増すことはあっても、リアリティーや「本気さ」を感じるには、あまりに中身の乏しい参院選ではなかったか。
そんななか、現在の政治や経済状況において疎外を感じている人々にストレートに訴えかけた「れいわ新選組」の進出が見られたことは、決して意外ではない。ただし、れいわ新撰組にしても、今後、政権を目指して政策を練り上げる過程では、現在の主張をそのまま維持していけるとは思えない。すべては、今後の展開次第であろう。
いずれにせよ、政党をめぐる座標軸は混乱したままである。実質的な議論が乏しいまま、与党は権力維持をますます自己目的化させ、野党は無限の分極化のループから出られないという意味で、いわば平成後期の選挙戦のあしき縮図が再現されたと言える。こうなると「政党の座標軸」という言葉自体が、なにか悪い冗談にも聞こえるかもしれない。政治をめぐる環境は悪化の一途をたどっているのである。
 IM_photo/shutterstock.com
IM_photo/shutterstock.comこのような状況でふと思い出すのが、19世紀フランスの政治思想家トクヴィルである。
トクヴィルは民主的な社会においてもなお、専制は存在すると主張した。その専制は力によって人々を支配することはないが、個人同士が相互に疎遠になり、人と人とをつなぐ共通の結びつきが存在しない状況を利用する。相互に議論したり協力したりしない個人は、無力になり、無気力となる。そのような人々は、柔らかいがそれでも確実に人を握り潰す力を持つ「権力」の手に、やすやすとして身を委ねる。トクヴィルはこれを民主的専制と呼んだのである。
そのような権力を前にすると、人々はもはや抵抗の思いすら抱かない。自分自身で身の回りの状況をコントロールできない以上、そのような権力に従う以外にどのような道がありうるというのか、とあきらめる。
もちろん、そのような柔らかい専制権力が、人々をどこに向かわせているかはわからない。とはいえ、日常生活ですら意のままにならない以上、長期的に自分がどこに押し流されようと、知ったことではない。人と人とのつながりを失った個人が無力感に圧倒され、結果として不透明な権力を生み出す危険性を、トクヴィルは警告したのである。
トクヴィルの議論を継承するフランスの思想家ジャン=ピエール・ルゴフは、『ポスト全体主義時代の民主主義』(渡名喜庸哲・中村督訳、青灯社)で現代的な、新たな全体主義の特徴を次のようにまとめている。
その全体主義は、かつての全体主義のように確固とした思想や理念を持つわけではないし、唯一絶対の党組織があるわけでもない。が、社会の既存の組織が力を失ってすべてが流動化するなかで、共通の意味が解体することで指針を失った個人は、メディアがたれ流す大量のパッチワーク的な情報の洪水に溺れてしまう。そこで個人は、政治参加を馬鹿にしながらも、相互に対立するイメージの断片に目を奪われ、踊らされる。
 Artur Szczybylo/shutterstock.com
Artur Szczybylo/shutterstock.comもし多くの人が、社会の動きは個人の力の及ぶところではなく、残されているのは、社会の大勢のおもむくままに流されていくことだけだと考えているとすれば、それはトクヴィルの「民主的専制」や、ルゴフの「新たな全体主義」に近いのではなかろうか。危険なレベルにまで低下した投票率と「政党の座標軸」の融解は、私にそのような危惧を抱かせる。
換言すれば、「静かな全体主義」が日本で進行している。そして、それこそが特定の個人や組織の思惑を超えた、日本社会の趨勢(すうせい)である。
とはいえ、そのような現状のただ追認するのであれば、それもまた「静かな全体主義」に対する従属に過ぎないだろう。諦観(ていかん)に身を委ねる余裕は、今の日本社会に残されていないように思われる。民主主義の立て直しのために、声を上げねばならない。「静か」になってはいけないのである。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください