留学生、送り出し国の増加で学生も多様化。知識・経験が違う学生をどう教えるか
2019年09月29日
 関西外国語大学。スタディールームで勉強会を開く日本人学生と留学生ら=2019年3月18日、大阪府枚方市御殿山南町
関西外国語大学。スタディールームで勉強会を開く日本人学生と留学生ら=2019年3月18日、大阪府枚方市御殿山南町
4月に特定技能制度が導入されて半年。人口減で労働職人口が減る日本では今後、外国人労働者が増えるのは確実だ。そこで問題になるのが、就労目的の留学生に対してどのような教育を与えるかだ。東京福祉大学で外国人留学生を教えた経験をもとに加藤博章さん(日本戦略研究フォーラム主任研究員)が提言する。
2019年4月に特定技能ビザが導入されてから半年が経過しようとしている。人口が着実に減少し、労働力不足が叫ばれるなか、2020東京オリンピック・パラリンピックを控えた日本では、あちこちで外国人労働者の姿を見かけることが多くなった。身近な所では、コンビニやファストフードショップ、目に触れない所では物流施設や弁当工場など、それこそ様々な場所で外国人労働者が働いている。
外国人の数が増加するにつれ、外国人に対する教育の問題もクローズアップされるようになった。筆者は国際関係論、特に日本の外交・安全保障を専門としており、留学生教育の経験は全くなかった。しかし、ひょんなことで東京福祉大学に勤務することになり、留学生教育の一端を担うことになった。この春、過去3年間に1600人を超える留学生の所在が不明になっていたことが発覚し、社会問題化した大学である。
本稿ではこの東京福祉大学での経験を踏まえ、これまで私が見聞きしてきたことを通して、留学生教育と大学教育の課題について考えてみたい。
筆者は、2019年7月に千倉書房から出版された『あらためて学ぶ日本と世界の現在地』という本に代表編者として関わった。これだけではただの宣伝だが、本書は、教科書として作成した本であり、本書の編集には、今回のテーマである留学生教育、そして教養教育という点が加味されている。そのため、本論の導入として、本書の成り立ちに触れることとする。
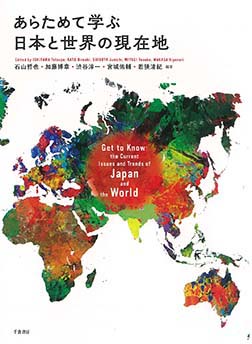 『あらためて学ぶ日本と世界の現在地』(千倉書房)
『あらためて学ぶ日本と世界の現在地』(千倉書房)本書企画の出発点は、「留学生を教育する上で類書が存在しない」ことだった。こういうと、例えば、留学生向けの日本語教科書など、様々な本がでているじゃないかという反論が寄せられるだろう。たしかに、この指摘は正しい。しかし、これらの本は、留学生向けの日本語教育の本であり、大学の教養課程、さらに言えば、そこに来る留学生の教育を想定したものではない。
ここまでいうと、日本語教育に携わっている人からは、「『国境を越えて』はどうなんだ」という声があがりそうだ。『国境を越えて』とは、立命館アジア太平洋大学の教授だった山本富美子さんのグループが作成した留学生・日本人学生のための一般教養書である。多くの大学で使用されている教科書であり、まさにベストセラーと言えよう。
何故、この本がベストセラーなのかといえば、類書がないからというのが最大の理由と思われる。たしかに、構成や形式は良く練られており、本編だけでなく、タスク編、語彙・文法編など、留学生を想定し、様々な用途に対応した本となっている。
しかし、本書には、中のデータが古いという難点がある。改訂版が出版されたのが2007年ということもあり、昨今の国際情勢や留学生事情など、近年の事情が反映されていないためだ。とはいえ、かわりになる本を探そうとしても、なかなか見つからないのが現状である。
近年の国際情勢や日本の状況も扱っていて、留学生の授業や大学に入学したての学生の教育に使える教科書がほしい。これが、『あらためて学ぶ日本と世界の現在地』出版のそもそもの動機である。類書がないのならば、作ってしまえということだ。
内容を少しだけ紹介しておこう。国内外の現状を把握してもらうため、戦争と平和、移民、開発やジェンダー、宗教、貧困などの問題を、国際的な観点から論じているのが本書の特徴だ。国際的な現状と日本の現状を複眼的にみて、多様な視点からまとめている。なかでも本書の「ウリ」の一つは、日本における移民・留学生問題について、いくつか章を設けたことだ。日本語教育の現状、留学生事情から留学生の就職に至るまで、今日の日本が直面している留学生や技能実習生など、移民を巡る問題をコンパクトにまとめている。
買って読んでいただければうれしいが、充実した中身になったという自負はある。
ところで、大学の一般教養で国際社会と日本についての授業を行おうとすれば、多岐にわたる問題や課題を論じる必要がある。それも、相手が留学生となると、日本人の学生に対して授業をするのとは異なる問題が生じてくる。
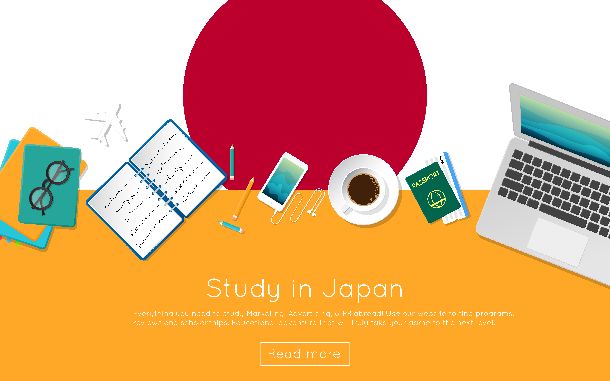 DoozyDo/shutterstock.com
DoozyDo/shutterstock.comこれは、留学生教育においては、当然の前提と思われるかもしれない。しかし、近年の状況は、留学生の急増と、それに伴う送り出す側の国の増加によって、従来の留学生教育とは様相が大きく変わっている。
2008年1月、当時の福田康夫首相は国会での施政方針演説のなかで、「日本を世界に開かれた国とする」と表明、人の移動の活発化を提議した。この方針に沿って、文部科学省は7月29日、2020年に日本国内の外国人留学生を30万人に増やすという、いわゆる「留学生30万人計画」を打ち出した。
この方針に沿って、日本国内における留学生の数はその後、右肩上がりに上昇する。日本学生支援機構の調査によると、計画が打ち出された2008年に約12万3千人だった留学生数は、2018年5月時点で約29万8千人。10年間で約17万人も増えた。
留学生の送り出す国も年々増えている。2008年は中国が約7万8千人と全体の60%を占め、韓国、台湾、ベトナム、マレーシアが続いている。2018年をみると、最多が中国なのは変わらないものの、その後はベトナム、ネパール、韓国、台湾など多様な国が並んでいる。
 宿泊業の特定技能試験にのぞむ外国人たち=2019年4月14日、東京・霞が関の国土交通省
宿泊業の特定技能試験にのぞむ外国人たち=2019年4月14日、東京・霞が関の国土交通省
実際、私が勤務していた東京福祉大学でも、そうした留学生が多く在籍していた。そのため、管理体制の問題が文部科学省と出入国在留管理庁から指摘され、是正のための指導も行われた。
日本では2019年4月に、「特定技能」という在留資格が新設された。人口減少によって不足する労働者を補うべく、外国人労働者の受け入れを拡大しようというものである。建設業や介護だけでなく、宿泊業、飲食料品製造業や外食業も受け入れの対象となった。留学生のアルバイト先になっている弁当工場なども対象で、就労目的の留学生の受け皿となることが予想されている。
このような留学生は、従来の留学生とは異なるタイプであることは言うまでもない。彼らは日本文化や日本にあこがれを持って留学してはいるものの、主目的はあくまでも就労である。また、経済的に余裕があるというより、借金をしてでも日本に来ている人々であり、教育レベルが高くない人々が少なくない。
そのため、大学で教育する場合は、前提となる知識や教育レベルを確認したうえで、授業をする必要がある。もっと言えば、日本では常識とされることも、あらためても教えなければならない。
例えば、カンニングはダメということ。外国人留学生には、カンニングを助け合いと捉え、互いに助け合うことを美徳と考えている学生もいる。経済的な理由からそもそも勉強をしたことがないという学生には、勉強の仕方から教えなくてはならない。こうした“基本的なこと”は本来、日本語学校などで教えるべき事柄だが、質の悪い日本語学校ではそれすら教えていない。そのため、大学で学習における「大前提」から教えなくてはならない。
他方、日本の教育が母国の教育と異なるために、留学生の刺激となることもある。特に歴史や政治についての授業は、学生にとって初めて教わるということが多い。国によっては、国の定めた歴史のみを教えたり、政治の干渉を嫌って授業でこういった問題を扱わなかったりということもある。そのため、自分の国の話なのに、初めて聞いたという反応を示すこともしばしばである。この点は、日本人相手では見られない光景であろう。
 Olga1818/shutterstock.com
Olga1818/shutterstock.com実学志向が強い学生が多いのもたしかだ。留学目的で来日しているとはいえ、彼らのほとんどは日本での就職を希望している。就職するまで通う学校の学費やその他の費用は、彼らにとって“経費”に過ぎない。すぐに就職可能ということで就学期間の短い専門学校を選んだり、経営などの実学系科目に興味を示すが、政治や歴史などの教養科目には興味を示さない学生も多々見られる。そうした学生に対して、大学に行く必要は何かを教えることは難しい。
実学教育が抱える問題は、一つの分野に特化した教育になるリスクがあることだ。実際、専門学校に入学した学生は、その分野に特化した勉強はできるが、他の分野にも応用出来る基礎的な技能を身に付けることが出来ないのが現状である。
実学教育が抱える問題は、一つの分野に特化した教育になるリスクがあることだ。実際、専門学校に入学した学生は、その分野に特化した勉強はできるが、他の分野にも応用出来る基礎的な技能を身に付けることが出来ないのが現状である。
大学と専門学校との違いは、一、二年生で一般教養を学ばせ、三年生以降は専門教育を行う点だ。とりわけ最初の2年間の教養教育が持つ意義は大きい。教授が長々と話をして終わりという授業も過去にはあったが、本来は専門教育を行うための基礎的な素養、例えばクリティカル・シンキングや基礎的な教養を身に付ける場である。
専門教育をする中で、自分の特性や志向が分かってくると、別の分野に移行することもあり得る。そこで重要になってくるのが、教養教育を受けているかどうかだ。実学教育だけだと、基礎的な素養がないので、他の分野を移ることが難しくなる。これまで見てきたように、基礎的な技能を身に付けていない留学生も多くおり、この点は日本人学生と比べて、問題となろう。
2019年4月に「特定技能」が始まって以来、留学生をめぐる問題が明らかになってきた。「特定技能」が開始されたことで、就労目的の留学生は減少することが予想される。しかし、それはかつてのように既に教育を受けた留学生のみを相手にして時代の留学生教育に戻る訳ではない。
今後も、初等教育を十分に受けてこなかった留学生は来日し続けるだろう。少子化の時代となり、学生の減少に悩む大学にとって、留学生は、経営上捨てることの出来ない顧客でもある。東京福祉大学の問題が明るみになったとはいえ、そのことに変わりはない。技能実習とは異なる形での就職を望む学生、何らかの理由で特定ビザを受け取れなかった学生など、留学生が就労目的の人々の受け皿となることは変わらないだろう。
そのような学生に対して、「なぜ一般教養が必要なのか」、「なぜ実学だけでは不十分なのか」を教えていかなければならない。東京福祉大学の問題は、管理出来る限界を超えた人数を受け入れていたという意味では特殊な問題であり、社会問題化するのも無理はない。しかし、人数の問題を除けば、どの大学でも起こり得る、表面化しないだけで実際に起こっている問題だ。大学教員にとっては決して他人事ではないのである。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください