「患者のため」だけでは医療者が疲弊してしまいバーンアウトを招いてしまう。
2019年10月09日
医療不信の風が吹き荒れていた15年前、「医を動かす」というミッションのもと、公募で選ばれた医療者、患者支援者、政策立案者、ジャーナリストら60人が集まり、「東京大学医療政策人材養成講座」(HSP)がスタートしました。1年間フラットな関係で学び合い、医療の課題解決に関する共同研究などを通じて養成された人材は、5年間で245人になります。しかし、「医は動いた」と言えるのでしょうか。東京大学大学院医学系研究科教授でHSPのプログラムディレクターだった高本眞一・東京大学名誉教授に、これからの医療改革に必要な視点を寄稿してもらいました。2回にわけて掲載していきます。(「論座」編集部)
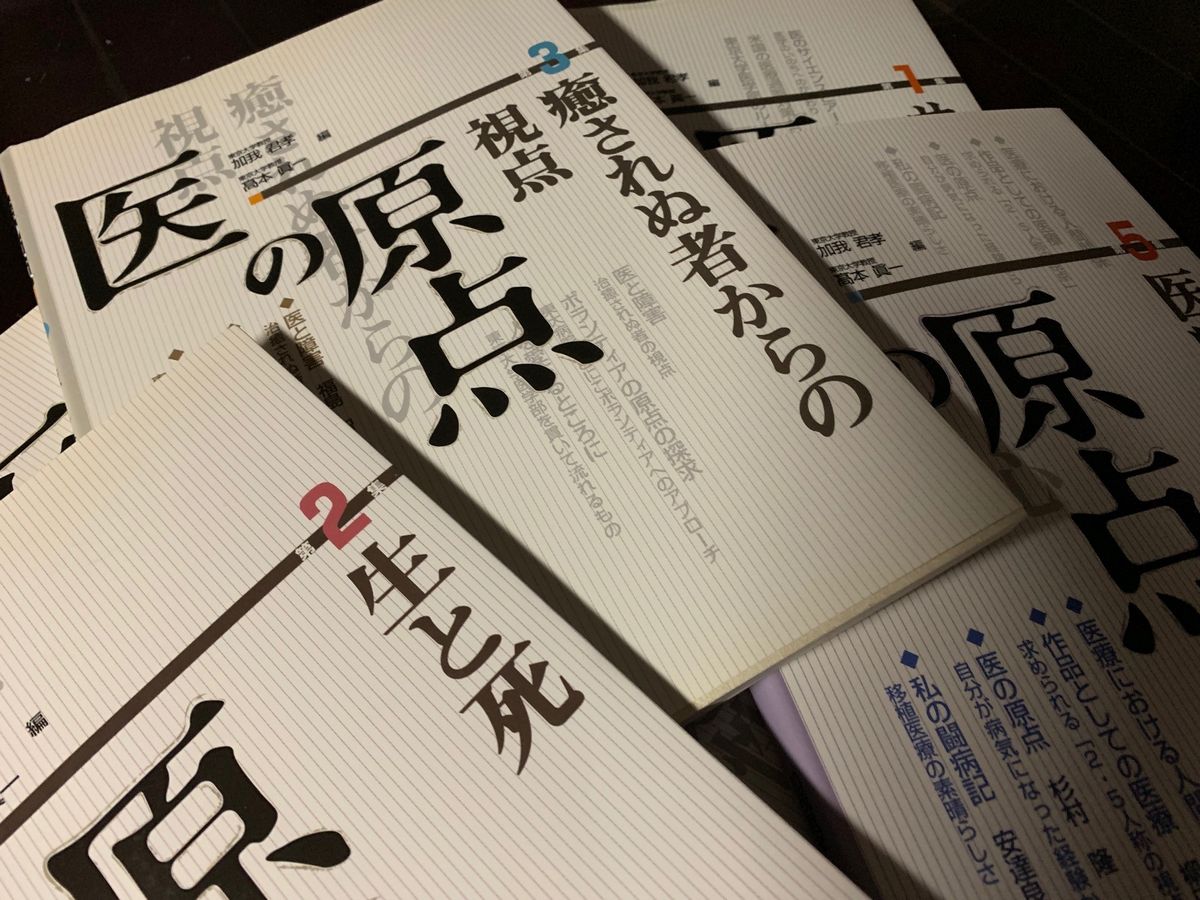
医の原点として最も大切なのは、ミッション(使命)をいかに理解して、行動するかということだと考えます。
福沢諭吉は144年前、現代にも通じるこのようなことを言っています。
福沢諭吉著「文明論之概略」
第一章 議論の本位を定る
議論の本位を定めざれば、その利害得失を談ずべからず。
(中略)
利害得失を論ずるは易しといえども、軽重是非を明らかにするはなはだ難し。一身の利害を以て天下の事を是非すべからず、一年の便不便を論じて百歳の謀を誤るべからず。
今の言葉に訳せばこういうことです。議論の本質をしっかりと理解してないで利害得失を談じてはいけない。身近な利害得失を論ずるのはやさしいが、天下の軽重、是非を明らかにするのはなかなか難しい。自分一人の身の利害で以て天下の事の是非を論じてはいけない。1年間の便不便を論じて、人生最後となる100歳の時の計画を誤ってはいけない。
人は大きな目的、将来のあるべき姿を求める本質的なことを考え、それをもとに行動しなければならないというのです。身近な自己中心主義ではなく、我々は人生において何をすべきかという大きな目標、ミッションを考え、それを中心に人間としての生き方を考慮し、また政治家も国の在り方について、ミッションを念頭に置いて判断をしなければならないという訳です。
アメリカのトランプ大統領の「アメリカ・ファースト」は自分の国の利益追求を第一に考え、また自分の利益を中心に考える価値観を全世界に広く公開しました。その価値観は、種々の団体にも影響し、以前よりも自己利益主義が大きく広がってきた感じがします。福沢諭吉が言うように100年後の世界にまで通用するような本質的な議論、ミッションを皆で重要視しなければならないと私は考えています。
医療の原点をしっかりと理解したうえで、医療についてのミッションを考えていきたいと思います。
私は心臓血管外科医として心臓血管外科の発展とともに歩んできました。新しい手術方法(逆行性脳循環法)、新しい超音波検査法(カラードプラによる経食道検査、カラードプラによる術中検査)などの発展に尽くしてきました。しかし、医学全体にわたって、すべての病気のことを全面的に知り得ることは不可能です。だからこそ、いつまでも勉強し続けないといけないと理解していました。
多くの人たちは、病気は医師が治すものと思っているかもしれません。近代西洋医学においては、患者さんが医師のもとを訪れ、症状を訴えると、問診や各種検査の後に病因を明確にし、投薬や手術によって病因を除去ないし弱体化して治癒に至る、というように考えられています。病原菌の発見と特効薬の発見による伝染病の克服に代表される近代西洋医学の歴史では、患者が薬や医師の援助の中で自ら治癒するのではなく、医師により薬や医術によって治癒せしめるというものが治療モデルとなっていました。
ただし、私自身、ほぼ理想に近い手術を行っても患者を助けることができなかったこともあれば、手術のやり方に満足がいかない時でも患者が元気になったことがありました。
 KPG_Payless/shutterstock.com
KPG_Payless/shutterstock.com医師が知っている医学の情報は生命が絡む病態のすべての情報から考えると極めてわずかなことです。その知識は数年後には間違った情報になる可能性もあります。
患者にとって一番働いているのは患者の持つ回復力や生命力です。患者の生命の力は、生きるように病気が治るようにという方向で働いています。医師は、患者の生命力ができるだけ正しい方向に向くようにガイドをしているだけなのです。
ですから医師と患者の関係は、医師が医学上知識としてよく知っているということで患者の上に立つのではなく、同格であり、医師は患者とともに生きなければならないのです。
患者は医療の中で癒し(いやし)が欲しいと思っていますが、医師や医療者も日常的にストレスを多く抱え、癒しを求めたいと思っています。患者も医師もお互いに理解し合ってこそ、癒しを得ることができると思います。
最近、認知症について「ユマニチュード」という患者との交流方法が話題になっています。認知症の患者に医療者の言うことが通じず、交流が全くできないことが多くの施設で問題になっています。
「ユマニチュード」は、医療者が認知症の患者を“人間らしい”存在としてその気持ちを理解し、大切に扱う思想や技術のことで、認知症の患者の気づき方、考え方などをよく理解して、体を近づけ、視線を合わせ、優しく体に触れて、話しかけるなどの方策を用います。フランス人のイヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティにより提唱されました。日本には2012年、国立病院機構東京病院センターの総合内科の医師をしていた本田美和子さん(HSP2期生)が導入し、今年10月には日本ユマニチュード学会として発展することになりました。
“人間らしい存在”というのは、相手の喜びも悲しみも自分のことと同じように感じあう人間として交流することです。ここまで述べてきた“患者とともに生きる”生き方であると言っていいと思います。
 Glowonconcept/shutterstock.com
Glowonconcept/shutterstock.com「ともに生きる」は、人間の理性、感性、霊性、情熱などを考慮し、現実の世界で生命を持って生きている人間のあるべき生き方で、哲学的な思想と言ってもいいでしょう。
私たちはいつも思った通りのことが出来るわけではありません。すべての人が全く同じ考えで同じ行動をするわけでもありません。性格、特徴など人によって考えは違うし、目標やそこへの到達方法も違うので、時にはぶつかり合うことがあります。しかし、そのような場合でも、対話をし、協力できることから始めるような、分裂状態を乗り越える情熱を持つ必要があります。その意味では我慢も必要ですし、甘くないことを自覚しながら、根気よく相手を理解しあうように努力しなければなりません。
「ともに生きる」ことの特徴を挙げると、下記のようなことになると思います。
• 能力のありなしにかかわらず、生命を持つその人を大事にする
• 人間として平等
• 人の能力を最大限引き出す
• 自分もベストを尽くして皆のために働く
• 誰も傷つけない
• 生きようとするエネルギーを大切にする
• 悲しみをともに、また喜びをともに
2011年3月、東日本大震災では、全国から東北地方に多くの援助物資が多く送られました。東北地方の住民が皆で協力し合ってそれを救援場所まで運ぶ姿がテレビ映像を通じて全世界に伝えられました。それを見た世界の人々は皆驚いたという話を、その後に訪れた欧米やアジアでの学会で聞かされました。どの国も同じようなことが起こったら、皆自分のために食料品を盗んできたり、入り口を火で焼いて部屋の中にあるものを盗んだりするのが普通で、日本のように皆で助け合うようなことはしない、と言っていました。日本は、基本的に近所付き合いを大切にする慣習があり、そのような環境で培った個々の力がこのような災害時に「ともに生きる」精神につながった可能性があると思います。
しかし、「ともに生きる」精神を発揮するためは、それぞれがミッションを心に刻み込み、どのような苦しい時もこの精神を発揮できるように頑張る必要があります。そのためには普段からそれなりの自己鍛錬が必要です。
 Have a nice day Photo/shutterstock.com
Have a nice day Photo/shutterstock.com「ともに生きる」考え方は、精神的なことだけではなく、技術的な面でもベストを尽くさなければならないと考えられます。手術、検査、薬物技術などの面でも患者にできるだけ有益な方法で医療の質を上げなければなりません。「クリニカルスキル」と言われており、現代でも多くの医師は全力を尽くして頑張っていると思います。
一方、患者との交流や伝達、医療の説明など、人間と人間性を重視した認知性や社会的なスキルは「ノンテクニカルスキル」と言われています。このことの不備により医療事故の50%以上が起こっていると言われています。この部分をしっかりと確立することが現代の医療の中でも大きな問題点でもあります。「患者とともに生きる」ことはノンテクニカルスキルとも合致して、医療安全の面でも大きく貢献できるのではないかと思います。「ともに生きる」精神や活動は、患者のためにテクニカルスキルとノンテクニカルスキルの両方を兼ねると考えられ、医療の発展、医療安全の遂行にも大いに役立つと考えられます。
リーダーの在り方として、アメリカのロバート・K・グリーンリーフ(Robert K. Greenleaf)は、サーバント・リーダーシップ(Servant Leadership)が必要であると提言しました。
通常のリーダーは 親分感覚でチームのメンバーを上から目線で指導します。しかし、チームのメンバーがいつも気持ちよく生きがいを持って活動ができるかというと難しいでしょう。サーバント・リーダーシップは、力ずくで引っ張るのではなく、ミッションに向かって自発的に歩み始める人を後押しするということです。それは使命感に基づいてなされる高貴な行動であり、組織やチームにも目標を達成させる大きな力になります。サーバント・リーダーシップは相手に奉仕して、その後相手を目標に向かって導くものです。
医師と患者との関係も通常は医師が上に立ち、患者を指導すると理解している医療者が多いと考えられます。医師がサーバント・リーダーシップをとり、患者のためにできるだけよい医療を提供して患者とともに生きることが、これからの新しい医師と患者の関係になるのではないかと考えられます。また、医師と患者は人間として同格であるので、医療の責任は医師だけが持つのではなく、患者も自分の病気に対して責任を持たなければなりません。このような関係に変えていくことによって、医療安全も高まることが期待されるし、患者が医療を信頼してくれる可能性も高まるのではないでしょうか。
 PR Image Factory/shutterstock.com
PR Image Factory/shutterstock.comアメリカでは1969年に「患者中心主義」(Patient-centered Care)が公表され、この言葉が医療界で広く使用されてきました。しかし、医療現場では患者の強い権利意識や主張などに翻弄されて、医療者がバーンアウトすることが増加しました。
そこで、1994年に「関係性中心主義」(Relationship-centered Care)が提案されました。「関係性中心主義」は「医療者と患者の関係」(Clinician-Patient Relationship)、「医療者と医療者の関係」(Clinician-Clinician Relationship)、「医療者と地域の関係」(Clinician-Community Relationship)の三つからなり、その関係性を大切にするという考え方です。医師も看護師も検査技師も、そして患者も、関係性をまず大切にするということで、患者の病気を治して皆が幸せになるようにがんばろうということです。
「患者のため」という言葉がよく使われます。しかし「患者のため」だけでは医療者が疲弊してしまい、バーンアウトを招きがちです。医療者も患者も皆で「ともに生きよう」という言葉が医療の現場で大切になってくるのです。
社会のために良いことをしたいと考えている人は、医療者だけでなく、政治家、経済人、教育家、そして一般人にも多くいます。ただ、社会を動かすためには次の三つのことが大切だと言われています。
1. Mission ミッション 使命
2. Passion パッション 情熱
3. Acton アクション 行動
ミッションという言葉は元々、宣教師(Missonary)が宗教を世界に広めるため、命を懸けて遠くの国に出かけ、自分のためでなく、宗教の絶対者と多くの民のために最善を尽すことがその人の生きがいにも通じるという生き方と考えられます。
しかし、日常社会では自分のミッションを公開してがんばっている人は多くいません。本人がミッションと言っていても、実際には比較的手軽な見通しであるビジョンの公開にとどまっていることが少なくありません。
ミッションは、基本的に自分の生命や生きがいを懸ける重い考えとなりうるものですが、ビジョンは 身近で短期的な目標が多く、重大な事態に対応できないこともあるし、周囲の関係から極めて安易に変更可能であります。
自分の中にミッション、使命がない場合、種々の判断を求められると自分の利益になるかどうかといった基準で判断や決定をしがちです。このようなことは、今日の政治経済の世界でもあらゆるところで噴出しているように思います。
医療では、働き方、医学教育、医療経済など様々な問題を抱えており、改革が叫ばれています。だからこそ医療におけるミッションを含んだ医療政策や改善策を確立し、実施していかなければならないと思います。私は、「患者とともに生きる」精神とその実行こそが医療の将来を導くものになると考えています。
人間は何のために生きているのだろうか、ということについて考察をし、それに合った働き方をすることが求められています。このような人がリーダーとなり、この社会や医療を改革してくれることが望まれています。

1947年生まれ。松山市で育つ。1973年東京大学医学部卒業。三井記念病院、ハーバード大学医学部、国立循環器病センターなどを経て、東京大学医学部胸部外科教授、日本心臓血管外科手術データベース機構代表幹事、医療政策人材養成講座設立、その後三井記念病院院長。日本心臓血管外科学会名誉会長。著書「患者さんに伝えたい医師の本心」など。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください