小此木政夫さんに聞く「朝鮮と日本の過去・未来」(1)
2020年01月14日
朝鮮政治史の第一人者として知られる小此木政夫・慶応大学名誉教授(74)が著した『朝鮮分断の起源 独立と統一の相克』(慶応義塾大学法学研究会叢書、2018年10月)が専門家の話題をさらっている。
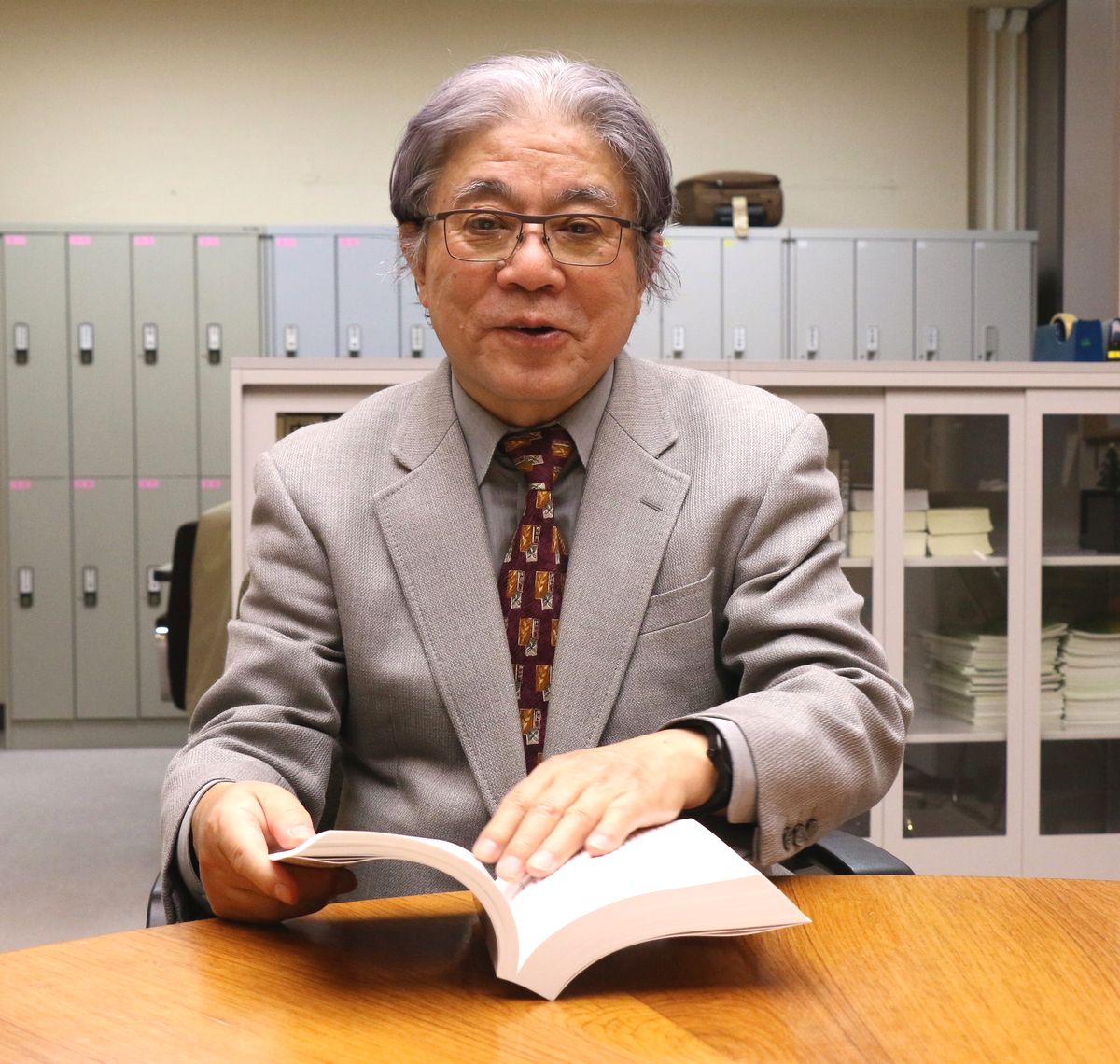 「教授に必要なことは研究、教育、学内行政、社会貢献、後進育成の5つだと恩師に教わりました。研究だけが不満足だったといえるでしょうか…」と語る小此木政夫さん=2019年12月、東京・三田の慶応大学、筆者撮影
「教授に必要なことは研究、教育、学内行政、社会貢献、後進育成の5つだと恩師に教わりました。研究だけが不満足だったといえるでしょうか…」と語る小此木政夫さん=2019年12月、東京・三田の慶応大学、筆者撮影日本軍の真珠湾攻撃による太平洋戦争開戦から記述は始まり、敗戦後の1946年までの激動の5年間を通して、米国や旧ソ連、朝鮮内部で何が起きていたかを立体的に再構成した。米公文書から韓国、中国の報道まで幅広く史料を集め、全572ページのうち、注や引用、索引だけで140ページを占める。
いわば太平洋戦争前後の「日米朝中ソ事典」の様相も呈し、それでいてドラマ仕立てのように要人の人間臭い言動や、行き交う電文や書簡が歴史上に何を刻んだかをくっきりと表している。
プロローグでは、日本の敗戦の「形」こそ、米ソ冷戦や朝鮮分断に少なからず影響を与えたことが強調されている。
原子爆弾の開発という軍事技術革命が日米戦争の終結に大きな役割を演じたとすれば、広島や長崎の住民にもたらされた深刻な被害とはまったく別の形で、それは朝鮮現代史、とりわけその地域の解放と分断に大きな影響を及ぼしたはずである。事実、もし米国が数カ月早く原子爆弾を完成し、それを連続的に投下していれば、ソ連軍が対日参戦の準備を整える前に日米戦争は終結して、朝鮮半島全体が米軍によって占領されたことだろう。また、もしその完成が数カ月遅れていれば、朝鮮半島は参戦したソ連軍の占領下に入ったことだろう。あのタイミングで原子爆弾が完成し、投下されたことが、朝鮮分断の大きな契機になり、5年後に米中両国を巻き込む大戦争を発生させる原因の一つになったのである
その直後に、こうも書く。
日本は日米戦争の一方の当事者であっただけではない。冷戦と呼ばれる米ソ対立の舞台を東アジアに設定するうえでも、大きな役割を演じた。なぜならば、日米戦争以前の時期、さらに開戦後の約6カ月の間に、大日本帝国の版図が日本列島から、台湾、朝鮮、満州、中国北部、インドシナ、南西太平洋諸島にまで拡大したからである。日本の敗戦によって、そこに、冷戦の舞台となる巨大な『力の真空』が発生したのである
この大論考を一読して再認識させられるのは、「力の真空」を目の当たりにして、米ソ両国は意外にもいきあたりばったり、しばしば計画性を欠いたまま朝鮮半島を管理しようとしたこと、そこにつけいる形で、日本から「解放」された朝鮮独立運動家が自発的な国家建設を目指したが、理想とする国家像の違いによりまとまらず分裂、米ソという超大国の思惑も壁となってうまくいかなかったことだ。
小此木さんは大学を定年退職した後、改めて大作に挑んだ動機について「地域研究と国際政治の両側面から50年近く研究し、大局を見る目がやっとできてきたからでしょうか…」と謙遜気味に語る。
小此木「できるだけ易しく、物語風に書いたつもりですが、いや、物語にはなっていないかも(笑)。日本の敗戦のタイミングが朝鮮分断にいかにかかわっていたかを改めて分析したのですが、負けるタイミングまで日本に責任があると言っているわけではありません。朝鮮分断は結局、米ソによるものだったということ。そのなかで、日本は舞台を設定したというか、敗戦までは朝鮮半島は日本の領土だったわけですから。その意味で分断に責任が全くなかったということでもないのです」
歴史に「もし」は禁句だが、原爆が登場せず、分断や占領がなかったら?
小此木「大国の勢力圏争いのようなものが起きなければ、中国と同様に朝鮮半島でも民族主義者と共産主義者の内戦が起きたのではないでしょうか。そしてどちらかが勝ったでしょう。共産軍が勝った可能性が高いと思います。仮に一時的に民族派が勝ったとしても、中国の国共内戦(=国民党軍と共産党軍の内戦)の延長で敗れたと思う。共産軍が旧満州の方から朝鮮北部へ入って来たと思います。朝鮮半島の共産化を避けるのは難しかったわけです。それが良かったか悪かったかというのは我々が判断することではないでしょう。共産主義国家になっても国が統一していたらよかったと思う人もいたでしょうから」
小此木さんは1945年4月生まれ。敗戦の4カ月前だった。
小此木さんの言う「70歳を過ぎてからの大局観」には理由がある。研究対象と現場感の積み重ねだ。
小此木「韓国で言うと、解放っ子、『ヘバン・ドンイ』と呼ばれる世代です。政治的にはノンポリだったものですから、慶応大学で朝鮮研究を始める時も、よく日本のインテリが語るような、政治的な動機みたいなものはありませんでした。はじめは中国研究をやりたくて、石川忠雄先生(=後に塾長)の門をたたいたのです。石川先生は中国共産党史研究の権威だったし、そのころは中国文化大革命の最中でもありました。ところが石川先生から『自分の弟子に中国研究をやる者はたくさんいるから、朝鮮研究をやってみないか』と勧められました。それで朝鮮研究に衣替えしたわけです。急な衣替えですから、いきなり韓国のことはできやしない。北朝鮮の共産主義の研究に入りました」
さらに、大学院の時に大阪市立大から国際政治学の第一人者、神谷不二教授が慶応に招聘され、その門下に「トレード」された。国際政治学は、まだ新たな学問として台頭する途上の分野だった。
小此木「半ば強制的でしたが、地域政治と国際政治のリンケージ(連結)という新しいテーマに取り組むことになりました。この二股、二本足でずっとやってきたことが、その後の研究に大きな影響を与えました。
世に出た最初の論文は1972年7月の『アジア経済』(アジア経済研究所)に載った『北朝鮮における対ソ自主性の萌芽 1953―55』というものでした。副題に『教条主義批判と〈主体〉概念』と付けました。
北朝鮮では朝鮮戦争後の復興期に、経済建設路線をめぐって重工業優先を主張する金日成(キム・イルソン)と消費財を重視する反対派の間で権力闘争が起きました。ソ連内の権力闘争を背景とするものだったのですが、1955年に入り、北朝鮮内では反対派が教条主義であると批判を受け、その過程で『主体』(チュチェ)という概念が誕生します。それが北朝鮮の掲げる『チュチェ思想』の出発点です。北朝鮮は戦前から主体思想があったかのように言いますが、そのようなことはなく、1955年にスタートしたのです。
その後しばらく、朝鮮半島をめぐる国際政治に関心が移り、朝鮮戦争の研究に従事しました。分断研究の原点には戦争研究がありました」
朝鮮半島の分断は、南北関係にも、冷戦の最も象徴的な場所という意味でも、日本の戦後補償にとっても、アジアや世界に大きな影響を与えてきた。
ただ、一般的には、南北分断を固定化したのは1950年6月に勃発した朝鮮戦争ではなかったのか? 少なくとも筆者はそう思っていた。だが、小此木さんは、前後関係が逆だったという。
小此木「半島分断と朝鮮戦争との関係でいえば、分断がなければ戦争はなかったということです。昔からずっと仮説として考えていたことですが、終戦直後に分断された朝鮮を何とか統一したいと、朝鮮の内部的な欲求(ナショナリズム)の高まりがまずあり、それが米ソ対立を戦争にまで引き込んだ要因だったのではないかということです。その仮説が今回、研究によって改めて証明されたと思っています」
小此木さんの「現場感」の話でいえば、1972年から74年にかけて韓国・延世(ヨンセ)大に留学したことがスタートだった。交換留学は今こそ珍しくないが、小此木さんは慶大と延世大の間で結ばれた協定によって派遣された最初の慶大生だった。
 1980年代以降は識者座談会の常連になった小此木政夫さん(右奥)=東京・築地の朝日新聞東京本社
1980年代以降は識者座談会の常連になった小此木政夫さん(右奥)=東京・築地の朝日新聞東京本社小此木「今よりはるかに、日本人にはアジア軽視、蔑視の傾向が強かった。慶応の同僚からも『韓国に行くのも留学なのか』と言われた時代です。韓国や台湾には軍事独裁のイメージもあり、行くこと自体、一部知識人からは相手にされなかったのです」
羽田を発ちソウル・金浦へ。雨に濡れた空港で、「すべてを捨てて白紙に自分の韓国像を描こう。体験したことだけを信じよう」と決意したことを今でも覚えているという。
韓国で待ち受けていたのは、今でも政治的激動の数年間だったといわれる大変革の連続だった。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください