地球温暖化で洪水が増加?限りある国の予算をどう使うか。切り札は?
2020年03月15日
3・11から9年。近年、日本が大きな災害に見舞われることが、ますます増えています。昨年10月の台風19号で、関東や東北の多くの河川で堤防が決壊、大きな被害が出たのは記憶に新しいところです。背景にあるのは地球温暖化。平均気温の上昇で雨量が増え、水害が起きやすくなっているともいいます。
“大災害時代”に入ったとも見える日本で、私たちはどう自然災害と向き合ったらいいのでしょうか? 政治はどのような役割を果たすべきなのでしょうか? 国民民主党の選対委員長で政治の基本は「治山治水」と思い定める岸本周平・衆院議員が、防災と「まちづくり」が専門の加藤孝明・東京大学教授に聞きました。(論座編集部)
 加藤孝明さん
加藤孝明さん加藤孝明(かとう・たかあき)
東京大学生産技術研究所教授、東京大学社会科学研究所特任教授。博士(工学)。専門は、地域安全システム学、都市計画。防災都市計画、事前復興などの理論研究の他、まちづくりの最前線にて、まちづくりの新しいモデルの構築に携わる。地域安全学会論文賞、都市計画家協会楠本賞などを受賞。携わる地域は、総務省防災まちづくり大賞(葛飾区新小岩北)、レジリエンスアワード・グランプリ(伊豆市土肥)、国土交通省先進街づくりシティコンペ(徳島県美波町伊座利)等を受賞。
――近年、日本全国で様々な災害が起きるようになっています。平成を通じて大地震が次々と起き、大雨や巨大台風などの水害が毎年のように列島を襲うようになっている。政治の基本は「治山治水」。私は防災が専門ではないですが、一人の政治家として、人の命を救うため、災害とどう向き合うかが問われるようになったと痛感しています。
加藤 平成以降、日本は明らかに“大災害時代”に入っていると思います。1995年の阪神大震災以降、全国各地で大地震が続いています。また台風・大雨による洪水も年々、頻度が高まっています。一昨年の西日本豪雨、昨秋の台風による千葉県の停電、関東や東北での同時多発の河川氾濫は衝撃的でした。私は防災に焦点をてた都市計画、まちづくりの専門家ですが、防災の専門家として国交省や内閣府で仕事をすることが増えています。
――いま“大災害時代”とおっしゃいましたが、同感です。もともと日本は災害が多い国ですが、昭和の後半は大きな災害が比較的少なかった印象です。それが平成になって変わってきた。令和でもそれが続いています。
加藤 防災に関して幾つか気がかりがあります。まず、2011年の東日本大震災以来、防災を取り巻く環境がそれ以前と様変わりしていること。地球が気候変動の時代に入り、従来型の災害対応では不十分になっている点にも注意が必要です。
――東日本大震災以降、そんなに変わりましたか?
加藤 まず気になるのが、ふたつの「バランスの崩れ」です。
――バランスの崩れ、とは。
加藤 ひとつは、「自助」、「共助」、「公助」のバランスの崩れ。震災直後の被災地での助け合いを通じ、自助、共助の大切さを学んだはずなのに、時がたつにつれ、公助頼りが強まっている。自然災害からの安全は公(おおやけ)が保障すべきだという空気すら感じます。ふたつは、何が重要な問題なのかについて、バランス感覚が崩れています。
――「国土強靱化」が象徴的ですね。洪水を避けるためには、堤防を高くするしかないと、補正予算であれ本予算であれ、どんどんお金をつける。実際、この3年間は、特例として7兆円の公共事業を防災名目で積み上げています。意味がないとは言いませんが、これだけがほんとうの防災対策なのか、私は疑問を持っています。
 岸本周平さん
岸本周平さん加藤 全国各地で住民が主体の「まちづくり」のお手伝いもしているのですが、先進的な地域では、行政だけでは想定される大きなハザードに対応できない。だから、住民もできることから率先して前に進めるしかない。つまり、共助を当たり前のこととしてとらえています。
――私はNPO議員連盟の事務局長をやっています。3年に一度、超党派でNPO法の見直しをするのですが、NPOはまさに共助の世界です。
日本人には、「官民」と「公私」を混同している人が多い気がします。「公」の仕事は官、「私」の仕事は民がやると考えている。でも、現実は違う。「公」のはずの官僚が天下り先に躍起になったり、忖度をしたり、すっかり「私」の集団になっているのに対し、NPOや社会課題解決に取り組む若い人が、まさに「公」の仕事をしている。先進的な地域では、そういう人たち共助を掲げて活動していると思います。
加藤 その通りです。NPOの活動が目立つようになった嚆矢(こうし)は阪神大震災。「NPO元年」と言われましたね。
――それを受けて、NPO法ができたのが1998年です。
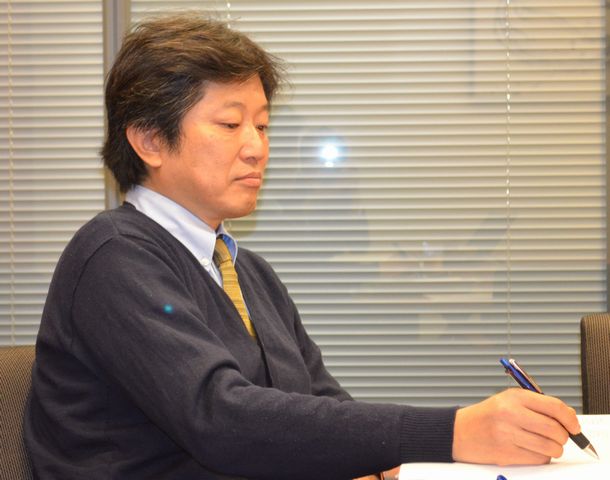 加藤孝明さん
加藤孝明さん
――同感です。ただ、NPOが脚光を浴びる一方で、日本にはもともと共助の伝統があるとも思います。消防団や自治会、町内会、交通安全母の会といった婦人団体、PTAなど、中間団体的な共助の組織は古くからあります。神社もそうですね。東北にいくと、神社が津波の被害からの逃れる場所にあることが多い。歴史のなかで、住民がかつてここまで津波がきたので神社はここにしようと決めた。これも共助です。
そうした昔からの知恵をもっと活用すればいいのに、旧来型の利権政治のせいかマスメディアが悪いのか、土手を高くする公共工事ばかりが目立つ。おかしいですよね。
加藤 最近、僕は「温故創新」という言葉を気に入っています。防災の分野でいま必要なのは、まさしく温故創新ではないかと。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください