美濃部達吉「憲法講話」の出版から100年余。これは戦後憲法学への挑戦の書だ
2020年03月15日
「健全な立憲思想」の普及を目指して、憲法学者の美濃部達吉が一般の人々に向けて体系的に憲法を論じた「憲法講話」が出版されたのは1912(明治45)年だった。それから100年余、同名の教科書「憲法講話 24の入門講座」(有斐閣)を、美濃部と同じ東大憲法学の系譜に連なる長谷部恭男・早大教授が出版した。「ですます調」で書かれ、長谷部教授が読者に「憲法とは何か」をまっすぐに語りかける。はしがきには「ごく標準的な教科書」とあるが、しかし、ここは額面通りに受け取らないほうがいい。戦後憲法学に対する挑戦の書でもある。長谷部教授に話を聞いた。
――タイトル「憲法講話」にはどんな思いを込められたのでしょうか。
長谷部 有斐閣さんからの提案です。美濃部の「憲法講話」はもともとの講演をおこしたもので、「ですます調」で人にわかりやすく語りかける文体になっています。わかりやすく、真っ直ぐに語りかける文章でいかがですかと言われ、引き受けました。
――美濃部の憲法講話の「序」にはこう記されています。
惟うに我が国に憲政を施行せられてより既に二十余年を経たりといえども、憲政の知識の未だ一般に普及せざること殆ど意想の外にあり。専門の学者にして憲法の事を論ずる者の間にすらも、なお言を国体に藉りてひたすらに専制的の思想を鼓吹し、国民の権利を抑えてその絶対の服従を要求し、立憲政治の仮想の下にその実は専制政治を行わんとするの主張を聞くこと稀ならず。
立憲主義の考えが浸透していないという点では、美濃部の指摘は現在にもあてはまる気がします。美濃部の問題意識も共有されているのでしょうか。
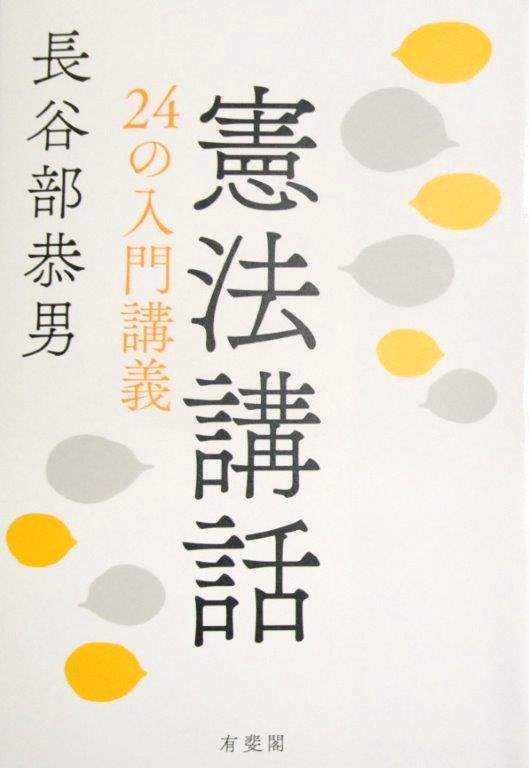
――日本国憲法の施行から今年で73年、大日本帝国憲法の施行(1890年11月)から130年を迎えます。ところが、立憲主義について尋ねられ、安倍晋三首相は「憲法について、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、今まさに憲法というのは、日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないか」と答弁しています。自民党の憲法改正草案に見られるように、国家ではなく、国民を縛るような逆立ちした憲法観が政治家の中に根強くあります。美濃部が生きていたら嘆いているのではないでしょうか。
長谷部 その点については様々な見方が可能でしょう。もっとも、美濃部がやろうとしたのは、彼の国家法人理論を土台にしながら、大日本帝国憲法を読み解いていくということです。国家を国民によって構成される社団法人だと見立て、国家の権限行使のあり方というものを位置づけ、制約する。その反面として、人々に自由な行動や表現できる空間を保障していくのです。それは時には憲法の条文とずれを起こします。
例えば、大日本帝国憲法第1条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあります。美濃部によれば、天皇は個人的な権利として統治権を持っているわけではなく、国家のために統治権を行使し、その効果も国家に帰属するというわけです。
また、万世一系の天皇が揺らぐことなく日本を統治してきたことは、国の歴史や倫理に関する問題であり、法律学とは無関係だという解釈をとります。彼は「憲法撮要」(有斐閣)にこう記しています。
憲法ノ文字ニ依リテ國家ノ本質ニ関スル学問上ノ観念ヲ求メントスルガ如キハ憲法ノ本義ヲ解セザルモノナリ
つまり、条文の枠だけで憲法がわかったような気にならないでほしいといっているのです。手形小切手法や道路交通法のようなものと憲法を解釈することは違うということです。
――条文にばかりこだわるというのは今の改憲論議にも通じます。
長谷部 現状と憲法の条文があってないように見えるから、憲法を変えるべきだという主張をしばしば聞きます。これは条文にこだわりすぎる「憲法典フェティシズム」で、それではだめですよ、というのが美濃部の警告です。
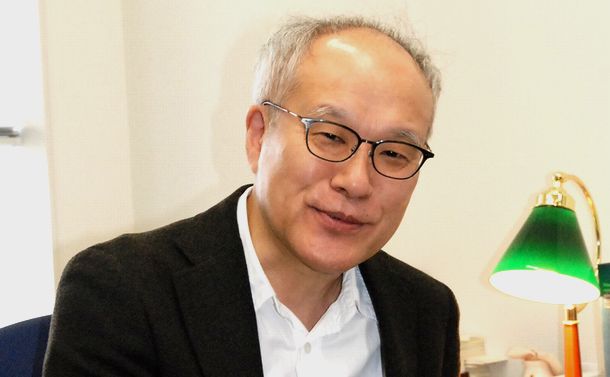 長谷部恭男・早大教授
長谷部恭男・早大教授――過去のことを学ぶことの大切さを今回の本では強調されていますね。
長谷部 私自身の反省もあるのですが、美濃部や上杉慎吉(※東京帝国大学の憲法講座担当教授で極端な君権優位を唱えた。美濃部の論敵)について、戦後の憲法学者はあまり勉強しなかったように思います。そのため、いつの間にか上杉と同じ見解を述べているということがあるのです。
――例えば、どんなケースでしょうか。
長谷部 美濃部の国家法人理論を中途半端な学説だと言っているのが、私の師匠である芦部先生です。芦部先生は教科書で国家法人説に触れて、「君主主権か国民主権かという近代憲法が直面した本質的問題を回避しようとした」と説明しています。要するに中途半端な理論だと言っているのですが、実は、上杉が言っていることと同じなのです。彼の「憲法述義」という本は国家法人説をとりあげて、君主にも主権はないが、国民にも主権はないということを言う理論だという説明をしています。
――今なぜ、美濃部や上杉の議論を振り返る必要があるのでしょうか。
長谷部 そもそも、法人でないとすると国家は何なのでしょうか。法律学的に国家をめぐる法現象を理解しようとすると、国家が法人だという前提をとらないことがありうるのか。これは私自身がずっと抱いていた疑問でした。そこを考えていく必要があるということです。
国家法人理論をとらずに、大日本帝国憲法の言葉を文字通りに受け取った時に何が起こるのか。美濃部が、「憲法撮要」の中で面白い説明をしています。
若シ統治権ガ君主ノ権利ナリトセバ、戦争ハ君主ノ私闘トナリ、租税ハ君主ノ個人的収入トナリ、国営鉄道ハ君主ノ個人的ノ営業トナリ、法律勅令ハ君主ノ崩ズルト共ニ其効力ヲ失フモノトナラザルベカラズ。其社会意識ニ反スルコト言ヲ待タズ
国家法人理論なくして、法律学としての憲法学が成り立つのかどうかを考えないといけないということです。
――新著は、国家法人説を正面から位置づけるという点で、師匠である芦部先生の憲法学に対する批判の書という面もあるのでしょうか。
長谷部 打倒芦部憲法学です。芦部先生の憲法学で説明がつかないところが残っているのでいくつか解決しないといけないと思っています。それを考えるためにも、美濃部にまで立ち返って考える必要がありました。
 芦部信喜
芦部信喜――国家法人説は中途半端と言い出したのは、芦部先生なのでしょうか。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください