緊急事態宣言が出され自粛圧力が強まる今、いまいちど考えてほしいこと(下)
2020年04月08日
『緊急提言!「命」とともに「いのち」を守れ』に続いて、政治学者の中島岳志・東工大教授、批評家の若松英輔・東工大教授が、東京都世田谷区で住民目線の行政を続けている保坂展人区長とともに、緊急事態宣言下に置かれた日本社会のあり方、そして日本の政治に決定的に欠けているものを考える。(論座編集部/この鼎談は3月27日夜にオンライン会議システムを使って行いました)
若松英輔・東工大教授 もう一つ、ここまでお話ししていて非常に大事だと思ったことがあります。先ほど保坂さんが、訪問介護の方たちが動けなくなったら、命を、そして「いのち」をつなげない人たちがたくさんいるという話をされました。
介護職も、メルケルのスピーチに出てきたスーパーのレジ係も、どちらかというと、これまでは社会的にはあまり高い評価と認識を得ることができなかった職業です。もっと端的に言えば、あまり高いお給料をもらっていない人たちです。
しかし、実際にはそうした人たちによってこそ社会が成り立っている。彼、彼女らによって「いのち」が守られているという事実が、今回のことで明らかになったと思います。
自分の利権だけを守ろうと汲々とする人も少なくない中で、彼らはまさに命をかけて高齢者や病人に寄り添い、あるいは食べ物などを手渡してくれている。本当の意味でこの世界を支えているのは誰なのかということを、この危機が過ぎ去ったら──本当はその前にやるべきことですが──十分な時間をかけて検証しなくてはならない。
そして介護職をはじめとする、これまで社会的に重視されてこなかった職業の誇りを取り戻し、「はたらく」ことにおける社会的な価値観を大きく転換するべきだと考えています。
保坂展人・世田谷区長 自粛要請が続く中で、飲食店などの商店、あるいは中小企業も大きなダメージを受けていますね。外国人旅行者が来なくなり、国内でも外出を控えようということになって、「今月の売上げがゼロに近い」と嘆いている経営者がたくさんいる。東日本大震災のときと比べても、「世界中が被災地になっている」だけに、そのダメージは大きいと思います。
世田谷にもたくさんいらっしゃいますが、音楽や演劇に関わる人たち、映画館やライブハウス経営など、ささやかであっても誇りをもって文化の仕事をしてきた人たちも、その波を正面から被っています。並大抵の試練ではありません。彼らを助けるには、10万円や20万円を貸しますというのでは到底間に合わない。事業主への営業補償も明確にならず、非常に深刻な事態だと思っています。
 保坂展人・世田谷区長
保坂展人・世田谷区長中島岳志・東工大教授 保坂さんも区長メッセージの中で、社会保険労務士による臨時労働電話相談、金利と信用保証料を区が全額負担する形での500万円の融資制度などの取り組みを発表されていましたが、今後そうした具体的な支援が早急に必要だと思います。
さらに、そこからもう一つ考えたいのは、今回の危機を一つのきっかけとして、お金の回し方自体の転換も考えていくべきなのではないかということです。
不況の際には、公共工事を増やすなどの形で経済の活性化が図られるわけですが、そのときにお金をどこに、どのように使っていくか。それが次の時代の都市のあり方をつくっていくことになる。保坂さんがずっと取り組んでこられた「グリーンインフラ」がその象徴だと思います。
保坂 これまで日本においては、大不況などによる失業対策事業の大半がハード型の公共事業によって行われてきました。ダム造成や道路整備などの公共工事ですね。
しかし、特に東京においては、そうしたハード型の公共事業のニーズはそこまで多くなくなっています。同時に、コンクリートに頼りすぎてきたがゆえに、東京は大変水に対して弱い街になってしまった。
それが顕著に表れたのが、昨年10月の台風19号における多摩川の氾濫です。あれは、単に多摩川の水があふれたというだけのものではありません。街がコンクリートで覆われているために、増水して水位があがった川に雨水が流れ込むことができず、押し返されて周辺にあふれ返ってしまったんですね。
こういうことが起こらないように、自然の脅威と力で対決するのではなく自然の力で受けとめるのが「グリーンインフラ」の考え方です。植物や土壌そのものの力を生かして雨水の流出を抑制し、地下水を涵養していく。コンクリート塀を生け垣にするといった小さな工事から、一戸建ての住宅や共同アパートの屋上に雨水を蓄えておける設備をつくる、駐車場のアスファルトを剥がして芝生にするなど、さまざまな技術が今、世界中で開発されています。
豪雨による被害を最小化するとともに、街の中の緑を増やしていく。それによって大小さまざまな規模の雇用が生まれる。まさに、21世紀型の公共事業といえると思います。住宅への雨水貯留槽の設置、公園の雨庭化、道路や歩道・街路樹周辺の改修、大型建造物の新設・改修等の事業が必要となります。
若松 コンクリートのインフラからグリーンインフラへの転換は、保坂さんの政治的ライフワークだといってよいのだと思います。しかし、実は世田谷区政において、保坂さんは「グリーン」だけではなく、もう一つのインフラもつくってこられたのではないかという気がしています。それが「いのちのインフラ」です。
今まで私たちは、インフラというと目に見える、手でさわれるものばかりを考えてきました。けれど、実はそれ以外にも、目に見えない「インフラ」──たとえば先ほどお話しいただいたような、孤立を防ぐための人と人とのつながりがなければ、我々の生活は成り立たない。それは「いのちのインフラ」と呼ぶべきものとだと思うのです。
グリーン(緑)は、生命/いのちの象徴ですから、これからの「グリーンインフラ」は、ただ緑を増やす、自然の力を利用するというだけではなく、「すべてのいのち」を守るための、目に見えない面も含めたインフラである、そんな気がしています。
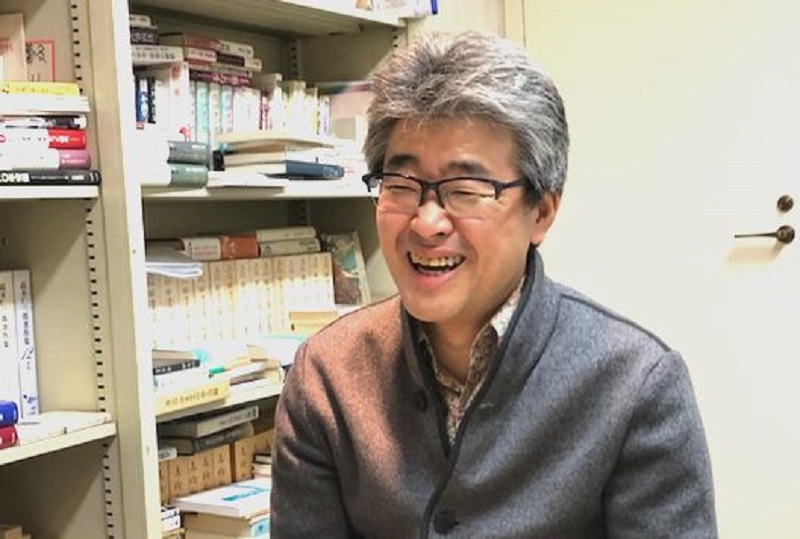 若松英輔・東工大教授
若松英輔・東工大教授中島 多摩川の氾濫の話が出ましたが、私はあの災害のさなか、保坂さんのツイッターを見ていて非常に感銘を受けました。というのは、保坂さんはあの日、深夜までずっとツイートをされ続けていたんですね。それも、こういうとき為政者の多くがやるような、威勢のいい強い言葉での書き込みとはまったく違った。ただ、区に集まってくる情報を正確に、淡々と流し続けておられたんです。
あれは、区民から見れば「区長は今、ずっと起きていて、私たちと一緒に災害と向き合っている」というふうに見えたと思います。
同じように状況に不安を感じながら、自分たちと手を取り合ってそこにいてくれている、という感覚。まさにいのちのレベルに届く言葉だったと思うし、保坂展人という政治家を非常に象徴していたと感じました。同時にそれは、現在の自公政権に決定的に欠けている部分なのではないか、と思うのです。
若松 私は、今の政治の言葉に完全に欠落しているのは「生活」だと思います。自粛要請で仕事がなくなって、明日の生活費に事欠く人も大勢いるという中で、なぜかお肉券だ、お魚券だと言い出す。一人ひとりの「生活」がまったく見えていないし、そういう報道がなされること自体が、私たちをどれだけ傷つけ、危機的な思いにさせるのか考えもしていないのでしょう。
さらに言えば、出されてくる対応がどれも場当たり的で、まったくビジョンが見えない。「多少の犠牲はしょうがない」ということを、どこかでにおわせているようにさえ感じます。「どの人もどの命も重要とする共同体」だと語ったメルケルとは、残念であるという意味で対照的です。
保坂 外出は自粛しろ、花見もダメだとする一方で、文部科学省は学校は再開させようとするし、旅行券の配布が検討されているというニュースまで流れてくる。あまりにも矛盾したベクトルの政策が飛び交っていますよね。文部科学省が出した「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」も、完全に感染症の専門家に判断を丸投げしたような内容で、学校という場が、子どものいのちそのものが紡がれていく場所であるということに工夫が見えない。ここは学校現場に丸投げです。
今回の件以外でも、検事長の定年延長問題や森友学園問題でも、政権はあまりにもひどい、がたがたの答弁を繰り返してきました。政府はきっといろんな問題を的確に処理してくれるはずだという信頼感が、これほどまでに大きく崩れたことはなかったのではないでしょうか。
そういう状況の中で今、統治機構に強大な権限を与える「緊急事態宣言」が出されたことを、私たちはどう考えるのかということですよね。
中島 私は、ここまで失策が続きながらも、安倍政権が倒れることなく来てしまった最大の理由は、「オルタナティブ(もう一つの選択肢)がないこと」だと思っています。かつて政権交代を実現させた民主党政権も、あるいは前回の東京都知事選で「新党ブーム」を引き起こした小池百合子知事も、自民党とは異なるようでいて、大きな世界観という意味では「もう一つの自民党」に過ぎなかったのではないでしょうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください